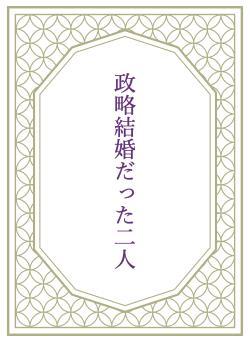「似てないわけあるか。よく見ろ、目なんてそっくりだろう」
「えっ……まあ、瞳の色は、似てるといえば似てるけど……」
「それに、笑えば瓜二つの愛くるしい兄妹だと昔から評判なんだぞ」
「そう言うなら笑ってみせなさいよ。その仏頂面じゃ判断しようがないわ」
オリバーの瞳は、深い茶色みがかった色合いをしていた。
黒いエプロンの下は簡素な白いシャツ。ロケットを首に下げているため、銀色の細い鎖が襟元から覗いている。
リサとヴェロニカはまだ何か言いたそうだったが、オリバーはそれぞれの手にカップを押し付けると、しっしっと手を振って追い払う仕草をした。
「それ、うちの新作候補。試飲させてやるから、向こうのテーブルで飲んできてくれる? ここにいられると邪魔だから」
「「感じわるっ……!!」」
そうして、ブーブー文句を言いながらも侍女達が離れるのを見届けると、彼はイヴの隣に並んだ幼馴染みに向き直った。
「やあ、ウィリアムくん。ただいまー。元気にしてた?」
「おかえり……相変わらずだな、君は。しかし、もう少し愛想よくできないのか?」
呆れた風に問うウィリアムに、オリバーは大真面目な顔をして首を横に振る。
「俺の愛想は有限なものでね。旅先で使いまくってきたから今は枯渇しているんだよ」
「そういえば、異国で兄さんを見かけたという方から、アンドルフにいる時とはまるで別人で不気味だった、と言われたことがあります」
「何でも極端なんだよ、オリバーは……」
「えっ……まあ、瞳の色は、似てるといえば似てるけど……」
「それに、笑えば瓜二つの愛くるしい兄妹だと昔から評判なんだぞ」
「そう言うなら笑ってみせなさいよ。その仏頂面じゃ判断しようがないわ」
オリバーの瞳は、深い茶色みがかった色合いをしていた。
黒いエプロンの下は簡素な白いシャツ。ロケットを首に下げているため、銀色の細い鎖が襟元から覗いている。
リサとヴェロニカはまだ何か言いたそうだったが、オリバーはそれぞれの手にカップを押し付けると、しっしっと手を振って追い払う仕草をした。
「それ、うちの新作候補。試飲させてやるから、向こうのテーブルで飲んできてくれる? ここにいられると邪魔だから」
「「感じわるっ……!!」」
そうして、ブーブー文句を言いながらも侍女達が離れるのを見届けると、彼はイヴの隣に並んだ幼馴染みに向き直った。
「やあ、ウィリアムくん。ただいまー。元気にしてた?」
「おかえり……相変わらずだな、君は。しかし、もう少し愛想よくできないのか?」
呆れた風に問うウィリアムに、オリバーは大真面目な顔をして首を横に振る。
「俺の愛想は有限なものでね。旅先で使いまくってきたから今は枯渇しているんだよ」
「そういえば、異国で兄さんを見かけたという方から、アンドルフにいる時とはまるで別人で不気味だった、と言われたことがあります」
「何でも極端なんだよ、オリバーは……」