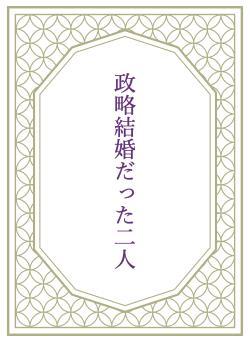「フォルコ殿下は、コーヒー以外にはまるで無頓着で、王族の自覚も威厳もなく、生活能力のない穀潰しの、まったくもってダメダメな方ではございましたが……」
「どうしよう、ご先祖さまが全力で悪口を言われている……ウィリアム様、私は怒った方がいいでしょうか?」
「必要とあらば私が後でまとめて怒ってやるから、イヴは聞き流していいぞ」
微妙な顔をするイヴとウィリアムをよそに、失礼極まりないネズミはしみじみと続けた。
「しかし、とても穏やかな、お優しい方でございました。みなさま、あの方を深く愛していらっしゃったのですよ」
もちろん、わたくしめも、とラテが目を細める。
彼が王宮を出入り禁止になったのは、コーヒー豆をだめにしたからではなく、それを発端とする厳罰から逃すための、フォルコ王子による苦肉の策だったのだ。
コーヒーを粗末にしたものは末代まで許すな、というフォルコ家の家訓は、これが歪曲して伝わったせいで生まれたのかもしれない。
ともあれ、ラテとしてもフォルコ王子に命を救われた自覚があるため、その子孫であるフォルコ家の人間には敬意を払うようにしてきた。
彼がイヴを〝イヴ様〟なんて呼ぶのもそのためだ。
しかしながら、代々のフォルコ家当主は誰も、初代の命を撤回してこなかった。
それはそうだろうと思ったイヴは、隣に座るウィリアムの耳にコソコソ内緒話をする。
「どうしよう、ご先祖さまが全力で悪口を言われている……ウィリアム様、私は怒った方がいいでしょうか?」
「必要とあらば私が後でまとめて怒ってやるから、イヴは聞き流していいぞ」
微妙な顔をするイヴとウィリアムをよそに、失礼極まりないネズミはしみじみと続けた。
「しかし、とても穏やかな、お優しい方でございました。みなさま、あの方を深く愛していらっしゃったのですよ」
もちろん、わたくしめも、とラテが目を細める。
彼が王宮を出入り禁止になったのは、コーヒー豆をだめにしたからではなく、それを発端とする厳罰から逃すための、フォルコ王子による苦肉の策だったのだ。
コーヒーを粗末にしたものは末代まで許すな、というフォルコ家の家訓は、これが歪曲して伝わったせいで生まれたのかもしれない。
ともあれ、ラテとしてもフォルコ王子に命を救われた自覚があるため、その子孫であるフォルコ家の人間には敬意を払うようにしてきた。
彼がイヴを〝イヴ様〟なんて呼ぶのもそのためだ。
しかしながら、代々のフォルコ家当主は誰も、初代の命を撤回してこなかった。
それはそうだろうと思ったイヴは、隣に座るウィリアムの耳にコソコソ内緒話をする。