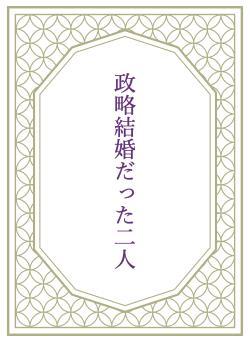「ところで、マンチカン伯爵閣下は、近くにはいらっしゃいませんでしょうね?」
「いらっしゃいませんよ。本日は、王都の外れの湖でボート釣りをなさるとおっしゃっていましたから」
「それはようございました……あの、わたくしめも、お邪魔させていただいてよろしいですか?」
「もちろんです。こちらへどうぞ」
ラテがマンチカン伯爵に怯えるのも無理はない。
猫が鼠を獲るように、かつてネコ族はネズミ族にとって最も恐ろしい捕食者だったのだ。
しかし、天敵と鉢合わせする危険がないと知ってほっとしたらしいラテは、おずおずと茂みから出てきた。
二本足で歩き、身長はイヴの胸くらい。白いシャツと深緑のズボン、黒いブーツを履いている。
彼は、ウィリアムの前までやってくると、改めてペコペコと頭を下げた。
「殿下、どうも。どうもでございます」
「そんなにビクビクせずとも、今のアンドルフ王国に君を捕って食おうとする者はいないぞ?」
城が建った当初からこの庭で働いているというラテだが、イヴが彼と初めて言葉を交わしてから、実はまだ一年も経っていない。
そもそも彼は、王宮への立ち入りを禁止されているというのだ。
さらにはフォルコ家と因縁があるらしく、その当主たるイヴの父や兄が城にいる間は、彼らに見つからないよう息を潜めて過ごしていたらしい。
「まあ、フォルコ家との因縁なんてのは、十中八九コーヒー絡みだろうがな。ラテ、何があったんだ?」
「はあ、それがですね、殿下。話せば長くなるのですが」
と言って話し始めたラテの話は、宣言通り長かった。
まわりくどくて冗長で、眠気を誘って仕方がなかったし、焚き火にかけていたポットのお湯なんてすっかり沸騰してしまったが、要約すると……
「コーヒーを飲もうとフォルコの研究室に忍び込んで、盛大にやらかした、と?」
「はい、まあ……そんなところでございます」
いやはやと照れたように笑うラテに、イヴとウィリアムは顔を見合わせるのだった。