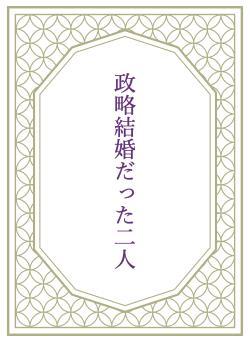「ウィリアム様、せっかくのお休みですのに、毎回付き合わせてしまって申し訳ありません」
「いや、好きでやっていることだから気にするな」
こうして、休日でも当たり前のように一緒に過ごしているイヴとウィリアムを見ると、クローディアなんかはよく、爆発しろ、などと言う。
そのクローディアだが、昨日は三時間ほどイヴを眺めていて仕事が終わらなかったため、本日は休日出勤している。
ともあれ、実際に爆ぜるのはイヴとウィリアムではなくコーヒー豆だ。
生の状態で産地から送られてくる豆を、『カフェ・フォルコ』では月に三度ほどこうしてまとめて焙煎していた。
「そもそも、私に焙煎の手順を仕込んでいったのはオリバーだしな。まあ、イヴにこの作業をさせたくないというあいつの気持ちもわからなくもない」
ザラザラと手網の中で豆を転がしつつ、ウィリアムが肩を竦める。
何しろ焙煎という作業は、火に近くて熱い上、豆を満遍なく煎るのにずっと手網を振っていなければいけないため、とにかく疲れるのだ。
可愛い妹にそんな苦労をさせたくないオリバーは、立っているものは王子でも遠慮せず使うらしい。
やがて、新しく焙煎を始めた豆からもパチパチと音がしだした。
「いや、好きでやっていることだから気にするな」
こうして、休日でも当たり前のように一緒に過ごしているイヴとウィリアムを見ると、クローディアなんかはよく、爆発しろ、などと言う。
そのクローディアだが、昨日は三時間ほどイヴを眺めていて仕事が終わらなかったため、本日は休日出勤している。
ともあれ、実際に爆ぜるのはイヴとウィリアムではなくコーヒー豆だ。
生の状態で産地から送られてくる豆を、『カフェ・フォルコ』では月に三度ほどこうしてまとめて焙煎していた。
「そもそも、私に焙煎の手順を仕込んでいったのはオリバーだしな。まあ、イヴにこの作業をさせたくないというあいつの気持ちもわからなくもない」
ザラザラと手網の中で豆を転がしつつ、ウィリアムが肩を竦める。
何しろ焙煎という作業は、火に近くて熱い上、豆を満遍なく煎るのにずっと手網を振っていなければいけないため、とにかく疲れるのだ。
可愛い妹にそんな苦労をさせたくないオリバーは、立っているものは王子でも遠慮せず使うらしい。
やがて、新しく焙煎を始めた豆からもパチパチと音がしだした。