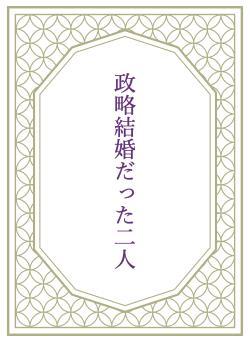パチパチと響いていた音が、ふいに止んだ。
「──今です。火から上げてください」
イヴの声を合図に炎から離れ、ザララッと網の上へ一気にぶちまけられたのは、焦茶色に煎り上がったコーヒー豆である。
イヴはすかさず風を送ってそれを冷ました。
「イヴ、次はどうする?」
「こちらの、粒の大きい豆を。今度は中深煎り二爆ぜでお願いします」
イヴの言葉に頷いて、受け取ったコーヒーの生豆を手網に放り込むのはウィリアムだ。
公休日であるこの日、二人は王城の庭の片隅にある広場で、コーヒー豆の焙煎を行っていた。
革の手袋を着けたウィリアムが焚き火の上で手網を振る中、イヴは焙煎が済んだ豆から焦げたものを取り除く。焦げた豆が混ざるとコーヒーにピリッとした苦味が出てしまうため、この一手間を惜しんではならない。
休日なので、イヴはエプロンドレスもヘッドドレスもつけず、年相応に愛らしいワンピース姿だ。ウィリアムも、今日はジャケットもクラバットも取り払い、ズボンとシャツという簡素な格好をしていた。
そんな二人が、店のかまどでも王宮の厨房を借りるのでもなく、わざわざ庭で火を焚いているのは、コーヒー豆の焙煎というのがとにかく散らかる作業だからだ。
煎り始めると豆の薄皮が剥がれて網の隙間からどんどん飛び出してくるし、焙煎が進めば煙だって激しくなる。
「──今です。火から上げてください」
イヴの声を合図に炎から離れ、ザララッと網の上へ一気にぶちまけられたのは、焦茶色に煎り上がったコーヒー豆である。
イヴはすかさず風を送ってそれを冷ました。
「イヴ、次はどうする?」
「こちらの、粒の大きい豆を。今度は中深煎り二爆ぜでお願いします」
イヴの言葉に頷いて、受け取ったコーヒーの生豆を手網に放り込むのはウィリアムだ。
公休日であるこの日、二人は王城の庭の片隅にある広場で、コーヒー豆の焙煎を行っていた。
革の手袋を着けたウィリアムが焚き火の上で手網を振る中、イヴは焙煎が済んだ豆から焦げたものを取り除く。焦げた豆が混ざるとコーヒーにピリッとした苦味が出てしまうため、この一手間を惜しんではならない。
休日なので、イヴはエプロンドレスもヘッドドレスもつけず、年相応に愛らしいワンピース姿だ。ウィリアムも、今日はジャケットもクラバットも取り払い、ズボンとシャツという簡素な格好をしていた。
そんな二人が、店のかまどでも王宮の厨房を借りるのでもなく、わざわざ庭で火を焚いているのは、コーヒー豆の焙煎というのがとにかく散らかる作業だからだ。
煎り始めると豆の薄皮が剥がれて網の隙間からどんどん飛び出してくるし、焙煎が進めば煙だって激しくなる。