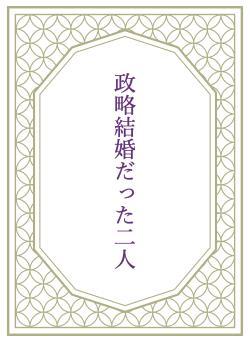「いつも、私を気にかけてくださり……ありがとうございます」
「……ん?」
「かっこよくて、世界一かわいくて……あの、大好き、です」
「……んん?」
思っていたものとは違う伝言に、彼は首を傾げる。
違うのは、それを伝えるイヴの口調もだ。
いつもは目の前にある文章を読み上げるがごとく淡々としていて淀みがないというのに、この時はゆっくりと噛み締めるように、そして少しだけ震えた声であった。
不思議に思って彼女を見下ろしたとたん、ウィリアムははっとする。
「イヴ……?」
カウンターの向こうにいるイヴのまろやかな頬も、黒髪から覗く丸い耳も、長いまつ毛が影を落とす目元も、赤く色づいていたからだ。
ぽかんとするウィリアムを少し潤んだコーヒー色の瞳でちらりと見上げ、彼女ははにかんでこう続けた。
「私からの伝言、でした」
とたん、ウィリアムのフサフサの尻尾が、千切れて飛んでいってしまいそうなくらいブンブンしたのは言うまでもない。
その場に居合わせた人々は、自然と笑顔になった。
「……ん?」
「かっこよくて、世界一かわいくて……あの、大好き、です」
「……んん?」
思っていたものとは違う伝言に、彼は首を傾げる。
違うのは、それを伝えるイヴの口調もだ。
いつもは目の前にある文章を読み上げるがごとく淡々としていて淀みがないというのに、この時はゆっくりと噛み締めるように、そして少しだけ震えた声であった。
不思議に思って彼女を見下ろしたとたん、ウィリアムははっとする。
「イヴ……?」
カウンターの向こうにいるイヴのまろやかな頬も、黒髪から覗く丸い耳も、長いまつ毛が影を落とす目元も、赤く色づいていたからだ。
ぽかんとするウィリアムを少し潤んだコーヒー色の瞳でちらりと見上げ、彼女ははにかんでこう続けた。
「私からの伝言、でした」
とたん、ウィリアムのフサフサの尻尾が、千切れて飛んでいってしまいそうなくらいブンブンしたのは言うまでもない。
その場に居合わせた人々は、自然と笑顔になった。