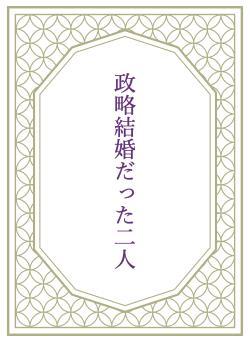ウィリアムの言葉は、決してお世辞ではない。
イヴは殊更記憶力に優れており、一度見聞きしたものはまるで脳内に書き写したみたいに正確に、かつ半永久的に覚えておくことが可能なのだ。
そのため、『カフェ・フォルコ』の作り付けの棚に保管されている膨大なコーヒー豆の銘柄も特徴も淹れ方も、余すことなく把握できている。彼女にそれを教えたのはもちろん、コーヒーに対して並々ならぬ情熱を抱く父や兄だ。
イヴが、コーヒーを注文した客の伝言を引き受けるようになったのも、いちいちメモをとらずとも一文一句違わず覚えられる、その優れた記憶力が所以だった。
それにしても、とウィリアムが彼女を見下ろして続ける。
「苦いのが苦手なのに、ブラックで飲んでみたいのか?」
すると、イヴはこくりと頷いて、彼を見返して答えた。
「だって、ウィリアム様がいつも幸せそうなお顔で飲んでいらっしゃいます」
「ん……?」
「ウィリアム様が幸せだと思うのはどんな味なのか知りたい──私も、ウィリアム様と同じ気持ちを味わってみたいです」
「……っ、いやもう、君は……」
ふいに立ち止まって目頭を押さえた相手に、イヴはきょとんと首を傾げる。
その他意のなさそうな顔を見てため息をつきつつも、銀髪に透けたウィリアムの耳はほのかに色づいていた。
「断言する──イヴが淹れてくれたものじゃなければ、そんな顔はしない」
イヴは殊更記憶力に優れており、一度見聞きしたものはまるで脳内に書き写したみたいに正確に、かつ半永久的に覚えておくことが可能なのだ。
そのため、『カフェ・フォルコ』の作り付けの棚に保管されている膨大なコーヒー豆の銘柄も特徴も淹れ方も、余すことなく把握できている。彼女にそれを教えたのはもちろん、コーヒーに対して並々ならぬ情熱を抱く父や兄だ。
イヴが、コーヒーを注文した客の伝言を引き受けるようになったのも、いちいちメモをとらずとも一文一句違わず覚えられる、その優れた記憶力が所以だった。
それにしても、とウィリアムが彼女を見下ろして続ける。
「苦いのが苦手なのに、ブラックで飲んでみたいのか?」
すると、イヴはこくりと頷いて、彼を見返して答えた。
「だって、ウィリアム様がいつも幸せそうなお顔で飲んでいらっしゃいます」
「ん……?」
「ウィリアム様が幸せだと思うのはどんな味なのか知りたい──私も、ウィリアム様と同じ気持ちを味わってみたいです」
「……っ、いやもう、君は……」
ふいに立ち止まって目頭を押さえた相手に、イヴはきょとんと首を傾げる。
その他意のなさそうな顔を見てため息をつきつつも、銀髪に透けたウィリアムの耳はほのかに色づいていた。
「断言する──イヴが淹れてくれたものじゃなければ、そんな顔はしない」