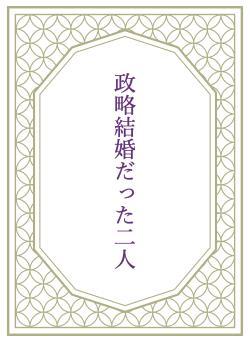コーヒーは、化学である。
お湯の温度、注ぐ速さ、粉の量、豆の挽き方、焙煎時間など、条件によってその味は自由自在千差万別。
しかしイヴは、それを特別意識したことはない。
コーヒーはただ、物心がついた頃から側にある、彼女にとってとても馴染み深いものだった。
深煎りの豆を細かく挽いて、濃いめのコーヒーを淹れる。
ふわり、とほのかに花のような甘い香りが立ち上り、イヴの口元が自然と綻んだ。
豆は、標高が高く昼夜の寒暖差が激しい山岳地帯で採れた、苦味と酸味のバランスがよいものだ。果実のような酸味とコクのあるコーヒーになる。
これを抽出している間にかまどに小鍋をかけてミルクを温めるが、決して沸騰させてはいけない。
最後に、温めておいたカップにコーヒーとミルクを注げば完成である。
「お待たせしました。カフェオレでございます」
明るい声でそう言って、イヴはカフェオレがなみなみと注がれたカップを木製のカウンターに置いた。
お湯の温度、注ぐ速さ、粉の量、豆の挽き方、焙煎時間など、条件によってその味は自由自在千差万別。
しかしイヴは、それを特別意識したことはない。
コーヒーはただ、物心がついた頃から側にある、彼女にとってとても馴染み深いものだった。
深煎りの豆を細かく挽いて、濃いめのコーヒーを淹れる。
ふわり、とほのかに花のような甘い香りが立ち上り、イヴの口元が自然と綻んだ。
豆は、標高が高く昼夜の寒暖差が激しい山岳地帯で採れた、苦味と酸味のバランスがよいものだ。果実のような酸味とコクのあるコーヒーになる。
これを抽出している間にかまどに小鍋をかけてミルクを温めるが、決して沸騰させてはいけない。
最後に、温めておいたカップにコーヒーとミルクを注げば完成である。
「お待たせしました。カフェオレでございます」
明るい声でそう言って、イヴはカフェオレがなみなみと注がれたカップを木製のカウンターに置いた。