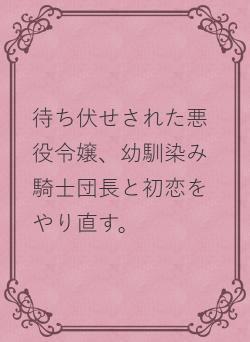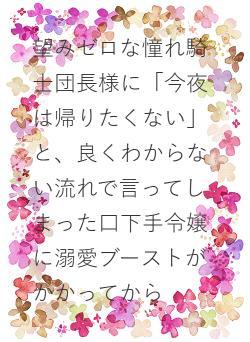「はじめまして。レニエラです。侯爵様。お会いできて嬉しいです」
……僕も本当に、君に会えて嬉しい。
顔合わせとして初めて間近で見たレニエラは、想像していた以上に可愛らしかった。
僕はレニエラを知っているが、レニエラは僕を知らない。ここは完全に初対面なのだから、何かしら褒め言葉をまず言うべきなんだろうと思った。
いつもなら特に何も考えずに、定番の褒め言葉に相手に合わせたお世辞が出て来るはずの口は、初恋の人に縁談を申し込んだという夢のような状況への緊張からか上手く動かない。
このままでは、変に思われてしまうと思えば思うほどに、言葉は出て来ない。
二人きりになっても言葉少なな僕に、レニエラは不思議そうな表情だった。
本来なら、この会話の主導権は僕が握るべきだ。彼女が結婚を望んだ訳でもない。
それに、ずるい僕は自分が縁談を申し込めば、彼女は受ける道しか居ないことを知っていた。
婚約破棄されたという過去は、何も悪くないレニエラに、まるで消えない黒い染みのように纏わり付いた。貴族令嬢としての普通の結婚は、もう絶望的だったはずだ。
レニエラは、何を言えば喜ぶだろうか。今まではずっと、話しかけることも出来ずに見ていただけだ。彼女はいつも、嫌な男に泣かされていた。
ずっと君に話しかけたかったけど、今まで婚約者が居たから、それは出来なくて……? そんなことを言う男は、レニエラは嫌ではないだろうか。
親に決められた女性と結婚をすることは、僕がまだ喋れなかった頃からの約束だ。それを反古にすることは僕には出来なかった。
オフィーリアとの婚約解消を匂わせた時に両親にもそう言われたし、仕事をするようになった今は自分でも納得していた。
僕一人の身勝手な感情で、それまでに様々な場所で決まっていた何もかもを、すべて捨ててしまう訳にはいかない。誰にどんな不利益が被るか、全く想像もつかない。
……僕も本当に、君に会えて嬉しい。
顔合わせとして初めて間近で見たレニエラは、想像していた以上に可愛らしかった。
僕はレニエラを知っているが、レニエラは僕を知らない。ここは完全に初対面なのだから、何かしら褒め言葉をまず言うべきなんだろうと思った。
いつもなら特に何も考えずに、定番の褒め言葉に相手に合わせたお世辞が出て来るはずの口は、初恋の人に縁談を申し込んだという夢のような状況への緊張からか上手く動かない。
このままでは、変に思われてしまうと思えば思うほどに、言葉は出て来ない。
二人きりになっても言葉少なな僕に、レニエラは不思議そうな表情だった。
本来なら、この会話の主導権は僕が握るべきだ。彼女が結婚を望んだ訳でもない。
それに、ずるい僕は自分が縁談を申し込めば、彼女は受ける道しか居ないことを知っていた。
婚約破棄されたという過去は、何も悪くないレニエラに、まるで消えない黒い染みのように纏わり付いた。貴族令嬢としての普通の結婚は、もう絶望的だったはずだ。
レニエラは、何を言えば喜ぶだろうか。今まではずっと、話しかけることも出来ずに見ていただけだ。彼女はいつも、嫌な男に泣かされていた。
ずっと君に話しかけたかったけど、今まで婚約者が居たから、それは出来なくて……? そんなことを言う男は、レニエラは嫌ではないだろうか。
親に決められた女性と結婚をすることは、僕がまだ喋れなかった頃からの約束だ。それを反古にすることは僕には出来なかった。
オフィーリアとの婚約解消を匂わせた時に両親にもそう言われたし、仕事をするようになった今は自分でも納得していた。
僕一人の身勝手な感情で、それまでに様々な場所で決まっていた何もかもを、すべて捨ててしまう訳にはいかない。誰にどんな不利益が被るか、全く想像もつかない。