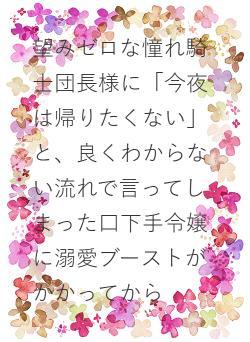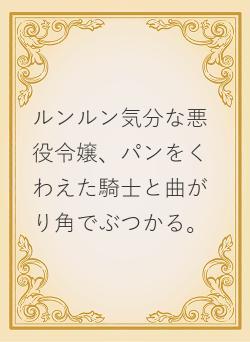「……いえ。それには、少し誤解があるようです。僕はレニエラ嬢が良いと思って、こうして貴女にヘイズ公爵夫人を通じて縁談を申し込んだので」
自分が曰く付きであることを十二分に理解している私は、追い詰められ切羽詰まった男性の耳障りの良い言葉になんて、絶対騙されたりしない。
「あの……叔母も貴方のことを、とても気に入っているようです。私からは断れません。貴方だって私のように、割り切った結婚相手の方が楽なはずです! お互いにここは逃げられないと思いますので、とりあえずここは、私たち結婚しましょう?」
ジョサイアは何故か空を見上げて、大きくため息をついた。
言い方が良くなかったかしら。けれど、彼は私の申し出に、不満なんてありえないはずだけど。
「僕の求婚をお受け下さり、本当にありがとうございます。君の希望は理解しましたから、とりあえずは、そういう事で。僕と結婚しましょう。レニエラ。よろしくお願いします」
私に向き直り真剣な表情のジョサイアは、この契約結婚に頷いてくれた。彼は右手を差し出したので、私が出した結婚に関する契約条件を飲んでくれたのだとちゃんと理解した。
満足して私も彼の大きな手を握り、にっこりと微笑んだ。
なんだか、それは結婚相手というか、これから大きな困難を抜けるための、戦友同士がするような握手だった。
自分が曰く付きであることを十二分に理解している私は、追い詰められ切羽詰まった男性の耳障りの良い言葉になんて、絶対騙されたりしない。
「あの……叔母も貴方のことを、とても気に入っているようです。私からは断れません。貴方だって私のように、割り切った結婚相手の方が楽なはずです! お互いにここは逃げられないと思いますので、とりあえずここは、私たち結婚しましょう?」
ジョサイアは何故か空を見上げて、大きくため息をついた。
言い方が良くなかったかしら。けれど、彼は私の申し出に、不満なんてありえないはずだけど。
「僕の求婚をお受け下さり、本当にありがとうございます。君の希望は理解しましたから、とりあえずは、そういう事で。僕と結婚しましょう。レニエラ。よろしくお願いします」
私に向き直り真剣な表情のジョサイアは、この契約結婚に頷いてくれた。彼は右手を差し出したので、私が出した結婚に関する契約条件を飲んでくれたのだとちゃんと理解した。
満足して私も彼の大きな手を握り、にっこりと微笑んだ。
なんだか、それは結婚相手というか、これから大きな困難を抜けるための、戦友同士がするような握手だった。