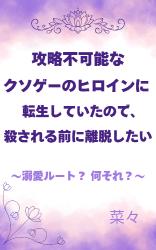「あの男の子は、ジョシュア殿下だったんですよね?」
「……なんで、知って……え?」
殿下はゴチャゴチャな頭の中を整理するかのように、右手で髪をかき上げて頭を押さえた。
今までの会話などを振り返っているのか、焦点が合っていない。
「あれが俺だと知っているのか……?」
「はい」
「そのブローチをあげたのが俺だってことも?」
「はい」
「……なら、さっき言った好きな人っていうのは……」
ジョシュア殿下がその事実に気づくまでの間、私はカタカタと震える手を必死に握りしめていた。
こんなにも緊張するのは人生で初かもしれない。
何かひどいことを言われたわけではないのに、なぜか無性に泣きたくなる。
「……ジョシュア殿下のことです。私、ジョシュア殿下が……」
あまりの緊張で言葉がうまく出てこない。
喉がカラカラに渇いていて、声すら出せないように思えてくる。
がんばるのよ、セアラ!