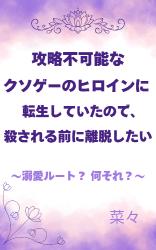セアラは俺のことを『男』ではなく『殿下は殿下だ』と言っていた。
もし俺が本気でセアラを妃候補にと言ったとしても、フレッド殿下との結婚を望む可能性が高い。
立場上仕方なく俺を選ぶかもしれないが、セアラの心にフレッド殿下と結婚したかったという思いが少しでも残っていたら、正直心穏やかではいられない。
そんな自分勝手な理由で、フレッド殿下からセアラへの面会要請はすべて断った。
会わせたくない。
ただそれだけだった。
それなのに、2人は偶然王宮で出会い、仲睦まじく話していた。
まるで俺の邪魔は2人の障害にすらならないと言われているようで、2人は運命の相手なのだと見せつけられているような気がして、ひどく落ち込んだ。
フレッド殿下から『セアラに求婚する』といった内容の手紙が届いたのは、その3日後だった。
なぜわざわざ俺にそんな報告をしてきたのかはわからないが、フレッド殿下の誠実さを見せつけられたようだった。
セアラはなんて答えるんだ?
行かないでほしい。行かせたくない。
昼間からずっと抱えていたこの思いが我慢できなくなり、俺は一度出た執務室へと引き返した。
本当は命令してでも行かせたくない。
フレッド殿下に会わせたくない。
……行かないでくれ。
しかし、こんな大事なときに限っていつものように自分の意思を無理やり押しつけることができなかった。
「冗談だ」
そうセアラにウソをついた俺は、不安と後悔で眠れぬ夜を過ごすことになった。