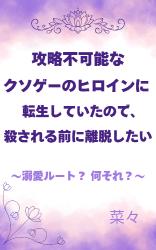「ど、どうなるか……って、どうなるっていうのよ!?」
「さあ。それは俺の口からは言えないよ」
「…………!!」
真っ青になった姉は、小さな声で「何も言わないわよ!」と言いながら姿勢を正して椅子に座り直した。
これだけ脅しておけばいいか。
遠回しに父に対しても牽制できたし。
家族に自分の恋愛事情を知られているのはなんとも居心地が悪いが、仕方ない。
特に反対されてはいないようだし、無理に他の女と婚約させられるより良かったかもしれない──そんな風に思っていた。
反対どころか、父や姉が俺のために行動してくれていたと知ったのは、セアラと姉が俺の妃候補の件で話しているのを盗み聞きしていたときだ。
あの頃の俺は、なぜ父は妃候補の中にセアラを入れなかったのかと苛立っていた。
俺の気持ちを知っているのに。
セアラなら人柄も家柄も何も問題ないはずなのに。
わざわざセアラを外した理由がわからない。
結局、父はセアラを候補者に入れていたが、セアラが勝手にその書類を抜いていただけだったというのがわかった。