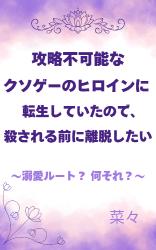もう正直に話してスッキリしたのか、さっきまで私から顔をそらしていた殿下はニヤニヤとした怪しい笑みを浮かべながら顔を近づけてきた。
殿下の腕に手を挟まれているため、離れることができない。
「俺は本当にセアラが好きなんだよ」
「…………」
綺麗な黄金の瞳に見つめられたまま言われ、体が硬直してしまう。
その目をそらすこともできず、動くこともできず、ただただ2人でしばらく見つめ合う。
「……じゃあ、行くか。いつまでもそんな格好のセアラを外に出しておきたくないし」
「…………」
声が……出ない。
何を言っているのとか、いい加減からかうのはやめてとか、いろいろ言いたいことはあるけれど、今は何も言えそうにない。
私は黙ったまま、殿下にエスコートされて会場をあとにした。