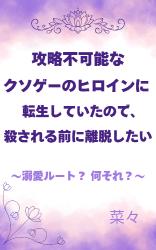「お前ってほんと変なヤツ」
「君に言われたくないよ」
「怒りながらも、次は甘くないお菓子を持ってくるって……なんでそんな発想になるのか理解できない」
「どうして? だって美味しいと思ってもらえるものを食べてほしいじゃない」
「……怒ってたら、普通はもうあげたくないとか思うものだろ」
そうなの?
男の子は私をバカにしているようでいて、どこか喜んでいるような気がした。
口元はあいかわらず笑みすらない無表情だし言い方もぶっきらぼうだけど、声が優しい。
「私はこれからも君とお菓子を食べたいよ」
「……そうかよ」
「次は甘くないお菓子を持ってくるから、一緒に食べようね」
「……ああ」
その約束を最後に、男の子は教会に来なくなった。
古い教会が壊されるまで通い続けたけど会うことはできず、約束は叶わないまま終わった。
ただ、来なかった約束の日に、いつもその男の子が座っていた椅子の上にブローチが置かれていた。
私の瞳の色──紫色の宝石がついた、可愛らしいブローチ。
手紙も何もなかったけど、あの男の子からの贈り物だと思ってる。
今も大事に持っている私の宝物だ。