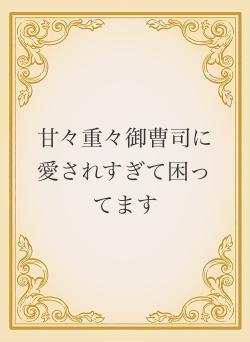神崎さんが言ったこと、間違っていない。
私は全てにおいて彼女には敵わないし、あの二人から同情で優しくしてもらっている事もわかってるつもり。身の程弁えているつもり。だからこそ、私だって努力はしてきたつもりだった。
入社して今まで、ずっと。神崎さん含め、周りから少しでも認めて貰えるようにと頑張ってきたつもりだった。課長から嫌がらせされようと、作った資料を無下にされようと、周りから浮いていると思われようと、自分なりに我慢して次に繋げようと走ってきたつもりだった。
____だけど。
さっきの神崎さんの言葉で全部無駄だったと気づいた。私なんかが頑張ったところで、マイナスがゼロになるだけ。プラスになることなんかないんだ。
視界が滲む。
神崎さんの言葉一つ一つがグサグサと心臓を突き刺して苦しい。わかっていたはずなのに、とても辛い。
「山下さん?」
優しい声。顔を見なくてもわかる、この声は間違いなく一之瀬さんだ。どうして一之瀬さんは私がこんなダメダメな姿の時にばかり現れるのだろう。
今振り向けばまた情ない顔を晒すことになる。心配をかける事になる。面倒臭いと思われてしまう。
「どうかしました?もうすぐ朝礼始まりますけど」
この場を上手くかわす方法を考えてる間にも、一之瀬さんが少しずつこちらに歩み寄って来ていることが靴の音から分かる。
どうしよう、どうしたら。
「一之瀬くん…っ!!」
私の時とは打って変わった甲高く甘い声の神崎さんの言葉が一之瀬さんを呼び止めた。