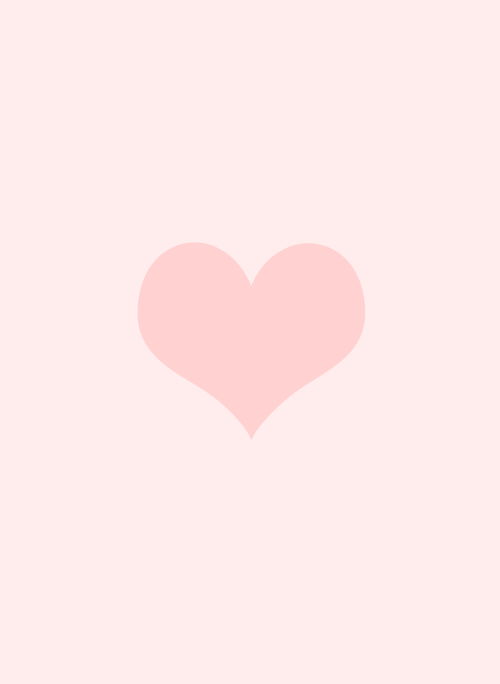「あれ、誰?」
「西野さんだよ、B組にいる双子の」
「ああー、花梨ちゃん、だっけ?」
「違う!胡桃ちゃんだ。名札見て」
「なんか花梨ちゃんと胡桃ちゃんって似てるけど、花梨ちゃんのほうが親しみやすい感じするよね」
「あ、それわかるかも」
私に聞こえていることに気がついていないのだろうか。
私より、花梨のほうが親しみやすい事なんてずっと前から知っている。
でも、改めて言われるとグサグサ胸に突き刺さってくる。
体調が悪いこともあって余計だ。
「聞かなくていい。お前はお前のままでいい」
淡々としていて、特別な優しさは感じないのに、その言葉は私の胸にストンと落ちた。
左京くんは好き勝手喋っている女子を目線でどけて私を抱えたまま進んでいった。
保健室はグラウンドから直接入れるように設計されている。
「ん、ついた」
左京くんがガラガラと保健室の扉を開けた。
私の体が保健室の固いベッドの上に下ろされる。
「……ありがとう。ごめん、重かったよね」
「別に。お前軽いから。…いいから寝てろ」
左京くんが掛け布団を肩の位置まであげてくれた。
暖かくて、そしてなぜか左京くんに安心感を覚えて、私の意識はゆっくりと落ちていった。
「西野さんだよ、B組にいる双子の」
「ああー、花梨ちゃん、だっけ?」
「違う!胡桃ちゃんだ。名札見て」
「なんか花梨ちゃんと胡桃ちゃんって似てるけど、花梨ちゃんのほうが親しみやすい感じするよね」
「あ、それわかるかも」
私に聞こえていることに気がついていないのだろうか。
私より、花梨のほうが親しみやすい事なんてずっと前から知っている。
でも、改めて言われるとグサグサ胸に突き刺さってくる。
体調が悪いこともあって余計だ。
「聞かなくていい。お前はお前のままでいい」
淡々としていて、特別な優しさは感じないのに、その言葉は私の胸にストンと落ちた。
左京くんは好き勝手喋っている女子を目線でどけて私を抱えたまま進んでいった。
保健室はグラウンドから直接入れるように設計されている。
「ん、ついた」
左京くんがガラガラと保健室の扉を開けた。
私の体が保健室の固いベッドの上に下ろされる。
「……ありがとう。ごめん、重かったよね」
「別に。お前軽いから。…いいから寝てろ」
左京くんが掛け布団を肩の位置まであげてくれた。
暖かくて、そしてなぜか左京くんに安心感を覚えて、私の意識はゆっくりと落ちていった。