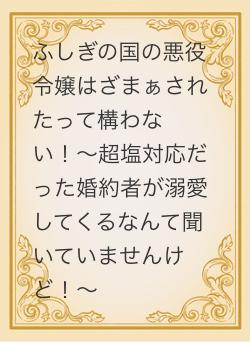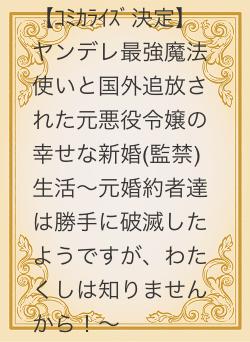今、父がキャンディスを映す瞳を見て、ずっと目を背けていた現実を知ることになる。
そこですべてを悟ったような気がした。
(ああ……わたくしはお父様にこんな目で見られていたのね)
それは血の繋がった娘を見るものではない背筋がゾッとするような冷たさだった。
まるでゴミを見るようだと思った。
そこで何かがプチリと切れたような気がした。
何のために今まで自分がやってきたのかがわからなくなってしまう。
血反吐が出るほどにがんばっても報われない理由を探していたが答えはこんなにも簡単だった。
「フフッ……アハハハッ!」
「…………」
「──アハハハハハハハハッ!」
キャンディスの笑い声が広場で響く。
目の前で父が剣を抜くのが見えた。
けれどキャンディスは笑うのを止められなかった。
銀色の光が見えた瞬間に視界が反転するとそこには血の海が広がる。
金色だったはずのペンダントはキャンディスの血に濡れて目の前で怪しく赤く光輝いている。
しかしその石も父に踏まれたことでバラバラに砕け散ってしまった。
(……このペンダントは、まるでわたくしみたい)
悲しみと絶望を抱きながらキャンディスは目を閉じた。
一筋の涙が頬に滑り落ちたような気がした。
* * *
そこですべてを悟ったような気がした。
(ああ……わたくしはお父様にこんな目で見られていたのね)
それは血の繋がった娘を見るものではない背筋がゾッとするような冷たさだった。
まるでゴミを見るようだと思った。
そこで何かがプチリと切れたような気がした。
何のために今まで自分がやってきたのかがわからなくなってしまう。
血反吐が出るほどにがんばっても報われない理由を探していたが答えはこんなにも簡単だった。
「フフッ……アハハハッ!」
「…………」
「──アハハハハハハハハッ!」
キャンディスの笑い声が広場で響く。
目の前で父が剣を抜くのが見えた。
けれどキャンディスは笑うのを止められなかった。
銀色の光が見えた瞬間に視界が反転するとそこには血の海が広がる。
金色だったはずのペンダントはキャンディスの血に濡れて目の前で怪しく赤く光輝いている。
しかしその石も父に踏まれたことでバラバラに砕け散ってしまった。
(……このペンダントは、まるでわたくしみたい)
悲しみと絶望を抱きながらキャンディスは目を閉じた。
一筋の涙が頬に滑り落ちたような気がした。
* * *