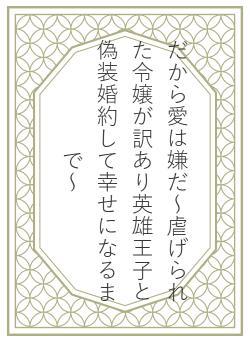お気に入りの白いワンピースを着ている私は、今日もとても可愛い。馬車に乗り込む私に護衛騎士がうっとりと見惚れている。こんなに可愛い私をエスコートできるなんて、あなたは本当に幸せ者ね。
私を乗せた馬車が向かう先は、ターチェ伯爵邸。そこにバルゴアの令息が滞在している。
お姉さまに騙されるなんて、本当に田舎者なのね。可哀想だから私が目を覚まさせてあげるわ。
馬車の窓から外を見ると、豪邸が見えた。
「わぁ、お城みたぁい」
私が住んでいる家よりもずっと大きい。私もいつかああいうお城みたいな家に住みたいわ。そんなことを考えていると、私を乗せた馬車は大きな門をくぐり、広い庭園を抜けて豪邸の前で止まった。
馬車の扉が開いて、護衛騎士がターチェ伯爵邸に着いたことを教えてくれる。
「ここが、伯爵、邸……なの?」
だって、私のお父様も同じ伯爵なのに、ターチェ家ほどの豪邸に住んでいないわ。
どうして? どうして、こんなに違いがあるの?
そう思ったとき、私はターチェ家がバルゴアと深い繋がりがあることを思い出した。
そっか、伯爵でもバルゴアと繋がっているほうが格上なのね。
今さらながらに、夜会でバルゴア令息が女性に取り囲まれていた理由がわかった。
バルゴア令息に選ばれるということは、お姫様になれるということだったんだわ。目の前にあるような豪邸に住んで、贅沢の限りを尽くせる、それがバルゴアに嫁ぐということ。
王都から遠く離れたバルゴア領になんて行きたくないけど、お姫様になれるのだったら話は別よ。
護衛騎士にエスコートされた私は、礼儀正しいメイドたちに迎え入れられた。
「こちらへどうぞ」
案内された客室は、広いけど少し地味。家具もなんだか古臭いし、飾られている絵もパッとしない。もっと煌びやかなものを想像していたからガッカリしてしまう。
でも、運ばれてきたお茶とお菓子は、とても美味しかった。
これは合格ね。
メイドも皆、従順そうだし、ここになら住んであげてもいいかも?
そんなことを考えていると、メイドが「奥様がいらっしゃいました」と告げて客室の扉を開いた。
この金髪の中年女性が、ターチェ伯爵夫人なのね。
ソファーから立ち上がると、私は満面の笑みを浮かべて挨拶をする。
「初めまして、ファルトン伯爵の娘マリンと申します」
「いらっしゃい、マリンさん。今日はどのような用件でいらしたのかしら?」
ニコリと微笑む夫人は、とても良い人そう。
「私のお姉さまがケガをして、こちらにご迷惑をおかけしていると聞きました。大変申し訳ありません」
私が悲しみの表情を浮かべながらうつむくと、夫人の視線を強く感じた。私の可憐さに見入っているのかもね。
「お姉さまに会わせていただけませんか?」
「セレナさんはケガをしているから、あまり動いてほしくないのだけど」
「でも、私、お姉さまのことが心配で……」
夫人は小さなため息をつくと、控えているメイドに声をかけた。
「セレナさんに来てもらって」
メイドがお姉さまを呼びに行っている間、夫人は私にソファーに座るように勧めてくれた。でも、特に話しかけてくる様子はない。仕方がないから、私から声をかけた。
「お茶とお菓子、とっても美味しかったです」
「そう」
せっかく私が話題をふってあげたのに、もう終わってしまった。
なんなの、この人? 良い人そうと思ったけど感じ悪い。
夫人は穏やかな微笑みを湛えたまま、扇を広げると口元を隠した。
「そういえば、マリンさん。何か誤解があるようだけど、セレナさんに迷惑をかけているのは私達のほうなの。手紙にその旨を書いたけど、あなたにはきちんと伝わっていないようね?」
そんなことを言われても、お父様がそう言っていたのだから知らないわ。
私があいまいな返事をすると、夫人はさらに言葉を続ける。
「それに心配だという割には、セレナさんがどれくらいのケガをしたのかも聞かないのね」
この人、何が言いたいの?
私を見つめる夫人の瞳はとても冷ややかだった。それはまるで、私のお母様が、セレナお姉さまを見ているときのような目で、背筋がゾクッと寒くなる。
メイドが「セレナお嬢様がいらっしゃいました」と告げて扉を開けた。
さすがお姉さま! すごく良いタイミングだわ。
ソファーから立ち上がった私が「お姉さま」と呼びかけたけど、そこには私のお姉さまはいなかった。
代わりに背が高くガッチリとした体格の男性が、ケガした女をお姫様だっこしている。男性のほうはバルゴア令息ね。女のほうは、うつむいているので顔がよく見えない。
夫人が「リオまで来たの?」と言ったので、令息の名前がリオ様だとわかった。
改めて見るリオ様の顔は、悪くはないけどパッとしない。なんというか、普通? これなら、ベイリー公爵家の次男クルト様のほうが何倍も素敵だわ。
でも、リオ様はお金持ちのバルゴアだから、それだけで価値があるのよね。お父様も仲良くしろって言ってたし。
それにしても、お姫様抱っこされている女はだれ? 私とワンピースの色がかぶっているのが許せないんだけど?
お姫様だっこされている女がチラリとこちらを見た。
「お、姉さま?」
その顔は確かにお姉さまだった。頬を赤く染めたお姉さまは、恥ずかしそうにうつむいている。
「リ、リオ様、下ろしてください」
「あなたの靴がないから下ろせません」
「でも……皆、こちらを見てます……」
リオ様は、お姉さまを抱きかかえたままソファーに座った。下ろしてもらえると思ったお姉さまの顔に一瞬笑みが浮かんだけど、ソファーではなくリオ様の膝の上に座らされ、赤かった顔が今度は青くなっていく。
リオ様がお姉さまに向ける瞳は、とても温かかった。優しく頭を撫でられたお姉さまは、なぜか文句を言いたそうな顔でリオ様をにらみつけている。
そんな二人を見た夫人が「……リオ、あとで話があります」と冷たい視線を送った。でも、夫人はお姉さまには「本当にうちの甥(おい)がごめんなさいね」と申し訳なさそうに謝っている。
……こんなのおかしいわ。
だって、皆に愛されるのは私で、冷たい視線を向けられるのがお姉さまの役目なのに。
だから、リオ様にお姫様抱っこされるのも私だし、優しく頭を撫でてもらうのも私じゃないとダメなのに……?
「お、お姉さま?」
何してるのよ!? 早くいつもみたいに私をいじめなさいよ!
どうしてお姉さまは、こんなに役立たずなの!?
またお父様に言って、食事を抜いてもらわないと。
「マリン」
お姉さまに名前を呼ばれて、私はハッと我に返った。
「私、もうあの家には帰らないわ」
淡々とした言葉に、私は喜んだ。やっぱりお姉さまは、私をいじめる悪役じゃないとね。
「そんなっお姉さま、どうしてそんなにひどいことを言うのですか!?」
こう言えば、いつも周りの人たちは、お姉さまをにらんで私を可哀想だと思ってくれる。
チラリとリオ様を見ると、お姉さましか見ていなかった。夫人は私を見て眉をひそめている。
「リオ、今の言葉、ひどいかしら?」
「さぁ?」
パチンと扇を閉じた夫人は、「マリンさん。あなた、何一つセレナさんのことを聞かないのね」とあきれたように言う。
「ケガの具合も、どうして家に帰りたくないのかも、何も聞かない。あなたを見ていると、セレナさんのことなんてどうでも良いように見えるわ」
「そんなこと、ないです……」
ウソだった。だって、お姉さまのことなんかどうでも良いもの。それより、どうして私が責められないといけないの!?
「セレナさんは、ケガが治るまでターチェ家で預かります」
「だったら、私もお姉さまの側にいさせてください!」
「なんのために?」
夫人の問いに私は答えられなかった。
「良かった。マリンさんまでセレナさんの世話をすると言いだすのかと思ったわ。セレナさんに付きまとうのはリオだけで十分よ」
ため息をついた夫人に、リオ様は「付きまとっていませんよ、お世話しているんです」と不服そうだ。
「そのお世話の仕方に問題があります!」
ピシャと怒鳴られて、リオ様は大きな体をビクッとふるわせた。それを見てクスッと微笑むお姉さま。
なにその笑顔? 私のことを見下してバカにしてるの!?
でもバカにされても仕方ないわ。だって、この部屋の中では、誰も私を見てくれない。部屋の隅に控えているメイドですら、私を見ていない。
お姉さまが自分の役目を果たさないから……。
私は両手を握りしめるとソファーから立ち上がった。ようやくリオ様が私を見た。でも、その視線はすぐにお姉さまに戻される。
「……私はこれで失礼します」
なんとかお辞儀をすると、私は部屋から飛び出した。誰も追いかけて来てくれない。扉の前で控えていた護衛騎士だけが「どうしましたか、マリンお嬢様!?」と聞いてくれた。
でも、こんな格下に心配されても少しも嬉しくない。
私は差し出された護衛騎士の手を、怒りに任せて叩き落とした。
ケガをしただけでお姉さまは、あのバルゴアのリオ様と、この豪邸に住んでいるターチェ夫人に心配してもらえるのに!
だったら私もケガをすればいいの!? でも痛いのは嫌。
帰りの馬車の中で、私の気分は最悪だった。
馬車がファルトン邸に着くと、一人のメイドが駆け寄ってきた。馬車に乗っていたのが私だとわかると、メイドが目に見えて肩を落とす。
たしかこのメイド、セレナお姉さまの専属メイドだわ。パサパサの茶色い髪を三つ編みにしている姿が平民らしく貧乏くさい。お姉さまにお似合いのメイド。
夜会からお姉さまが帰ってこないから心配しているのね。
「あ、そうだわ」
良いことを思いついた私は、お姉さまのメイドに手招きをする。
戸惑いながら近づいてきたメイドに、お姉さまがケガをしてターチェ伯爵家に迷惑をかけていることを教えてあげた。
驚くメイドに私は「お姉さまのお世話をしにいってくれる?」とお願いする。
「もちろんです!」
「付いてきて。すごく良いものがあるの」
メイドを私の部屋に招き入れ、私はガラスの小瓶に入った特別な薬を手渡した。
これは願いが叶う魔法の薬。この薬でお父様も幸せを手に入れたんだって。お父様はカギがかかった小箱にこの薬を大切に保管していたけど、お父様がいないときに、私がこっそりすり替えたの。
だって、私も幸せになりたいもの。
「とても高価なお薬よ。ケガを早く治すために、セレナお姉さまの食事に、毎日一滴ずついれてね」
そうすれば、リオ様にお姫様抱っこされるのも、ターチェ伯爵夫人に心配されるのも私になる。
ほらね、これで皆、幸せでしょう?
私を乗せた馬車が向かう先は、ターチェ伯爵邸。そこにバルゴアの令息が滞在している。
お姉さまに騙されるなんて、本当に田舎者なのね。可哀想だから私が目を覚まさせてあげるわ。
馬車の窓から外を見ると、豪邸が見えた。
「わぁ、お城みたぁい」
私が住んでいる家よりもずっと大きい。私もいつかああいうお城みたいな家に住みたいわ。そんなことを考えていると、私を乗せた馬車は大きな門をくぐり、広い庭園を抜けて豪邸の前で止まった。
馬車の扉が開いて、護衛騎士がターチェ伯爵邸に着いたことを教えてくれる。
「ここが、伯爵、邸……なの?」
だって、私のお父様も同じ伯爵なのに、ターチェ家ほどの豪邸に住んでいないわ。
どうして? どうして、こんなに違いがあるの?
そう思ったとき、私はターチェ家がバルゴアと深い繋がりがあることを思い出した。
そっか、伯爵でもバルゴアと繋がっているほうが格上なのね。
今さらながらに、夜会でバルゴア令息が女性に取り囲まれていた理由がわかった。
バルゴア令息に選ばれるということは、お姫様になれるということだったんだわ。目の前にあるような豪邸に住んで、贅沢の限りを尽くせる、それがバルゴアに嫁ぐということ。
王都から遠く離れたバルゴア領になんて行きたくないけど、お姫様になれるのだったら話は別よ。
護衛騎士にエスコートされた私は、礼儀正しいメイドたちに迎え入れられた。
「こちらへどうぞ」
案内された客室は、広いけど少し地味。家具もなんだか古臭いし、飾られている絵もパッとしない。もっと煌びやかなものを想像していたからガッカリしてしまう。
でも、運ばれてきたお茶とお菓子は、とても美味しかった。
これは合格ね。
メイドも皆、従順そうだし、ここになら住んであげてもいいかも?
そんなことを考えていると、メイドが「奥様がいらっしゃいました」と告げて客室の扉を開いた。
この金髪の中年女性が、ターチェ伯爵夫人なのね。
ソファーから立ち上がると、私は満面の笑みを浮かべて挨拶をする。
「初めまして、ファルトン伯爵の娘マリンと申します」
「いらっしゃい、マリンさん。今日はどのような用件でいらしたのかしら?」
ニコリと微笑む夫人は、とても良い人そう。
「私のお姉さまがケガをして、こちらにご迷惑をおかけしていると聞きました。大変申し訳ありません」
私が悲しみの表情を浮かべながらうつむくと、夫人の視線を強く感じた。私の可憐さに見入っているのかもね。
「お姉さまに会わせていただけませんか?」
「セレナさんはケガをしているから、あまり動いてほしくないのだけど」
「でも、私、お姉さまのことが心配で……」
夫人は小さなため息をつくと、控えているメイドに声をかけた。
「セレナさんに来てもらって」
メイドがお姉さまを呼びに行っている間、夫人は私にソファーに座るように勧めてくれた。でも、特に話しかけてくる様子はない。仕方がないから、私から声をかけた。
「お茶とお菓子、とっても美味しかったです」
「そう」
せっかく私が話題をふってあげたのに、もう終わってしまった。
なんなの、この人? 良い人そうと思ったけど感じ悪い。
夫人は穏やかな微笑みを湛えたまま、扇を広げると口元を隠した。
「そういえば、マリンさん。何か誤解があるようだけど、セレナさんに迷惑をかけているのは私達のほうなの。手紙にその旨を書いたけど、あなたにはきちんと伝わっていないようね?」
そんなことを言われても、お父様がそう言っていたのだから知らないわ。
私があいまいな返事をすると、夫人はさらに言葉を続ける。
「それに心配だという割には、セレナさんがどれくらいのケガをしたのかも聞かないのね」
この人、何が言いたいの?
私を見つめる夫人の瞳はとても冷ややかだった。それはまるで、私のお母様が、セレナお姉さまを見ているときのような目で、背筋がゾクッと寒くなる。
メイドが「セレナお嬢様がいらっしゃいました」と告げて扉を開けた。
さすがお姉さま! すごく良いタイミングだわ。
ソファーから立ち上がった私が「お姉さま」と呼びかけたけど、そこには私のお姉さまはいなかった。
代わりに背が高くガッチリとした体格の男性が、ケガした女をお姫様だっこしている。男性のほうはバルゴア令息ね。女のほうは、うつむいているので顔がよく見えない。
夫人が「リオまで来たの?」と言ったので、令息の名前がリオ様だとわかった。
改めて見るリオ様の顔は、悪くはないけどパッとしない。なんというか、普通? これなら、ベイリー公爵家の次男クルト様のほうが何倍も素敵だわ。
でも、リオ様はお金持ちのバルゴアだから、それだけで価値があるのよね。お父様も仲良くしろって言ってたし。
それにしても、お姫様抱っこされている女はだれ? 私とワンピースの色がかぶっているのが許せないんだけど?
お姫様だっこされている女がチラリとこちらを見た。
「お、姉さま?」
その顔は確かにお姉さまだった。頬を赤く染めたお姉さまは、恥ずかしそうにうつむいている。
「リ、リオ様、下ろしてください」
「あなたの靴がないから下ろせません」
「でも……皆、こちらを見てます……」
リオ様は、お姉さまを抱きかかえたままソファーに座った。下ろしてもらえると思ったお姉さまの顔に一瞬笑みが浮かんだけど、ソファーではなくリオ様の膝の上に座らされ、赤かった顔が今度は青くなっていく。
リオ様がお姉さまに向ける瞳は、とても温かかった。優しく頭を撫でられたお姉さまは、なぜか文句を言いたそうな顔でリオ様をにらみつけている。
そんな二人を見た夫人が「……リオ、あとで話があります」と冷たい視線を送った。でも、夫人はお姉さまには「本当にうちの甥(おい)がごめんなさいね」と申し訳なさそうに謝っている。
……こんなのおかしいわ。
だって、皆に愛されるのは私で、冷たい視線を向けられるのがお姉さまの役目なのに。
だから、リオ様にお姫様抱っこされるのも私だし、優しく頭を撫でてもらうのも私じゃないとダメなのに……?
「お、お姉さま?」
何してるのよ!? 早くいつもみたいに私をいじめなさいよ!
どうしてお姉さまは、こんなに役立たずなの!?
またお父様に言って、食事を抜いてもらわないと。
「マリン」
お姉さまに名前を呼ばれて、私はハッと我に返った。
「私、もうあの家には帰らないわ」
淡々とした言葉に、私は喜んだ。やっぱりお姉さまは、私をいじめる悪役じゃないとね。
「そんなっお姉さま、どうしてそんなにひどいことを言うのですか!?」
こう言えば、いつも周りの人たちは、お姉さまをにらんで私を可哀想だと思ってくれる。
チラリとリオ様を見ると、お姉さましか見ていなかった。夫人は私を見て眉をひそめている。
「リオ、今の言葉、ひどいかしら?」
「さぁ?」
パチンと扇を閉じた夫人は、「マリンさん。あなた、何一つセレナさんのことを聞かないのね」とあきれたように言う。
「ケガの具合も、どうして家に帰りたくないのかも、何も聞かない。あなたを見ていると、セレナさんのことなんてどうでも良いように見えるわ」
「そんなこと、ないです……」
ウソだった。だって、お姉さまのことなんかどうでも良いもの。それより、どうして私が責められないといけないの!?
「セレナさんは、ケガが治るまでターチェ家で預かります」
「だったら、私もお姉さまの側にいさせてください!」
「なんのために?」
夫人の問いに私は答えられなかった。
「良かった。マリンさんまでセレナさんの世話をすると言いだすのかと思ったわ。セレナさんに付きまとうのはリオだけで十分よ」
ため息をついた夫人に、リオ様は「付きまとっていませんよ、お世話しているんです」と不服そうだ。
「そのお世話の仕方に問題があります!」
ピシャと怒鳴られて、リオ様は大きな体をビクッとふるわせた。それを見てクスッと微笑むお姉さま。
なにその笑顔? 私のことを見下してバカにしてるの!?
でもバカにされても仕方ないわ。だって、この部屋の中では、誰も私を見てくれない。部屋の隅に控えているメイドですら、私を見ていない。
お姉さまが自分の役目を果たさないから……。
私は両手を握りしめるとソファーから立ち上がった。ようやくリオ様が私を見た。でも、その視線はすぐにお姉さまに戻される。
「……私はこれで失礼します」
なんとかお辞儀をすると、私は部屋から飛び出した。誰も追いかけて来てくれない。扉の前で控えていた護衛騎士だけが「どうしましたか、マリンお嬢様!?」と聞いてくれた。
でも、こんな格下に心配されても少しも嬉しくない。
私は差し出された護衛騎士の手を、怒りに任せて叩き落とした。
ケガをしただけでお姉さまは、あのバルゴアのリオ様と、この豪邸に住んでいるターチェ夫人に心配してもらえるのに!
だったら私もケガをすればいいの!? でも痛いのは嫌。
帰りの馬車の中で、私の気分は最悪だった。
馬車がファルトン邸に着くと、一人のメイドが駆け寄ってきた。馬車に乗っていたのが私だとわかると、メイドが目に見えて肩を落とす。
たしかこのメイド、セレナお姉さまの専属メイドだわ。パサパサの茶色い髪を三つ編みにしている姿が平民らしく貧乏くさい。お姉さまにお似合いのメイド。
夜会からお姉さまが帰ってこないから心配しているのね。
「あ、そうだわ」
良いことを思いついた私は、お姉さまのメイドに手招きをする。
戸惑いながら近づいてきたメイドに、お姉さまがケガをしてターチェ伯爵家に迷惑をかけていることを教えてあげた。
驚くメイドに私は「お姉さまのお世話をしにいってくれる?」とお願いする。
「もちろんです!」
「付いてきて。すごく良いものがあるの」
メイドを私の部屋に招き入れ、私はガラスの小瓶に入った特別な薬を手渡した。
これは願いが叶う魔法の薬。この薬でお父様も幸せを手に入れたんだって。お父様はカギがかかった小箱にこの薬を大切に保管していたけど、お父様がいないときに、私がこっそりすり替えたの。
だって、私も幸せになりたいもの。
「とても高価なお薬よ。ケガを早く治すために、セレナお姉さまの食事に、毎日一滴ずついれてね」
そうすれば、リオ様にお姫様抱っこされるのも、ターチェ伯爵夫人に心配されるのも私になる。
ほらね、これで皆、幸せでしょう?