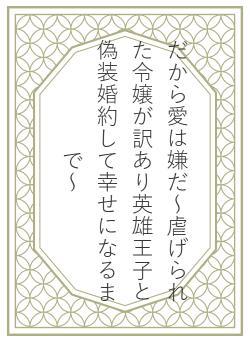抱きかかえているセレナ嬢から、俺への警戒心がフッと消えた。
それまで強張っていた身体からも、いつの間にか力が抜けたようだ。
今までの生活がつらいものだったので、セレナ嬢が他人を警戒するのは仕方がない。
この警戒心の強さ……どこかで見たような?
考えた末に、俺は数年前に山で出会った手負いの山猫を思い出した。手当してやろうと俺が近づくと毛を逆立てて「シャー!」と威嚇してくる。うかつに手を出せば鋭い爪で引っ掻かれそうだった。
仕方がないので、俺は山猫の側でしばらくじっとしていた。俺に敵意がないことをわかってもらうには、そうするしかない。俺への警戒心が少し薄れたころに、持っていた干し肉を小さくちぎって山猫の近くに置いた。
警戒しながらクンクンと匂いを嗅いている間、俺はしらんぷりをする。俺のほうをチラチラと見て警戒しながらも、よっぽど腹が減っていたのか山猫は干し肉にかぶりついた。
そのあと、もっと干し肉をよこせと言わんばかりに、山猫はジッと俺に視線を送ってきた。
あのときに感じた『よし!』という手ごたえを、俺は今セレナ嬢に感じている。
ひとまず俺がセレナ嬢への敵意を持っていないことは伝わったようだな。
この庭園を気に入ったのか、セレナ嬢が花を見つめる表情は、それまでと違いとても穏やかだった。つい先ほどまでは、それこそ毛を逆立てて威嚇する山猫のようだったのに。
警戒心を解いてもらえたことがとても嬉しい。
庭園の散歩を終えて、部屋に戻ると俺はセレナ嬢を慎重にソファーの上に下ろした。その際に少しうつむきながらだったけど「ありがとうございます」とお礼を言ってくれた。
「その……私、重くなかったですか?」
「正直に言うと軽すぎて驚きました。あなたはもっと食べたほうが良いですよ」
ケガをさせてしまったという罪悪感と共に、セレナ嬢にしっかり食べさせなければという謎の使命感も湧いてくる。
散歩を終えたあとも、俺はセレナ嬢の側にいた。
バルゴア領では、やることが多いけど、ここでは嫁探し以外することがない。朝晩の鍛錬は、バルゴアから付いてきた護衛騎士のエディと欠かさずやっている。ようするに、朝と夜に鍛錬すること以外、やることがなくて暇だった。
始めは部屋から出ていかない俺に迷惑そうな視線を向けていたセレナ嬢も、昼になるころには俺がいることに慣れたようだ。
そういうところも、あのときの山猫に似ている。
セレナ嬢は、食べることが好きなようで、運ばれてきた昼食に瞳をキラキラと輝かせた。
昼食のメニューは鶏(とり)の蒸し煮、パンにサラダだ。俺が鶏の蒸し煮を切り分けると、セレナ嬢はフォークを寄こせと無言で手を差し出す。
そこには『絶対に自分で食べます。あなたに食べさせてなんかもらいません』という強い意志を感じた。そういう簡単に人を頼らないところも山猫っぽい。
ペロリと昼食を平らげたセレナ嬢の前に、デザートが運ばれてきた。きょとんとしたセレナ嬢は、俺に視線を寄こす。
その顔には『これも食べていいの?』と書かれていた。
俺はデザートのワッフルをナイフとフォークで切り分けた。ワッフルには、はちみつがたっぷりとかけられてしたたっている。
セレナ嬢の顔がパァと明るくなった。この瞬間、セレナ嬢の目にはワッフルしか映っていなかったんだろうな。
俺からフォークを受け取ることを忘れて、そのままパクリとかぶりついた。そうとうおいしかったようで、瞳を輝かせながら「んー!」と幸せそうな声を漏らす。
「久しぶりに食べました! すごく美味しいです」
「好きなんですか?」
「はい、母がいたころはよく一緒に食べていました」
「もっと食べますか?」
「はい!」
元気にお返事したセレナ嬢の口元にフォークで刺したワッフルを近づけると、あーんと口を開けたあと、ハッと顔を強張らせた。
俺に食べさせてもらっていることに、気がついてしまったようだ。
「……自分で食べます」
そういったセレナ嬢の声は冷たい。でもその顔は、真っ赤に染まっていた。
俺はなぜか急にセレナ嬢の頭を『よーしよしよし』と撫でたくなった。なんだ、この気持ちは。
フォークを受け取ったセレナ嬢は、ワッフルを食べながら「んー!」とまた幸せそうな声を出している。
撫でたい。よし撫でよう!
セレナ嬢の白に近い金髪は、とてもサラサラしていて心地いい。大きく見開かれた水色の瞳は、美しい湖面を思い出させる。
フルフルと肩をふるわせたかと思うと『シャー!』と威嚇するように怒られてしまった。
「失礼にもほどがあります!」
そういえば、俺の妹も頭を撫でられるのを嫌がっていたな。『子ども扱いしないでよ! もうっ! 髪が乱れるじゃない!』って言ってたっけ。
部屋から追い出されてしまうかも? と思ったけど、セレナ嬢は「……でも、リオ様が食べる手助けをしてくださっていることには感謝しています」と不服そうにお礼を言う。
「ふ、はは」
「どうして笑うのですか!?」
「いや、すみません」
こんなに綺麗で可愛い山猫を俺は見たことがない。俺以外には、まだ少し警戒しているところも愛らしい。
甘いものが好きなようだから、今度、王都で有名な菓子でも調べて買ってこようかな?
そうしたら、また幸せそうに「んー!」と言ってくれるかもしれない。
そんな楽しいことを考えていると、セレナ嬢の部屋に叔母さんがやってきた。
俺がいるのを見て「いないと思ったらここにいたの?」と驚いている。
「リオ、あんたセレナさんに迷惑かけていないでしょうね?」
「もちろんですよ」
「部屋で二人きりになっていないわよね? 未婚女性にそんな失礼なことをしていたら、いくら可愛い甥(おい)でも叩くわよ」
ギロリとにらみつけられて、俺は視線をそらした。やばい、そこまで考えていなかった。今度からはメイドに同席してもらおう。
叔母さんに「大丈夫?」と聞かれたセレナ嬢は「はい」とうなずく。
「ならいいけど……」
納得したような、していないような表情を浮かべた叔母さんは、セレナ嬢に一通の手紙を見せた。
「ファルトン家からよ。あなたを迎えに来たいと書いてあったわ」
とたんにセレナ嬢の顔が曇る。
「あの家には、戻りたくありません」
「そうよね。断っておくわ」
急に窓の外が騒がしくなった。
窓から騒ぎのほうをのぞくと、邸宅の前に馬車が一台止まっている。馬車の後ろには白馬に乗った騎士の姿も見えた。
あの顔、どこかで見たような?
騎士は、馬から降りると馬車の扉を開けた。そこから金髪の小柄な令嬢が下りてくる。
それと同時にメイド長が部屋に駆け込んできた。
「奥様、ファルトン伯爵家のご令嬢がいらっしゃいました」
「まぁ、断る前に来てしまったの!?」
セレナ嬢の顔からサッと血の気が引いた。
「マリン……」
そうつぶやいた声はふるえていた。
それまで強張っていた身体からも、いつの間にか力が抜けたようだ。
今までの生活がつらいものだったので、セレナ嬢が他人を警戒するのは仕方がない。
この警戒心の強さ……どこかで見たような?
考えた末に、俺は数年前に山で出会った手負いの山猫を思い出した。手当してやろうと俺が近づくと毛を逆立てて「シャー!」と威嚇してくる。うかつに手を出せば鋭い爪で引っ掻かれそうだった。
仕方がないので、俺は山猫の側でしばらくじっとしていた。俺に敵意がないことをわかってもらうには、そうするしかない。俺への警戒心が少し薄れたころに、持っていた干し肉を小さくちぎって山猫の近くに置いた。
警戒しながらクンクンと匂いを嗅いている間、俺はしらんぷりをする。俺のほうをチラチラと見て警戒しながらも、よっぽど腹が減っていたのか山猫は干し肉にかぶりついた。
そのあと、もっと干し肉をよこせと言わんばかりに、山猫はジッと俺に視線を送ってきた。
あのときに感じた『よし!』という手ごたえを、俺は今セレナ嬢に感じている。
ひとまず俺がセレナ嬢への敵意を持っていないことは伝わったようだな。
この庭園を気に入ったのか、セレナ嬢が花を見つめる表情は、それまでと違いとても穏やかだった。つい先ほどまでは、それこそ毛を逆立てて威嚇する山猫のようだったのに。
警戒心を解いてもらえたことがとても嬉しい。
庭園の散歩を終えて、部屋に戻ると俺はセレナ嬢を慎重にソファーの上に下ろした。その際に少しうつむきながらだったけど「ありがとうございます」とお礼を言ってくれた。
「その……私、重くなかったですか?」
「正直に言うと軽すぎて驚きました。あなたはもっと食べたほうが良いですよ」
ケガをさせてしまったという罪悪感と共に、セレナ嬢にしっかり食べさせなければという謎の使命感も湧いてくる。
散歩を終えたあとも、俺はセレナ嬢の側にいた。
バルゴア領では、やることが多いけど、ここでは嫁探し以外することがない。朝晩の鍛錬は、バルゴアから付いてきた護衛騎士のエディと欠かさずやっている。ようするに、朝と夜に鍛錬すること以外、やることがなくて暇だった。
始めは部屋から出ていかない俺に迷惑そうな視線を向けていたセレナ嬢も、昼になるころには俺がいることに慣れたようだ。
そういうところも、あのときの山猫に似ている。
セレナ嬢は、食べることが好きなようで、運ばれてきた昼食に瞳をキラキラと輝かせた。
昼食のメニューは鶏(とり)の蒸し煮、パンにサラダだ。俺が鶏の蒸し煮を切り分けると、セレナ嬢はフォークを寄こせと無言で手を差し出す。
そこには『絶対に自分で食べます。あなたに食べさせてなんかもらいません』という強い意志を感じた。そういう簡単に人を頼らないところも山猫っぽい。
ペロリと昼食を平らげたセレナ嬢の前に、デザートが運ばれてきた。きょとんとしたセレナ嬢は、俺に視線を寄こす。
その顔には『これも食べていいの?』と書かれていた。
俺はデザートのワッフルをナイフとフォークで切り分けた。ワッフルには、はちみつがたっぷりとかけられてしたたっている。
セレナ嬢の顔がパァと明るくなった。この瞬間、セレナ嬢の目にはワッフルしか映っていなかったんだろうな。
俺からフォークを受け取ることを忘れて、そのままパクリとかぶりついた。そうとうおいしかったようで、瞳を輝かせながら「んー!」と幸せそうな声を漏らす。
「久しぶりに食べました! すごく美味しいです」
「好きなんですか?」
「はい、母がいたころはよく一緒に食べていました」
「もっと食べますか?」
「はい!」
元気にお返事したセレナ嬢の口元にフォークで刺したワッフルを近づけると、あーんと口を開けたあと、ハッと顔を強張らせた。
俺に食べさせてもらっていることに、気がついてしまったようだ。
「……自分で食べます」
そういったセレナ嬢の声は冷たい。でもその顔は、真っ赤に染まっていた。
俺はなぜか急にセレナ嬢の頭を『よーしよしよし』と撫でたくなった。なんだ、この気持ちは。
フォークを受け取ったセレナ嬢は、ワッフルを食べながら「んー!」とまた幸せそうな声を出している。
撫でたい。よし撫でよう!
セレナ嬢の白に近い金髪は、とてもサラサラしていて心地いい。大きく見開かれた水色の瞳は、美しい湖面を思い出させる。
フルフルと肩をふるわせたかと思うと『シャー!』と威嚇するように怒られてしまった。
「失礼にもほどがあります!」
そういえば、俺の妹も頭を撫でられるのを嫌がっていたな。『子ども扱いしないでよ! もうっ! 髪が乱れるじゃない!』って言ってたっけ。
部屋から追い出されてしまうかも? と思ったけど、セレナ嬢は「……でも、リオ様が食べる手助けをしてくださっていることには感謝しています」と不服そうにお礼を言う。
「ふ、はは」
「どうして笑うのですか!?」
「いや、すみません」
こんなに綺麗で可愛い山猫を俺は見たことがない。俺以外には、まだ少し警戒しているところも愛らしい。
甘いものが好きなようだから、今度、王都で有名な菓子でも調べて買ってこようかな?
そうしたら、また幸せそうに「んー!」と言ってくれるかもしれない。
そんな楽しいことを考えていると、セレナ嬢の部屋に叔母さんがやってきた。
俺がいるのを見て「いないと思ったらここにいたの?」と驚いている。
「リオ、あんたセレナさんに迷惑かけていないでしょうね?」
「もちろんですよ」
「部屋で二人きりになっていないわよね? 未婚女性にそんな失礼なことをしていたら、いくら可愛い甥(おい)でも叩くわよ」
ギロリとにらみつけられて、俺は視線をそらした。やばい、そこまで考えていなかった。今度からはメイドに同席してもらおう。
叔母さんに「大丈夫?」と聞かれたセレナ嬢は「はい」とうなずく。
「ならいいけど……」
納得したような、していないような表情を浮かべた叔母さんは、セレナ嬢に一通の手紙を見せた。
「ファルトン家からよ。あなたを迎えに来たいと書いてあったわ」
とたんにセレナ嬢の顔が曇る。
「あの家には、戻りたくありません」
「そうよね。断っておくわ」
急に窓の外が騒がしくなった。
窓から騒ぎのほうをのぞくと、邸宅の前に馬車が一台止まっている。馬車の後ろには白馬に乗った騎士の姿も見えた。
あの顔、どこかで見たような?
騎士は、馬から降りると馬車の扉を開けた。そこから金髪の小柄な令嬢が下りてくる。
それと同時にメイド長が部屋に駆け込んできた。
「奥様、ファルトン伯爵家のご令嬢がいらっしゃいました」
「まぁ、断る前に来てしまったの!?」
セレナ嬢の顔からサッと血の気が引いた。
「マリン……」
そうつぶやいた声はふるえていた。