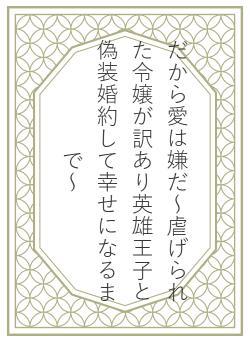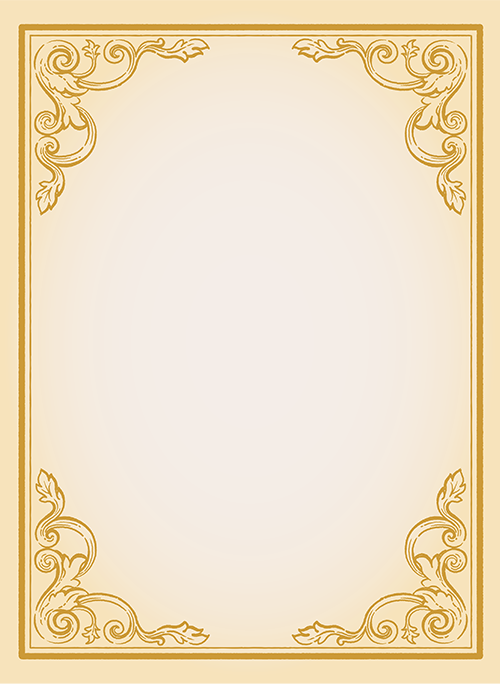目覚めると、目の前にリオ様の顔があった。
「おはよう。セレナ」
お互いの額がくっついてしまいそうなほどの距離に驚きながらも、そういえば昨晩、一緒のベッドで眠ったのよね、と思い出す。
私が起きる前からリオ様は起きていたようで、ベッドに横になっているものの眠そうな様子はない。なんとなく、このまま起きてしまうのがもったいないような気がして、私もベッドから起き上がらなかった。
「昨日は済まない」
「?」
急に謝られてもなんのことだか分からない。
「ほら、寝るまで話そうと言っていたのに、先に寝てしまったから」
「あっ、そのことですか」
昨晩は呆れてしまったけど、今はなんとも思っていない。
「リオ様ったら、ベッドに横になったとたんに寝ているんですもの。いつもそんなに寝つきがいいんですか?」
クスクスと笑いながら尋ねると「そうでもないのだが……」と戸惑う声が返ってくる。
「確かに俺は外でもどこでも寝ることができるが、近くに人がいると眠りが浅いんだ。無意識に周囲を警戒してしまうというか」
リオ様の話を聞きながら『なんだか野生動物みたいね』と思ってしまう。
「だから、まさかこんな朝までぐっすり眠れるなんて……」
「疲れていたのですね」
「いや、そうじゃなくて」
リオ様は両腕を伸ばすと、私をギュッと抱きしめた。
「セレナの側が居心地良すぎるんだ。ほら、こうしていると、もう眠くなってくる……」
「ふふっ、ではリオ様が眠れない日は、私がお役に立てますね」
心地好さそうに目を瞑るリオ様を見ていると、絶対的な信頼を寄せてもらっているようで嬉しくなる。
問題があるとすれば、私もリオ様の腕の中が心地好すぎて、眠くなってしまうこと。
まどろんでいるといつの間にか二人とも眠ってしまったようで、私達は贅沢な二度寝を楽しんだ。
*
遅めの朝食を終えたあと、リオ様と私は『これからどうするか?』ということについて話し合った。
「私達が急いでタイセン国から出る必要はなくなりましたものね……」
元はといえば、これ以上、ライラ様やディーク殿下と顔を合わせて問題を起こさないために、予定より早くバルゴア領へ帰ろうとしていた。
「俺としては、今回の件をカルロスがどう治めるのか気になっている。しばらくタイセン国に留まりたいのだが」
「アイリーン様のこともありますものね。私もしばらく滞在することに賛成です」
こちらで保護しているアイリーン様を置いて帰るわけにはいかない。それに私はまだアイリーン様との約束を果たせていない。私達は、一緒にドレスを買いに行くと約束したのだから。
でも、リオ様はアイリーン様が多くを知りすぎていて、命を狙われる可能性があると言っていた。そんなアイリーン様を王宮外に連れ出すわけにはいかない。
「リオ様、お願いがあるのですが……」
私はリオ様に、ここにタイセン国の服飾士を呼んでもらえないかと相談した。
すぐに動いてくれたリオ様は「カルロスが、王宮お抱えの服飾士を呼んでくれた。なんでも好きに作ってくれとのことだ」と言ったあとに、私の耳元で囁く。
「どうやら、ディークがアイリーン嬢に使うための資金を、全てライラ嬢に貢いでいたようだ」
「なるほど。それでアイリーン様には、何も贈っていなかったと」
『流行おくれのドレスだ。田舎者だ』とアイリーン様をバカにしていたディーク殿下こそが、アイリーン様が流行おくれのドレスを着るしかない状況に追い込んでいたなんて。
「実はカルロスから、アイリーン嬢が好きなだけドレスや宝石を見立ててやってくれと頼まれた」
「任せてください」
戸惑うアイリーン様をよそに、私とアレッタは服飾士が持って来たデザインに次々と目を通す。
「タイセン国ではこういうドレスが流行っているのね」
なんだかどれもこれもフワフワキラキラしていて、ライラ様に似合いそうなデザインばかりだった。それだけ、この国でのライラ様の影響力が大きいということ。
こういうのはアイリーン様には似合わないような気がする。
念のためにアイリーン様にデザインを見せたけど、本人も困ったように首をかしげた。
「アイリーン様は、どういう雰囲気のドレスがお好きですか?」
私がそう尋ねると、アイリーン様は頬を赤く染めてうつむく。
「わ、私なんかが似合うとは思わないのですが……。私は、その、セレナ様がお茶会で着ていたような、強くて美しい感じのドレスに憧れていて……」
「お茶会のときの?」
お茶会といえば、ライラ様主催のものにしか出席していない。あのときは、ディーク殿下を避けるためにわざと濃いメイクをして、私が持っているドレスの中で一番派手なものを着ていた。
ようするに、毒婦スタイル。
私とアレッタは顔を見合わせた。アイリーン様がまさかあの姿に憧れていたなんて!
でも、芯が強いアイリーン様は、ああいう雰囲気の格好が似合うかもしれない。
私が「アレッタ。アイリーン様にお化粧をしてくれる?」とお願いすると、アレッタは「はい!」と元気なお返事をしてから嬉しそうに化粧道具を取りに行く。
戻って来たアレッタは、ほとんど化粧をしていないアイリーン様に濃い目の化粧を施していった。
数分後。
「お嬢様……!」
アレッタが瞳を輝かせながら私を見ている。私もアイリーン様から目が離せない。
毒婦まではいかないものの、濃い目の化粧でキリッとした雰囲気が出て、アイリーン様は知的な魅力に溢れている。
「とてもお似合いですよ」
アレッタから手鏡を受け取ったアイリーン様は、恐る恐る鏡の中の自分を見たあとに、大きく目を見開いた。
「ウ、ウソ……。これが、私?」
呆然と呟くアイリーン様を見ていると、もっともっと彼女を着飾りたいという気持ちが湧きおこってくる。
それは、その場にいた全員が感じたようで、私、アレッタ、服飾士の三人の心がひとつになった瞬間だった。
王都で私のお義母様になってくれたターチェ伯爵夫人や、その家に仕えるメイド長が張り切って私を着飾ってくれた気持ちが今なら分かる。
アイリーン様は磨かれる前のダイヤの原石なのね。原石のままでも十分価値があるのに、見た目でしか判断しない者たちにはその価値が分からない。
だから、そんな愚か者たちでも理解できるように、これを磨きに磨いて、今までバカにしてきた連中を見返したい。この純度の高い輝きを見て驚くがいいわ!
そんな気持ちでいっぱいだった。
服飾士が、今のアイリーン様に似合うドレスを提案する。
「アイリーン様には濃く美しい色がお似合いになると思いますわ!」
激しく同意したアレッタも「フワフワしたものより、スッとした細身のドレスのほうがお似合いかと!」と発言する。
その勢いに押されていたアイリーン様だったけど、私が「アイリーン様の希望はどうかしら?」と尋ねるとちゃんと自分の意見も言ってくれた。
「実は……。男性のエスコートがなくても問題がないドレスを着たいのです。私はエスコートを受けることができないので……」
その発言で、ディーク殿下が今まで一度たりともアイリーン様をエスコートしたことがないのが分かった。
一体どれだけディーク殿下は、アイリーン様に恥をかかせて傷つけてきたのだろう……。
アイリーン様の発言に、服飾士も信じられないといったようにポカンと口を開けている。
「だから、私は高いヒールを履きたくありません。エスコートがないと歩くとき危ないので。長いドレスはすそを踏んでしまう可能性があります。それに、何か緊急事態が起こったとき、すぐに動けるようにしたいんです」
チラッと私を見たアイリーン様は「ドレスの下にブーツを履いていたセレナ様のように」と言って頬を赤く染める。
確かに私は、アイリーン様を追いかけたとき、ドレスの下にブーツを履いていた。でも、それは緊急事態だったからで、その恰好が通常時のものとは言えない。
服飾士も心配そうに「規則違反ではありませんが、社交界ではよく思われないかもしれませんよ?」とアイリーン様に説明している。
「大丈夫です。私は元からよく思われていないので。王宮内に友達もひとりもいません」
そう明るく答えたアイリーン様に、私の胸が苦しくなる。私はアイリーン様の手をそっと握りしめた。
「でしたら、私がアイリーン様の一人目の友達と言うことですね。嬉しいです。これから、アイリーン様の希望のドレスを皆で考えましょう。誰に何を言われても、私はあなたの味方です」
「はい!」
嬉しそうに微笑んだアイリーン様の目尻には涙が浮かんでいる。
気合の入った服飾士とアレッタが、あーでもない、こーでもないと話し合っている間に、私はアイリーン様に話しかけた。
「もし、アイリーン様さえよければ、私達と一緒にバルゴア領に来ませんか? まだ、リオ様にはお話ししていないのですが……」
アイリーン様は、ディーク殿下に変わってその仕事をこなせるくらい優秀だから、きっとリオ様も喜んでくれるはず。
大きく目を見開いたアイリーン様は、「嬉しい」と呟いたあとに、小さく首を振った。
「あ、ありがとうございます。でも、実は昨晩カルロス殿下に文官にならないかとお誘いを受けまして……。信じられないくらいの好待遇で、タゼア家の書物探しにも、全面協力してくださるとのことです」
「そうなのね。一緒にいけないのは残念だけど、アイリーン様が正当に評価されて嬉しいわ」
「はい」
心の底から嬉しそうに微笑むアイリーン様は、今まで辛い思いをした分、明るい未来が待っているのだと分かる。
「セレナ様のおかげです。本当にありがとうございました。あの、これを……」
アイリーン様は自身の首からネックレスを外して私に見せてくれた。
ネックレスの飾り部分には、フクロウの紋章が刻まれている。
「このフクロウは、タゼア家の紋章です。フクロウは夜目が効きます。その豊富な知識量で闇夜すら見渡せる家門という意味が込められているのです。セレナ様、どうぞお手を」
アイリーン様は、ネックレスをそっと私の手のひらに置く。
「私、アイリーン=タゼアは、セレナ様に生涯感謝し続けることをこの紋章に誓います。この誓いのネックレスを受け取っていただけますか?」
「いいのかしら?」
「はい、ぜひ」
ネックレスを受け取ると、アイリーン様は嬉しそうに微笑んだ。
「セレナ様。困ったことがあれば、いつでも私をお訪ねくださいね。そして、この紋章を持つ者をタゼア家が拒むことはありません。完璧とは言えませんが、それでもタゼア家の蔵書量は世界有数です。タゼア家の知識を、そして、書物をどうか存分にお役立てください」
「ありがとう。ふふっ、友達からの贈り物としていただくわ」
「友達というより、忠誠に近いですが……。そうですね、私の忠誠は新しいタイセン国王に捧げるので、セレナ様は友達として貰ってください」
明るい表情でハキハキと話すアイリーン様には、壁際でひとりうつむいていた頃の面影はない。
きっと今のアイリーン様が、本当のアイリーン様なのね。
私達は、微笑み合うと、理想のドレスを制作するために話し合いに戻っていった。
「おはよう。セレナ」
お互いの額がくっついてしまいそうなほどの距離に驚きながらも、そういえば昨晩、一緒のベッドで眠ったのよね、と思い出す。
私が起きる前からリオ様は起きていたようで、ベッドに横になっているものの眠そうな様子はない。なんとなく、このまま起きてしまうのがもったいないような気がして、私もベッドから起き上がらなかった。
「昨日は済まない」
「?」
急に謝られてもなんのことだか分からない。
「ほら、寝るまで話そうと言っていたのに、先に寝てしまったから」
「あっ、そのことですか」
昨晩は呆れてしまったけど、今はなんとも思っていない。
「リオ様ったら、ベッドに横になったとたんに寝ているんですもの。いつもそんなに寝つきがいいんですか?」
クスクスと笑いながら尋ねると「そうでもないのだが……」と戸惑う声が返ってくる。
「確かに俺は外でもどこでも寝ることができるが、近くに人がいると眠りが浅いんだ。無意識に周囲を警戒してしまうというか」
リオ様の話を聞きながら『なんだか野生動物みたいね』と思ってしまう。
「だから、まさかこんな朝までぐっすり眠れるなんて……」
「疲れていたのですね」
「いや、そうじゃなくて」
リオ様は両腕を伸ばすと、私をギュッと抱きしめた。
「セレナの側が居心地良すぎるんだ。ほら、こうしていると、もう眠くなってくる……」
「ふふっ、ではリオ様が眠れない日は、私がお役に立てますね」
心地好さそうに目を瞑るリオ様を見ていると、絶対的な信頼を寄せてもらっているようで嬉しくなる。
問題があるとすれば、私もリオ様の腕の中が心地好すぎて、眠くなってしまうこと。
まどろんでいるといつの間にか二人とも眠ってしまったようで、私達は贅沢な二度寝を楽しんだ。
*
遅めの朝食を終えたあと、リオ様と私は『これからどうするか?』ということについて話し合った。
「私達が急いでタイセン国から出る必要はなくなりましたものね……」
元はといえば、これ以上、ライラ様やディーク殿下と顔を合わせて問題を起こさないために、予定より早くバルゴア領へ帰ろうとしていた。
「俺としては、今回の件をカルロスがどう治めるのか気になっている。しばらくタイセン国に留まりたいのだが」
「アイリーン様のこともありますものね。私もしばらく滞在することに賛成です」
こちらで保護しているアイリーン様を置いて帰るわけにはいかない。それに私はまだアイリーン様との約束を果たせていない。私達は、一緒にドレスを買いに行くと約束したのだから。
でも、リオ様はアイリーン様が多くを知りすぎていて、命を狙われる可能性があると言っていた。そんなアイリーン様を王宮外に連れ出すわけにはいかない。
「リオ様、お願いがあるのですが……」
私はリオ様に、ここにタイセン国の服飾士を呼んでもらえないかと相談した。
すぐに動いてくれたリオ様は「カルロスが、王宮お抱えの服飾士を呼んでくれた。なんでも好きに作ってくれとのことだ」と言ったあとに、私の耳元で囁く。
「どうやら、ディークがアイリーン嬢に使うための資金を、全てライラ嬢に貢いでいたようだ」
「なるほど。それでアイリーン様には、何も贈っていなかったと」
『流行おくれのドレスだ。田舎者だ』とアイリーン様をバカにしていたディーク殿下こそが、アイリーン様が流行おくれのドレスを着るしかない状況に追い込んでいたなんて。
「実はカルロスから、アイリーン嬢が好きなだけドレスや宝石を見立ててやってくれと頼まれた」
「任せてください」
戸惑うアイリーン様をよそに、私とアレッタは服飾士が持って来たデザインに次々と目を通す。
「タイセン国ではこういうドレスが流行っているのね」
なんだかどれもこれもフワフワキラキラしていて、ライラ様に似合いそうなデザインばかりだった。それだけ、この国でのライラ様の影響力が大きいということ。
こういうのはアイリーン様には似合わないような気がする。
念のためにアイリーン様にデザインを見せたけど、本人も困ったように首をかしげた。
「アイリーン様は、どういう雰囲気のドレスがお好きですか?」
私がそう尋ねると、アイリーン様は頬を赤く染めてうつむく。
「わ、私なんかが似合うとは思わないのですが……。私は、その、セレナ様がお茶会で着ていたような、強くて美しい感じのドレスに憧れていて……」
「お茶会のときの?」
お茶会といえば、ライラ様主催のものにしか出席していない。あのときは、ディーク殿下を避けるためにわざと濃いメイクをして、私が持っているドレスの中で一番派手なものを着ていた。
ようするに、毒婦スタイル。
私とアレッタは顔を見合わせた。アイリーン様がまさかあの姿に憧れていたなんて!
でも、芯が強いアイリーン様は、ああいう雰囲気の格好が似合うかもしれない。
私が「アレッタ。アイリーン様にお化粧をしてくれる?」とお願いすると、アレッタは「はい!」と元気なお返事をしてから嬉しそうに化粧道具を取りに行く。
戻って来たアレッタは、ほとんど化粧をしていないアイリーン様に濃い目の化粧を施していった。
数分後。
「お嬢様……!」
アレッタが瞳を輝かせながら私を見ている。私もアイリーン様から目が離せない。
毒婦まではいかないものの、濃い目の化粧でキリッとした雰囲気が出て、アイリーン様は知的な魅力に溢れている。
「とてもお似合いですよ」
アレッタから手鏡を受け取ったアイリーン様は、恐る恐る鏡の中の自分を見たあとに、大きく目を見開いた。
「ウ、ウソ……。これが、私?」
呆然と呟くアイリーン様を見ていると、もっともっと彼女を着飾りたいという気持ちが湧きおこってくる。
それは、その場にいた全員が感じたようで、私、アレッタ、服飾士の三人の心がひとつになった瞬間だった。
王都で私のお義母様になってくれたターチェ伯爵夫人や、その家に仕えるメイド長が張り切って私を着飾ってくれた気持ちが今なら分かる。
アイリーン様は磨かれる前のダイヤの原石なのね。原石のままでも十分価値があるのに、見た目でしか判断しない者たちにはその価値が分からない。
だから、そんな愚か者たちでも理解できるように、これを磨きに磨いて、今までバカにしてきた連中を見返したい。この純度の高い輝きを見て驚くがいいわ!
そんな気持ちでいっぱいだった。
服飾士が、今のアイリーン様に似合うドレスを提案する。
「アイリーン様には濃く美しい色がお似合いになると思いますわ!」
激しく同意したアレッタも「フワフワしたものより、スッとした細身のドレスのほうがお似合いかと!」と発言する。
その勢いに押されていたアイリーン様だったけど、私が「アイリーン様の希望はどうかしら?」と尋ねるとちゃんと自分の意見も言ってくれた。
「実は……。男性のエスコートがなくても問題がないドレスを着たいのです。私はエスコートを受けることができないので……」
その発言で、ディーク殿下が今まで一度たりともアイリーン様をエスコートしたことがないのが分かった。
一体どれだけディーク殿下は、アイリーン様に恥をかかせて傷つけてきたのだろう……。
アイリーン様の発言に、服飾士も信じられないといったようにポカンと口を開けている。
「だから、私は高いヒールを履きたくありません。エスコートがないと歩くとき危ないので。長いドレスはすそを踏んでしまう可能性があります。それに、何か緊急事態が起こったとき、すぐに動けるようにしたいんです」
チラッと私を見たアイリーン様は「ドレスの下にブーツを履いていたセレナ様のように」と言って頬を赤く染める。
確かに私は、アイリーン様を追いかけたとき、ドレスの下にブーツを履いていた。でも、それは緊急事態だったからで、その恰好が通常時のものとは言えない。
服飾士も心配そうに「規則違反ではありませんが、社交界ではよく思われないかもしれませんよ?」とアイリーン様に説明している。
「大丈夫です。私は元からよく思われていないので。王宮内に友達もひとりもいません」
そう明るく答えたアイリーン様に、私の胸が苦しくなる。私はアイリーン様の手をそっと握りしめた。
「でしたら、私がアイリーン様の一人目の友達と言うことですね。嬉しいです。これから、アイリーン様の希望のドレスを皆で考えましょう。誰に何を言われても、私はあなたの味方です」
「はい!」
嬉しそうに微笑んだアイリーン様の目尻には涙が浮かんでいる。
気合の入った服飾士とアレッタが、あーでもない、こーでもないと話し合っている間に、私はアイリーン様に話しかけた。
「もし、アイリーン様さえよければ、私達と一緒にバルゴア領に来ませんか? まだ、リオ様にはお話ししていないのですが……」
アイリーン様は、ディーク殿下に変わってその仕事をこなせるくらい優秀だから、きっとリオ様も喜んでくれるはず。
大きく目を見開いたアイリーン様は、「嬉しい」と呟いたあとに、小さく首を振った。
「あ、ありがとうございます。でも、実は昨晩カルロス殿下に文官にならないかとお誘いを受けまして……。信じられないくらいの好待遇で、タゼア家の書物探しにも、全面協力してくださるとのことです」
「そうなのね。一緒にいけないのは残念だけど、アイリーン様が正当に評価されて嬉しいわ」
「はい」
心の底から嬉しそうに微笑むアイリーン様は、今まで辛い思いをした分、明るい未来が待っているのだと分かる。
「セレナ様のおかげです。本当にありがとうございました。あの、これを……」
アイリーン様は自身の首からネックレスを外して私に見せてくれた。
ネックレスの飾り部分には、フクロウの紋章が刻まれている。
「このフクロウは、タゼア家の紋章です。フクロウは夜目が効きます。その豊富な知識量で闇夜すら見渡せる家門という意味が込められているのです。セレナ様、どうぞお手を」
アイリーン様は、ネックレスをそっと私の手のひらに置く。
「私、アイリーン=タゼアは、セレナ様に生涯感謝し続けることをこの紋章に誓います。この誓いのネックレスを受け取っていただけますか?」
「いいのかしら?」
「はい、ぜひ」
ネックレスを受け取ると、アイリーン様は嬉しそうに微笑んだ。
「セレナ様。困ったことがあれば、いつでも私をお訪ねくださいね。そして、この紋章を持つ者をタゼア家が拒むことはありません。完璧とは言えませんが、それでもタゼア家の蔵書量は世界有数です。タゼア家の知識を、そして、書物をどうか存分にお役立てください」
「ありがとう。ふふっ、友達からの贈り物としていただくわ」
「友達というより、忠誠に近いですが……。そうですね、私の忠誠は新しいタイセン国王に捧げるので、セレナ様は友達として貰ってください」
明るい表情でハキハキと話すアイリーン様には、壁際でひとりうつむいていた頃の面影はない。
きっと今のアイリーン様が、本当のアイリーン様なのね。
私達は、微笑み合うと、理想のドレスを制作するために話し合いに戻っていった。