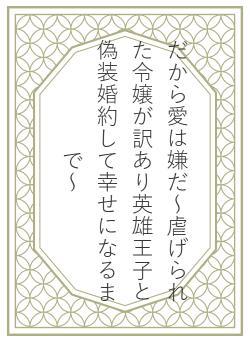「コニー? アレッタ?」
私が名前を呼びながら部屋の中を見渡していると、隣にいるリオ様が「ワインの香りがする」と呟いた。
「ワイン?」
言われてみれば、お酒の香りが微かに漂っているような気もする。でも、この部屋でお酒を飲んだことはない。
「一体、どこから……?」
ズンズンと歩いていったリオ様は、ソファに触れたあとにしゃがみ込み絨毯にも触れた。
「濡れている」
そう言いながらソファに顔を近づけたかと思うと、「カルロスに貰ったワインの香りだ」と断言した。
「え?」
確かカルロス殿下から頂いたワインは希少なものだとリオ様が言っていた。
「俺がカルロスに会いに行ったとき、このワインを一緒に飲んだんだ。ワインなんて俺は夜会のときくらいしか飲まないから、すぐには分からなかったが、ワイン会のときに飲み比べて気がついた。貰ったワインは、他のワインより果実の香りが強く、少しだけ草のような独特な香りがしていたから間違いない」
そういえば、リオ様は鼻が利くんだったわ。
「では、誰かが、頂いたワインをここにこぼしてしまったのでしょうか?」
「そうだと思うが、肝心のワインボトルがない。そもそも、あのワインはまだ開けていない」
リオ様が開けてないワインを、この部屋に出入りできるコニー・アレッタ・エディ様の三人のうちの誰かが勝手に開けることなんて絶対にない。
それは、リオ様ももちろん分かっている。
「しかも、ソファや絨毯にこぼれたものを、乱暴に拭き取ったようなあとがある」
よく見ると、たしかに拭いた跡が見える。
「どういうことなのでしょうか?」
私がそっとソファに触れると、指先に痛みが走った。
「痛っ!」
リオ様が慌てて私の手を握る。
「大丈夫か?」
痛みが走った指先は、切れてうっすらと血が滲んでいた。私が触れたソファをよく見ると、小さな何かが光っている。
「ガラス片……でしょうか?」
私とリオ様は、同時にハッとなり顔を見合わせた。
「もしかして、ワインボトルの欠片?」
「ここでワインボトルが割れたということか」
そのとき、エディ様が戻ってきたけど、特に慌てている様子はない。
「リオ、結婚式は無事に終わったようだな。出発の準備はもう済んでいるぞ。あとは荷馬車ではなく、馬車に一緒に乗せる、セレナ様用の荷物を運び出すだけだ」
「エディ、コニーとアレッタはどこだ?」
「二人ならセレナ様の荷物の最終確認をしていたが?」
「部屋の中にいないんだ」
「ふーん? 世話になった王宮メイドにでも挨拶に行ったのかもな」
だったら、いいのだけれど……。
リオ様はそう思っていないようだ。
「カルロスに貰ったワインボトルが割れて、中身がこぼれたようだ。そして、それを雑に片づけた者がいる」
「はぁ? それはない。ワインボトルはアレッタが割れないように丁寧に梱包していた。万が一、アレッタかコニーが割ったなら、絶対にリオとセレナ様が戻るまで待機して、すぐに報告するはずだ」
「俺もそう思う。だが、ここにはワインがこぼれた跡があり、ガラス片が落ちている。じゃあ、誰が片づけたんだ?」
「ちょっと待ってくれ。たしか、貰ったワインは手で持って慎重に運ぶからとここに……」
エディ様が確認した場所にワインボトルはない。とたんに、エディ様の顔色が変わった。慌てた様子で話し出す。
「俺が二人を最後に見てから、一時間ほど経っている。王宮の馬車乗り場には、バルゴアの騎士達がいるから、犯人が馬車を使って逃げた可能性は低い」
「それもそうだが、今日はカルロス達の結婚式で、王宮の警護がいつもより厳重になっている。部外者が誰にも見つからずここまで入り込んで、二人を外に連れ出すことは不可能に近い。まだ王宮内にいるはずだ」
「リオ、どうする?」
「現状ではタイセンの王宮騎士は信用できない。バルゴアの騎士を王宮内に入れて、コニーとアレッタを捜させる」
「他国の騎士は、簡単に王宮には入れない。まして、王宮内を勝手に捜し回るなんて不可能だぞ⁉ そんなことができるのか⁉」
「できる。分かりやすい合図を送るから、おまえはバルゴアの騎士達と合流してすぐに動けるように指示してくれ」
「分かった!」
そう叫んだと同時に、エディ様は走り去る。
深刻な二人には申し訳ないけど、何が起こっているのか私にはまったく分からなかった。
「リ、リオ様?」
「手当が遅くなってすまない。痛むか?」
そう言いながら、リオ様は部屋に置かれていた水差しの匂いを嗅いで安全を確認したあと、その中に入っていた水を使い私の指先の傷口を洗い、胸ポケットに入っていたハンカチを巻き付けた。
「セレナ、落ち着いて聞いてほしい。コニーとアレッタが何者かに攫われた可能性がある」
私の心臓がドクンと大きく跳ねた。
「そ、それはどうして?」
「すでに梱包していたはずのワインが割れていたということは、わざわざ梱包を外して誰かが割ったんだ」
「割ったのは、犯人ですか?」
リオ様は首を振る。
「いや、おそらくコニーだと思う」
「コニーがどうして?」
「バルゴアの騎士には、山の中で何か問題が起こったとき、後から来た者が状況を分かるように印を残すように指導している。例えば、ここを通ったことを示すために、木に布を巻き付けたり、枝を組み合わせて『こっちに行った』と矢印を残したりだ。だから、何か予期せぬ問題が起こり、コニーが咄嗟に印を残そうとしたのかもしれない」
「で、でも、希少なワインボトルを割るなんて、普通は思い浮かばなくないですか?」
リオ様は、不思議そうな顔をした。
「俺なら真っ先に割る。希少なワインだからこそ、何か問題が起こったのだと手っ取り早く味方に知らせることができるからな。セレナを守るためなら、コニーもなんのためらいもなく割るだろう」
きっぱり言い切ったリオ様は、「もうそろそろエディの準備も整ったかな? こっちも動くか」と言いながら、おもむろにソファの上に置いてあったクッションを引きちぎった。
「え?」
薄い布が破れ、中に入っていた羽毛が舞い散る。
「さて、救出作戦を始めよう」
私が名前を呼びながら部屋の中を見渡していると、隣にいるリオ様が「ワインの香りがする」と呟いた。
「ワイン?」
言われてみれば、お酒の香りが微かに漂っているような気もする。でも、この部屋でお酒を飲んだことはない。
「一体、どこから……?」
ズンズンと歩いていったリオ様は、ソファに触れたあとにしゃがみ込み絨毯にも触れた。
「濡れている」
そう言いながらソファに顔を近づけたかと思うと、「カルロスに貰ったワインの香りだ」と断言した。
「え?」
確かカルロス殿下から頂いたワインは希少なものだとリオ様が言っていた。
「俺がカルロスに会いに行ったとき、このワインを一緒に飲んだんだ。ワインなんて俺は夜会のときくらいしか飲まないから、すぐには分からなかったが、ワイン会のときに飲み比べて気がついた。貰ったワインは、他のワインより果実の香りが強く、少しだけ草のような独特な香りがしていたから間違いない」
そういえば、リオ様は鼻が利くんだったわ。
「では、誰かが、頂いたワインをここにこぼしてしまったのでしょうか?」
「そうだと思うが、肝心のワインボトルがない。そもそも、あのワインはまだ開けていない」
リオ様が開けてないワインを、この部屋に出入りできるコニー・アレッタ・エディ様の三人のうちの誰かが勝手に開けることなんて絶対にない。
それは、リオ様ももちろん分かっている。
「しかも、ソファや絨毯にこぼれたものを、乱暴に拭き取ったようなあとがある」
よく見ると、たしかに拭いた跡が見える。
「どういうことなのでしょうか?」
私がそっとソファに触れると、指先に痛みが走った。
「痛っ!」
リオ様が慌てて私の手を握る。
「大丈夫か?」
痛みが走った指先は、切れてうっすらと血が滲んでいた。私が触れたソファをよく見ると、小さな何かが光っている。
「ガラス片……でしょうか?」
私とリオ様は、同時にハッとなり顔を見合わせた。
「もしかして、ワインボトルの欠片?」
「ここでワインボトルが割れたということか」
そのとき、エディ様が戻ってきたけど、特に慌てている様子はない。
「リオ、結婚式は無事に終わったようだな。出発の準備はもう済んでいるぞ。あとは荷馬車ではなく、馬車に一緒に乗せる、セレナ様用の荷物を運び出すだけだ」
「エディ、コニーとアレッタはどこだ?」
「二人ならセレナ様の荷物の最終確認をしていたが?」
「部屋の中にいないんだ」
「ふーん? 世話になった王宮メイドにでも挨拶に行ったのかもな」
だったら、いいのだけれど……。
リオ様はそう思っていないようだ。
「カルロスに貰ったワインボトルが割れて、中身がこぼれたようだ。そして、それを雑に片づけた者がいる」
「はぁ? それはない。ワインボトルはアレッタが割れないように丁寧に梱包していた。万が一、アレッタかコニーが割ったなら、絶対にリオとセレナ様が戻るまで待機して、すぐに報告するはずだ」
「俺もそう思う。だが、ここにはワインがこぼれた跡があり、ガラス片が落ちている。じゃあ、誰が片づけたんだ?」
「ちょっと待ってくれ。たしか、貰ったワインは手で持って慎重に運ぶからとここに……」
エディ様が確認した場所にワインボトルはない。とたんに、エディ様の顔色が変わった。慌てた様子で話し出す。
「俺が二人を最後に見てから、一時間ほど経っている。王宮の馬車乗り場には、バルゴアの騎士達がいるから、犯人が馬車を使って逃げた可能性は低い」
「それもそうだが、今日はカルロス達の結婚式で、王宮の警護がいつもより厳重になっている。部外者が誰にも見つからずここまで入り込んで、二人を外に連れ出すことは不可能に近い。まだ王宮内にいるはずだ」
「リオ、どうする?」
「現状ではタイセンの王宮騎士は信用できない。バルゴアの騎士を王宮内に入れて、コニーとアレッタを捜させる」
「他国の騎士は、簡単に王宮には入れない。まして、王宮内を勝手に捜し回るなんて不可能だぞ⁉ そんなことができるのか⁉」
「できる。分かりやすい合図を送るから、おまえはバルゴアの騎士達と合流してすぐに動けるように指示してくれ」
「分かった!」
そう叫んだと同時に、エディ様は走り去る。
深刻な二人には申し訳ないけど、何が起こっているのか私にはまったく分からなかった。
「リ、リオ様?」
「手当が遅くなってすまない。痛むか?」
そう言いながら、リオ様は部屋に置かれていた水差しの匂いを嗅いで安全を確認したあと、その中に入っていた水を使い私の指先の傷口を洗い、胸ポケットに入っていたハンカチを巻き付けた。
「セレナ、落ち着いて聞いてほしい。コニーとアレッタが何者かに攫われた可能性がある」
私の心臓がドクンと大きく跳ねた。
「そ、それはどうして?」
「すでに梱包していたはずのワインが割れていたということは、わざわざ梱包を外して誰かが割ったんだ」
「割ったのは、犯人ですか?」
リオ様は首を振る。
「いや、おそらくコニーだと思う」
「コニーがどうして?」
「バルゴアの騎士には、山の中で何か問題が起こったとき、後から来た者が状況を分かるように印を残すように指導している。例えば、ここを通ったことを示すために、木に布を巻き付けたり、枝を組み合わせて『こっちに行った』と矢印を残したりだ。だから、何か予期せぬ問題が起こり、コニーが咄嗟に印を残そうとしたのかもしれない」
「で、でも、希少なワインボトルを割るなんて、普通は思い浮かばなくないですか?」
リオ様は、不思議そうな顔をした。
「俺なら真っ先に割る。希少なワインだからこそ、何か問題が起こったのだと手っ取り早く味方に知らせることができるからな。セレナを守るためなら、コニーもなんのためらいもなく割るだろう」
きっぱり言い切ったリオ様は、「もうそろそろエディの準備も整ったかな? こっちも動くか」と言いながら、おもむろにソファの上に置いてあったクッションを引きちぎった。
「え?」
薄い布が破れ、中に入っていた羽毛が舞い散る。
「さて、救出作戦を始めよう」