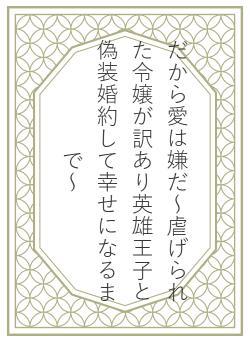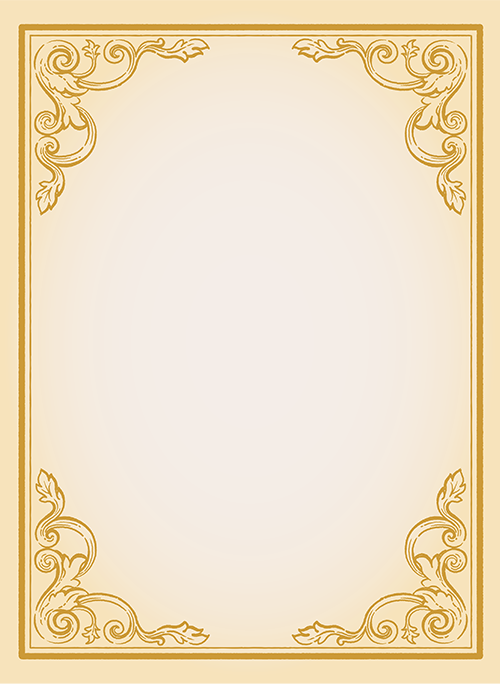ファルトン伯爵家で行われていた悪事はリオ様に暴かれて、またたく間に王国中に広まった。
それと同時に、銀食器に反応しない毒があるという事実に人々はふるえあがった。
これまで病死扱いで亡くなった人の中に「毒殺された人がいたのではないか?」と疑う声も上がっている。
そんな中でも、ターチェ伯爵家は平和そのものだった。
私は、バルコニーから美しいターチェ家の庭園をぼんやりと眺めていた。リオ様のおかげで、祖父と母の敵(かたき)を取ることができた。
でも、私は、あの日から、リオ様に避けられている。
最初は気のせいかと思っていた。
きっとリオ様は、ファルトン家の事件の処理などで忙しいのよね、と。
でも、難しいことを考えるのが苦手だというリオ様は、事件後のことはすべてターチェ伯爵に任せているらしい。
そういうわけで、リオ様は忙しくない。それなのに、なぜか会えない。
今までよく顔を合わせていたのは、リオ様が私に会いに来てくれていたからなのね。リオ様に、改めてお礼が言いたいのに……。
だったら、私のほうから会いに行けばいいのよ。
そう思った私が、朝晩の鍛錬中に何度か押しかけたけど、そこでもリオ様には会えなかった。
「リオ様はどちらに?」
エディ様が目を泳がせている。
「あー……えっと、今日は、リオはその、具合が悪くて……」
鍛錬に参加していたコニーが、私が来た方角と反対を指さした。
「リオ様は、セレナお嬢様が来たとたんに、あっちに全力疾走していきましたよ」
「わー!? コラッ弟子! 空気を読め!」
「はぁ? それが次の鍛錬ですか?」
それを聞いて、私はようやくリオ様に避けられているのねと気がついた。
避けられている原因はわかっている。
ファルトン伯爵家から帰る馬車の中で、リオ様に『なら、どうして俺をかばおうとしたんですか!?』と怒られた。
今思えば、怒られても仕方がない。
だって、私なんかがリオ様を守ろうと飛び出したのだから。バルゴア騎士を率いるリオ様にとって、その行動がどれほど失礼なことになるかなんて思っていなかった。
きっとリオ様は、私の愚かさにあきれてしまったんだわ……。
リオ様が私を避けるようになっても、ターチェ伯爵家の人々は相変わらず私に優しくしてくれる。とても幸せなはずなのに、私の心はずっと沈んでいた。
だから、ようやく自分の気持ちに気がつけた。
「私って、リオ様のことが好きだったのね……」
いつの間にそんな思いが育っていたのかしら? 気がつけば、リオ様の存在が私の中でとても大きくなっていた。
そのことに、リオ様に嫌われ避けられてから気がつくなんて遅すぎる。
私は包帯が巻かれた右手首を見つめた。
リオ様は『あなたのケガが治ったら、聞いてほしいことがあります。とても大切なことなんです』と言っていた。
「それって、やっぱり私の今後の話よね?」
何を言われるのか想像がつかない。でも、あのときのリオ様の顔は、すごく真剣で怖かった。
良い話とは思えない。
「それに……」
私はこれまでのことを思い出した。
リオ様は、私を見ると、すぐに赤くなったり照れたりするけど、そこに深い意味はない。
だって、前にエディ様に『結婚するつもりはないんですか?』と聞かれて『私を妻に求める人なんていませんわ』と返したとき、リオ様は『そんなことないですよ』って言ってくれなかったから。
それに、あの日の馬車の帰り道で、私が『こんなひどいことを言う女は、嫌ですよね……』と聞いても、やっぱりリオ様は何も言ってくれなかった。
「そうよね……。だって、私はリオ様の嫁候補にすら入っていないもの……」
わざわざ王都にまで来て嫁探しをするんだから、その目的は高位貴族との繋がりだと思う。
私はまだ一応貴族だけど、父、継母(ままはは)、マリンは投獄されている。今は、私の祖父と母の毒殺に、継母とマリンがどこまで関わっているか調べられているそうだ。
父方の親戚たちは、私の母が亡くなってすぐに、父が継母と再婚しようとしたことに大反対したらしい。しかも、私とそう年が変わらないマリンがいたことから、父が長年にわたり浮気をしていたことは明らかだった。
親戚たちの言い分は「浮気をするなとは言わないが、もっと世間体を考えろ。私達の顔に泥を塗る気か!」だ。
そのときに、もめにもめて絶縁したそうで、今回の事件に自分たちは一切関わっていないと主張している。
だから、一人残された私を支えようという親戚はいない。
このままでは、私が婿養子を取ってファルトン伯爵家を継ぐことになってしまう。それだけは嫌だとターチェ伯爵に相談したら、「君は何も心配しなくていい。これからは好きに生きていいんだよ」と言ってくれた。
だから、ケガが治りターチェ伯爵家を出たら、以前から考えていたように、私はバルゴア領に移り住んで平民として暮らすことに決めた。
でも、そうすると、結婚したリオ様やその奥様を遠くから見ることになるわけで……。
リオ様の優しい微笑みが私以外の女性に向けられると思うと胸が苦しくなってしまう。
「……王都の女性をエスコートする練習なんてしなければ良かった」
そうすれば、リオ様はいつまでたっても奥さんを見つけられなかったかもしれない。
「そんなわけないか。だってリオ様、素敵だもの」
早く、この気持ちを、終わらせないと。
私のつぶやきは、バルコニーを吹き抜ける風にかき消された。
*
しばらくすると、ターチェ伯爵夫人が私の元を訪れた。
「セレナさん、今、少しいいかしら?」
「はい、もちろんです」
ターチェ伯爵夫人は、平静を装っているけど、空気がとげとげしい。
「……何かあったのですか?」
夫人は、大きなため息をついた。
「セレナさん、私と一緒に夜会に参加してくださらない?」
「え? 夜会、ですか?」
「そう夜会! ほんっとうに腹立たしいのよ!」
夫人がいうには、社交界では今、ファルトン伯爵家のことで持ち切りだそうだ。
「セレナさんは、ひどい目に遭(あ)わされていた被害者なのに、そうじゃないと主張する人達がいるのよ!」
「は、はぁ……?」
「社交界の毒婦も、何か犯罪に手を染めているんじゃないかって! だから、表舞台に出てこれないんだって! ああっもう! 今のこの可憐なセレナさんを見せつけて、そいつら全員黙らせてやるんだから!」
怒りに燃える夫人は、相変わらず優しい人だ。私の名誉を挽回(ばんかい)してくれようとするその気持ちはとても嬉しい。でも、私は丁重にお断りした。
「ありがとうございます。でも、私はもう二度と社交界に戻る気はありません」
「そうなの!?」
驚く夫人に、私はバルゴア領に行こうと思っていることを告げた。すると、夫人は「まぁまぁまぁ」と嬉しそうに微笑む。
「そうだったのね!? やっとリオが……もうあの子ったら、あなたのケガが治ってからとか、最高級の指輪を見つけてからとか、ずっとウダウダ言っていたから心配していたのよ!」
「ケガが治ったら、指輪を?」
私の言葉を聞いて夫人はハッと口を押さえた。
「ごめんなさい! まだ指輪のことは、リオから聞いていなかったのね? あらやだ、先に言っちゃったわ、どうしましょう」
「リオ様が、指輪をどうするんですか?」
夫人は少し悩んだあとに、「もう言っちゃったから良いわよね?」と開き直った。
「それはもちろん、リオが愛する人にあげるために準備しているのよ」
「愛する、人……」
頭を殴られたような衝撃を感じた。
夫人は、なぜかリオ様が私に指輪を贈ると誤解しているようだった。
でも、私は自分の指のサイズを知らない。今まで指輪を買ってもらったことなんてなかったから。
それにリオ様に、指のサイズなんて聞かれたことがない。だから、どう考えても、その指輪は私に贈るために準備されているものではない。
胸がジクジクと痛む。
そっか、リオ様に愛する人ができたんだわ。だから、私が会おうとしても会ってくれなかったのね。
他に愛する人がいるのに、私に優しくするわけにはいかない。そんなことをして本当に愛する女性に誤解されてしまったら困るもの。だから、避けられていたのね。
リオ様は、なんて誠実な人なんだろうと思う。そして、リオ様に愛される人がうらやましくて仕方ない。
夫人が「これは、夫がくれた指輪で――」と幸せそうに話してくれたけど、私はうまく返事ができなかった。
それと同時に、銀食器に反応しない毒があるという事実に人々はふるえあがった。
これまで病死扱いで亡くなった人の中に「毒殺された人がいたのではないか?」と疑う声も上がっている。
そんな中でも、ターチェ伯爵家は平和そのものだった。
私は、バルコニーから美しいターチェ家の庭園をぼんやりと眺めていた。リオ様のおかげで、祖父と母の敵(かたき)を取ることができた。
でも、私は、あの日から、リオ様に避けられている。
最初は気のせいかと思っていた。
きっとリオ様は、ファルトン家の事件の処理などで忙しいのよね、と。
でも、難しいことを考えるのが苦手だというリオ様は、事件後のことはすべてターチェ伯爵に任せているらしい。
そういうわけで、リオ様は忙しくない。それなのに、なぜか会えない。
今までよく顔を合わせていたのは、リオ様が私に会いに来てくれていたからなのね。リオ様に、改めてお礼が言いたいのに……。
だったら、私のほうから会いに行けばいいのよ。
そう思った私が、朝晩の鍛錬中に何度か押しかけたけど、そこでもリオ様には会えなかった。
「リオ様はどちらに?」
エディ様が目を泳がせている。
「あー……えっと、今日は、リオはその、具合が悪くて……」
鍛錬に参加していたコニーが、私が来た方角と反対を指さした。
「リオ様は、セレナお嬢様が来たとたんに、あっちに全力疾走していきましたよ」
「わー!? コラッ弟子! 空気を読め!」
「はぁ? それが次の鍛錬ですか?」
それを聞いて、私はようやくリオ様に避けられているのねと気がついた。
避けられている原因はわかっている。
ファルトン伯爵家から帰る馬車の中で、リオ様に『なら、どうして俺をかばおうとしたんですか!?』と怒られた。
今思えば、怒られても仕方がない。
だって、私なんかがリオ様を守ろうと飛び出したのだから。バルゴア騎士を率いるリオ様にとって、その行動がどれほど失礼なことになるかなんて思っていなかった。
きっとリオ様は、私の愚かさにあきれてしまったんだわ……。
リオ様が私を避けるようになっても、ターチェ伯爵家の人々は相変わらず私に優しくしてくれる。とても幸せなはずなのに、私の心はずっと沈んでいた。
だから、ようやく自分の気持ちに気がつけた。
「私って、リオ様のことが好きだったのね……」
いつの間にそんな思いが育っていたのかしら? 気がつけば、リオ様の存在が私の中でとても大きくなっていた。
そのことに、リオ様に嫌われ避けられてから気がつくなんて遅すぎる。
私は包帯が巻かれた右手首を見つめた。
リオ様は『あなたのケガが治ったら、聞いてほしいことがあります。とても大切なことなんです』と言っていた。
「それって、やっぱり私の今後の話よね?」
何を言われるのか想像がつかない。でも、あのときのリオ様の顔は、すごく真剣で怖かった。
良い話とは思えない。
「それに……」
私はこれまでのことを思い出した。
リオ様は、私を見ると、すぐに赤くなったり照れたりするけど、そこに深い意味はない。
だって、前にエディ様に『結婚するつもりはないんですか?』と聞かれて『私を妻に求める人なんていませんわ』と返したとき、リオ様は『そんなことないですよ』って言ってくれなかったから。
それに、あの日の馬車の帰り道で、私が『こんなひどいことを言う女は、嫌ですよね……』と聞いても、やっぱりリオ様は何も言ってくれなかった。
「そうよね……。だって、私はリオ様の嫁候補にすら入っていないもの……」
わざわざ王都にまで来て嫁探しをするんだから、その目的は高位貴族との繋がりだと思う。
私はまだ一応貴族だけど、父、継母(ままはは)、マリンは投獄されている。今は、私の祖父と母の毒殺に、継母とマリンがどこまで関わっているか調べられているそうだ。
父方の親戚たちは、私の母が亡くなってすぐに、父が継母と再婚しようとしたことに大反対したらしい。しかも、私とそう年が変わらないマリンがいたことから、父が長年にわたり浮気をしていたことは明らかだった。
親戚たちの言い分は「浮気をするなとは言わないが、もっと世間体を考えろ。私達の顔に泥を塗る気か!」だ。
そのときに、もめにもめて絶縁したそうで、今回の事件に自分たちは一切関わっていないと主張している。
だから、一人残された私を支えようという親戚はいない。
このままでは、私が婿養子を取ってファルトン伯爵家を継ぐことになってしまう。それだけは嫌だとターチェ伯爵に相談したら、「君は何も心配しなくていい。これからは好きに生きていいんだよ」と言ってくれた。
だから、ケガが治りターチェ伯爵家を出たら、以前から考えていたように、私はバルゴア領に移り住んで平民として暮らすことに決めた。
でも、そうすると、結婚したリオ様やその奥様を遠くから見ることになるわけで……。
リオ様の優しい微笑みが私以外の女性に向けられると思うと胸が苦しくなってしまう。
「……王都の女性をエスコートする練習なんてしなければ良かった」
そうすれば、リオ様はいつまでたっても奥さんを見つけられなかったかもしれない。
「そんなわけないか。だってリオ様、素敵だもの」
早く、この気持ちを、終わらせないと。
私のつぶやきは、バルコニーを吹き抜ける風にかき消された。
*
しばらくすると、ターチェ伯爵夫人が私の元を訪れた。
「セレナさん、今、少しいいかしら?」
「はい、もちろんです」
ターチェ伯爵夫人は、平静を装っているけど、空気がとげとげしい。
「……何かあったのですか?」
夫人は、大きなため息をついた。
「セレナさん、私と一緒に夜会に参加してくださらない?」
「え? 夜会、ですか?」
「そう夜会! ほんっとうに腹立たしいのよ!」
夫人がいうには、社交界では今、ファルトン伯爵家のことで持ち切りだそうだ。
「セレナさんは、ひどい目に遭(あ)わされていた被害者なのに、そうじゃないと主張する人達がいるのよ!」
「は、はぁ……?」
「社交界の毒婦も、何か犯罪に手を染めているんじゃないかって! だから、表舞台に出てこれないんだって! ああっもう! 今のこの可憐なセレナさんを見せつけて、そいつら全員黙らせてやるんだから!」
怒りに燃える夫人は、相変わらず優しい人だ。私の名誉を挽回(ばんかい)してくれようとするその気持ちはとても嬉しい。でも、私は丁重にお断りした。
「ありがとうございます。でも、私はもう二度と社交界に戻る気はありません」
「そうなの!?」
驚く夫人に、私はバルゴア領に行こうと思っていることを告げた。すると、夫人は「まぁまぁまぁ」と嬉しそうに微笑む。
「そうだったのね!? やっとリオが……もうあの子ったら、あなたのケガが治ってからとか、最高級の指輪を見つけてからとか、ずっとウダウダ言っていたから心配していたのよ!」
「ケガが治ったら、指輪を?」
私の言葉を聞いて夫人はハッと口を押さえた。
「ごめんなさい! まだ指輪のことは、リオから聞いていなかったのね? あらやだ、先に言っちゃったわ、どうしましょう」
「リオ様が、指輪をどうするんですか?」
夫人は少し悩んだあとに、「もう言っちゃったから良いわよね?」と開き直った。
「それはもちろん、リオが愛する人にあげるために準備しているのよ」
「愛する、人……」
頭を殴られたような衝撃を感じた。
夫人は、なぜかリオ様が私に指輪を贈ると誤解しているようだった。
でも、私は自分の指のサイズを知らない。今まで指輪を買ってもらったことなんてなかったから。
それにリオ様に、指のサイズなんて聞かれたことがない。だから、どう考えても、その指輪は私に贈るために準備されているものではない。
胸がジクジクと痛む。
そっか、リオ様に愛する人ができたんだわ。だから、私が会おうとしても会ってくれなかったのね。
他に愛する人がいるのに、私に優しくするわけにはいかない。そんなことをして本当に愛する女性に誤解されてしまったら困るもの。だから、避けられていたのね。
リオ様は、なんて誠実な人なんだろうと思う。そして、リオ様に愛される人がうらやましくて仕方ない。
夫人が「これは、夫がくれた指輪で――」と幸せそうに話してくれたけど、私はうまく返事ができなかった。