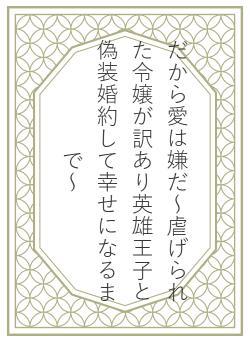私は、リオ様との仲を見せつけるために、とりあえず、甘えているふりをしようと思った。
正直に言うと甘え方なんてわからない。でも、マリンは甘え上手だから、マリンっぽいことをしておけばいいわよね?
「リオ様ぁ」
ぴったりとくっつきながら、私が背の高いリオ様を見上げると、リオ様は、手で口元を押さえながら、顔を思いっきり背けていた。
顔は見えないけど、耳も首も真っ赤に染まっている。
「え?」
こんなの空気を読むのが、うまくなくてもわかる。
「も、もしかして、照れてます?」
コクリとうなずくリオ様。
「これは演技ですよ?」
「わ、わかっているんですが。……俺、演技はできそうにないです」
「でも、さっきは、ダンスしながら楽しそうに、笑っていたじゃないですか」
物騒な話をしながら、ニコニコと楽しそうにしていたリオ様なら演技ができると思う。
「あれは、あなたと踊るのが楽しかっただけです」
「ええっ!?」
ダンスを終えた私達を、犯罪者である父、継母がにらみつけている。私達がダンスを踊っている間にマリンも来たようで、不機嫌そうな顔を隠そうともしていない。
リオ様に演技は期待できない。
だったら、もう私が一人でやるしかないわ。
なんとか、父に冷静さを失わせて、この場で毒を使いたくなるような状況を作らなければ。
私は意地の悪そうに見える笑みをマリンに向けた。鏡の前で一生懸命練習したので、この笑みには自信がある。
「マリン、せっかく出迎えてくれたのに、一人で戻らせてごめんね? リオ様が私から離れたくないって言うから……」
私が困ったようにため息をつくと、マリンは醜く顔を歪めた。でも、すぐに表情を戻し、フッと鼻で笑う。
「気にしないで、お姉さま。だって、お姉さまはケガをされているんだもの。ケガ人を優先するのは当たり前だわ」
なるほど、『あんたがリオ様に優先されているのは、ケガのせいよ』と言いたいのね。
私はクスッと笑うと、いつも夜会でマリンに言うように指示されていた言葉を言ってあげた。
「なーに? 愛人の子の分際で生意気ね!」
とたんに父の目に殺気がこもる。
「貴様、今なんて言った!?」
私につかみかかろうとした父の右腕を、リオ様がすばやくつかんだ。
今、絶対、父に殴られると思った……恐怖で心臓が早鐘を打っている。でも、リオ様が助けてくれた。
そっか、リオ様は演技ができなくても、私の味方でいてくれるのね。そのことがとても心強い。
「ファルトン伯爵。今、セレナ嬢に、何をしようとした?」
リオ様の紫色の瞳が、怖いくらい殺気を放っている。
「躾(しつけ)です! セレナが、無礼な発言をしたので!」
「無礼な発言? ただの事実だろう」
父は「ぐっ」と言葉につまった。リオ様がつかんでいた腕を離すと、父がよろめいたので継母があわてて支える。
何か言おうとした継母を、父が制した。
「リオ様、私達の間には、何か誤解があるようです」
そう言いながら私をにらみつける父は、私がリオ様にいろいろ吹き込んだと思っているのでしょうね。でも、私は事実しか伝えていない。
「奥の部屋に、晩餐(ばんさん)の準備をしてあります。食事をしながら誤解を解きましょう。どうぞ、こちらへ」
父に案内され、私達は晩餐の席についた。
「セレナ、お前は部屋に戻っていなさい」
冷たい父の言葉を無視して、リオ様が隣の席に私を座らせてくれる。
咳払いする父。
「そこは、マリンのために準備した席です」
「そうですか。では、マリン嬢には、別の席に座ってもらいましょう」
父も継母もマリンも、怒りを抑え込むのに必死なように見える。でも、リオ様には何も言えない。王国一の軍事力を持つバルゴアを、敵に回すわけにはいかないから。
そんなリオ様が、私の味方になってくれているなんて……なんだか不思議な気分。
でも、文句がいえない相手に対して好き勝手するのは、たとえ相手がだれでも、あまり良い気がしない。
だからこそ、それをずっと私にやってきた、この人たちの心は歪んでいる。
父が片手を上げると、初老の執事がすぐによってきた。何か指示を受けて去っていく。
もしかして、毒を入れるように指示したの!?
私がリオ様を見ると、リオ様もそう思っていたのか、視線をエディ様に送っていた。エディ様は小さくうなずくと、パーティー会場内で控えていた護衛騎士に指示を出す。指示を受けた護衛は、静かに執事のあとをつけていった。
もし、これで毒を使うところを押さえられたら、すべてが解決する。
緊張でドキドキしている私の前に、スープが運ばれてきた。
リオ様が運ばれてきたスープの香りを嗅いで、さりげなく毒が入っていないか確認してくれる。
「良い香りですね」
毒は入っていないみたい。その証拠にリオ様は、ニコリと微笑みかけてくれた。
前菜、メインの肉料理と順番に運ばれてきたけど、毒は入っていなかった。やっぱり、こんなところで毒を使わせるなんて無理なのかしら?
だとしたら、どうすれば……。
「セレナお嬢様、ワインはいかがですか?」
初老の執事の声で私は我に返った。この執事は、先ほど父に何かを命令されていた執事だ。なんだか顔色が悪い。
「……いただくわ」
丁寧なしぐさでワインを注いで、私の前にグラスを置く。他の人には、もうワインが注がれたあとだった。
父が「では、乾杯」とグラスを掲げる。
私はグラスに口をつけずに、リオ様に差し出した。
「リオ様、ワインはお好きですか?」
グラスに顔を近づけたリオ様は「はい」とうなずく。そして、そっと私からグラスを受け取った。
父が「セレナ、無礼にもほどがあるぞ!」とあせるように声をあらげている。
ワインの香りを嗅いだリオ様は、一気にワインを飲みほした。
えっ! そのワイン、大丈夫なの!?
あせる私以上に、父があせっている。
リオ様は「おいしいです」とニッコリ微笑んだ。ホッと胸をなでおろすと、私の前の席に座っていた継母が「うっ」とえずいた。継母の顔は真っ青で、両手が小刻みにふるえている。
「どうした!?」
驚く父に、継母は信じられないといったような顔を向けた。
「あ、あなた……もしかして、私に?」
「ち、違う! これは何かの間違いだ!」
「うえっ!」
「きゃあ!? お母さま!」
継母は、口元を押さえるとその場に崩れ落ちた。吐き気を押さえきれないといった様子だ。
「な、なぜだ!?」
動揺する父に、リオ様は静かに語りかけた。
「落ち着いてください、伯爵。その毒は、少量飲んだくらいでは、すぐに死に至るものではないのでしょう?」
「なっ!?」
見ると、ワインを注いでいた初老の執事は、バルゴアの騎士に取り押さえられている。
「話が違う! あなた達のいう通りにしたら、私だけは見逃してくれると!」
ああ、なるほど。毒を盛ろうとした執事を、現行犯で捕まえて、裏で取引したのね。
そして、私じゃなくて継母のほうに、毒入りワインを飲ませるように仕向けた。ワインは、みんな同じものを注がれたから、毒はグラスに塗られていたのかもしれない。
リオ様は、自分に配られたワインの香りを嗅いでいた。
「俺のは、嗅いだことがある匂いだ。これは、睡眠薬だな」
「リオ様のものにまで!?」
席から立ち上がったリオ様は、驚く私をエスコートして立たせてくれる。
「ファルトン伯爵。セレナ嬢に毒を盛ろうとした罪、そして、俺に睡眠薬を盛ろうとした罪。どう償うつもりだ?」
その声はどこまでも冷酷で、瞳は怒りで燃え上がっていた。
父は、大きなため息をついたあと、ニヤリと口端を上げる。
「リオ様、急に毒だと言われても私には、なんのことだかわかりません。まさか、その執事の証言だけを信じるつもりですか?」
「そんなっ、旦那さま!?」
このままだと父は、執事にすべての罪をかぶせて逃げてしまうのでは?
不安になった私がリオ様を見上げると、リオ様は「大丈夫ですよ。想定どおりです」と私の耳元でささやいた。
「セレナ嬢。捕らえられた敵兵たちの将が、自分だけ助かろうと配下に罪をなすりつけて見捨てると、どうなると思います?」
「わ、わかりません」
「多くは、だったら自分も助かりたいと、壮絶な罪の擦り付け合い、足の引っ張り合いになるんですよ」
「は、はぁ?」
「この邸宅内から逃げ場をなくし、同じような環境を作ったので、おそらく今からそれが始まるでしょう」
私は、リオ様の言っていることが、少しも理解できなかった。
正直に言うと甘え方なんてわからない。でも、マリンは甘え上手だから、マリンっぽいことをしておけばいいわよね?
「リオ様ぁ」
ぴったりとくっつきながら、私が背の高いリオ様を見上げると、リオ様は、手で口元を押さえながら、顔を思いっきり背けていた。
顔は見えないけど、耳も首も真っ赤に染まっている。
「え?」
こんなの空気を読むのが、うまくなくてもわかる。
「も、もしかして、照れてます?」
コクリとうなずくリオ様。
「これは演技ですよ?」
「わ、わかっているんですが。……俺、演技はできそうにないです」
「でも、さっきは、ダンスしながら楽しそうに、笑っていたじゃないですか」
物騒な話をしながら、ニコニコと楽しそうにしていたリオ様なら演技ができると思う。
「あれは、あなたと踊るのが楽しかっただけです」
「ええっ!?」
ダンスを終えた私達を、犯罪者である父、継母がにらみつけている。私達がダンスを踊っている間にマリンも来たようで、不機嫌そうな顔を隠そうともしていない。
リオ様に演技は期待できない。
だったら、もう私が一人でやるしかないわ。
なんとか、父に冷静さを失わせて、この場で毒を使いたくなるような状況を作らなければ。
私は意地の悪そうに見える笑みをマリンに向けた。鏡の前で一生懸命練習したので、この笑みには自信がある。
「マリン、せっかく出迎えてくれたのに、一人で戻らせてごめんね? リオ様が私から離れたくないって言うから……」
私が困ったようにため息をつくと、マリンは醜く顔を歪めた。でも、すぐに表情を戻し、フッと鼻で笑う。
「気にしないで、お姉さま。だって、お姉さまはケガをされているんだもの。ケガ人を優先するのは当たり前だわ」
なるほど、『あんたがリオ様に優先されているのは、ケガのせいよ』と言いたいのね。
私はクスッと笑うと、いつも夜会でマリンに言うように指示されていた言葉を言ってあげた。
「なーに? 愛人の子の分際で生意気ね!」
とたんに父の目に殺気がこもる。
「貴様、今なんて言った!?」
私につかみかかろうとした父の右腕を、リオ様がすばやくつかんだ。
今、絶対、父に殴られると思った……恐怖で心臓が早鐘を打っている。でも、リオ様が助けてくれた。
そっか、リオ様は演技ができなくても、私の味方でいてくれるのね。そのことがとても心強い。
「ファルトン伯爵。今、セレナ嬢に、何をしようとした?」
リオ様の紫色の瞳が、怖いくらい殺気を放っている。
「躾(しつけ)です! セレナが、無礼な発言をしたので!」
「無礼な発言? ただの事実だろう」
父は「ぐっ」と言葉につまった。リオ様がつかんでいた腕を離すと、父がよろめいたので継母があわてて支える。
何か言おうとした継母を、父が制した。
「リオ様、私達の間には、何か誤解があるようです」
そう言いながら私をにらみつける父は、私がリオ様にいろいろ吹き込んだと思っているのでしょうね。でも、私は事実しか伝えていない。
「奥の部屋に、晩餐(ばんさん)の準備をしてあります。食事をしながら誤解を解きましょう。どうぞ、こちらへ」
父に案内され、私達は晩餐の席についた。
「セレナ、お前は部屋に戻っていなさい」
冷たい父の言葉を無視して、リオ様が隣の席に私を座らせてくれる。
咳払いする父。
「そこは、マリンのために準備した席です」
「そうですか。では、マリン嬢には、別の席に座ってもらいましょう」
父も継母もマリンも、怒りを抑え込むのに必死なように見える。でも、リオ様には何も言えない。王国一の軍事力を持つバルゴアを、敵に回すわけにはいかないから。
そんなリオ様が、私の味方になってくれているなんて……なんだか不思議な気分。
でも、文句がいえない相手に対して好き勝手するのは、たとえ相手がだれでも、あまり良い気がしない。
だからこそ、それをずっと私にやってきた、この人たちの心は歪んでいる。
父が片手を上げると、初老の執事がすぐによってきた。何か指示を受けて去っていく。
もしかして、毒を入れるように指示したの!?
私がリオ様を見ると、リオ様もそう思っていたのか、視線をエディ様に送っていた。エディ様は小さくうなずくと、パーティー会場内で控えていた護衛騎士に指示を出す。指示を受けた護衛は、静かに執事のあとをつけていった。
もし、これで毒を使うところを押さえられたら、すべてが解決する。
緊張でドキドキしている私の前に、スープが運ばれてきた。
リオ様が運ばれてきたスープの香りを嗅いで、さりげなく毒が入っていないか確認してくれる。
「良い香りですね」
毒は入っていないみたい。その証拠にリオ様は、ニコリと微笑みかけてくれた。
前菜、メインの肉料理と順番に運ばれてきたけど、毒は入っていなかった。やっぱり、こんなところで毒を使わせるなんて無理なのかしら?
だとしたら、どうすれば……。
「セレナお嬢様、ワインはいかがですか?」
初老の執事の声で私は我に返った。この執事は、先ほど父に何かを命令されていた執事だ。なんだか顔色が悪い。
「……いただくわ」
丁寧なしぐさでワインを注いで、私の前にグラスを置く。他の人には、もうワインが注がれたあとだった。
父が「では、乾杯」とグラスを掲げる。
私はグラスに口をつけずに、リオ様に差し出した。
「リオ様、ワインはお好きですか?」
グラスに顔を近づけたリオ様は「はい」とうなずく。そして、そっと私からグラスを受け取った。
父が「セレナ、無礼にもほどがあるぞ!」とあせるように声をあらげている。
ワインの香りを嗅いだリオ様は、一気にワインを飲みほした。
えっ! そのワイン、大丈夫なの!?
あせる私以上に、父があせっている。
リオ様は「おいしいです」とニッコリ微笑んだ。ホッと胸をなでおろすと、私の前の席に座っていた継母が「うっ」とえずいた。継母の顔は真っ青で、両手が小刻みにふるえている。
「どうした!?」
驚く父に、継母は信じられないといったような顔を向けた。
「あ、あなた……もしかして、私に?」
「ち、違う! これは何かの間違いだ!」
「うえっ!」
「きゃあ!? お母さま!」
継母は、口元を押さえるとその場に崩れ落ちた。吐き気を押さえきれないといった様子だ。
「な、なぜだ!?」
動揺する父に、リオ様は静かに語りかけた。
「落ち着いてください、伯爵。その毒は、少量飲んだくらいでは、すぐに死に至るものではないのでしょう?」
「なっ!?」
見ると、ワインを注いでいた初老の執事は、バルゴアの騎士に取り押さえられている。
「話が違う! あなた達のいう通りにしたら、私だけは見逃してくれると!」
ああ、なるほど。毒を盛ろうとした執事を、現行犯で捕まえて、裏で取引したのね。
そして、私じゃなくて継母のほうに、毒入りワインを飲ませるように仕向けた。ワインは、みんな同じものを注がれたから、毒はグラスに塗られていたのかもしれない。
リオ様は、自分に配られたワインの香りを嗅いでいた。
「俺のは、嗅いだことがある匂いだ。これは、睡眠薬だな」
「リオ様のものにまで!?」
席から立ち上がったリオ様は、驚く私をエスコートして立たせてくれる。
「ファルトン伯爵。セレナ嬢に毒を盛ろうとした罪、そして、俺に睡眠薬を盛ろうとした罪。どう償うつもりだ?」
その声はどこまでも冷酷で、瞳は怒りで燃え上がっていた。
父は、大きなため息をついたあと、ニヤリと口端を上げる。
「リオ様、急に毒だと言われても私には、なんのことだかわかりません。まさか、その執事の証言だけを信じるつもりですか?」
「そんなっ、旦那さま!?」
このままだと父は、執事にすべての罪をかぶせて逃げてしまうのでは?
不安になった私がリオ様を見上げると、リオ様は「大丈夫ですよ。想定どおりです」と私の耳元でささやいた。
「セレナ嬢。捕らえられた敵兵たちの将が、自分だけ助かろうと配下に罪をなすりつけて見捨てると、どうなると思います?」
「わ、わかりません」
「多くは、だったら自分も助かりたいと、壮絶な罪の擦り付け合い、足の引っ張り合いになるんですよ」
「は、はぁ?」
「この邸宅内から逃げ場をなくし、同じような環境を作ったので、おそらく今からそれが始まるでしょう」
私は、リオ様の言っていることが、少しも理解できなかった。