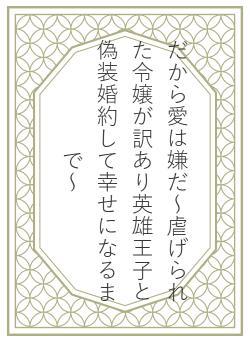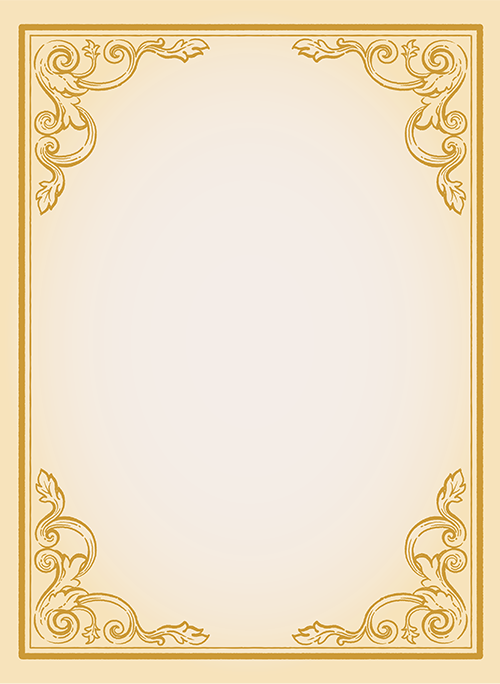ボソボソとした話し声が聞こえる。
「――ですから、おそらく骨にヒビが入っていますね」
「骨にヒビ!?」
驚く女性の声で、それまでぼんやりとしていた私の意識がハッキリとした。
目を開くと白い天井が見える。すぐに誠実そうな青年が私の顔をのぞき込み「大丈夫ですか?」と聞いてくれた。
「……えっと?」
ダークブラウンの髪に、澄んだ紫色の瞳。今は心配そうに眉毛が下がっているけど、この顔は、たしか夜会会場で見たバルゴアの令息だったはず。
なぜかベッドに横になっていることに気がついた私は、起き上がろうとしたけど、あわててバルゴア令息に止められた。
「動いたらダメだ! 王宮医が言うには、骨にヒビが入っているそうです」
『王宮医』ということは、ここは王宮内にある治療施設なのね。
どうやら、あのゴギッと嫌な音が鳴ったときに、私の手首なり腕なりがポッキリいってしまったらしい。
その証拠に、私の右腕には添え木が当てられ、包帯でぐるぐる巻きにされている。ついでに腫れていた肩も治療してくれたようで、こちらも包帯が巻かれていた。包帯の下からは、薬特有の独特な匂いが漂っている。
「俺のせいで……すみません」
頭を深く下げたバルゴア令息に驚いてしまう。貴族がこんなに簡単に頭を下げていいの?
「あなたのせいではないでしょう? あなたは、体勢を崩した私を支えただけですから」
そのときに運悪くおかしな方向に力が入ってしまったのね。だから、バルゴア令息は別に悪くない。
当たり前のことを言っただけなのに、顔をあげたバルゴア令息はなぜか驚いていた。
王宮医が年配女性との話を切り上げて、こちらに近づいてくる。
「気がつきましたね。気分はどうですか? 吐き気はありませんか?」
「ありません」
私の答えに王宮医は、小さくうなずいた。
「それは良かったです。あなたの手首の骨にヒビが入っています。こちらで適切な処置をしましたが2~3日はひどく痛みますよ。とにかくひと月は、絶対に右腕を動かさないこと。安静にしていれば元通りになります」
ケガをしただけでなく、ひと月も右手を使えないとなると父や継母に何を言われるかわからない。あの家で安静にするなんて絶対に無理だった。
「安静にしないとどうなりますか?」
「手が動かしにくくなるといったような軽い後遺症が残るかもしれません」
「……そうですか。ありがとうございました」
ベッドから起き上がろうとした私を、なぜかバルゴア令息が支えてくれた。私の背中に大きな手が添えられている。
壁にかけられている鏡を見ると、右側は包帯でぐるぐる巻きになっているものの、私の姿はほぼ夜会に参加したままだった。少し髪が乱れてドレスにシワがよっているけど、外を歩けないほどじゃない。
私は王宮医に馬車を手配するように頼んだ。ケガ人なのだから、馬車くらいは貸してほしい。
バルゴア令息に「どこへ?」と尋ねられたので「家に帰ります」と当たり前のことを伝える。
「いや、待って! 俺が馬車で送ります! 叔母さん、いいですよね?」
叔母さんと呼ばれた年配女性は「もちろんよ」と、青い顔で力なくうなずいた。
バルゴアの令息に『叔母さん』と呼ばれるこの女性は、ターチェ伯爵夫人だ。
バルゴア辺境伯と親戚関係にあるターチェ家は、私の父と同じ伯爵位だけど、その権力差は歴然だった。
ようするに、バルゴアと親戚関係になるということは、王都でも権力をふるえるということ。
もし異母妹マリンがバルゴア令息に嫁いだら、私の家もターチェ家と同じような権力を持つことができる。
父はマリンに婿をとってもらい伯爵位を継がせたがっているけど、バルゴアの親戚になれるのなら、喜んでマリンを嫁に出すはず。
そうなると、私が婿をとることになるけど、父が連れてくる男なんてろくなもんじゃないでしょうね。
ハァとため息をつくと、急にバルゴア令息に左手をつかまれたので私は「ひっ」と悲鳴をあげた。
「あ、すみません! あなたがフラフラしていたので、こけそうで怖くて」
「そうだとしても、急に女性にふれるのはマナー違反です!」
「そ、そうですよね、すみません……」
申し訳なさそうにうつむくバルゴア令息は、今までの男性とは違い私を無理やり人気のないところに連れて行こうとしているわけではないみたい。
痛めた肩と手首が痛すぎて、たしかにフラフラしてしまっている。こけてしまったら大変だ。
私はまだしょんぼりしているバルゴア令息の右腕にふれた。
「でしたら、手をつかむのではなく、あなたの腕を貸してください」
「え?」
驚くバルゴア令息に「エスコートです。私を馬車までエスコートしてください」と伝えると「ああ、王都に来る前に練習したあれですね!」とポンと手を打つ。
練習したあれって……。
もしかしてバルゴア領では女性をエスコートするという習慣がないのかしら?
田舎だとは聞いていたけど、王都とはだいぶ違った生活をしているみたい。それとも、この令息が変わっているだけ?
エスコートをうけながら歩き出した私に、バルゴア令息が話しかけてきた。
「叔母さんから聞いたんですが、あなたのお名前セレナ嬢、ですよね?」
どうせ私の悪いウワサでも聞いたんでしょう。そう思って無視していると、「セレナ嬢は、有名な女優さんなんですか?」とわけのわからないことを言ってきた。
「……は?」
バカにされていると思い、バルゴア令息をにらみつけると、その顔にはニコニコ笑顔が浮かんでいる。
「いやぁ、素晴らしい演技でした。さっきのあれ『悪役令嬢』っていうんでしょう? 俺の妹が『今、王都で流行ってる』って教えてくれたやつだ」
「あなた、さっきから何を言って……」
バルゴア令息は、私の言葉をさえぎり「俺はリオです。リオと呼んでください」と無邪気に笑う。
「あなたは……」
「リオですよ。リオ」
「では、リオ様は……」としぶしぶ折れた私に「様なんてつけなくていいのに」と馴れ馴れしいことを言ってきた。
少し話しただけでわかる。リオ様は、人から愛されることが当たり前で、他人を警戒する必要がない人生なのね。
いつも周囲の空気を読んで、その日その日をなんとか生き延びている私とは大違いだわ。
「私は女優ではありません。これでも一応、ファルトン伯爵家の長女です」
「え? それは失礼しました!」
「……どうして、私が女優だなんて思ったのですか?」
少し首をかしげたリオ様は、「だって、セレナ嬢がずっと演技をしていたから」と、当たり前のことのように真実を言い当てた。
母が亡くなったあと、私が異母妹マリンに無理やり悪役を演じさせられていることを、仲が良かった友人たちに話しても誰も信じてくれなかったのに。
一番、仲が良かったはずの子爵令嬢には事情をすべて説明して『助けて』と頼んだら、『へぇ、セレナって当主の伯爵様に嫌われてるんだぁ』とニタリと笑った。その日から、私は彼女に嫌がらせをされるようになった。
他の友人たちは、嫌がらせはしないものの、みんな、私と距離をとった。
もう誰も信じられない。
それなのにリオ様は、私が演技をしているとあの一瞬でわかったの?
まじまじとリオ様を見つめると「俺の顔に何かついてます?」とゴシゴシと顔をこする。
なんだか、自然体のリオ様を見ていると空気を読んで必死に自分を偽って生きていることがバカみたいに思えてきた。
「うらやましいわ」
私のつぶやきを聞いたリオ様が、またいろいろ質問してきたけど、もう何も答えなかった。私の家の事情なんて、他の人からすればどうでもいいことだって、もうわかっているから。
私を助けてくれる人なんてどこにもいない。かといって、あてもなく家出したお嬢様の末路なんて悲惨なものしか想像できない。
広い王宮内を歩き、やっとのことで馬車乗り場にたどりついたときに、背後から「お姉さま!」と呼びかけられた。
振りかえると、異母妹マリンがこちらにかけよってきている。
私がご希望通り、頭からワインをぶっかけてあげたのに、なぜかマリンは身綺麗になっていた。マリンからは、ほのかにワインの香りがするものの、ドレスは新しいものに着替えているし、髪もメイクも少しも崩れていない。
マリンの後ろには、大きな荷物を持ったマリン専属の護衛騎士と、控えめなドレスを着たマリン専属メイドの姿が見えた。
なるほど、着替えの準備は万端だったということなのね。
私にも一人、専属メイドがいるけど、彼女は平民なので夜会には参加できない。
貴族出身のメイドと護衛騎士は、マリンにだけつけられている。
それは、父がマリンだけを愛しているという証拠。
父の愛を一身に受けるマリンは、悲しそうな表情を浮かべた。
「お姉さま、今までどちらにいらしたのですか? ずっと探していたんですよ?」
私に話しかけているはずなのに、マリンの瞳はリオ様に向けられている。
はいはい、ケガした私をほったらかしにして、マリンは夜会を最後まで楽しんでいたのね。
あれだけ私にいじめられたあとだから、きっとたくさんの人がマリンを優しく慰めてくれたはず。
それに満足して、馬車で帰ろうとしたところに、偶然、バルゴア令息がいるのを見つけて、令息目当てにかけよってきたと。
「お姉さま!」
そう言いながら私に抱き着こうとしたマリンの顔面を、リオ様が左手でガシッとわしづかみにした。
予想外すぎる出来事に私は息をのんだ。
私だけじゃない。あのマリンが、儚げな演技をすることもできずぼうぜんとしている。マリンを守ることが仕事の護衛騎士ですら、あまりのことに対応できずポカンと口を開けていた。護衛騎士が持っていた大きな荷物が、ゴトッと地面に落ちる。
「セレナ嬢はケガをしている! 抱き着くなんてありえない! 見ればわかるでしょう!?」
リオ様の手の隙間から見えるマリンの頬がヒクッと引きつった。
リオ様は「なんて非常識なんだ!」と怒っているけど、急に女性の顔面をわしづかみにするような人に常識を語られたくない。
「セレナ嬢、これはあなたの知り合いですか?」
みんなに愛されている可愛いマリンを、これ呼ばわりする人を初めて見た。
「こ、これ……あ、はい。母は違いますが妹です」
「これがあなたの妹!? 俺が知っている妹とぜんぜん違う。それにあなたの妹にしては、演技が下手すぎでは?」
そういう問題なの!?
リオ様はようやくマリンの顔面から手を離した。ふらついたマリンを、あわてて護衛騎士が支えている。
顔面をつかまれていたマリンが痛がっている様子はない。ケガをしないように、リオ様なりに手加減はしてくれているようだ。
「これがあなたの妹ということは、同じ家に住んでいるんですよね? ケガを悪化させるような行動をとる者がいる場所に、あなたを帰すわけにはいきません」
マリンは表情を作るのも忘れるほど怒っているのか、恐ろしい顔をしていた。そんなマリンを気遣うような表情を浮かべてから、護衛騎士がこちらをにらみつける。
その憎しみがこもった視線をまったく相手にせず、リオ様は私を豪華な馬車内へとエスコートした。
護衛騎士がマリンを侮辱されたことに抗議でもするかと思ったけど、結局、彼は何も言わなかった。
伯爵令嬢のマリンだって、歯噛みをするだけで何も言えない。夜会帰りの多くの人が、この現場を遠巻きに見ていたけど、だれ一人リオ様に抗議する人はいなかった。
王都中の貴族を黙らせることができる、これがバルゴアの力なのね。
リオ様と私を乗せた馬車は、マリンと護衛騎士を残してゆっくりと動き出した。
むちゃくちゃな行動をとるリオ様に、恐怖を感じないわけではない。でも、それ以上にさっきのマリンの顔が面白すぎた。
ケガをしていないほうの手で顔を隠して必死にこらえていたのに、こらえきれずに私の両肩がゆれてしまう。
「あ、いたっ」
笑うと肩が痛いのに、笑うのをやめられない。
向かいの席に座っているリオ様が、心配そうにこちらを見ていた。
「セレナ嬢、大丈夫ですか?」
そんなことを言っているけど、この人はマリンの顔面をわしづかみにするような人だ。
もうダメ、我慢できない。
「ふ、ふふっ、リオ様って、不思議な方ですね」
笑いすぎて肩だけじゃなくて、お腹まで痛くなってきた。
ふとリオ様を見ると、私を凝視している。
「何か?」
「い、いえ……」
そういって顔をそらしたリオ様の耳は、なぜか赤くなっていた。
「――ですから、おそらく骨にヒビが入っていますね」
「骨にヒビ!?」
驚く女性の声で、それまでぼんやりとしていた私の意識がハッキリとした。
目を開くと白い天井が見える。すぐに誠実そうな青年が私の顔をのぞき込み「大丈夫ですか?」と聞いてくれた。
「……えっと?」
ダークブラウンの髪に、澄んだ紫色の瞳。今は心配そうに眉毛が下がっているけど、この顔は、たしか夜会会場で見たバルゴアの令息だったはず。
なぜかベッドに横になっていることに気がついた私は、起き上がろうとしたけど、あわててバルゴア令息に止められた。
「動いたらダメだ! 王宮医が言うには、骨にヒビが入っているそうです」
『王宮医』ということは、ここは王宮内にある治療施設なのね。
どうやら、あのゴギッと嫌な音が鳴ったときに、私の手首なり腕なりがポッキリいってしまったらしい。
その証拠に、私の右腕には添え木が当てられ、包帯でぐるぐる巻きにされている。ついでに腫れていた肩も治療してくれたようで、こちらも包帯が巻かれていた。包帯の下からは、薬特有の独特な匂いが漂っている。
「俺のせいで……すみません」
頭を深く下げたバルゴア令息に驚いてしまう。貴族がこんなに簡単に頭を下げていいの?
「あなたのせいではないでしょう? あなたは、体勢を崩した私を支えただけですから」
そのときに運悪くおかしな方向に力が入ってしまったのね。だから、バルゴア令息は別に悪くない。
当たり前のことを言っただけなのに、顔をあげたバルゴア令息はなぜか驚いていた。
王宮医が年配女性との話を切り上げて、こちらに近づいてくる。
「気がつきましたね。気分はどうですか? 吐き気はありませんか?」
「ありません」
私の答えに王宮医は、小さくうなずいた。
「それは良かったです。あなたの手首の骨にヒビが入っています。こちらで適切な処置をしましたが2~3日はひどく痛みますよ。とにかくひと月は、絶対に右腕を動かさないこと。安静にしていれば元通りになります」
ケガをしただけでなく、ひと月も右手を使えないとなると父や継母に何を言われるかわからない。あの家で安静にするなんて絶対に無理だった。
「安静にしないとどうなりますか?」
「手が動かしにくくなるといったような軽い後遺症が残るかもしれません」
「……そうですか。ありがとうございました」
ベッドから起き上がろうとした私を、なぜかバルゴア令息が支えてくれた。私の背中に大きな手が添えられている。
壁にかけられている鏡を見ると、右側は包帯でぐるぐる巻きになっているものの、私の姿はほぼ夜会に参加したままだった。少し髪が乱れてドレスにシワがよっているけど、外を歩けないほどじゃない。
私は王宮医に馬車を手配するように頼んだ。ケガ人なのだから、馬車くらいは貸してほしい。
バルゴア令息に「どこへ?」と尋ねられたので「家に帰ります」と当たり前のことを伝える。
「いや、待って! 俺が馬車で送ります! 叔母さん、いいですよね?」
叔母さんと呼ばれた年配女性は「もちろんよ」と、青い顔で力なくうなずいた。
バルゴアの令息に『叔母さん』と呼ばれるこの女性は、ターチェ伯爵夫人だ。
バルゴア辺境伯と親戚関係にあるターチェ家は、私の父と同じ伯爵位だけど、その権力差は歴然だった。
ようするに、バルゴアと親戚関係になるということは、王都でも権力をふるえるということ。
もし異母妹マリンがバルゴア令息に嫁いだら、私の家もターチェ家と同じような権力を持つことができる。
父はマリンに婿をとってもらい伯爵位を継がせたがっているけど、バルゴアの親戚になれるのなら、喜んでマリンを嫁に出すはず。
そうなると、私が婿をとることになるけど、父が連れてくる男なんてろくなもんじゃないでしょうね。
ハァとため息をつくと、急にバルゴア令息に左手をつかまれたので私は「ひっ」と悲鳴をあげた。
「あ、すみません! あなたがフラフラしていたので、こけそうで怖くて」
「そうだとしても、急に女性にふれるのはマナー違反です!」
「そ、そうですよね、すみません……」
申し訳なさそうにうつむくバルゴア令息は、今までの男性とは違い私を無理やり人気のないところに連れて行こうとしているわけではないみたい。
痛めた肩と手首が痛すぎて、たしかにフラフラしてしまっている。こけてしまったら大変だ。
私はまだしょんぼりしているバルゴア令息の右腕にふれた。
「でしたら、手をつかむのではなく、あなたの腕を貸してください」
「え?」
驚くバルゴア令息に「エスコートです。私を馬車までエスコートしてください」と伝えると「ああ、王都に来る前に練習したあれですね!」とポンと手を打つ。
練習したあれって……。
もしかしてバルゴア領では女性をエスコートするという習慣がないのかしら?
田舎だとは聞いていたけど、王都とはだいぶ違った生活をしているみたい。それとも、この令息が変わっているだけ?
エスコートをうけながら歩き出した私に、バルゴア令息が話しかけてきた。
「叔母さんから聞いたんですが、あなたのお名前セレナ嬢、ですよね?」
どうせ私の悪いウワサでも聞いたんでしょう。そう思って無視していると、「セレナ嬢は、有名な女優さんなんですか?」とわけのわからないことを言ってきた。
「……は?」
バカにされていると思い、バルゴア令息をにらみつけると、その顔にはニコニコ笑顔が浮かんでいる。
「いやぁ、素晴らしい演技でした。さっきのあれ『悪役令嬢』っていうんでしょう? 俺の妹が『今、王都で流行ってる』って教えてくれたやつだ」
「あなた、さっきから何を言って……」
バルゴア令息は、私の言葉をさえぎり「俺はリオです。リオと呼んでください」と無邪気に笑う。
「あなたは……」
「リオですよ。リオ」
「では、リオ様は……」としぶしぶ折れた私に「様なんてつけなくていいのに」と馴れ馴れしいことを言ってきた。
少し話しただけでわかる。リオ様は、人から愛されることが当たり前で、他人を警戒する必要がない人生なのね。
いつも周囲の空気を読んで、その日その日をなんとか生き延びている私とは大違いだわ。
「私は女優ではありません。これでも一応、ファルトン伯爵家の長女です」
「え? それは失礼しました!」
「……どうして、私が女優だなんて思ったのですか?」
少し首をかしげたリオ様は、「だって、セレナ嬢がずっと演技をしていたから」と、当たり前のことのように真実を言い当てた。
母が亡くなったあと、私が異母妹マリンに無理やり悪役を演じさせられていることを、仲が良かった友人たちに話しても誰も信じてくれなかったのに。
一番、仲が良かったはずの子爵令嬢には事情をすべて説明して『助けて』と頼んだら、『へぇ、セレナって当主の伯爵様に嫌われてるんだぁ』とニタリと笑った。その日から、私は彼女に嫌がらせをされるようになった。
他の友人たちは、嫌がらせはしないものの、みんな、私と距離をとった。
もう誰も信じられない。
それなのにリオ様は、私が演技をしているとあの一瞬でわかったの?
まじまじとリオ様を見つめると「俺の顔に何かついてます?」とゴシゴシと顔をこする。
なんだか、自然体のリオ様を見ていると空気を読んで必死に自分を偽って生きていることがバカみたいに思えてきた。
「うらやましいわ」
私のつぶやきを聞いたリオ様が、またいろいろ質問してきたけど、もう何も答えなかった。私の家の事情なんて、他の人からすればどうでもいいことだって、もうわかっているから。
私を助けてくれる人なんてどこにもいない。かといって、あてもなく家出したお嬢様の末路なんて悲惨なものしか想像できない。
広い王宮内を歩き、やっとのことで馬車乗り場にたどりついたときに、背後から「お姉さま!」と呼びかけられた。
振りかえると、異母妹マリンがこちらにかけよってきている。
私がご希望通り、頭からワインをぶっかけてあげたのに、なぜかマリンは身綺麗になっていた。マリンからは、ほのかにワインの香りがするものの、ドレスは新しいものに着替えているし、髪もメイクも少しも崩れていない。
マリンの後ろには、大きな荷物を持ったマリン専属の護衛騎士と、控えめなドレスを着たマリン専属メイドの姿が見えた。
なるほど、着替えの準備は万端だったということなのね。
私にも一人、専属メイドがいるけど、彼女は平民なので夜会には参加できない。
貴族出身のメイドと護衛騎士は、マリンにだけつけられている。
それは、父がマリンだけを愛しているという証拠。
父の愛を一身に受けるマリンは、悲しそうな表情を浮かべた。
「お姉さま、今までどちらにいらしたのですか? ずっと探していたんですよ?」
私に話しかけているはずなのに、マリンの瞳はリオ様に向けられている。
はいはい、ケガした私をほったらかしにして、マリンは夜会を最後まで楽しんでいたのね。
あれだけ私にいじめられたあとだから、きっとたくさんの人がマリンを優しく慰めてくれたはず。
それに満足して、馬車で帰ろうとしたところに、偶然、バルゴア令息がいるのを見つけて、令息目当てにかけよってきたと。
「お姉さま!」
そう言いながら私に抱き着こうとしたマリンの顔面を、リオ様が左手でガシッとわしづかみにした。
予想外すぎる出来事に私は息をのんだ。
私だけじゃない。あのマリンが、儚げな演技をすることもできずぼうぜんとしている。マリンを守ることが仕事の護衛騎士ですら、あまりのことに対応できずポカンと口を開けていた。護衛騎士が持っていた大きな荷物が、ゴトッと地面に落ちる。
「セレナ嬢はケガをしている! 抱き着くなんてありえない! 見ればわかるでしょう!?」
リオ様の手の隙間から見えるマリンの頬がヒクッと引きつった。
リオ様は「なんて非常識なんだ!」と怒っているけど、急に女性の顔面をわしづかみにするような人に常識を語られたくない。
「セレナ嬢、これはあなたの知り合いですか?」
みんなに愛されている可愛いマリンを、これ呼ばわりする人を初めて見た。
「こ、これ……あ、はい。母は違いますが妹です」
「これがあなたの妹!? 俺が知っている妹とぜんぜん違う。それにあなたの妹にしては、演技が下手すぎでは?」
そういう問題なの!?
リオ様はようやくマリンの顔面から手を離した。ふらついたマリンを、あわてて護衛騎士が支えている。
顔面をつかまれていたマリンが痛がっている様子はない。ケガをしないように、リオ様なりに手加減はしてくれているようだ。
「これがあなたの妹ということは、同じ家に住んでいるんですよね? ケガを悪化させるような行動をとる者がいる場所に、あなたを帰すわけにはいきません」
マリンは表情を作るのも忘れるほど怒っているのか、恐ろしい顔をしていた。そんなマリンを気遣うような表情を浮かべてから、護衛騎士がこちらをにらみつける。
その憎しみがこもった視線をまったく相手にせず、リオ様は私を豪華な馬車内へとエスコートした。
護衛騎士がマリンを侮辱されたことに抗議でもするかと思ったけど、結局、彼は何も言わなかった。
伯爵令嬢のマリンだって、歯噛みをするだけで何も言えない。夜会帰りの多くの人が、この現場を遠巻きに見ていたけど、だれ一人リオ様に抗議する人はいなかった。
王都中の貴族を黙らせることができる、これがバルゴアの力なのね。
リオ様と私を乗せた馬車は、マリンと護衛騎士を残してゆっくりと動き出した。
むちゃくちゃな行動をとるリオ様に、恐怖を感じないわけではない。でも、それ以上にさっきのマリンの顔が面白すぎた。
ケガをしていないほうの手で顔を隠して必死にこらえていたのに、こらえきれずに私の両肩がゆれてしまう。
「あ、いたっ」
笑うと肩が痛いのに、笑うのをやめられない。
向かいの席に座っているリオ様が、心配そうにこちらを見ていた。
「セレナ嬢、大丈夫ですか?」
そんなことを言っているけど、この人はマリンの顔面をわしづかみにするような人だ。
もうダメ、我慢できない。
「ふ、ふふっ、リオ様って、不思議な方ですね」
笑いすぎて肩だけじゃなくて、お腹まで痛くなってきた。
ふとリオ様を見ると、私を凝視している。
「何か?」
「い、いえ……」
そういって顔をそらしたリオ様の耳は、なぜか赤くなっていた。