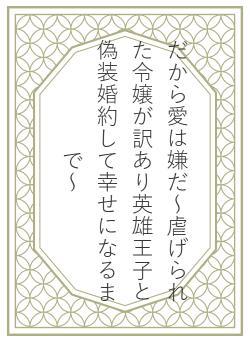私はぼんやりと窓の外を眺めていた。
ターチェ家の庭園は、とても広く美しい。でも、今の私は花を愛でる余裕がない。
異母妹マリンが、コニーに渡したガラスの小瓶。
もし、あの中身が毒だったとしたら……。
私は母が亡くなったときのことを思い出していた。
祖父が病に倒れベッドから起き上がれなくなったころ、母にも同じような症状が現れた。
吐き気やひどい頭痛に苦しみながら、母の食はどんどんと細くなっていく。お医者さんに見てもらっても、原因がわからず吐き気止めと痛み止めの薬を処方されるだけだった。
祖父も母も苦しんだ末に衰弱して亡くなった。
もし、あれが、病ではなく毒のせいだったら?
祖父と母が亡くなったのは、マリンたちがファルトン家に来る前のこと。だとしたら、祖父と母に毒を盛ったのは……。
私は父の冷酷な瞳を思い出し全身がふるえた。
「セレナお嬢様、寒いんですか?」
コニーの言葉で我に返る。
「ううん、大丈夫よ」
そう、大丈夫。これは私の想像で、まだそうだと決まったわけではないのだから。
「庭園のお花が綺麗だから見惚れていただけ」
「でしたら、バルコニーでお茶にしませんか?」
「いいわね、コニーも一緒にお茶にしましょうね」
「はい! お嬢様は、こちらに座ってください」
バルコニーに置かれているテーブルセットの椅子を、コニーが座りやすいように後ろに引いてくれた。ここからは庭園が一望できる。
リオ様やターチェ家の人たちは、私にとてもよい客室を貸してくれているのね。ターチェ家のメイドたちもすごく良くしてくれるし、ここまでしてもらうとなんだか申し訳なくなってくる。
かといって、他に行く当てもないので、大人しくお世話になるしかない。
腕のケガが治ったら、どうしようかしら?
もう二度と実家のファルトン家に帰るつもりはない。ターチェ家かバルゴア領で職を紹介してもらうのもいいかも?
頑張って働いて、小さな家を借りてコニーと一緒に暮らせたらとても幸せだと思う。
そんなことを考えていたら、リオ様が部屋に来た。王都で有名なお菓子を買ってきてくれたらしい。
リオ様が、水色のリボンをほどいて箱を開けると甘酸っぱいリンゴの香りが漂う。
「ありがとうございます。皆でいただきましょう。コニー、リオ様やエディ様の分のお茶も淹(い)れてくれる?」
「……はーい」
不満そうなコニーの襟首をエディ様がつかんだ。
「態度が悪いぞ、狂犬メイド!」
「お前にだけは言われたくない! あ、セレナお嬢様、エディ様はお茶いらないそうですー」
「いるわ! 飲むし食べるわ!」
エディ様は「それを買うの大変だったんだからな!?」とコニーに愚痴っている。
私がリオ様に「大変だったのですか?」と尋ねると、リオ様は「いや、ぜんぜん」と首をふった。
切り分けるためにコニーがタルトにナイフを刺すとサクッと良い音がする。
「お嬢様……これは、絶対、おいしいやつです」
「そうね、これは絶対においしいやつだわ」
コニーの瞳がキラキラ輝いているけど、たぶん、私の目もそんな感じになっていると思う。
予想通りというか、予想を遥かに超えてリンゴのタルトはおいしかった。
「んー!!!」
あまりのおいしさに、心の中で買ってきてくれたリオ様に感謝の祈りを捧げてしまう。
リオ様は、終始ニコニコしていた。なんだろう、この人。いつも機嫌が良いし、美味しいものをたくさんくれるし、すごく良い人だわ。
いつでも不機嫌そうににらみつけてくる私の父とは大違い。
父に冷遇される母を見て育ったから、結婚に少しの憧れも持っていなかったけど、きっとこういう人と結婚したら、結婚後も幸せになれるのね。
「とっても美味しかったです。ありがとうございます。リオ様のお嫁さんになれる方は幸せですね」
心の底から感謝の気持ちを伝えると、お茶を飲んでいたエディ様がゴフッと小さくむせた。
「大丈夫ですか?」
「……大丈夫です。そのセレナ様はご結婚の予定、いや予定というか、結婚するつもりはないんですか?」
「結婚ですか……」
貴族の嫁入りには持参金が必要だった。父が私のために持参金を用意してくれるはずがない。
もしマリンが他に嫁いだら、私が無理やり婿を取らされて跡を継ぐこともあるかもしれないと思っていたけど、もうあの家には帰らないので、その可能性もなくなった。
家を出た私は、平民として生きていくことになると思う。これまでは怖くてその選択ができなかったけど、ターチェ家やリオ様と繋がりができた今ならなんとかなりそうな気がしている。
「生きることに精一杯で、結婚なんて考えたこともないです」
「そ、なんですね」
「それに、『社交界の毒婦』なんて呼ばれている私を妻に求める人なんていませんわ」
「そんなことは……」
エディ様はなぜかリオ様をチラチラ見ているけど、リオ様は変わらずニコニコしているだけだった。
タルトを食べ終わったコニーが「そういえば、ガラスの小瓶の中身、なんだったんですか?」と聞いてくれた。
私もそのことが気になっていた。
一瞬顔を見合わせたリオ様とエディ様。
「調べたのですが、中身は水でした」
コニーが椅子から立ち上がり「そんなわけない!」と叫ぶ。
「マリンの言い方だと、あれは毒だ!」
コニーの言う通り、私もマリンはコニーに毒を渡したのだと思う。ただ、中身がマリンが思っていたものじゃなかっただけでは……?
となると、ガラスの小瓶はマリンのものじゃない。もしかして、父の持ち物をマリンが勝手に持ち出したから、中身を間違えたの?
そう考えたらすべてのつじつまが合ってしまう。
リオ様に「セレナ嬢、顔が真っ青ですよ!?」と声をかけられて、私は自分がうつむいていたことに気がついた。
「気分が悪いんですか?」
「少し……きゃあ!?」
うなずいたとたんに、リオ様が私を抱きかかえたので悲鳴を上げてしまう。
「寝室へ運びます!」
「そこまでではないです!」
「ダメです、休んでください。エディ、医者を呼んでくれ! コニーは水を!」
テキパキと指示するリオ様。気がつけば、私はリオ様にベッドに寝かしつけられていた。
「すぐに医者がきます。ゆっくり休んでください」
「どうして、ここまで……」
困惑しながら尋ねると「それは、俺がケガをさせてしまったから」という聞きなれた言葉が返ってくる。
真面目すぎるというか、なんというか。
こんなに後悔しているなら、罪悪感から私の言うことをなんでも聞いてくれそうな気がしてきた。最低な考え方だけど、これを利用しない手はない。
ベッドの側から離れようとしたリオ様の服の袖を私はつかんだ。
「リオ様……」
「えっ、は、はい?」
私はベッドから上半身を起こすと、私が思いついてしまった最悪の事態のことをリオ様に話した。普通の人ならバカバカしいと鼻で笑われるような話だけど、なぜかリオ様ならちゃんと私の話を聞いてくれる気がする。
「もしかすると、祖父と私の母は……父に毒を盛られていたのかも……?」
今思えば、おかしなことがたくさんあったのに、なぜかあのときはその可能性にたどりつけなかった。毒なら銀食器に反応するだろうという思い込みと、いくら父が祖父や母を憎んでいるからといって、そこまではしないだろうという甘い考え。
母や私のことが嫌いでも、父と私は血がつながった家族なのだからという幻想が音を立てて崩れていく。
あの家で暮らしていたら、私もいつか毒を盛られて殺されていたのかもしれない。ううん、わざわざ私を生かしているのだから、それよりもっとひどいめに遭(あ)わされていたのかも?
「今までは、父と縁が切れてあの家から出ていければ、それでいいと思っていました。でも、もし、父が祖父や母を殺しているのなら……。私は父を……あの男を絶対に許さない」
私の声は情けないくらいふるえていた。でも、この決心だけは揺らがない。
私はリオ様に深く頭を下げた。そのときに、固定されている右腕が痛んだけど、気にしている場合じゃない。
「リオ様、もうお菓子も慰謝料もいりません。私にケガをさせて悪いと思っているのなら、真相を解き明かす手助けをしてください。お願いします!」
断られたら、ケガをさせたことで脅してやろうと思っていた。それなのに、リオ様はあっさりと同意する。
「わかりました」
「……いいのですか?」
「え? はい、もちろん。でもなぁ」
腕を組んだリオ様は、困った顔をしている。
「俺、考えるのが苦手なので、とりあえずファルトン家に乗り込んでいいですか?」
「乗り込む、ですか?」
「はい、悪い奴は見たらだいたいわかりますから」
「そういうものなんですか?」
「そういうものなんです」
きっぱりと言い切ったリオ様。もしかして、バルゴア領の人は皆わかることなの? だから、バルゴアはこの国最強とか言われているの?
なんだかよくわからないけど、私はすごい味方を手に入れたみたい。
「でしたら、私も一緒に行きます」
「うーん、セレナ嬢にはここに残ってほしいけど、たぶんセレナ嬢がいたほうが相手の悪意がわかりやすいと思うんですよ。だから、一緒に行きましょう」
「はい」
ニコリと微笑んだリオ様は、誠実そうな瞳で私を見つめている。
「大丈夫、何があっても俺が必ずあなたを守ります」
考えることが苦手だと言うリオ様は、たぶん何も考えていない。だから、この言葉にはなんの意味も込められていない。
それがわかっているのに、私は……不覚にもときめいてしまった。
ターチェ家の庭園は、とても広く美しい。でも、今の私は花を愛でる余裕がない。
異母妹マリンが、コニーに渡したガラスの小瓶。
もし、あの中身が毒だったとしたら……。
私は母が亡くなったときのことを思い出していた。
祖父が病に倒れベッドから起き上がれなくなったころ、母にも同じような症状が現れた。
吐き気やひどい頭痛に苦しみながら、母の食はどんどんと細くなっていく。お医者さんに見てもらっても、原因がわからず吐き気止めと痛み止めの薬を処方されるだけだった。
祖父も母も苦しんだ末に衰弱して亡くなった。
もし、あれが、病ではなく毒のせいだったら?
祖父と母が亡くなったのは、マリンたちがファルトン家に来る前のこと。だとしたら、祖父と母に毒を盛ったのは……。
私は父の冷酷な瞳を思い出し全身がふるえた。
「セレナお嬢様、寒いんですか?」
コニーの言葉で我に返る。
「ううん、大丈夫よ」
そう、大丈夫。これは私の想像で、まだそうだと決まったわけではないのだから。
「庭園のお花が綺麗だから見惚れていただけ」
「でしたら、バルコニーでお茶にしませんか?」
「いいわね、コニーも一緒にお茶にしましょうね」
「はい! お嬢様は、こちらに座ってください」
バルコニーに置かれているテーブルセットの椅子を、コニーが座りやすいように後ろに引いてくれた。ここからは庭園が一望できる。
リオ様やターチェ家の人たちは、私にとてもよい客室を貸してくれているのね。ターチェ家のメイドたちもすごく良くしてくれるし、ここまでしてもらうとなんだか申し訳なくなってくる。
かといって、他に行く当てもないので、大人しくお世話になるしかない。
腕のケガが治ったら、どうしようかしら?
もう二度と実家のファルトン家に帰るつもりはない。ターチェ家かバルゴア領で職を紹介してもらうのもいいかも?
頑張って働いて、小さな家を借りてコニーと一緒に暮らせたらとても幸せだと思う。
そんなことを考えていたら、リオ様が部屋に来た。王都で有名なお菓子を買ってきてくれたらしい。
リオ様が、水色のリボンをほどいて箱を開けると甘酸っぱいリンゴの香りが漂う。
「ありがとうございます。皆でいただきましょう。コニー、リオ様やエディ様の分のお茶も淹(い)れてくれる?」
「……はーい」
不満そうなコニーの襟首をエディ様がつかんだ。
「態度が悪いぞ、狂犬メイド!」
「お前にだけは言われたくない! あ、セレナお嬢様、エディ様はお茶いらないそうですー」
「いるわ! 飲むし食べるわ!」
エディ様は「それを買うの大変だったんだからな!?」とコニーに愚痴っている。
私がリオ様に「大変だったのですか?」と尋ねると、リオ様は「いや、ぜんぜん」と首をふった。
切り分けるためにコニーがタルトにナイフを刺すとサクッと良い音がする。
「お嬢様……これは、絶対、おいしいやつです」
「そうね、これは絶対においしいやつだわ」
コニーの瞳がキラキラ輝いているけど、たぶん、私の目もそんな感じになっていると思う。
予想通りというか、予想を遥かに超えてリンゴのタルトはおいしかった。
「んー!!!」
あまりのおいしさに、心の中で買ってきてくれたリオ様に感謝の祈りを捧げてしまう。
リオ様は、終始ニコニコしていた。なんだろう、この人。いつも機嫌が良いし、美味しいものをたくさんくれるし、すごく良い人だわ。
いつでも不機嫌そうににらみつけてくる私の父とは大違い。
父に冷遇される母を見て育ったから、結婚に少しの憧れも持っていなかったけど、きっとこういう人と結婚したら、結婚後も幸せになれるのね。
「とっても美味しかったです。ありがとうございます。リオ様のお嫁さんになれる方は幸せですね」
心の底から感謝の気持ちを伝えると、お茶を飲んでいたエディ様がゴフッと小さくむせた。
「大丈夫ですか?」
「……大丈夫です。そのセレナ様はご結婚の予定、いや予定というか、結婚するつもりはないんですか?」
「結婚ですか……」
貴族の嫁入りには持参金が必要だった。父が私のために持参金を用意してくれるはずがない。
もしマリンが他に嫁いだら、私が無理やり婿を取らされて跡を継ぐこともあるかもしれないと思っていたけど、もうあの家には帰らないので、その可能性もなくなった。
家を出た私は、平民として生きていくことになると思う。これまでは怖くてその選択ができなかったけど、ターチェ家やリオ様と繋がりができた今ならなんとかなりそうな気がしている。
「生きることに精一杯で、結婚なんて考えたこともないです」
「そ、なんですね」
「それに、『社交界の毒婦』なんて呼ばれている私を妻に求める人なんていませんわ」
「そんなことは……」
エディ様はなぜかリオ様をチラチラ見ているけど、リオ様は変わらずニコニコしているだけだった。
タルトを食べ終わったコニーが「そういえば、ガラスの小瓶の中身、なんだったんですか?」と聞いてくれた。
私もそのことが気になっていた。
一瞬顔を見合わせたリオ様とエディ様。
「調べたのですが、中身は水でした」
コニーが椅子から立ち上がり「そんなわけない!」と叫ぶ。
「マリンの言い方だと、あれは毒だ!」
コニーの言う通り、私もマリンはコニーに毒を渡したのだと思う。ただ、中身がマリンが思っていたものじゃなかっただけでは……?
となると、ガラスの小瓶はマリンのものじゃない。もしかして、父の持ち物をマリンが勝手に持ち出したから、中身を間違えたの?
そう考えたらすべてのつじつまが合ってしまう。
リオ様に「セレナ嬢、顔が真っ青ですよ!?」と声をかけられて、私は自分がうつむいていたことに気がついた。
「気分が悪いんですか?」
「少し……きゃあ!?」
うなずいたとたんに、リオ様が私を抱きかかえたので悲鳴を上げてしまう。
「寝室へ運びます!」
「そこまでではないです!」
「ダメです、休んでください。エディ、医者を呼んでくれ! コニーは水を!」
テキパキと指示するリオ様。気がつけば、私はリオ様にベッドに寝かしつけられていた。
「すぐに医者がきます。ゆっくり休んでください」
「どうして、ここまで……」
困惑しながら尋ねると「それは、俺がケガをさせてしまったから」という聞きなれた言葉が返ってくる。
真面目すぎるというか、なんというか。
こんなに後悔しているなら、罪悪感から私の言うことをなんでも聞いてくれそうな気がしてきた。最低な考え方だけど、これを利用しない手はない。
ベッドの側から離れようとしたリオ様の服の袖を私はつかんだ。
「リオ様……」
「えっ、は、はい?」
私はベッドから上半身を起こすと、私が思いついてしまった最悪の事態のことをリオ様に話した。普通の人ならバカバカしいと鼻で笑われるような話だけど、なぜかリオ様ならちゃんと私の話を聞いてくれる気がする。
「もしかすると、祖父と私の母は……父に毒を盛られていたのかも……?」
今思えば、おかしなことがたくさんあったのに、なぜかあのときはその可能性にたどりつけなかった。毒なら銀食器に反応するだろうという思い込みと、いくら父が祖父や母を憎んでいるからといって、そこまではしないだろうという甘い考え。
母や私のことが嫌いでも、父と私は血がつながった家族なのだからという幻想が音を立てて崩れていく。
あの家で暮らしていたら、私もいつか毒を盛られて殺されていたのかもしれない。ううん、わざわざ私を生かしているのだから、それよりもっとひどいめに遭(あ)わされていたのかも?
「今までは、父と縁が切れてあの家から出ていければ、それでいいと思っていました。でも、もし、父が祖父や母を殺しているのなら……。私は父を……あの男を絶対に許さない」
私の声は情けないくらいふるえていた。でも、この決心だけは揺らがない。
私はリオ様に深く頭を下げた。そのときに、固定されている右腕が痛んだけど、気にしている場合じゃない。
「リオ様、もうお菓子も慰謝料もいりません。私にケガをさせて悪いと思っているのなら、真相を解き明かす手助けをしてください。お願いします!」
断られたら、ケガをさせたことで脅してやろうと思っていた。それなのに、リオ様はあっさりと同意する。
「わかりました」
「……いいのですか?」
「え? はい、もちろん。でもなぁ」
腕を組んだリオ様は、困った顔をしている。
「俺、考えるのが苦手なので、とりあえずファルトン家に乗り込んでいいですか?」
「乗り込む、ですか?」
「はい、悪い奴は見たらだいたいわかりますから」
「そういうものなんですか?」
「そういうものなんです」
きっぱりと言い切ったリオ様。もしかして、バルゴア領の人は皆わかることなの? だから、バルゴアはこの国最強とか言われているの?
なんだかよくわからないけど、私はすごい味方を手に入れたみたい。
「でしたら、私も一緒に行きます」
「うーん、セレナ嬢にはここに残ってほしいけど、たぶんセレナ嬢がいたほうが相手の悪意がわかりやすいと思うんですよ。だから、一緒に行きましょう」
「はい」
ニコリと微笑んだリオ様は、誠実そうな瞳で私を見つめている。
「大丈夫、何があっても俺が必ずあなたを守ります」
考えることが苦手だと言うリオ様は、たぶん何も考えていない。だから、この言葉にはなんの意味も込められていない。
それがわかっているのに、私は……不覚にもときめいてしまった。