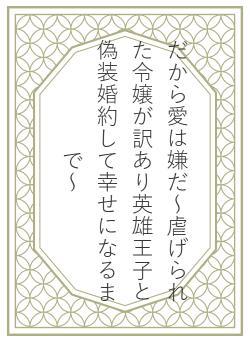俺の幼馴染エディがさっきからずっとブツブツと文句を言っている。
まぁピンク色の可愛らしい菓子店の行列に、むさ苦しい男二人で並んでいるので、文句を言いたくなる気持ちもわかる。
「そんなに嫌ならついて来なくていいのに……」
俺があきれた視線を向けると、エディは「これでも俺はお前の護衛騎士なんだよ!」と目を吊り上げている。
「どうしてリオが並ぶんだ! こういうことは、ターチェ家の使用人に任せればいいだろ?」
エディの言うことはもっともで、列には貴族の使用人と思われる人も多くいた。
「でも、あの家の中で一番ヒマなの俺だし」
「はぁ?」
バルゴア領にいたときと違い、王都では嫁探しをすること以外やることがない。俺の護衛騎士としてついて来たエディも、ヒマを持て余しているはずだ。
「ヒマって、嫁探しはしなくていいのかよ?」
エディの言葉に俺はなぜか驚いてしまった。
「あ、いや、今はほら、セレナ嬢の世話が……」
「世話は狂犬メイドがやってるからしなくていいだろ?」
「うっ」
エディの言う通り、セレナ嬢の世話係役をコニーに取られてしまった。セレナ嬢自身も俺に世話をされるより、気心の知れたメイドに世話をしてもらうほうが良いらしい。
「だから、王都で有名な菓子でも買って贈ろうかと……」
「どうしてだよ?」
「どうしてって、そうすればセレナ嬢が喜んでくれる、から?」
エディがなんとも言えない顔をした。腕を組みながら「ケガをさせた罪悪感か? それともそっちなのか?」と唸(うな)っている。
そうしているうちに列が進み、俺は無事に有名店の菓子を買えた。
このリンゴのタルトは、甘みと酸味が程よくタルト部分がサクサクですごく美味しいと叔母さんが言っていた。
贈り物だと伝えると、店員がリボンをつけてくれると言うので水色のリボンをつけてもらった。
「無事に買えて良かったな。せっかく街まで来たんだから、薬師のところに寄ってから帰ろうぜ」
「ああ、そうだな」
コニーからガラスの小瓶を受け取ったエディは、あのあとターチェ家の使用人に聞いて、信頼できる薬師を紹介してもらったらしい。
ガラスの小瓶の中身がなんだったのか、俺も早く知りたい。
有名菓子店があった大通りから離れ、裏道に入ったところにその薬師は店を構えていた。年季の入った店構えで、店前には葉が茂った植木鉢がズラリと並んでいる。
薬草ばかりだったけど、俺が知らない植物もあった。
エディは木の扉をドンドン叩くと「じぃさんいる?」と大声を出す。中から返事はない。
「あれいないのかな?」
ドンドンドンと扉を叩いていると「うるさい!」と中から怒鳴り声がした。
「あ、なんだいたのか!」
エディが店の扉を開けたとたんに、強烈な薬の臭いが辺りに漂う。
「う」
「リオ、臭かったら外で待っていていいぞ」
「いや、俺も入る」
店の中では白髪の老人がすり鉢で何かをすり潰していた。俺たちの姿を見て「まったく田舎者はこれだから」と悪態をつく。
「じぃさん、昨日頼んだヤツ、調べておいてくれたか?」
「ああ、あれな」
薬師は立ち上がると、奥からガラスの小瓶を取ってきた。
「これは薬じゃない。ただの水じゃよ」
「だとよ、リオ」
「やっぱり水だったか」
俺の言葉に薬師は目を鋭くした。
「わかっていたのか?」
「いや、確信がなかったんだ。調べてもらって助かったよ」
エディが薬師に代金を支払っている。
ふと気になった俺は「この店では毒も取り扱っているのか?」と聞いてみた。
代金を受け取った薬師は「まさか」と首をふる。
「そういうのがほしいのなら、情報屋に行きな。裏社会の連中と繋げてくれるさ。まぁとんでもない金額を要求されるがな」
やはり王都でも毒は、簡単に手に入るものではないようだ。
ガラスの小瓶は、セレナ嬢の妹のイタズラだったのか? でも、そうだとしたらなんのために?
「う、考えるのは苦手だ。いっそのこと本人たちに会えば悪意がわかるのになぁ」
「ファルトン伯爵家に乗り込むつもりか? さすがに捕まるぞ」
「そうだな」
エディと共にターチェ伯爵家に戻ると、ちょうど叔父さんも帰ってきたところだった。
「リオくん、ちょっといいかな?」
「はい」
叔父さんの執務室に通された俺たちは、ソファーにかけるように言われた。こういうときのエディは数歩下がって黙って俺の背後に立っている。
主(あるじ)と護衛騎士は、本来ならこの距離が正しいけど、俺のほうから二人のときは今まで通りにしてくれと頼んでいた。
向かいのソファーに座った叔父さんは小さなため息をつく。
「セレナさんのことだけどね」
叔父さんは、いろいろとファルトン伯爵家のことを調べてくれたそうだ。
「やはりセレナさんの言っていることが正しいようだね」
「と、言うと?」
「セレナさんは、ファルトン伯爵家で家族と認められていなかったみたいだよ」
叔父さんが言うには、ファルトン伯爵家は仲の良い『三人』家族だそうだ。
「高級レストランで食事をしたり、服飾士を呼んでドレスを作ったりする際も、伯爵と伯爵夫人、その娘の三人しか目撃されていないんだ。店の若い従業員や服飾士にセレナさんのことを聞いたら、『もう一人娘さんがいたんですか?』と驚かれてしまったよ」
それでも、長く勤めている店員たちは、セレナ嬢のことを知っていた。でも、数年前にセレナ嬢の母が亡くなったときに、セレナ嬢も一緒に亡くなったかと思われていたそうだ。
「それくらい、セレナさんは外に出ていなかったようだね」
「家の中に閉じ込められていたってことですか?」
自分が思っていた以上に冷たい声が出た。
「そういうことだろうね。セレナさんは、貴族が集まる夜会にだけは出ていて『社交界の毒婦』なんて呼ばれていたけど、社交界を知らない人たちに聞いたら、すぐに真実が浮き上がってきたよ」
「これでセレナ嬢を助けられるんですか?」
「いや、これだけでは無理だね。いろいろ調べているうちにわかったことなんだけど、セレナさんの母親が亡くなったあとに、ファルトン家では大量に使用人が解雇されたそうなんだ」
叔父さんは、今、そのときに解雇された使用人を探してくれているそうだ。
「ありがとうございます。叔父さん」
叔父さんは「まぁ、これも何かの縁だから」とニコリと微笑む。
解雇された使用人たちが見つかり、セレナ嬢がひどい目に遭(あ)わされていたという証言を得られれば、セレナ嬢はあの家と縁を切れる。
早くそうなればいいと願いながら、俺はセレナ嬢の部屋の扉をノックした。なぜかエディも付いてきている。
すぐに「はーい」という声が聞こえてコニーが顔を出した。
「げ」
「げって」
コニーは未だに俺を警戒している。まぁ、大切な主(あるじ)の腕を折った男だから仕方がない。
「セレナお嬢様に、何か用ですか?」
俺は手に持っていた箱を見せた。
「王都で有名な菓子を買って来たんだ」
「へぇ、じゃあ、お嬢様に渡しておきます」
箱を受け取ろうとしたコニーから逃げるように俺は後ずさる。
「なんなんですか?」
「いや、直接渡したいなって」
「はぁ?」
だって直接渡さないと、喜んでもらえたかわからない。
コニーはしぶしぶ俺を部屋の中に入れてくれた。
セレナ嬢はちょうどお茶の時間だったようで、バルコニーに置かれたテーブルでお茶を楽しんでいた。
「リオ様?」
その顔には『何か用かしら?』と書かれている。世話係から外された俺は、用がないとセレナ嬢に会うことすらできない。
「ちょうどお茶をしていたところです。リオ様も一緒にどうですか?」
すすめられるままに席に座ると、俺はタルトが入った箱をテーブルに置いた。
「これは?」
「王都で有名な菓子店で買ってきました」
俺が箱を開けて中を見せると、セレナ嬢の顔がパァと明るくなる。
「すごくおいしそうですね」
瞳がキラキラと輝き、口元には笑みが浮かんでいる。
嬉しそうなセレナ嬢を見られて、俺は心の底から『買ってきて良かった』と思えた。
まぁピンク色の可愛らしい菓子店の行列に、むさ苦しい男二人で並んでいるので、文句を言いたくなる気持ちもわかる。
「そんなに嫌ならついて来なくていいのに……」
俺があきれた視線を向けると、エディは「これでも俺はお前の護衛騎士なんだよ!」と目を吊り上げている。
「どうしてリオが並ぶんだ! こういうことは、ターチェ家の使用人に任せればいいだろ?」
エディの言うことはもっともで、列には貴族の使用人と思われる人も多くいた。
「でも、あの家の中で一番ヒマなの俺だし」
「はぁ?」
バルゴア領にいたときと違い、王都では嫁探しをすること以外やることがない。俺の護衛騎士としてついて来たエディも、ヒマを持て余しているはずだ。
「ヒマって、嫁探しはしなくていいのかよ?」
エディの言葉に俺はなぜか驚いてしまった。
「あ、いや、今はほら、セレナ嬢の世話が……」
「世話は狂犬メイドがやってるからしなくていいだろ?」
「うっ」
エディの言う通り、セレナ嬢の世話係役をコニーに取られてしまった。セレナ嬢自身も俺に世話をされるより、気心の知れたメイドに世話をしてもらうほうが良いらしい。
「だから、王都で有名な菓子でも買って贈ろうかと……」
「どうしてだよ?」
「どうしてって、そうすればセレナ嬢が喜んでくれる、から?」
エディがなんとも言えない顔をした。腕を組みながら「ケガをさせた罪悪感か? それともそっちなのか?」と唸(うな)っている。
そうしているうちに列が進み、俺は無事に有名店の菓子を買えた。
このリンゴのタルトは、甘みと酸味が程よくタルト部分がサクサクですごく美味しいと叔母さんが言っていた。
贈り物だと伝えると、店員がリボンをつけてくれると言うので水色のリボンをつけてもらった。
「無事に買えて良かったな。せっかく街まで来たんだから、薬師のところに寄ってから帰ろうぜ」
「ああ、そうだな」
コニーからガラスの小瓶を受け取ったエディは、あのあとターチェ家の使用人に聞いて、信頼できる薬師を紹介してもらったらしい。
ガラスの小瓶の中身がなんだったのか、俺も早く知りたい。
有名菓子店があった大通りから離れ、裏道に入ったところにその薬師は店を構えていた。年季の入った店構えで、店前には葉が茂った植木鉢がズラリと並んでいる。
薬草ばかりだったけど、俺が知らない植物もあった。
エディは木の扉をドンドン叩くと「じぃさんいる?」と大声を出す。中から返事はない。
「あれいないのかな?」
ドンドンドンと扉を叩いていると「うるさい!」と中から怒鳴り声がした。
「あ、なんだいたのか!」
エディが店の扉を開けたとたんに、強烈な薬の臭いが辺りに漂う。
「う」
「リオ、臭かったら外で待っていていいぞ」
「いや、俺も入る」
店の中では白髪の老人がすり鉢で何かをすり潰していた。俺たちの姿を見て「まったく田舎者はこれだから」と悪態をつく。
「じぃさん、昨日頼んだヤツ、調べておいてくれたか?」
「ああ、あれな」
薬師は立ち上がると、奥からガラスの小瓶を取ってきた。
「これは薬じゃない。ただの水じゃよ」
「だとよ、リオ」
「やっぱり水だったか」
俺の言葉に薬師は目を鋭くした。
「わかっていたのか?」
「いや、確信がなかったんだ。調べてもらって助かったよ」
エディが薬師に代金を支払っている。
ふと気になった俺は「この店では毒も取り扱っているのか?」と聞いてみた。
代金を受け取った薬師は「まさか」と首をふる。
「そういうのがほしいのなら、情報屋に行きな。裏社会の連中と繋げてくれるさ。まぁとんでもない金額を要求されるがな」
やはり王都でも毒は、簡単に手に入るものではないようだ。
ガラスの小瓶は、セレナ嬢の妹のイタズラだったのか? でも、そうだとしたらなんのために?
「う、考えるのは苦手だ。いっそのこと本人たちに会えば悪意がわかるのになぁ」
「ファルトン伯爵家に乗り込むつもりか? さすがに捕まるぞ」
「そうだな」
エディと共にターチェ伯爵家に戻ると、ちょうど叔父さんも帰ってきたところだった。
「リオくん、ちょっといいかな?」
「はい」
叔父さんの執務室に通された俺たちは、ソファーにかけるように言われた。こういうときのエディは数歩下がって黙って俺の背後に立っている。
主(あるじ)と護衛騎士は、本来ならこの距離が正しいけど、俺のほうから二人のときは今まで通りにしてくれと頼んでいた。
向かいのソファーに座った叔父さんは小さなため息をつく。
「セレナさんのことだけどね」
叔父さんは、いろいろとファルトン伯爵家のことを調べてくれたそうだ。
「やはりセレナさんの言っていることが正しいようだね」
「と、言うと?」
「セレナさんは、ファルトン伯爵家で家族と認められていなかったみたいだよ」
叔父さんが言うには、ファルトン伯爵家は仲の良い『三人』家族だそうだ。
「高級レストランで食事をしたり、服飾士を呼んでドレスを作ったりする際も、伯爵と伯爵夫人、その娘の三人しか目撃されていないんだ。店の若い従業員や服飾士にセレナさんのことを聞いたら、『もう一人娘さんがいたんですか?』と驚かれてしまったよ」
それでも、長く勤めている店員たちは、セレナ嬢のことを知っていた。でも、数年前にセレナ嬢の母が亡くなったときに、セレナ嬢も一緒に亡くなったかと思われていたそうだ。
「それくらい、セレナさんは外に出ていなかったようだね」
「家の中に閉じ込められていたってことですか?」
自分が思っていた以上に冷たい声が出た。
「そういうことだろうね。セレナさんは、貴族が集まる夜会にだけは出ていて『社交界の毒婦』なんて呼ばれていたけど、社交界を知らない人たちに聞いたら、すぐに真実が浮き上がってきたよ」
「これでセレナ嬢を助けられるんですか?」
「いや、これだけでは無理だね。いろいろ調べているうちにわかったことなんだけど、セレナさんの母親が亡くなったあとに、ファルトン家では大量に使用人が解雇されたそうなんだ」
叔父さんは、今、そのときに解雇された使用人を探してくれているそうだ。
「ありがとうございます。叔父さん」
叔父さんは「まぁ、これも何かの縁だから」とニコリと微笑む。
解雇された使用人たちが見つかり、セレナ嬢がひどい目に遭(あ)わされていたという証言を得られれば、セレナ嬢はあの家と縁を切れる。
早くそうなればいいと願いながら、俺はセレナ嬢の部屋の扉をノックした。なぜかエディも付いてきている。
すぐに「はーい」という声が聞こえてコニーが顔を出した。
「げ」
「げって」
コニーは未だに俺を警戒している。まぁ、大切な主(あるじ)の腕を折った男だから仕方がない。
「セレナお嬢様に、何か用ですか?」
俺は手に持っていた箱を見せた。
「王都で有名な菓子を買って来たんだ」
「へぇ、じゃあ、お嬢様に渡しておきます」
箱を受け取ろうとしたコニーから逃げるように俺は後ずさる。
「なんなんですか?」
「いや、直接渡したいなって」
「はぁ?」
だって直接渡さないと、喜んでもらえたかわからない。
コニーはしぶしぶ俺を部屋の中に入れてくれた。
セレナ嬢はちょうどお茶の時間だったようで、バルコニーに置かれたテーブルでお茶を楽しんでいた。
「リオ様?」
その顔には『何か用かしら?』と書かれている。世話係から外された俺は、用がないとセレナ嬢に会うことすらできない。
「ちょうどお茶をしていたところです。リオ様も一緒にどうですか?」
すすめられるままに席に座ると、俺はタルトが入った箱をテーブルに置いた。
「これは?」
「王都で有名な菓子店で買ってきました」
俺が箱を開けて中を見せると、セレナ嬢の顔がパァと明るくなる。
「すごくおいしそうですね」
瞳がキラキラと輝き、口元には笑みが浮かんでいる。
嬉しそうなセレナ嬢を見られて、俺は心の底から『買ってきて良かった』と思えた。