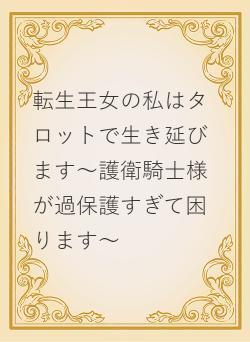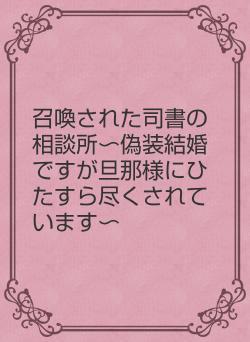決行日は、一週間後。近衛騎士団の団員さん、主にジルケの協力の下、カーティス様のお休みを調整してもらったのだ。
その分、彼女たちに負担がかかるため、お礼は何がいいのか聞いたところ……。
「最近できたという、猫に会える喫茶店というところに行ってみたいのですが」
多くの団員さんが、そう答えた。彼女たちが何故、私に言うのかというと、それは偏に“猫”が絡んでいるからだ。
けれど、実際は関わっているようで、いなかった。
実はドリス王女にグレー猫を紹介した後、あの仮店舗に猫が住み着いたのだ。雨風が凌げる上に、質の良い絨毯、カーペット、ソファー。さらに綺麗な調度品の数々。
これらはすべて、ドリス王女とヴェルナー殿下を招くために用意したものだった。
けれど、猫たちにそんな事情は関係ない。自分たちのために用意された物だと勘違いしたのだ。
結果、彼らが居座ってしまった、というわけである。
加えて彼らは、凶暴ではない。が、大人し過ぎる猫でもなかった。それに目を付けた人物がいたのだ。
場所も仮店舗ということもあって、その人物は猫たちの世話を焼きながら、喫茶店を開いた、というのが事の真相だった。
一応、マクギニス伯爵家とヴェルナー殿下、ドリス王女に許可を得には来たので、知ってはいた。が、行ったことがないだけで……。
団員さんたちに紹介する前に、カーティス様と行ってみたかったんだけど、今日はダメ。だって、まずはモディカ公園の猫たちに、ちゃんと認識してもらう方が重要だったから。
理由はどうあれ、初めて出会った場所に、ケチをつけたくない、というのが本音だった。
「モディカ公園の中をルフィナと歩いていると、あの時のことを思い出すな」
それはカーティス様も思ってくれているらしい。特別な場所だと。
「もう、あの時のような恰好はしないのか?」
「眼鏡ですか? 嫌ですよ。お母様に間違えられたくありませんから」
「そっちじゃない。三つ編みやベレー帽は、もう被らないのか?」
カーティス様はそう言いながら、私の頭をそっと撫でた。
「いつも私のことを鈍感のように言いますが、カーティス様も同じようですね」
「ん? そうか?」
「今みたいに触れるから、できないんです!」
王城に出入りしている時などは特に、凝った髪型をして行きたいのだが、変に崩されるのが嫌だった。いや、本音を言うと、逆にない方が不安に感じてしまう。何か気に障ることをしたのかなって思えて、催促したこともあった。
「すまない。これからは控える」
「それは……嫌です」
小さい声で言った、私の我が儘をカーティス様は見逃さなかった。
「ルフィナ」
優しく呼ばれたのと同時に、もう片方の腕が私に伸びて来る。このままカーティス様の腕の中に包まれても良かったのだけれど、それではモディカ公園に来た意味がない。
私は意を決して、その腕を掴んだ。
「実は、来ていただきたいところがあるんです」
「それは急ぐほどのことなのか?」
カーティス様の不満げな顔と声に、私は視線を逸らした。
「猫たちを待たせているんです」
嘘じゃない。けれど、我ながら卑怯な手だと思った。そのように言えば、カーティス様は従わざるを得ない。私が猫憑きだから。
「ならば、仕方がないな」
案の定、カーティス様は苦笑しながらも、理解を示してくれた。逆に私は、この選択が間違いではなかったと思ってもらえるよう、さらに決心を固めた。
***
「ここは……」
カーティス様が驚きの声を上げる。
私と知り合ってから、猫を見る機会が増えても、やはり目の前の光景は珍しいのだろうか。
「モディカ公園にいる猫たちの寝床です」
「そんなところに立ち入っても大丈夫なのか?」
今更とでも言うような質問に、私はクスクス笑った。
「はい。今日は特別に許可をいただいて、こちらに。本当なら、私でもダメな場所なんです」
「だったら余計、俺が入るべきではないと思うんだが……」
「いいえ。カーティス様……ではなく、カーティスと一緒じゃないとダメなんです!」
慣れない呼び方に、私は思わず叫んでしまった。この場にいる猫たちが驚いて、一斉に私たちの方を見る。
途端、ひっそりと姿を消していたピナが現れ、慌てて猫たちを宥め始めた。
「ピナに、言われたんです。私がいつまでも、よそよそしく“様”をつけて呼んでいるから、この子たちも同じように接するんだと。だから――……」
「もう一度言ってもらえるか?」
「え? ど、どこから……」
「俺の名前」
あっ。今日のメインを失念していたわけではないけれど、再度お願いされると、緊張がぶり返して来た。
それはカーティスも同じなのだろう。猫たちのことなど気にしている様子はなかった。
「……カ、カーティス」
「もう一回」
「カーティス」
「もう一回」
催促されている内に、私も段々と緊張が抜けていく。お陰で最後の方は、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
それが顔に出てしまったのだろう。ハッとなったカーティスが、私の頬に手を伸ばした。
「すまない、ルフィナ。嬉し過ぎて、何度も言わせてしまった。嫌じゃなかったか?」
「私の方こそ、ごめんなさい。こんなにも、カーティスに我慢してもらっていたとは思わなかったの」
「いや、俺もそこまで自覚していたわけじゃないんだ。まだ婚約中だからな。結婚を機に呼んでもらえればと、思っていたくらいだ」
「ごめんなさい」
居た堪れなくて、私は顔を両手で覆いながら蹲った。
「ダメだよ~、ルフィナ~。ちゃんとこいつらに示さないと~。カーティスがルフィナの相手だってことをさ~」
「ピナ君?」
「こいつらはさ~、他のところの奴らと違って、ちょっと頑固なんだ~。プライドも高くてさ~」
「猫ですが、我が家への忠誠心と仕事に対する信念が強いんです」
ラリマーを飼っているカーティスなら、この意味が分かるはずだ。元々、モディカ公園の猫だったから。
「だから、私がちゃんとカーティスを愛していることを知ってもらえれば、もうあんな態度は取らない。いいえ、取らせません」
私はカーティスの首に腕を回して、一気に引き寄せた。目を閉じ、顔を傾ける。
驚いたまま、開いている口に合わせると、腰と背中にカーティスの腕が触れた。私たちの体の隙間を埋めても尚、強く抱き締められる。
結婚式はいつになるか分からないが、ピナと猫たちの前で、私たちは誓いのキスをした。
その分、彼女たちに負担がかかるため、お礼は何がいいのか聞いたところ……。
「最近できたという、猫に会える喫茶店というところに行ってみたいのですが」
多くの団員さんが、そう答えた。彼女たちが何故、私に言うのかというと、それは偏に“猫”が絡んでいるからだ。
けれど、実際は関わっているようで、いなかった。
実はドリス王女にグレー猫を紹介した後、あの仮店舗に猫が住み着いたのだ。雨風が凌げる上に、質の良い絨毯、カーペット、ソファー。さらに綺麗な調度品の数々。
これらはすべて、ドリス王女とヴェルナー殿下を招くために用意したものだった。
けれど、猫たちにそんな事情は関係ない。自分たちのために用意された物だと勘違いしたのだ。
結果、彼らが居座ってしまった、というわけである。
加えて彼らは、凶暴ではない。が、大人し過ぎる猫でもなかった。それに目を付けた人物がいたのだ。
場所も仮店舗ということもあって、その人物は猫たちの世話を焼きながら、喫茶店を開いた、というのが事の真相だった。
一応、マクギニス伯爵家とヴェルナー殿下、ドリス王女に許可を得には来たので、知ってはいた。が、行ったことがないだけで……。
団員さんたちに紹介する前に、カーティス様と行ってみたかったんだけど、今日はダメ。だって、まずはモディカ公園の猫たちに、ちゃんと認識してもらう方が重要だったから。
理由はどうあれ、初めて出会った場所に、ケチをつけたくない、というのが本音だった。
「モディカ公園の中をルフィナと歩いていると、あの時のことを思い出すな」
それはカーティス様も思ってくれているらしい。特別な場所だと。
「もう、あの時のような恰好はしないのか?」
「眼鏡ですか? 嫌ですよ。お母様に間違えられたくありませんから」
「そっちじゃない。三つ編みやベレー帽は、もう被らないのか?」
カーティス様はそう言いながら、私の頭をそっと撫でた。
「いつも私のことを鈍感のように言いますが、カーティス様も同じようですね」
「ん? そうか?」
「今みたいに触れるから、できないんです!」
王城に出入りしている時などは特に、凝った髪型をして行きたいのだが、変に崩されるのが嫌だった。いや、本音を言うと、逆にない方が不安に感じてしまう。何か気に障ることをしたのかなって思えて、催促したこともあった。
「すまない。これからは控える」
「それは……嫌です」
小さい声で言った、私の我が儘をカーティス様は見逃さなかった。
「ルフィナ」
優しく呼ばれたのと同時に、もう片方の腕が私に伸びて来る。このままカーティス様の腕の中に包まれても良かったのだけれど、それではモディカ公園に来た意味がない。
私は意を決して、その腕を掴んだ。
「実は、来ていただきたいところがあるんです」
「それは急ぐほどのことなのか?」
カーティス様の不満げな顔と声に、私は視線を逸らした。
「猫たちを待たせているんです」
嘘じゃない。けれど、我ながら卑怯な手だと思った。そのように言えば、カーティス様は従わざるを得ない。私が猫憑きだから。
「ならば、仕方がないな」
案の定、カーティス様は苦笑しながらも、理解を示してくれた。逆に私は、この選択が間違いではなかったと思ってもらえるよう、さらに決心を固めた。
***
「ここは……」
カーティス様が驚きの声を上げる。
私と知り合ってから、猫を見る機会が増えても、やはり目の前の光景は珍しいのだろうか。
「モディカ公園にいる猫たちの寝床です」
「そんなところに立ち入っても大丈夫なのか?」
今更とでも言うような質問に、私はクスクス笑った。
「はい。今日は特別に許可をいただいて、こちらに。本当なら、私でもダメな場所なんです」
「だったら余計、俺が入るべきではないと思うんだが……」
「いいえ。カーティス様……ではなく、カーティスと一緒じゃないとダメなんです!」
慣れない呼び方に、私は思わず叫んでしまった。この場にいる猫たちが驚いて、一斉に私たちの方を見る。
途端、ひっそりと姿を消していたピナが現れ、慌てて猫たちを宥め始めた。
「ピナに、言われたんです。私がいつまでも、よそよそしく“様”をつけて呼んでいるから、この子たちも同じように接するんだと。だから――……」
「もう一度言ってもらえるか?」
「え? ど、どこから……」
「俺の名前」
あっ。今日のメインを失念していたわけではないけれど、再度お願いされると、緊張がぶり返して来た。
それはカーティスも同じなのだろう。猫たちのことなど気にしている様子はなかった。
「……カ、カーティス」
「もう一回」
「カーティス」
「もう一回」
催促されている内に、私も段々と緊張が抜けていく。お陰で最後の方は、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
それが顔に出てしまったのだろう。ハッとなったカーティスが、私の頬に手を伸ばした。
「すまない、ルフィナ。嬉し過ぎて、何度も言わせてしまった。嫌じゃなかったか?」
「私の方こそ、ごめんなさい。こんなにも、カーティスに我慢してもらっていたとは思わなかったの」
「いや、俺もそこまで自覚していたわけじゃないんだ。まだ婚約中だからな。結婚を機に呼んでもらえればと、思っていたくらいだ」
「ごめんなさい」
居た堪れなくて、私は顔を両手で覆いながら蹲った。
「ダメだよ~、ルフィナ~。ちゃんとこいつらに示さないと~。カーティスがルフィナの相手だってことをさ~」
「ピナ君?」
「こいつらはさ~、他のところの奴らと違って、ちょっと頑固なんだ~。プライドも高くてさ~」
「猫ですが、我が家への忠誠心と仕事に対する信念が強いんです」
ラリマーを飼っているカーティスなら、この意味が分かるはずだ。元々、モディカ公園の猫だったから。
「だから、私がちゃんとカーティスを愛していることを知ってもらえれば、もうあんな態度は取らない。いいえ、取らせません」
私はカーティスの首に腕を回して、一気に引き寄せた。目を閉じ、顔を傾ける。
驚いたまま、開いている口に合わせると、腰と背中にカーティスの腕が触れた。私たちの体の隙間を埋めても尚、強く抱き締められる。
結婚式はいつになるか分からないが、ピナと猫たちの前で、私たちは誓いのキスをした。