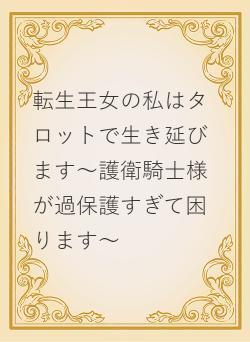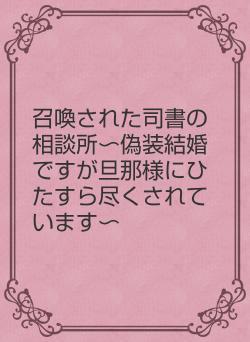ドリス王女の『頼みたいこと』を聞いてから、一カ月後。私とカーティス様は、ドリス王女とヴェルナー殿下を伴って、ある場所に来ていた。
お忙しいヴェルナー殿下は、どう予定を調整しても、遠出をすることは叶わず。だからといって、除け者にするのは気の毒過ぎて。結局、それは首都の一角にある空き店舗で行われた。
「ようこそ、お越しくださいました」
早速、扉を開けて中に誘導する。私を先頭に、ドリス王女、ヴェルナー殿下。カーティス様は念のため、お二人の護衛という立場で、最後に扉をくぐった。
「といっても、ヴェルナー殿下に紹介していただいた建物なんですが」
そう、ドリス王女の『頼みたいこと』を実現するには、場所が必要だった。広くて、誰の迷惑にもかからない場所が。
最初に提案されたのは、我がマクギニス伯爵家だった。猫好きのドリス王女が所望したのだ。けれど、カーティス様に敢え無く却下された。
理由はヴェルナー殿下がついて来るから、というもの。婚約者の家に、王子殿下といえど殿方を入れたくない、と主張したのだ。
これは王家への不敬罪にならないか、ハラハラしたのだが、そこはカーティス様とヴェルナー殿下。
「分かったよ。カーティスがそういうのなら、仕方がないね」
あっさりと承諾してくれた。
次に提案されたのは、そのカーティス様の家。これは私が許可できなかった。まぁ、理由はカーティス様と同じ。
足を踏み入れてほしくなかったのだ。ドリス王女に。
ならば、と持ち上がったのが、各自が所有する領地、または別荘。……こちらは、ヴェルナー殿下が大反対。
故に、解決策をヴェルナー殿下ご自身で提案、実行に移されたのだ。
「いいんだよ。そもそも、私の我が儘……いや、ドリスのか、それから始まったことなんだからね」
「まぁ、お兄様ったら! 困ったら、すぐに私のせいにするんだから」
「まあまあお二人とも。中で『頼まれたもの』たちが待っていますので」
兄妹仲が良いことは悪いことではない。けれど、ドリス王女の『頼みたいこと』によって招集された『もの』たちのことを思うと、立ち話が長くなるのは困ってしまう。
何せ、彼らは気まぐれだから。
「どうぞ」
「キャーー!!」
入ってすぐの扉を開けた瞬間、説明する間もなく、ドリス王女が歓喜の声を上げた。
「ドリス王女様。あまり大きな声は……。猫たちが怖がりますので」
私はカーティス様のお陰で免疫はついたけれど、部屋の中にいる彼らは違う。そう、部屋の中には多数の猫たちがいるのだ。
ドリス王女の『頼みたいこと』とは、猫を紹介してほしい、というもの。王城で飼うための愛玩用の猫を。
私は知らなかったのだが、ドリス王女はお母様に再三お願いしていたらしい。それも、王城で働いている猫たちを所望していたというのだ。
それを聞いた私は、お母様が断るのも無理もないと思った。何故なら、あの猫たちを見つけるのに、とてつもない手間がかかるのだ。
そもそも猫に、真面目に仕事をしろというのは無理がある。けれど稀に、それが性に合う猫がいるのだ。誰かに必要とされたい。承認欲求が強い猫が。
シーラやピナ、イダには、そういう猫を常に何匹かキープさせている。故に、そんな猫をおいそれと愛玩用にはできなかった。
「そうね。でも、こんなにたくさんの猫ちゃんたちがいる光景なんて、初めてだから、つい」
「しかし、驚かせてはなりません。皆、ドリス王女様のために集まってくれたんですから」
「まぁ!」
さらに歓喜の声を上げて、猫たちをうっとりした眼差しで見つめるドリス王女。
彼女の『頼みたいこと』を叶えるには、二つの条件があった。
一つ、王様とお母様の許可を得ること。
前もって話を通さなければ、王城で働いている猫たちを、私がドリス王女に譲渡したと勘違いされ兼ねないからだ。お母様が王様を通して断っていた、という理由もある。
二つ、猫にかまけて政務を放棄しないこと。
これはヴェルナー殿下が出した条件だ。一回でも破れば、即没収という厳しいもの。それでもドリス王女は、条件を呑んだ。
「一応、ドリス王女様のお好みの猫を集めましたが、それ以外の子もいますので、ご自由に見て回ってみてください」
「いいの?」
「そのための猫たちですから」
部屋の中には、大小さまざまな猫たちがいた。色もまちまちである。
ソファーで寛ぐ猫。テーブルの上、下。先ほどの声で驚き、全然隠れていないのに、隠れるように様子を窺う猫。逆に好奇心が旺盛なのか、ドリス王女に近づく勇者もいた。
ドリス王女の好みは元気な猫だったが、住まいは王城だ。元気過ぎて物を壊すような猫を紹介したら……お母様の雷が落ちそうだ。
故に、ほどほどの子を用意した。先ほどの声に驚かない子は……肝が据わっているか、もしくは鈍感なだけだろう。
ドリス王女は、自身に向かって来るグレーの猫を見つめた。
「さ、触っても?」
「大丈夫ですよ。粗相をしないようには言ってありますので。しかし、猫が嫌がることはしないでくださいね。言い聞かせても、猫は気まぐれですから」
「分かったわ。でも、これはダメって思ったら、遠慮なく教えてちょうだい」
「勿論です」
大事な猫をお渡しするのだから、王女といえど、そこはきちんと、ね。
「噛まない?」
「嫌がることをしなければしません」
「引っ掻くことも?」
「ご経験が?」
「ないわ。でも、そういう者もいるから」
なるほど。もしかしたら、王城で猫を見かけても、話しかけたり、触ったりしていないのかもしれなかった。
だから私は、グレーの猫を抱き上げて、ドリス王女に渡す。
「どうですか?」
「温かいわ。って、え? 何?」
始めは大人しく抱かれていたグレーの猫だったが、突然、ドリス王女の顔に近づき、肩に頭を乗せた。さらに髪に擦り寄る。
「ふふふっ。どうやらこの子は、ドリス王女様のことが気に入ったようです」
「本当?」
「多分、銀髪を見て同類と思ったのかもしれません」
言い終わった瞬間、私はハッとなった。猫と王女様を同類だなんて、不敬にあたるのではないだろうか。
「それなら、この子にするわ」
「え? 他の子もご覧にならないのですか?」
「勿論見るけど、この子を抱っこしたままでもいいでしょう?」
「はい。しかし、疲れたら仰ってください。代わりますから」
そういうとドリス王女は、首を横に振った。
「嫌よ。マクギニス嬢と抱き方を比べられたくないもの」
まさか張り合われるとは思わず、私は苦笑した。
お忙しいヴェルナー殿下は、どう予定を調整しても、遠出をすることは叶わず。だからといって、除け者にするのは気の毒過ぎて。結局、それは首都の一角にある空き店舗で行われた。
「ようこそ、お越しくださいました」
早速、扉を開けて中に誘導する。私を先頭に、ドリス王女、ヴェルナー殿下。カーティス様は念のため、お二人の護衛という立場で、最後に扉をくぐった。
「といっても、ヴェルナー殿下に紹介していただいた建物なんですが」
そう、ドリス王女の『頼みたいこと』を実現するには、場所が必要だった。広くて、誰の迷惑にもかからない場所が。
最初に提案されたのは、我がマクギニス伯爵家だった。猫好きのドリス王女が所望したのだ。けれど、カーティス様に敢え無く却下された。
理由はヴェルナー殿下がついて来るから、というもの。婚約者の家に、王子殿下といえど殿方を入れたくない、と主張したのだ。
これは王家への不敬罪にならないか、ハラハラしたのだが、そこはカーティス様とヴェルナー殿下。
「分かったよ。カーティスがそういうのなら、仕方がないね」
あっさりと承諾してくれた。
次に提案されたのは、そのカーティス様の家。これは私が許可できなかった。まぁ、理由はカーティス様と同じ。
足を踏み入れてほしくなかったのだ。ドリス王女に。
ならば、と持ち上がったのが、各自が所有する領地、または別荘。……こちらは、ヴェルナー殿下が大反対。
故に、解決策をヴェルナー殿下ご自身で提案、実行に移されたのだ。
「いいんだよ。そもそも、私の我が儘……いや、ドリスのか、それから始まったことなんだからね」
「まぁ、お兄様ったら! 困ったら、すぐに私のせいにするんだから」
「まあまあお二人とも。中で『頼まれたもの』たちが待っていますので」
兄妹仲が良いことは悪いことではない。けれど、ドリス王女の『頼みたいこと』によって招集された『もの』たちのことを思うと、立ち話が長くなるのは困ってしまう。
何せ、彼らは気まぐれだから。
「どうぞ」
「キャーー!!」
入ってすぐの扉を開けた瞬間、説明する間もなく、ドリス王女が歓喜の声を上げた。
「ドリス王女様。あまり大きな声は……。猫たちが怖がりますので」
私はカーティス様のお陰で免疫はついたけれど、部屋の中にいる彼らは違う。そう、部屋の中には多数の猫たちがいるのだ。
ドリス王女の『頼みたいこと』とは、猫を紹介してほしい、というもの。王城で飼うための愛玩用の猫を。
私は知らなかったのだが、ドリス王女はお母様に再三お願いしていたらしい。それも、王城で働いている猫たちを所望していたというのだ。
それを聞いた私は、お母様が断るのも無理もないと思った。何故なら、あの猫たちを見つけるのに、とてつもない手間がかかるのだ。
そもそも猫に、真面目に仕事をしろというのは無理がある。けれど稀に、それが性に合う猫がいるのだ。誰かに必要とされたい。承認欲求が強い猫が。
シーラやピナ、イダには、そういう猫を常に何匹かキープさせている。故に、そんな猫をおいそれと愛玩用にはできなかった。
「そうね。でも、こんなにたくさんの猫ちゃんたちがいる光景なんて、初めてだから、つい」
「しかし、驚かせてはなりません。皆、ドリス王女様のために集まってくれたんですから」
「まぁ!」
さらに歓喜の声を上げて、猫たちをうっとりした眼差しで見つめるドリス王女。
彼女の『頼みたいこと』を叶えるには、二つの条件があった。
一つ、王様とお母様の許可を得ること。
前もって話を通さなければ、王城で働いている猫たちを、私がドリス王女に譲渡したと勘違いされ兼ねないからだ。お母様が王様を通して断っていた、という理由もある。
二つ、猫にかまけて政務を放棄しないこと。
これはヴェルナー殿下が出した条件だ。一回でも破れば、即没収という厳しいもの。それでもドリス王女は、条件を呑んだ。
「一応、ドリス王女様のお好みの猫を集めましたが、それ以外の子もいますので、ご自由に見て回ってみてください」
「いいの?」
「そのための猫たちですから」
部屋の中には、大小さまざまな猫たちがいた。色もまちまちである。
ソファーで寛ぐ猫。テーブルの上、下。先ほどの声で驚き、全然隠れていないのに、隠れるように様子を窺う猫。逆に好奇心が旺盛なのか、ドリス王女に近づく勇者もいた。
ドリス王女の好みは元気な猫だったが、住まいは王城だ。元気過ぎて物を壊すような猫を紹介したら……お母様の雷が落ちそうだ。
故に、ほどほどの子を用意した。先ほどの声に驚かない子は……肝が据わっているか、もしくは鈍感なだけだろう。
ドリス王女は、自身に向かって来るグレーの猫を見つめた。
「さ、触っても?」
「大丈夫ですよ。粗相をしないようには言ってありますので。しかし、猫が嫌がることはしないでくださいね。言い聞かせても、猫は気まぐれですから」
「分かったわ。でも、これはダメって思ったら、遠慮なく教えてちょうだい」
「勿論です」
大事な猫をお渡しするのだから、王女といえど、そこはきちんと、ね。
「噛まない?」
「嫌がることをしなければしません」
「引っ掻くことも?」
「ご経験が?」
「ないわ。でも、そういう者もいるから」
なるほど。もしかしたら、王城で猫を見かけても、話しかけたり、触ったりしていないのかもしれなかった。
だから私は、グレーの猫を抱き上げて、ドリス王女に渡す。
「どうですか?」
「温かいわ。って、え? 何?」
始めは大人しく抱かれていたグレーの猫だったが、突然、ドリス王女の顔に近づき、肩に頭を乗せた。さらに髪に擦り寄る。
「ふふふっ。どうやらこの子は、ドリス王女様のことが気に入ったようです」
「本当?」
「多分、銀髪を見て同類と思ったのかもしれません」
言い終わった瞬間、私はハッとなった。猫と王女様を同類だなんて、不敬にあたるのではないだろうか。
「それなら、この子にするわ」
「え? 他の子もご覧にならないのですか?」
「勿論見るけど、この子を抱っこしたままでもいいでしょう?」
「はい。しかし、疲れたら仰ってください。代わりますから」
そういうとドリス王女は、首を横に振った。
「嫌よ。マクギニス嬢と抱き方を比べられたくないもの」
まさか張り合われるとは思わず、私は苦笑した。