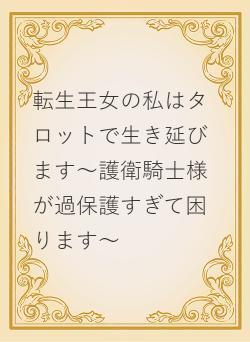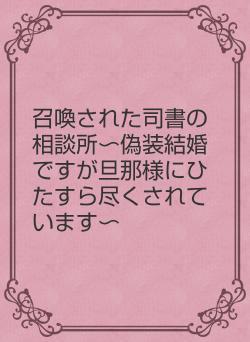「悪かった。お詫びとして、依頼のこともあるから、我がグルーバー邸に来てもらえないだろうか」
「え? そんなつもりで言ったわけではありませんので、お気遣いなく」
「だが、どのみち、場所を移動した方がいいだろう」
騎士団長様はすでに、私が依頼を受ける前提で話を進めている。
これで私が「実は依頼をお断りするために来たんです」と言ったらどうなるだろう。突然、激高して怒鳴ってきたりするのだろうか。
騎士団では、指導が厳しい団長様だと聞いたことがある。
「分かりました。その代わり、この白猫を連れて行ってもいいでしょうか」
「白猫を?」
「はい」
「そういえば、今日のマクギニス嬢の服も白いな」
あら、よくぞお気づきで。でも、残念。これは白ではなくパールグレー。
変装というほど大袈裟なものにはしたくなかったから、探偵風とお忍びを混ぜたテーマにしてみたのだ。
もしかしたら日差しに当たって、白く見えたのだろうか。または、白猫を抱いているから、錯覚した可能性もある。
「騎士団長様もご存じの通り、我がマクギニス伯爵家は猫憑きですから。私に憑いている猫が、この子と同じ白猫なんです。だから自然と、似た色を選んでしまうようで」
「なるほど。通りで白が入った猫たちが集まってくるわけだ」
「集まる?」
「周りをよく見てみるといい」
騎士団長様に促されて見てみると、確かに猫の姿が、あちらこちらに見えた。勿論、白猫もいたが、ブチや三毛猫などが、茂みからこちらを窺っている。
もしかして、さっき私が驚いたり怯えたりしたから?
「まぁ、随分と心配をかけてしまったようですね」
「心配?」
「その、さきほど、騎士団長様に驚いてしまって。何分、心の準備ができていなかったものですから」
思わず洗いざらい答えてしまった。私のために集まってくれた猫たちを前に、嘘はつきたくなかったのだ。
抱いている白猫も「にゃー」と鳴いた。
「そうね。君にも。ありがとう」
再びギュッと抱き締めて、顔を埋めた。野良猫とは思えないほど、ふさふさしていて、しかも臭くない。
「依頼を言う前から、マクギニス嬢には何度も迷惑をかけてしまったな」
「そんなことは。ですが、心苦しいようでしたら、依頼の方は……ん?」
騎士団長様が私に手を差し出した。
何ですか、この手は。私は犬ではないので、お手などしませんよ。むしろ騎士団長様の方が犬ではないのですか?
黒髪に水色の瞳など、まるでシベリアンハスキーのようではないですか。その目つきといい体格といい。とても似ていますわよ。
「向こうに馬車を用意している。そこまでエスコートさせてもらえないだろうか」
「あの、その馬車はいつから?」
「俺がモディカ公園に来るのに使っているから、そうだな。二時間ほど前からか」
「に、二時間!?」
私がモディカ公園に着いたのは、朝の十時。
「八時からここにいらしていたんですか?」
「あぁ」
「一週間前から、ずっとですか?」
「あぁ。良かった。なかなか猫に接触できなかったから、伝わっていないのかと心配していたが、そうではなかったのだな」
マズい。墓穴を掘った。一週間前から、モディカ公園に騎士団長様が通っているのを知っておきながら、放置していたことを、うっかり喋ってしまった。
ごめんなさい、お母様。いや、謝る相手が違うわ。
「申し訳ございません。その、猫たちが」
「大丈夫。俺も分かっている。猫たちに避けられていたことくらい」
「はい。それで私たちも判断し兼ねまして……」
「ということは、マクギニス伯爵も知っている、ということか」
あっ……。終わった。これは、騎士団長様の誘導尋問に引っかかってしまいました、と正直に話すしかないわね。
でも、お母様相手に騎士団長様が萎縮なんてするかしら。確かに親子ほど、年が離れているけれど。
「あの、騎士団長様は母と、どのような関係で? あっ、深い意味はないんです。ただ今回は私が話を聞くようにと言われたので」
「なるほど。多分伯爵は、俺が依頼する内容を知っているのだろう。だから、マクギニス嬢を指名したんだと思う」
「それは母では無理だということですか?」
「あぁ」
騎士団長様は頷き、ご自分の手を見た後、再び私に視線を向けた。
これはどういうことなのかしら。仮にお母様がモディカ公園で騎士団長様とお会いしても、結果は同じだったということ?
だから、回りくどいやり方で、私に行かせたというの? なぜ?
あっ、私が猫たちと同じで、忠犬と呼ばれている騎士団長様に対して、苦手意識を持っているから、敢えてこのようなことを……。
「マクギニス嬢」
そろそろいいだろうか、と声と目で催促される。
私は私で、この仕組まれた感じがどうにも釈然とせず、上げた手をそのまま騎士団長様の手に乗せることができなかった。
騎士団長様に、何も非がなくても。
すると、突然手を掴まれた。
「すまないが、もうあまり時間がないんだ。すぐに話がしたいから、馬車に乗ってくれ」
「は、はい」
そうだった。すでに一週間も待たせている状態なのだから、騎士団長様が急かすのも無理はなかった。
それでも、私の歩調に合わせて歩いてくれるのは、さすが近衛騎士団長様ともいえる。
王妃様や王女殿下、他国の貴賓などをエスコートする方だ。
私は白猫を落とさないように、ギュッと抱き締めながら、その騎士団長様の後ろを歩いた。
「え? そんなつもりで言ったわけではありませんので、お気遣いなく」
「だが、どのみち、場所を移動した方がいいだろう」
騎士団長様はすでに、私が依頼を受ける前提で話を進めている。
これで私が「実は依頼をお断りするために来たんです」と言ったらどうなるだろう。突然、激高して怒鳴ってきたりするのだろうか。
騎士団では、指導が厳しい団長様だと聞いたことがある。
「分かりました。その代わり、この白猫を連れて行ってもいいでしょうか」
「白猫を?」
「はい」
「そういえば、今日のマクギニス嬢の服も白いな」
あら、よくぞお気づきで。でも、残念。これは白ではなくパールグレー。
変装というほど大袈裟なものにはしたくなかったから、探偵風とお忍びを混ぜたテーマにしてみたのだ。
もしかしたら日差しに当たって、白く見えたのだろうか。または、白猫を抱いているから、錯覚した可能性もある。
「騎士団長様もご存じの通り、我がマクギニス伯爵家は猫憑きですから。私に憑いている猫が、この子と同じ白猫なんです。だから自然と、似た色を選んでしまうようで」
「なるほど。通りで白が入った猫たちが集まってくるわけだ」
「集まる?」
「周りをよく見てみるといい」
騎士団長様に促されて見てみると、確かに猫の姿が、あちらこちらに見えた。勿論、白猫もいたが、ブチや三毛猫などが、茂みからこちらを窺っている。
もしかして、さっき私が驚いたり怯えたりしたから?
「まぁ、随分と心配をかけてしまったようですね」
「心配?」
「その、さきほど、騎士団長様に驚いてしまって。何分、心の準備ができていなかったものですから」
思わず洗いざらい答えてしまった。私のために集まってくれた猫たちを前に、嘘はつきたくなかったのだ。
抱いている白猫も「にゃー」と鳴いた。
「そうね。君にも。ありがとう」
再びギュッと抱き締めて、顔を埋めた。野良猫とは思えないほど、ふさふさしていて、しかも臭くない。
「依頼を言う前から、マクギニス嬢には何度も迷惑をかけてしまったな」
「そんなことは。ですが、心苦しいようでしたら、依頼の方は……ん?」
騎士団長様が私に手を差し出した。
何ですか、この手は。私は犬ではないので、お手などしませんよ。むしろ騎士団長様の方が犬ではないのですか?
黒髪に水色の瞳など、まるでシベリアンハスキーのようではないですか。その目つきといい体格といい。とても似ていますわよ。
「向こうに馬車を用意している。そこまでエスコートさせてもらえないだろうか」
「あの、その馬車はいつから?」
「俺がモディカ公園に来るのに使っているから、そうだな。二時間ほど前からか」
「に、二時間!?」
私がモディカ公園に着いたのは、朝の十時。
「八時からここにいらしていたんですか?」
「あぁ」
「一週間前から、ずっとですか?」
「あぁ。良かった。なかなか猫に接触できなかったから、伝わっていないのかと心配していたが、そうではなかったのだな」
マズい。墓穴を掘った。一週間前から、モディカ公園に騎士団長様が通っているのを知っておきながら、放置していたことを、うっかり喋ってしまった。
ごめんなさい、お母様。いや、謝る相手が違うわ。
「申し訳ございません。その、猫たちが」
「大丈夫。俺も分かっている。猫たちに避けられていたことくらい」
「はい。それで私たちも判断し兼ねまして……」
「ということは、マクギニス伯爵も知っている、ということか」
あっ……。終わった。これは、騎士団長様の誘導尋問に引っかかってしまいました、と正直に話すしかないわね。
でも、お母様相手に騎士団長様が萎縮なんてするかしら。確かに親子ほど、年が離れているけれど。
「あの、騎士団長様は母と、どのような関係で? あっ、深い意味はないんです。ただ今回は私が話を聞くようにと言われたので」
「なるほど。多分伯爵は、俺が依頼する内容を知っているのだろう。だから、マクギニス嬢を指名したんだと思う」
「それは母では無理だということですか?」
「あぁ」
騎士団長様は頷き、ご自分の手を見た後、再び私に視線を向けた。
これはどういうことなのかしら。仮にお母様がモディカ公園で騎士団長様とお会いしても、結果は同じだったということ?
だから、回りくどいやり方で、私に行かせたというの? なぜ?
あっ、私が猫たちと同じで、忠犬と呼ばれている騎士団長様に対して、苦手意識を持っているから、敢えてこのようなことを……。
「マクギニス嬢」
そろそろいいだろうか、と声と目で催促される。
私は私で、この仕組まれた感じがどうにも釈然とせず、上げた手をそのまま騎士団長様の手に乗せることができなかった。
騎士団長様に、何も非がなくても。
すると、突然手を掴まれた。
「すまないが、もうあまり時間がないんだ。すぐに話がしたいから、馬車に乗ってくれ」
「は、はい」
そうだった。すでに一週間も待たせている状態なのだから、騎士団長様が急かすのも無理はなかった。
それでも、私の歩調に合わせて歩いてくれるのは、さすが近衛騎士団長様ともいえる。
王妃様や王女殿下、他国の貴賓などをエスコートする方だ。
私は白猫を落とさないように、ギュッと抱き締めながら、その騎士団長様の後ろを歩いた。