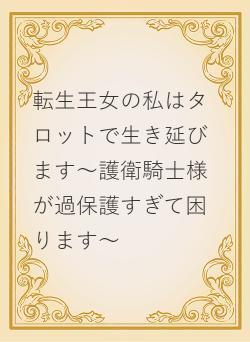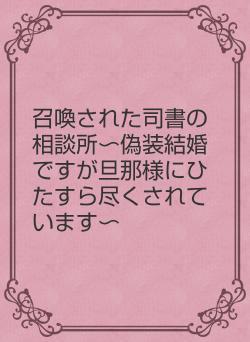茶トラを埋葬したのは、翌日。
即日にしなかったのは、皆でしたかったからだ。見送りを。あの場にいた猫たちと共に。
また、昨夜は事の結末を聞きたくて、お母様の帰りを待っていた。
けれど、やはり慣れない仮面舞踏会。エスコート役のカーティス様の存在。さらには潜入調査という緊張の連続で、私の体力と気力が底をついてしまったのだ。
「お話を聞かせてもらえますか、お母様」
そうして今、疲れきった顔のお母様の前に立っている。勿論、執務机の前で。
「あぁ。ドリス王女の話によると、床に叩きつけられた茶トラを持ち上げた途端に、猫たちが地下に現れて、一気に押し寄せたんだそうだ」
檻に入れられていた少年少女は勿論のこと、その場にいたオークションの品であったものたちも驚いてしまい、騒ぎがさらに拡大した。
無理もない。室内に猫がひしめいている光景など、そうそうお目にかかる機会はないだろうから。
「案の定、オークションに出品されるものたちは大わらわ。偶々居合わせたというシュッセル公子は、奥の壁で身動きが取れずにいたところを――……」
「お縄についた、というわけですか」
「ノハンダ伯爵の言う通り、品物の購入から搬入まで、シュッセル公爵名義でやっていたからな。さらに護衛たちも、公爵から借りていたらしい」
「あっ、だからあの時、落ち着いていたんですね」
会話内容はうろ覚えだったから、これで納得した。ということは――……。
「ノハンダ伯爵はドリス王女の協力者だったんですか?」
「本人は途中から鞍替えしたと言っていたが、どこまで本当か、怪しいものだがな」
「でも何故ですか? 王族とはいえ、シュッセル公爵よりもドリス王女につく理由が分かりません」
「馬鹿者。人の心理を表面上だけで考えるな。下の者とて、自らを使ってくれる者を見定める。ノハンダ伯爵にとってシュッセル公爵は、それに値しなかった。ただそれだけだったということだ」
なるほど。今回シュッセル公子の方を調べたが、子が子なら親も親なのだろう。それでも権力に群がるハエは絶えない。
「たとえ協力者であっても、仮面舞踏会にオークション。さらには取引不可の品物の出品まで。それらを主導、手引きをしたのだから、罪は免れん。が、大きさとしては、やはりシュッセル公爵の方が上だ」
「それはつまり、ドリス王女の思惑通りになったということですか?」
降嫁先に相応しくない。それさえ認めさせればいいのだから。
「まぁな。グルーバー侯爵様がさらに口添えをしたのだから、婚約者候補からは消えただろう」
ホッと一息ついたのも束の間。カーティス様の名前を聞いて、私は動揺した。
「それでお前はどうするつもりなんだ?」
「えっ!」
「グルーバー侯爵様は本気のようだぞ」
「いきなりそんなことを聞かれても……困ります」
本音としては「こんな心境で答えられるか!」ではあるが、そんなことを言えるはずもなく。私は静かにカーテシーをして執務室から出ていった。
***
「クソッ!」
首都の繁華街で、壁に悪態をつける男。ここではよく見かける光景だ。
一晩で身ぐるみを剥がされたり、やけ酒の末に叩き出されたり。しまいには美人局に遭って、身も心もボロボロになるケースもある。
故に、それがこの国でも指折りな有力貴族の令息であっても、皆、見ぬ振りをするのだ。
自業自得だろう。ここで遊ぶのなら、もっと紳士的に、スマートにやるのが貴族だ、とでもいうように。
その男の目にも、彼らの姿はそう映ったのだろう。男の行動はさらにエスカレートしていった。
「たかだが、あの程度のことで騒ぎやがって」
裏路地に置いてあるゴミ箱を蹴る。
「謹慎だぁ、徐免だぁ。そんなこと、知ったことかよ!」
飛び散ったゴミがズボンにつき、払うようにしてまた壁を蹴る。
「クソ親父めっ! あれくらいどうにかできるだろうが!」
その瞬間、鈍い音がする。何度も壁を蹴れば、いずれそうなることを男は知らなかったらしい。足を抱えて悶絶していた。
「そもそも、アレがあの場にいなけりゃこんなことには……」
涙目になりながら、男はゴミ箱が飛んだ先を見る。するとそこには……。
「いなければ。いや、いちゃいけないんだよ、なぁ」
散らばったゴミに近づく三毛猫を見て、男はニヤリと笑った。
「猫なんかさ」
即日にしなかったのは、皆でしたかったからだ。見送りを。あの場にいた猫たちと共に。
また、昨夜は事の結末を聞きたくて、お母様の帰りを待っていた。
けれど、やはり慣れない仮面舞踏会。エスコート役のカーティス様の存在。さらには潜入調査という緊張の連続で、私の体力と気力が底をついてしまったのだ。
「お話を聞かせてもらえますか、お母様」
そうして今、疲れきった顔のお母様の前に立っている。勿論、執務机の前で。
「あぁ。ドリス王女の話によると、床に叩きつけられた茶トラを持ち上げた途端に、猫たちが地下に現れて、一気に押し寄せたんだそうだ」
檻に入れられていた少年少女は勿論のこと、その場にいたオークションの品であったものたちも驚いてしまい、騒ぎがさらに拡大した。
無理もない。室内に猫がひしめいている光景など、そうそうお目にかかる機会はないだろうから。
「案の定、オークションに出品されるものたちは大わらわ。偶々居合わせたというシュッセル公子は、奥の壁で身動きが取れずにいたところを――……」
「お縄についた、というわけですか」
「ノハンダ伯爵の言う通り、品物の購入から搬入まで、シュッセル公爵名義でやっていたからな。さらに護衛たちも、公爵から借りていたらしい」
「あっ、だからあの時、落ち着いていたんですね」
会話内容はうろ覚えだったから、これで納得した。ということは――……。
「ノハンダ伯爵はドリス王女の協力者だったんですか?」
「本人は途中から鞍替えしたと言っていたが、どこまで本当か、怪しいものだがな」
「でも何故ですか? 王族とはいえ、シュッセル公爵よりもドリス王女につく理由が分かりません」
「馬鹿者。人の心理を表面上だけで考えるな。下の者とて、自らを使ってくれる者を見定める。ノハンダ伯爵にとってシュッセル公爵は、それに値しなかった。ただそれだけだったということだ」
なるほど。今回シュッセル公子の方を調べたが、子が子なら親も親なのだろう。それでも権力に群がるハエは絶えない。
「たとえ協力者であっても、仮面舞踏会にオークション。さらには取引不可の品物の出品まで。それらを主導、手引きをしたのだから、罪は免れん。が、大きさとしては、やはりシュッセル公爵の方が上だ」
「それはつまり、ドリス王女の思惑通りになったということですか?」
降嫁先に相応しくない。それさえ認めさせればいいのだから。
「まぁな。グルーバー侯爵様がさらに口添えをしたのだから、婚約者候補からは消えただろう」
ホッと一息ついたのも束の間。カーティス様の名前を聞いて、私は動揺した。
「それでお前はどうするつもりなんだ?」
「えっ!」
「グルーバー侯爵様は本気のようだぞ」
「いきなりそんなことを聞かれても……困ります」
本音としては「こんな心境で答えられるか!」ではあるが、そんなことを言えるはずもなく。私は静かにカーテシーをして執務室から出ていった。
***
「クソッ!」
首都の繁華街で、壁に悪態をつける男。ここではよく見かける光景だ。
一晩で身ぐるみを剥がされたり、やけ酒の末に叩き出されたり。しまいには美人局に遭って、身も心もボロボロになるケースもある。
故に、それがこの国でも指折りな有力貴族の令息であっても、皆、見ぬ振りをするのだ。
自業自得だろう。ここで遊ぶのなら、もっと紳士的に、スマートにやるのが貴族だ、とでもいうように。
その男の目にも、彼らの姿はそう映ったのだろう。男の行動はさらにエスカレートしていった。
「たかだが、あの程度のことで騒ぎやがって」
裏路地に置いてあるゴミ箱を蹴る。
「謹慎だぁ、徐免だぁ。そんなこと、知ったことかよ!」
飛び散ったゴミがズボンにつき、払うようにしてまた壁を蹴る。
「クソ親父めっ! あれくらいどうにかできるだろうが!」
その瞬間、鈍い音がする。何度も壁を蹴れば、いずれそうなることを男は知らなかったらしい。足を抱えて悶絶していた。
「そもそも、アレがあの場にいなけりゃこんなことには……」
涙目になりながら、男はゴミ箱が飛んだ先を見る。するとそこには……。
「いなければ。いや、いちゃいけないんだよ、なぁ」
散らばったゴミに近づく三毛猫を見て、男はニヤリと笑った。
「猫なんかさ」