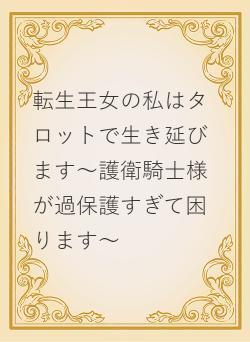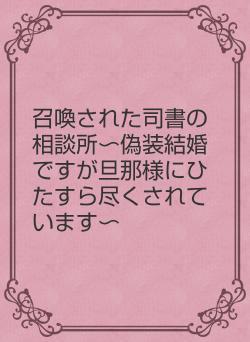「そんなに警戒しないでください。というのは無理な話のようですね」
「あぁ。たとえいい話を切り出されても、難しいだろうな」
私はカーティス様の腕の中で、大いに同意した。嫌な空気が肌まで伝わってくる。
ピナと感情や、時には感覚さえも共にすることがあるからなのか、自然と私も敏感になった。
「そうですか。私としては、あまり騒ぎ立てられるのは困るのですよ。特にそちらのお嬢さんには」
「なっ、私は無闇に――……」
騒いだりしません、と言うためにカーティス様の体を押し退けて、振り返った。直後、ふわりと浮き上がる。
「え?」
気がつくと私は背後にいるカーティス様に腰を掴まれ、まるでダンスのステップを踏むように百八十度回転した。カーティス様の体ごと。
何? 何が起こったの?
そう思った瞬間、目の前にあったのはカーティス様ではなく、壁だった。
「用があるのは俺ではないのか?」
その問いは、明らかに私に向けられたものではない。振り返ると、カーティス様の背中が見えた。どうやら、私は庇われたらしい。
それがちょっと悔しくて、前に手を伸ばす。
騎士として、非戦闘員である私を背に隠すのは、当然の判断だと思うけれど。私だって……一緒に潜入調査をする仲間……じゃないの?
背中に触れると驚いたのか、カーティス様が首を横に向けた。
「大丈夫だ」
違う。心配な気持ちはあるけれど、そういう意味で触れたわけじゃないの。
私はただ、足手まといにはなりたくないから、黙って頷いた。
「実は困った案件が起きまして。近衛騎士団長様とマクギニス嬢に手伝っていただきたいのです」
「国民を守るのが我々の使命だ。余程のことがない限りは聞こう。だが、マクギニス嬢は我々の傘下ではない。協力者だ。彼女に強制することは控えてもらおうか」
「こちらを見ても、同じことが言えますか?」
ノハンダ伯爵の言葉が終えると、扉が開く音がした。
そこから漂ってくる気配。
先ほど感じた嫌な空気よりも、親しみやすい。けれど鳥肌が立つほど感じる、この恐怖は何?
私はカーティス様の肩と腕を掴み、真横まで歩み寄る。
「っ!」
「ルフィナ嬢!」
扉から現れた人物が抱えるソレに、私は駆け寄った。驚くカーティス様の声は耳に入らず、抱える人物も目に入らなかった。
ただただソレが、その子が痛々しくて。
私は奪い取るように、布に包まれた虎柄の猫を抱いた。
オレンジ色の縞模様が特徴の茶トラ猫。人懐っこくて、調査にはもってこいだが、目的をしばしば忘れることが多い、可愛い猫ちゃん。
触ると柔らかくて、いつまでも撫でていたくなる胴体が硬い。動き回るのが好きなのに、ピクリとも反応を示さない。
冷たくなった体に、少しでも温もりが戻って欲しくて、私は茶トラを抱き締めた。頬を流れる涙で、茶トラが濡れることもお構いなしに。
***
しゃがみ込む私に、影を落とす者がいた。
「マクギニス嬢……」
愛らしい声に似合わない憂いを帯びた声音。床に広がる私のドレスを気遣いながら近づけるのは、一人しかいなかった。
そう、休憩室に茶トラを連れてきてくれた女性。
私はお礼すら言っていないことに気がつき、顔を上げた。涙を拭える余裕がなかったから、酷い顔をしていたことだろう。
それでも女性は気にせずに私の頬を撫でた。今、私が他の誰かに茶トラを触られたくないのを、理解してくれているようだった。
「ごめんなさい。私がもう少し、速く動けていたら、こんなことにはならなかったのに」
紫色の瞳が悲しげに私を見つめ、茶トラへと移動する。
何故、そんな目で茶トラを見るの? 茶トラは野良だ。本来なら、彼女の目に留まることなどあり得ない存在。
いや、王城にいる猫にすら、膝を折って挨拶をする女性だ。猫がお好きなことも知っている。
恐らく、ノハンダ伯爵邸で茶トラを見かけたのだろう。ここに連れてきたのがその証拠だ。
ならば何故、このようなことが起こったのか。それを知っているに違いない。
私は震える声で尋ねた。
「どういうことですか? ドリス王女殿下」
再び視線が向けられる。美しい銀髪と相まって、その姿はとても儚げに見えた。
「あぁ。たとえいい話を切り出されても、難しいだろうな」
私はカーティス様の腕の中で、大いに同意した。嫌な空気が肌まで伝わってくる。
ピナと感情や、時には感覚さえも共にすることがあるからなのか、自然と私も敏感になった。
「そうですか。私としては、あまり騒ぎ立てられるのは困るのですよ。特にそちらのお嬢さんには」
「なっ、私は無闇に――……」
騒いだりしません、と言うためにカーティス様の体を押し退けて、振り返った。直後、ふわりと浮き上がる。
「え?」
気がつくと私は背後にいるカーティス様に腰を掴まれ、まるでダンスのステップを踏むように百八十度回転した。カーティス様の体ごと。
何? 何が起こったの?
そう思った瞬間、目の前にあったのはカーティス様ではなく、壁だった。
「用があるのは俺ではないのか?」
その問いは、明らかに私に向けられたものではない。振り返ると、カーティス様の背中が見えた。どうやら、私は庇われたらしい。
それがちょっと悔しくて、前に手を伸ばす。
騎士として、非戦闘員である私を背に隠すのは、当然の判断だと思うけれど。私だって……一緒に潜入調査をする仲間……じゃないの?
背中に触れると驚いたのか、カーティス様が首を横に向けた。
「大丈夫だ」
違う。心配な気持ちはあるけれど、そういう意味で触れたわけじゃないの。
私はただ、足手まといにはなりたくないから、黙って頷いた。
「実は困った案件が起きまして。近衛騎士団長様とマクギニス嬢に手伝っていただきたいのです」
「国民を守るのが我々の使命だ。余程のことがない限りは聞こう。だが、マクギニス嬢は我々の傘下ではない。協力者だ。彼女に強制することは控えてもらおうか」
「こちらを見ても、同じことが言えますか?」
ノハンダ伯爵の言葉が終えると、扉が開く音がした。
そこから漂ってくる気配。
先ほど感じた嫌な空気よりも、親しみやすい。けれど鳥肌が立つほど感じる、この恐怖は何?
私はカーティス様の肩と腕を掴み、真横まで歩み寄る。
「っ!」
「ルフィナ嬢!」
扉から現れた人物が抱えるソレに、私は駆け寄った。驚くカーティス様の声は耳に入らず、抱える人物も目に入らなかった。
ただただソレが、その子が痛々しくて。
私は奪い取るように、布に包まれた虎柄の猫を抱いた。
オレンジ色の縞模様が特徴の茶トラ猫。人懐っこくて、調査にはもってこいだが、目的をしばしば忘れることが多い、可愛い猫ちゃん。
触ると柔らかくて、いつまでも撫でていたくなる胴体が硬い。動き回るのが好きなのに、ピクリとも反応を示さない。
冷たくなった体に、少しでも温もりが戻って欲しくて、私は茶トラを抱き締めた。頬を流れる涙で、茶トラが濡れることもお構いなしに。
***
しゃがみ込む私に、影を落とす者がいた。
「マクギニス嬢……」
愛らしい声に似合わない憂いを帯びた声音。床に広がる私のドレスを気遣いながら近づけるのは、一人しかいなかった。
そう、休憩室に茶トラを連れてきてくれた女性。
私はお礼すら言っていないことに気がつき、顔を上げた。涙を拭える余裕がなかったから、酷い顔をしていたことだろう。
それでも女性は気にせずに私の頬を撫でた。今、私が他の誰かに茶トラを触られたくないのを、理解してくれているようだった。
「ごめんなさい。私がもう少し、速く動けていたら、こんなことにはならなかったのに」
紫色の瞳が悲しげに私を見つめ、茶トラへと移動する。
何故、そんな目で茶トラを見るの? 茶トラは野良だ。本来なら、彼女の目に留まることなどあり得ない存在。
いや、王城にいる猫にすら、膝を折って挨拶をする女性だ。猫がお好きなことも知っている。
恐らく、ノハンダ伯爵邸で茶トラを見かけたのだろう。ここに連れてきたのがその証拠だ。
ならば何故、このようなことが起こったのか。それを知っているに違いない。
私は震える声で尋ねた。
「どういうことですか? ドリス王女殿下」
再び視線が向けられる。美しい銀髪と相まって、その姿はとても儚げに見えた。