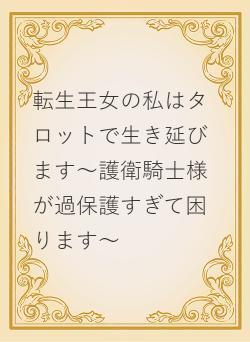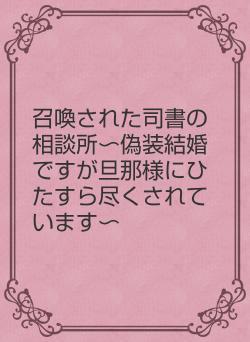そうしてカーティス様から聞き出した話はこうだった。
給仕数名と護衛数名がすでに、ノハンダ伯爵邸に忍び込んでいるという。
「なるほど。それで私も普通に入ることができたんですね」
「俺も周りに知れ渡っているからな。他の者たちも似たような立場だ。まずはそこをクリアしなければならなかったんだ」
貴族派が主催する舞踏会に、王党派が出席するのはよくあること。揉め事を起こさなければ、寛容なのだ。
けれど、仮面舞踏会などといった、裏社会に通じ易い場所には立ち入らない。それが暗黙のルールだった。
中立派である我が家が敵視されているのは、また別の理由がある。猫憑きの特性が、あらぬ誤解を招いていたのだ。
猫を使役して偵察や探索など。人では得られないような情報を手にできることから、スパイ活動をしている、と勝手に思われているらしい。
実際は猫や人からの依頼で、そんなことをしている暇なんてないんだけどね。本音としては、家でゴロゴロしていたいんだから。
けれどそんな言い訳は通用しないらしい。国の裏社会から一目置かれているが、警戒もまたされていた。だからカーティス様とは、また違った意味でマズかったのだ。
まぁ、仮に正体がバレたとしても、お母様ではなく小娘。それも一人だ。遊びに来たという言い訳が通じるだろう。それであっても、問題なく入れたのは凄いことだった。
「とても優秀なのですね」
「あぁ。とある筋から借りた人材だからな」
「まさか……」
「それくらい妹を心配している、と思ってくれ」
もしかしなくても、ヴェルナー殿下からの人員。ということは、王家の影!? そんな優秀な人たちを先に忍ばせていたなんて……。
「……後日、顔を合わせる機会ってできますか?」
「どっちと?」
「勿論、前者です」
途端、嫌な顔をされたので「冗談です」と舌を出して誤魔化した。
さすがに、王家の影と簡単に会えるとは思っていない。けれど、彼らの活躍は猫たちの目を通していても、憧れてしまうのだ。
「はぁ。いずれにしても、彼らは君を認識している。何かあれば力になってくれるだろう」
「今宵限定の共闘ですね。何だかワクワクしてきました」
「……会場に入る前に君が言った言葉を、そのまま送ろうか?」
え? と首を傾げると、突然耳元で囁かれた。
「緊張感だけは持ってくれ」
「わ、分かりました。分かりましたから、少しだけ離れてください」
カーティス様の顔を押したくても、今はダンス中。それは不可能だった。
「話によると、さっきドリス王女がいた場所の奥から、例の場所へ入れるらしい。それからルフィナ嬢に渡したカフスボタンは、ザヤラ子爵家の物だ」
「っ! 最近、ノハンダ伯爵に近づいた家の者ではありませんか。まさか」
この日のために?
驚きのあまり、未だカーティス様の顔が真横にあっても気にならなかった。
「そういうわけだから、二階に上がったら、恋人の振りではなく、ザヤラ子爵夫人として振る舞ってくれ」
「えっ!」
離れていくカーティス様の顔が、先ほどの仕返しとでもいうような、茶目っ気のある笑みを浮かべていた。
***
ザヤラ子爵。私は猫たちから得た情報を元に、脳内で検索をかけた。
最近貴族派に鞍替えした、王党派の貴族。全く怪しまれなかったのは、それが結婚した直後だったからだ。
何か思うことがあったのだろう、と気にも留めなかった。そう、誰も。
王党派は裏切り者だと言わなかったし、迎え入れた貴族派も不審に思わなかった。中立派である、我が家さえも。
それがまさか、この潜入調査のためだったなんて……!
さらにザヤラ子爵の背丈は、カーティス様とあまり変わらない。体躯も。年齢は確か、カーティス様よりも若かったと思う。
だって、奥様となられた方は……私と同じ十九歳だったから。
「確かに、ザヤラ子爵様ですね。ではこちらへ」
髪色や瞳の色が違っていても、使用人は我関せずといった様子だった。これも忍ばせていた人物なのか、とカーティス様の方を見た。が、首を振られたので、違うらしい。
「ノハンダ伯爵は強かな男でな。客であれば、小さなネズミが入り込んでいても構わないらしい。ただし、あとでシュッセル公爵に言い訳できるように、来場のチェックはしているんだ」
「ただの腰巾着になりたいわけではない、ということですか?」
休憩室に案内してくれた使用人は、役目が終えたのか、そそくさと席を外した。
偏にザヤラ子爵と夫人が新婚だからなのか、それとも明らかに別人だから、関わりたくないと判断したか、のどちらかだろう。
ともあれ、人目を気にせずに話せるのは有り難かった。
「俺の、いや俺らの憶測だがな」
「あっ、だから今日を選んだんですね」
緩いチェックに加えて、ノハンダ伯爵の人物像。まだ、王城に出入りできるほどではないからこそ、見極めに行ってくれとでも言われたのだろう。ヴェルナー殿下に。
ドリス王女のついでというのには、多過ぎるお使いだ。
「権力に惹かれただけなら、こちらの方が魅力的だろう?」
「それはまぁ、分かりますが……。そ、そんな人間、信用できません」
「俺もするつもりはないさ。だが、必要な役割があるんだ」
必要とは? と聞こうとした瞬間、カーティス様に腰を掴まれた。さらにもう片方の手は頭の後ろに。一気に引き寄せられる。
「誰だ」
頭上から降ってくるカーティス様の声は、とても冷たかった。思わず体を強張らせると、頭に置かれた手がゆっくりと動き出す。
まるで、大丈夫だと言わんばかりに撫でられ、私はそのまま、カーティス様の胸に顔を埋めた。
「ノックもなく入ってくるとは、随分と失礼ではないのか?」
「そうですね。本物のザヤラ子爵ならば、別に失礼だとは思いませんよ」
丁寧な言葉使い。けれど、カーティス様を揶揄しているかのような口調で、自ずと相手が誰だか見当はついた。たとえ背を向けていても。
その答えを教えてくれるかのように、カーティス様が口を開く。
「なるほど。俺たちの正体を知っていて、わざわざ訪ねたというのだな、ノハンダ伯爵」
「でなければ、このようなお部屋には通しません」
「何?」
声と共に力が入る腕。痛いとは言っていられない。ノハンダ伯爵がどんな意図でやって来たのか分からない以上、声を出すのは危険。
私はカーティス様の背中に手を回し、上着をギュッと握った。
給仕数名と護衛数名がすでに、ノハンダ伯爵邸に忍び込んでいるという。
「なるほど。それで私も普通に入ることができたんですね」
「俺も周りに知れ渡っているからな。他の者たちも似たような立場だ。まずはそこをクリアしなければならなかったんだ」
貴族派が主催する舞踏会に、王党派が出席するのはよくあること。揉め事を起こさなければ、寛容なのだ。
けれど、仮面舞踏会などといった、裏社会に通じ易い場所には立ち入らない。それが暗黙のルールだった。
中立派である我が家が敵視されているのは、また別の理由がある。猫憑きの特性が、あらぬ誤解を招いていたのだ。
猫を使役して偵察や探索など。人では得られないような情報を手にできることから、スパイ活動をしている、と勝手に思われているらしい。
実際は猫や人からの依頼で、そんなことをしている暇なんてないんだけどね。本音としては、家でゴロゴロしていたいんだから。
けれどそんな言い訳は通用しないらしい。国の裏社会から一目置かれているが、警戒もまたされていた。だからカーティス様とは、また違った意味でマズかったのだ。
まぁ、仮に正体がバレたとしても、お母様ではなく小娘。それも一人だ。遊びに来たという言い訳が通じるだろう。それであっても、問題なく入れたのは凄いことだった。
「とても優秀なのですね」
「あぁ。とある筋から借りた人材だからな」
「まさか……」
「それくらい妹を心配している、と思ってくれ」
もしかしなくても、ヴェルナー殿下からの人員。ということは、王家の影!? そんな優秀な人たちを先に忍ばせていたなんて……。
「……後日、顔を合わせる機会ってできますか?」
「どっちと?」
「勿論、前者です」
途端、嫌な顔をされたので「冗談です」と舌を出して誤魔化した。
さすがに、王家の影と簡単に会えるとは思っていない。けれど、彼らの活躍は猫たちの目を通していても、憧れてしまうのだ。
「はぁ。いずれにしても、彼らは君を認識している。何かあれば力になってくれるだろう」
「今宵限定の共闘ですね。何だかワクワクしてきました」
「……会場に入る前に君が言った言葉を、そのまま送ろうか?」
え? と首を傾げると、突然耳元で囁かれた。
「緊張感だけは持ってくれ」
「わ、分かりました。分かりましたから、少しだけ離れてください」
カーティス様の顔を押したくても、今はダンス中。それは不可能だった。
「話によると、さっきドリス王女がいた場所の奥から、例の場所へ入れるらしい。それからルフィナ嬢に渡したカフスボタンは、ザヤラ子爵家の物だ」
「っ! 最近、ノハンダ伯爵に近づいた家の者ではありませんか。まさか」
この日のために?
驚きのあまり、未だカーティス様の顔が真横にあっても気にならなかった。
「そういうわけだから、二階に上がったら、恋人の振りではなく、ザヤラ子爵夫人として振る舞ってくれ」
「えっ!」
離れていくカーティス様の顔が、先ほどの仕返しとでもいうような、茶目っ気のある笑みを浮かべていた。
***
ザヤラ子爵。私は猫たちから得た情報を元に、脳内で検索をかけた。
最近貴族派に鞍替えした、王党派の貴族。全く怪しまれなかったのは、それが結婚した直後だったからだ。
何か思うことがあったのだろう、と気にも留めなかった。そう、誰も。
王党派は裏切り者だと言わなかったし、迎え入れた貴族派も不審に思わなかった。中立派である、我が家さえも。
それがまさか、この潜入調査のためだったなんて……!
さらにザヤラ子爵の背丈は、カーティス様とあまり変わらない。体躯も。年齢は確か、カーティス様よりも若かったと思う。
だって、奥様となられた方は……私と同じ十九歳だったから。
「確かに、ザヤラ子爵様ですね。ではこちらへ」
髪色や瞳の色が違っていても、使用人は我関せずといった様子だった。これも忍ばせていた人物なのか、とカーティス様の方を見た。が、首を振られたので、違うらしい。
「ノハンダ伯爵は強かな男でな。客であれば、小さなネズミが入り込んでいても構わないらしい。ただし、あとでシュッセル公爵に言い訳できるように、来場のチェックはしているんだ」
「ただの腰巾着になりたいわけではない、ということですか?」
休憩室に案内してくれた使用人は、役目が終えたのか、そそくさと席を外した。
偏にザヤラ子爵と夫人が新婚だからなのか、それとも明らかに別人だから、関わりたくないと判断したか、のどちらかだろう。
ともあれ、人目を気にせずに話せるのは有り難かった。
「俺の、いや俺らの憶測だがな」
「あっ、だから今日を選んだんですね」
緩いチェックに加えて、ノハンダ伯爵の人物像。まだ、王城に出入りできるほどではないからこそ、見極めに行ってくれとでも言われたのだろう。ヴェルナー殿下に。
ドリス王女のついでというのには、多過ぎるお使いだ。
「権力に惹かれただけなら、こちらの方が魅力的だろう?」
「それはまぁ、分かりますが……。そ、そんな人間、信用できません」
「俺もするつもりはないさ。だが、必要な役割があるんだ」
必要とは? と聞こうとした瞬間、カーティス様に腰を掴まれた。さらにもう片方の手は頭の後ろに。一気に引き寄せられる。
「誰だ」
頭上から降ってくるカーティス様の声は、とても冷たかった。思わず体を強張らせると、頭に置かれた手がゆっくりと動き出す。
まるで、大丈夫だと言わんばかりに撫でられ、私はそのまま、カーティス様の胸に顔を埋めた。
「ノックもなく入ってくるとは、随分と失礼ではないのか?」
「そうですね。本物のザヤラ子爵ならば、別に失礼だとは思いませんよ」
丁寧な言葉使い。けれど、カーティス様を揶揄しているかのような口調で、自ずと相手が誰だか見当はついた。たとえ背を向けていても。
その答えを教えてくれるかのように、カーティス様が口を開く。
「なるほど。俺たちの正体を知っていて、わざわざ訪ねたというのだな、ノハンダ伯爵」
「でなければ、このようなお部屋には通しません」
「何?」
声と共に力が入る腕。痛いとは言っていられない。ノハンダ伯爵がどんな意図でやって来たのか分からない以上、声を出すのは危険。
私はカーティス様の背中に手を回し、上着をギュッと握った。