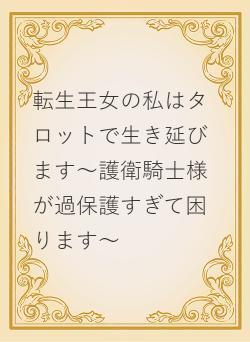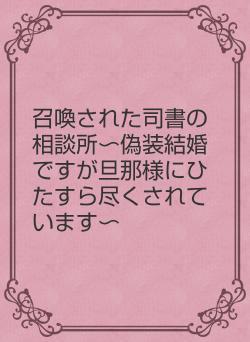「ジルケ……」
俺は目の前に立っている金髪の女性、いや部下の名前を呼んだ。
二時間前と同じ口調で。違うのは、場所がカフェから、俺の執務室があるグルーバー侯爵邸になったぐらいだろうか。
ジルケは表情を変えずに、赤い瞳で俺を見据えた。
「今日のお前の役目は、ルフィナ嬢の護衛だ。さらに、接触禁止だと命じていたはずだが」
「命令違反をしたのは認めます。けれど、あれは緊急事態だったのです」
シレっと言うジルケに、俺は声を低くした。
「どこが緊急事態だ。あの場にいた俺でも分かるように説明してくれ」
「はい。それは、全く相手にされていないところです。恐らく、私だけでなく、団員のほとんどが感じていることでしょう。近衛騎士団長ともあろう方が情けない」
「それはまだ、知り合って間もないから……」
仕方がないだろう。元々、騎士団の行事や練習場など、令嬢でも立ち入りができる場所にも来ない女性だ。こちらに一切、関心がないのだろう。
それをここまで漕ぎ着けたというのに、非難される覚えはない。
「だからこその緊急事態ではありませんか。今回の潜入調査。マクギニス嬢が一番適任だと、我々も思っています」
「そうか」
騎士団の中には疑問視する者も出るだろう、と思っていただけに、ジルケの言葉は心強かった。が、それは束の間だった。
次に出てきた言葉は、矢となって俺の胸に突き刺さる。
「しかし、騎士団としては、ヴェルナー殿下からマクギニス伯爵へ命令。その後は手続きに乗っ取って、マクギニス嬢と面談されるのが正規。違いますか?」
「……その通りだ」
「けれど、団長は直接交渉なさった。マクギニス嬢と。なら、答えは簡単ではありませんか」
ニコリと笑ってみせるジルケ。俺は人選を間違えたのではないか、と後悔し始めた。
騎士団の中でも腕が立つ上に、自ら志願した。故に任せたのだが……。
「ですが、団長はマクギニス嬢の視界にすら入っていない」
「……ぐっ」
「これを緊急事態でなく、何と言うんですか! 仮に、私が出ていかなかったら、団長は何と返事をするおつもりだったのでしょうか」
『私は……そこまで誰かに好意を抱いたことがないので……』
表情を見せたくなかったのか、俯くルフィナ嬢の姿が脳裏に浮かぶ。
「お答えできませんか。ならば尚更、私が出ていって正解だったのでは?」
「そんなことはないだろう。変に誤解されたらどうする!」
「誤解などあり得ません。むしろ団長にとって、有益な情報を仕入れてきた私を褒めていただきたいくらいです」
「有益な……情報……?」
「はい」
ジルケは不適な笑みを浮かべ、その時のことを話し始めた。
そう、俺とルフィナ嬢の間に割った後の出来事を。
***
「失礼いたします。本日、マクギニス嬢の護衛をさせていただいている、ジルケ・ブルメスターという者です」
「まぁ、私は――……」
席を立ち、挨拶しようとするルフィナ嬢を制した。
「ジルケ」
「団長、お願いがございます。少しだけでもいいので、マクギニス嬢とお話しさせてはもらえないでしょうか」
「理由は?」
「秘密です。込み入った話なので」
「許可できると思うか?」
そう言うと、ジルケは何を思ったのか、ルフィナ嬢に近づいて耳打ちをした。
さすがに声を拾うことまではできなかったが、驚いたり、顔を赤らめたりするルフィナ嬢に、内心苛立った。
コロコロと表情を変えることは、俺の前でもしていたが、赤面は……!
「カーティス様。その、私からもお願いできないでしょうか」
「ジルケ!」
「団長」
ジルケの視線が動く。斜め下。そこにいるのは……。
「すまない、ルフィナ嬢。大声を出してしまって」
「い、いえ……」
やってしまった。他の令嬢よりも、ルフィナ嬢は大きな音に過敏だと分かっていたのにも関わらず。
「団長。ここは私に任せていただけませんか?」
「だが……」
「カーティス様」
まだ怯えが消えない瞳で見つめられ、俺は返答に困ってしまった。しかも上目遣い。
俺はその緑色の瞳から逃げるように、目を閉じた。しかし、耳までは防げなかった。
「お願いします」
「……三十分だけだ。ジルケ、いいな」
「はい。ありがとうございます」
頭を下げるジルケを見て、内心悪態をついた。恐らく、デートだと思っているのは俺だけなのだろう。あとは騎士団の者たちくらいか。
けれど、ルフィナ嬢は……。そんな彼女に対して強引な手は使えない。独占欲を出せば、逃げて行ってしまうだろう。
それほどまでにルフィナ嬢は、人間に警戒心を抱く。怯えることに慣れ、期待はしない。頼るのは人ではなく猫だ。好意さえも。
だから余計に癪に障った。
「団長。機嫌を直してください」
ルフィナ嬢たちから離れると、すぐに別の団員が近づいてきた。一部始終を知られているだけに、俺はそのまま不機嫌な表情を向ける。
「これはこれで、チャンスですよ!」
「チャンス?」
「席を離れている間に、プレゼントを用意するんです。ほら、宝石店に入った時、他の物も興味津々に見ていたじゃないですか」
「そうだな。帰りの馬車の中で渡すのはどうだろうか」
「いいと思いますよ。それじゃ、早速行きましょう」
浮かれる団員の背中を見ながら、俺の足取りも軽くなった。どんなアクセサリーが似合うだろうか。
そう考えただけで緩む口元を、俺は咄嗟に手で隠した。
俺は目の前に立っている金髪の女性、いや部下の名前を呼んだ。
二時間前と同じ口調で。違うのは、場所がカフェから、俺の執務室があるグルーバー侯爵邸になったぐらいだろうか。
ジルケは表情を変えずに、赤い瞳で俺を見据えた。
「今日のお前の役目は、ルフィナ嬢の護衛だ。さらに、接触禁止だと命じていたはずだが」
「命令違反をしたのは認めます。けれど、あれは緊急事態だったのです」
シレっと言うジルケに、俺は声を低くした。
「どこが緊急事態だ。あの場にいた俺でも分かるように説明してくれ」
「はい。それは、全く相手にされていないところです。恐らく、私だけでなく、団員のほとんどが感じていることでしょう。近衛騎士団長ともあろう方が情けない」
「それはまだ、知り合って間もないから……」
仕方がないだろう。元々、騎士団の行事や練習場など、令嬢でも立ち入りができる場所にも来ない女性だ。こちらに一切、関心がないのだろう。
それをここまで漕ぎ着けたというのに、非難される覚えはない。
「だからこその緊急事態ではありませんか。今回の潜入調査。マクギニス嬢が一番適任だと、我々も思っています」
「そうか」
騎士団の中には疑問視する者も出るだろう、と思っていただけに、ジルケの言葉は心強かった。が、それは束の間だった。
次に出てきた言葉は、矢となって俺の胸に突き刺さる。
「しかし、騎士団としては、ヴェルナー殿下からマクギニス伯爵へ命令。その後は手続きに乗っ取って、マクギニス嬢と面談されるのが正規。違いますか?」
「……その通りだ」
「けれど、団長は直接交渉なさった。マクギニス嬢と。なら、答えは簡単ではありませんか」
ニコリと笑ってみせるジルケ。俺は人選を間違えたのではないか、と後悔し始めた。
騎士団の中でも腕が立つ上に、自ら志願した。故に任せたのだが……。
「ですが、団長はマクギニス嬢の視界にすら入っていない」
「……ぐっ」
「これを緊急事態でなく、何と言うんですか! 仮に、私が出ていかなかったら、団長は何と返事をするおつもりだったのでしょうか」
『私は……そこまで誰かに好意を抱いたことがないので……』
表情を見せたくなかったのか、俯くルフィナ嬢の姿が脳裏に浮かぶ。
「お答えできませんか。ならば尚更、私が出ていって正解だったのでは?」
「そんなことはないだろう。変に誤解されたらどうする!」
「誤解などあり得ません。むしろ団長にとって、有益な情報を仕入れてきた私を褒めていただきたいくらいです」
「有益な……情報……?」
「はい」
ジルケは不適な笑みを浮かべ、その時のことを話し始めた。
そう、俺とルフィナ嬢の間に割った後の出来事を。
***
「失礼いたします。本日、マクギニス嬢の護衛をさせていただいている、ジルケ・ブルメスターという者です」
「まぁ、私は――……」
席を立ち、挨拶しようとするルフィナ嬢を制した。
「ジルケ」
「団長、お願いがございます。少しだけでもいいので、マクギニス嬢とお話しさせてはもらえないでしょうか」
「理由は?」
「秘密です。込み入った話なので」
「許可できると思うか?」
そう言うと、ジルケは何を思ったのか、ルフィナ嬢に近づいて耳打ちをした。
さすがに声を拾うことまではできなかったが、驚いたり、顔を赤らめたりするルフィナ嬢に、内心苛立った。
コロコロと表情を変えることは、俺の前でもしていたが、赤面は……!
「カーティス様。その、私からもお願いできないでしょうか」
「ジルケ!」
「団長」
ジルケの視線が動く。斜め下。そこにいるのは……。
「すまない、ルフィナ嬢。大声を出してしまって」
「い、いえ……」
やってしまった。他の令嬢よりも、ルフィナ嬢は大きな音に過敏だと分かっていたのにも関わらず。
「団長。ここは私に任せていただけませんか?」
「だが……」
「カーティス様」
まだ怯えが消えない瞳で見つめられ、俺は返答に困ってしまった。しかも上目遣い。
俺はその緑色の瞳から逃げるように、目を閉じた。しかし、耳までは防げなかった。
「お願いします」
「……三十分だけだ。ジルケ、いいな」
「はい。ありがとうございます」
頭を下げるジルケを見て、内心悪態をついた。恐らく、デートだと思っているのは俺だけなのだろう。あとは騎士団の者たちくらいか。
けれど、ルフィナ嬢は……。そんな彼女に対して強引な手は使えない。独占欲を出せば、逃げて行ってしまうだろう。
それほどまでにルフィナ嬢は、人間に警戒心を抱く。怯えることに慣れ、期待はしない。頼るのは人ではなく猫だ。好意さえも。
だから余計に癪に障った。
「団長。機嫌を直してください」
ルフィナ嬢たちから離れると、すぐに別の団員が近づいてきた。一部始終を知られているだけに、俺はそのまま不機嫌な表情を向ける。
「これはこれで、チャンスですよ!」
「チャンス?」
「席を離れている間に、プレゼントを用意するんです。ほら、宝石店に入った時、他の物も興味津々に見ていたじゃないですか」
「そうだな。帰りの馬車の中で渡すのはどうだろうか」
「いいと思いますよ。それじゃ、早速行きましょう」
浮かれる団員の背中を見ながら、俺の足取りも軽くなった。どんなアクセサリーが似合うだろうか。
そう考えただけで緩む口元を、俺は咄嗟に手で隠した。