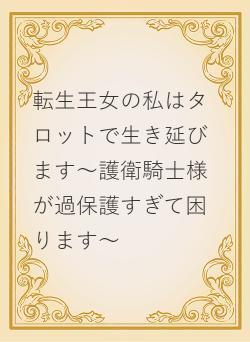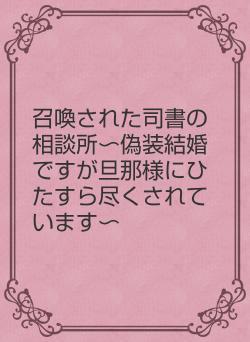「それはそうと、本題に入ってもいいだろうか」
「勿論です。そのために来たんですから」
何故か少しだけ落胆した姿を見せたカーティス様は、服の内ポケットから、一枚の紙を取り出した。
それをそのままテーブルの上に置き、私の方に向かって、そっと押し出す。
これが何なのか、言わずに差し出すということは、言葉に出せない案件。
つまり仮面舞踏会、またはシュッセル公子のことか。あるいはドリス王女殿下の情報かもしれない。
私は躊躇わずに紙を広げ、中身を確認した。
案の定、シュッセル公子に関することだった。その延長線上にある仮面舞踏会で行われているであろう、ある憶測の件も一緒に。
「読んだ後に言うのもなんですが、このような物を出して、大丈夫なんですか?」
「あぁ。問題ない。さらに言うと、話題に出しても平気だ」
「え? でも……」
私は手元の紙に、再び視線を向けた。さらに周囲も。
「周りにいるのは騎士団の者だからな」
「……確かに女性もいる、と話をしましたが、もしかして護衛……ですか?」
「厳密にいうと、その予行練習だ」
何の? と聞くのは野暮なこと。
仮面舞踏会でなくても、舞踏会の会場に入れば、カーティス様の傍に終始いるのは不可能。さらに猫たちも入れない場所なのだ。
自分の身を守る術は学んでいるものの、さすがに腕利きや多数で来られても対処はできない。ピナがいなければ所詮、その程度の人間。
結局、カーティス様のお荷物になってしまうのだ。
「すみません」
「何がだ?」
「そのような手配までしていただいたことに、です」
「依頼した側が護衛を用意するのは、確かにおかしなことだが、ルフィナ嬢を危険に晒すわけにもいかない。……ふむ。これも矛盾しているな」
横髪をかき分けながら、首の後ろに手を当てるカーティス様。
「ふふふ。いいえ。騎士団長様として頼もしい限りですわ」
「そ、そうか」
「はい」
何故だろう。普段は騎士団長として、隙のないカーティス様を見ているせいだろうか。
困惑したり、慌てたりする姿を見ると、頬が緩んでしまう。
けれど、今日の目的を果たさなくては。私は紙を折り畳み、カーティス様を見据えた。
「ここに記されている、シュッ……いえ、者についてですが、こちらでも裏が取れています」
「全く同じ内容か?」
「はい」
シュッセル公子……ローマン・シュッセル公爵令息は、ある案件に手を染めていた。
オークション。その背後にある人身売買。
それら全てが仮面舞踏会の裏で取引されていた。
「どの会場でも主催者は、やはり別の者でした。さすがにここで言うのは、差し控えさせていただきます。それよりも、あの者は何故、あのようなところに王……いえ、女性を伴って行かれるのでしょうか」
「考えられる可能性は三つ」
「三つも……?」
私は一つくらいだったのに。さすがは近衛騎士団長様だわ。
「女性の財布以外に、何があるんですか?」
「財布、か。なかなか面白い表現をするな」
「そうですか? 的確で分かりやすいと思ったんですが」
首を傾けて笑って見せると、カーティス様も笑顔で返してくれた。
「そうだな。けれど、相手も財政難に陥る者ではない。まぁ、個人的に借金をしていなければ、の話だがな」
「確かに、他にも悪いお友だちがいらっしゃるようですからね」
その者らとカジノに行き、豪遊っぷりを披露している、とのことだ。まさに絵に描いたようなドラ息子である。
「だから、財布にしている可能性も否定できない。あとは内政だな」
「え? まさか女性を利用して、さらに力をつける魂胆でもある、と仰るんですか? けれど……」
ドリス王女は内政に関心がない。であるならば、シュッセル公子または公爵の頼みなど聞くだろうか。
むしろ、話を正しく理解できるかどうか、それさえも怪しいというのに……。
「その女性にできるかできないか、などあの者たちには関係ない。そうせざるを得ない状況に持っていけば、誰だって必死になってやらせることは可能だ」
「まさか、やく……危ないものを口にさせるおつもりで?」
薬物と言おうとした口を隠しながら尋ねた。
「否定できないだろうな。そこに書いてあるものが氷山の一角ならば、女性とその兄を仲違いさせ、弱体化。もしくは失脚までも視野に入れているのかもしれない。それくらいの効果はある」
「なるほど。カーティス様を通して依頼されるほど、大事にされていますからね。十分あり得そうです」
「いや、これは……」
突然、言葉を詰まらせるカーティス様。それを不思議そうに眺めていると、一つ咳払いをされた。
「と、ともかく、犯罪に巻き込まれている可能性が大いにある、ということだ」
「……そうですね。女性をわざわざ誘っておいて、放置するとは思えませんし。そのような扱いを受けると分かっていて、のこのことついて行くのは、いくらなんでも考え辛いです」
ドリス王女はお世辞にも賢いとは言い難い。が、仮にも王族だ。無礼な扱いを受けてまで、シュッセル公子と行動を共にするだろうか。
「だが、三つ目の可能性だった場合は否定できない」
「財布、政治……。残る一つは何ですか?」
「……好意だ」
「……好……意?」
つまり、シュッセル公子が好きだから、どんな扱いを受けても構わないと?
「それだけで、ついて行けますか?」
「ルフィナ嬢はできないと?」
「私は……そこまで誰かに好意を抱いたことがないので……」
声が小さくなるのと同時に、私の頭も下がっていく。カーティス様を直視できなかったのだ。
すると、後ろからガタンと音がして、思わず肩が跳ねる。
頭上に感じる気配に、そっと目を開けた。テーブルの上にある影が重なって、色が濃くなる。
けれど、それはカーティス様の影ではなかったらしい。
「ジルケ……」
「え?」
別の名を呼ぶ声に、私は顔を上げた。だってそれは、女性の名前だったからだ。
「勿論です。そのために来たんですから」
何故か少しだけ落胆した姿を見せたカーティス様は、服の内ポケットから、一枚の紙を取り出した。
それをそのままテーブルの上に置き、私の方に向かって、そっと押し出す。
これが何なのか、言わずに差し出すということは、言葉に出せない案件。
つまり仮面舞踏会、またはシュッセル公子のことか。あるいはドリス王女殿下の情報かもしれない。
私は躊躇わずに紙を広げ、中身を確認した。
案の定、シュッセル公子に関することだった。その延長線上にある仮面舞踏会で行われているであろう、ある憶測の件も一緒に。
「読んだ後に言うのもなんですが、このような物を出して、大丈夫なんですか?」
「あぁ。問題ない。さらに言うと、話題に出しても平気だ」
「え? でも……」
私は手元の紙に、再び視線を向けた。さらに周囲も。
「周りにいるのは騎士団の者だからな」
「……確かに女性もいる、と話をしましたが、もしかして護衛……ですか?」
「厳密にいうと、その予行練習だ」
何の? と聞くのは野暮なこと。
仮面舞踏会でなくても、舞踏会の会場に入れば、カーティス様の傍に終始いるのは不可能。さらに猫たちも入れない場所なのだ。
自分の身を守る術は学んでいるものの、さすがに腕利きや多数で来られても対処はできない。ピナがいなければ所詮、その程度の人間。
結局、カーティス様のお荷物になってしまうのだ。
「すみません」
「何がだ?」
「そのような手配までしていただいたことに、です」
「依頼した側が護衛を用意するのは、確かにおかしなことだが、ルフィナ嬢を危険に晒すわけにもいかない。……ふむ。これも矛盾しているな」
横髪をかき分けながら、首の後ろに手を当てるカーティス様。
「ふふふ。いいえ。騎士団長様として頼もしい限りですわ」
「そ、そうか」
「はい」
何故だろう。普段は騎士団長として、隙のないカーティス様を見ているせいだろうか。
困惑したり、慌てたりする姿を見ると、頬が緩んでしまう。
けれど、今日の目的を果たさなくては。私は紙を折り畳み、カーティス様を見据えた。
「ここに記されている、シュッ……いえ、者についてですが、こちらでも裏が取れています」
「全く同じ内容か?」
「はい」
シュッセル公子……ローマン・シュッセル公爵令息は、ある案件に手を染めていた。
オークション。その背後にある人身売買。
それら全てが仮面舞踏会の裏で取引されていた。
「どの会場でも主催者は、やはり別の者でした。さすがにここで言うのは、差し控えさせていただきます。それよりも、あの者は何故、あのようなところに王……いえ、女性を伴って行かれるのでしょうか」
「考えられる可能性は三つ」
「三つも……?」
私は一つくらいだったのに。さすがは近衛騎士団長様だわ。
「女性の財布以外に、何があるんですか?」
「財布、か。なかなか面白い表現をするな」
「そうですか? 的確で分かりやすいと思ったんですが」
首を傾けて笑って見せると、カーティス様も笑顔で返してくれた。
「そうだな。けれど、相手も財政難に陥る者ではない。まぁ、個人的に借金をしていなければ、の話だがな」
「確かに、他にも悪いお友だちがいらっしゃるようですからね」
その者らとカジノに行き、豪遊っぷりを披露している、とのことだ。まさに絵に描いたようなドラ息子である。
「だから、財布にしている可能性も否定できない。あとは内政だな」
「え? まさか女性を利用して、さらに力をつける魂胆でもある、と仰るんですか? けれど……」
ドリス王女は内政に関心がない。であるならば、シュッセル公子または公爵の頼みなど聞くだろうか。
むしろ、話を正しく理解できるかどうか、それさえも怪しいというのに……。
「その女性にできるかできないか、などあの者たちには関係ない。そうせざるを得ない状況に持っていけば、誰だって必死になってやらせることは可能だ」
「まさか、やく……危ないものを口にさせるおつもりで?」
薬物と言おうとした口を隠しながら尋ねた。
「否定できないだろうな。そこに書いてあるものが氷山の一角ならば、女性とその兄を仲違いさせ、弱体化。もしくは失脚までも視野に入れているのかもしれない。それくらいの効果はある」
「なるほど。カーティス様を通して依頼されるほど、大事にされていますからね。十分あり得そうです」
「いや、これは……」
突然、言葉を詰まらせるカーティス様。それを不思議そうに眺めていると、一つ咳払いをされた。
「と、ともかく、犯罪に巻き込まれている可能性が大いにある、ということだ」
「……そうですね。女性をわざわざ誘っておいて、放置するとは思えませんし。そのような扱いを受けると分かっていて、のこのことついて行くのは、いくらなんでも考え辛いです」
ドリス王女はお世辞にも賢いとは言い難い。が、仮にも王族だ。無礼な扱いを受けてまで、シュッセル公子と行動を共にするだろうか。
「だが、三つ目の可能性だった場合は否定できない」
「財布、政治……。残る一つは何ですか?」
「……好意だ」
「……好……意?」
つまり、シュッセル公子が好きだから、どんな扱いを受けても構わないと?
「それだけで、ついて行けますか?」
「ルフィナ嬢はできないと?」
「私は……そこまで誰かに好意を抱いたことがないので……」
声が小さくなるのと同時に、私の頭も下がっていく。カーティス様を直視できなかったのだ。
すると、後ろからガタンと音がして、思わず肩が跳ねる。
頭上に感じる気配に、そっと目を開けた。テーブルの上にある影が重なって、色が濃くなる。
けれど、それはカーティス様の影ではなかったらしい。
「ジルケ……」
「え?」
別の名を呼ぶ声に、私は顔を上げた。だってそれは、女性の名前だったからだ。