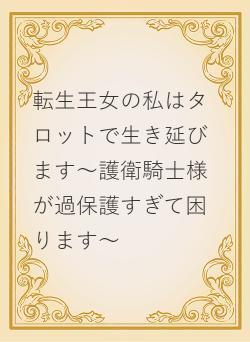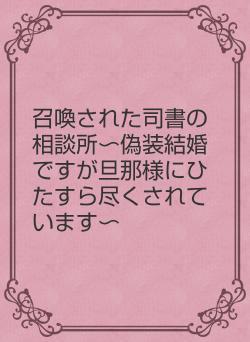そうして、あっという間に仮面舞踏会の日がやってきた――……。
といいたいところだが、その前にやることがある。
そう打ち合わせだ。勿論、相手はカーティス様。
情報の共有は白猫を通してでもできる。が、さすがにそれだけで、本番を迎えるのは無謀だということくらい、私も理解している。だから仮面舞踏会の二日前に当たる今日、会うことになったのだ。
場所はグルーバー侯爵邸……ではなく、首都にあるカフェ。
理由は、社交の場で突然、エスコートをすると、変に勘繰られてしまうからというもの。その前に二人でいるところを周りに見せてはどうだろう、かと提案されたのだ。
なるほど、一理ある、とその時は納得したのだけれど……。
「あ、あの……やはりこのような場所で、話す話題ではないと思うのですが」
周りにいる同世代の女性たちの視線が痛い……。
カーティス様は、気にも止めない様子だった。
確かに見せつけるのが目的だけど、色々おかしくない!?
まずはこのカフェへ来るまでの道のりだ。
舞踏会でのエスコートの練習だと言われて、カーティス様の腕を組むように要求され。
今度は、ドレスのお礼と共に、アクセサリーを身につけられない事情を話すと、突然、宝石店に連れて行かれ、ブローチをプレゼントされてしまったのだ。
そ、そんなつもりで言ったのではありません!
「いや、却ってこういう場所の方が、怪しまれない」
「そういうものですか」
一応、同意してみたものの、内心は驚いていた。
何せ、カーティス様がこんなにも話の通じない人だとは思わなかったからだ。
それとも、私が一般世間を知らないだけ? これが常識なの?
「ルフィナ嬢」
「は、はい。何でしょう」
「こういう場所は嫌か?」
は?
「いえ、そんなことはないです」
むしろ、嬉しかった。こういうお洒落なカフェには憧れていたから。
入店を断られたことはないけれど、自然と私が入ってはいけないような気がして、なかなか足が向かなかったのだ。
「ただ場違いといいますか。私が入って良かったのかと、思っただけなんです」
「何故だ? この店の雰囲気が合わないのなら仕方がないが」
「この店“の”、ではなく、“に”です。その、私はあそこにいる令嬢たちとは、違いますから」
何が? と首を傾げるカーティス様を見て、私は俯いた。
どうして、今日は話が噛み合わないんだろう、と疑念が次から次へと浮かんでくる。
お仕事の話をしていないから? そういう話ではないと、一般の人と会話ができないの? 私が猫憑きだから……。
「なるほど。確かに違うな」
カーティス様の言葉に、私は体に力を入れた。
そうでないと、ビクッと跳ねてしまいそうだったからだ。
「俺にはルフィナ嬢が一番……可愛く見える」
「え?」
「いや、綺麗と言うべきか……」
予想外の言葉。言い換えられた言葉に、どう返事をしていいのか分からず、私はそっと顔を上げた。
するとそこには、片手で口元を隠すカーティス様の姿があった。私以上に照れている。
それなら、言わなければいいのに、と思わず笑みが零れた。
「すまない。俺もこういう場は慣れていないんだ」
「ふふふ。そのようですね。ならば、何故このような場所を?」
改めて尋ねてみた。
「ここなら、ルフィナ嬢も気兼ねしないで済むと思ったんだ。こないだは……初対面ということもあって、緊張していたようだったからな」
「あれは……その……」
違うんです、と言おうとしたが、声に出すのが憚られた。
何故なら、理由が『忠犬』
犬でもない相手に対して、苦手意識を勝手にした、なんて知られたら、顔から火が出てしまうほど恥ずかしい。
しかも、ここはカフェ。グルーバー侯爵邸ではない。失態を犯せば、カーティス様にまで迷惑がかかってしまう。
いや、すでに失礼を欠いている状態だ。
どう繕っても、無駄な行為にも取れた。
そんな私の悩んでいる姿に、カーティス様は肯定と捉えたのか、話を進めてくれた。
「大丈夫だ。慣れない場所は俺も緊張する。そんな俺を見ていれば、多少はしなくなるだろう。ほら、緊張している人間が近くにいると、逆に緊張しなくなる、という話があるくらいだ」
「迷信ですが、私も聞いたことがあります。確か、自分の代わりに緊張してくれているように見えるから、という理由でしたっけ」
「理屈はよく分からないが、そうらしいな」
カーティス様の微笑みに、私もつられて笑った。
あぁ、その通りかもしれない。今の私は、誰がどう見ても緊張しているようには見えないだろう。
カーティス様の心遣いに感謝をしながら、話を切り出した。
「さすがは近衛騎士団長様ですね。王子殿下だけではなく、騎士の方々から信頼されているだけのことはあります。が、私に護衛はいりません。街中でしたら、猫たちが目を光らせてくれますから」
「っ! やはり気づいていたか」
「勿論です。街を歩いている時など違和感はないので、パトロールのついでだと思うでしょう。けれど、このカフェにまで騎士の方々が入られているのは、明らかに不自然ですから」
傍にいなくても私とピナは常に繋がっている。
故に先日、あのような惨事が起きたのだ。
そもそも伯爵令嬢の私が、お供も連れずにモディカ公園に行ったのがいい証拠だ。
街中にいる猫たちが、私の周りをうろつく不審者を教えてくれる。
変な動きを見せれば、集団で襲う……らしい。
逆に危険な目に遭いそうなので、心配だけど。どうやらそこら辺の匙加減はピナがしているのか、そういう事例はない。
「ルフィナ嬢に隠し事はできないようだな。実は今日の打ち合わせは、事前にルフィナ嬢のことを部下たちに認識させるのも、目的の一つだったんだ」
「あっ、そうですね。謂わば私も、皆さんと一緒に調査をする身。仲間……になるわけですから」
言い得て妙だが、少しだけ嬉しくなった。
猫たち以外の仲間……。それも人間の……。
「本来なら、きちんと席を設けて紹介するべきなのだろうが、それではルフィナ嬢が困ると思って、このような形にした。が、逆に不審がられてしまったようだな」
「いえいえ。そういう事情なら仕方がありませんわ。確かに、騎士の方々を目の前にしたら、今以上に緊張してしまいそうですから」
想像しただけで、身震いしそうだった。
代わりに猫たちがきちんと並んで、自己紹介をしてくれたら、と勝手に想像する。うん、これは可愛い。
「まぁ、理由はそれだけではないんだが……」
「何か言いまして?」
「いや、何でもない」
物思いに耽っていて、カーティス様の言葉を聞き逃してしまった。が、カーティス様は、手を振って苦笑いを見せただけ。
失礼を欠いたわけではないらしいが、少しだけ気になった。
といいたいところだが、その前にやることがある。
そう打ち合わせだ。勿論、相手はカーティス様。
情報の共有は白猫を通してでもできる。が、さすがにそれだけで、本番を迎えるのは無謀だということくらい、私も理解している。だから仮面舞踏会の二日前に当たる今日、会うことになったのだ。
場所はグルーバー侯爵邸……ではなく、首都にあるカフェ。
理由は、社交の場で突然、エスコートをすると、変に勘繰られてしまうからというもの。その前に二人でいるところを周りに見せてはどうだろう、かと提案されたのだ。
なるほど、一理ある、とその時は納得したのだけれど……。
「あ、あの……やはりこのような場所で、話す話題ではないと思うのですが」
周りにいる同世代の女性たちの視線が痛い……。
カーティス様は、気にも止めない様子だった。
確かに見せつけるのが目的だけど、色々おかしくない!?
まずはこのカフェへ来るまでの道のりだ。
舞踏会でのエスコートの練習だと言われて、カーティス様の腕を組むように要求され。
今度は、ドレスのお礼と共に、アクセサリーを身につけられない事情を話すと、突然、宝石店に連れて行かれ、ブローチをプレゼントされてしまったのだ。
そ、そんなつもりで言ったのではありません!
「いや、却ってこういう場所の方が、怪しまれない」
「そういうものですか」
一応、同意してみたものの、内心は驚いていた。
何せ、カーティス様がこんなにも話の通じない人だとは思わなかったからだ。
それとも、私が一般世間を知らないだけ? これが常識なの?
「ルフィナ嬢」
「は、はい。何でしょう」
「こういう場所は嫌か?」
は?
「いえ、そんなことはないです」
むしろ、嬉しかった。こういうお洒落なカフェには憧れていたから。
入店を断られたことはないけれど、自然と私が入ってはいけないような気がして、なかなか足が向かなかったのだ。
「ただ場違いといいますか。私が入って良かったのかと、思っただけなんです」
「何故だ? この店の雰囲気が合わないのなら仕方がないが」
「この店“の”、ではなく、“に”です。その、私はあそこにいる令嬢たちとは、違いますから」
何が? と首を傾げるカーティス様を見て、私は俯いた。
どうして、今日は話が噛み合わないんだろう、と疑念が次から次へと浮かんでくる。
お仕事の話をしていないから? そういう話ではないと、一般の人と会話ができないの? 私が猫憑きだから……。
「なるほど。確かに違うな」
カーティス様の言葉に、私は体に力を入れた。
そうでないと、ビクッと跳ねてしまいそうだったからだ。
「俺にはルフィナ嬢が一番……可愛く見える」
「え?」
「いや、綺麗と言うべきか……」
予想外の言葉。言い換えられた言葉に、どう返事をしていいのか分からず、私はそっと顔を上げた。
するとそこには、片手で口元を隠すカーティス様の姿があった。私以上に照れている。
それなら、言わなければいいのに、と思わず笑みが零れた。
「すまない。俺もこういう場は慣れていないんだ」
「ふふふ。そのようですね。ならば、何故このような場所を?」
改めて尋ねてみた。
「ここなら、ルフィナ嬢も気兼ねしないで済むと思ったんだ。こないだは……初対面ということもあって、緊張していたようだったからな」
「あれは……その……」
違うんです、と言おうとしたが、声に出すのが憚られた。
何故なら、理由が『忠犬』
犬でもない相手に対して、苦手意識を勝手にした、なんて知られたら、顔から火が出てしまうほど恥ずかしい。
しかも、ここはカフェ。グルーバー侯爵邸ではない。失態を犯せば、カーティス様にまで迷惑がかかってしまう。
いや、すでに失礼を欠いている状態だ。
どう繕っても、無駄な行為にも取れた。
そんな私の悩んでいる姿に、カーティス様は肯定と捉えたのか、話を進めてくれた。
「大丈夫だ。慣れない場所は俺も緊張する。そんな俺を見ていれば、多少はしなくなるだろう。ほら、緊張している人間が近くにいると、逆に緊張しなくなる、という話があるくらいだ」
「迷信ですが、私も聞いたことがあります。確か、自分の代わりに緊張してくれているように見えるから、という理由でしたっけ」
「理屈はよく分からないが、そうらしいな」
カーティス様の微笑みに、私もつられて笑った。
あぁ、その通りかもしれない。今の私は、誰がどう見ても緊張しているようには見えないだろう。
カーティス様の心遣いに感謝をしながら、話を切り出した。
「さすがは近衛騎士団長様ですね。王子殿下だけではなく、騎士の方々から信頼されているだけのことはあります。が、私に護衛はいりません。街中でしたら、猫たちが目を光らせてくれますから」
「っ! やはり気づいていたか」
「勿論です。街を歩いている時など違和感はないので、パトロールのついでだと思うでしょう。けれど、このカフェにまで騎士の方々が入られているのは、明らかに不自然ですから」
傍にいなくても私とピナは常に繋がっている。
故に先日、あのような惨事が起きたのだ。
そもそも伯爵令嬢の私が、お供も連れずにモディカ公園に行ったのがいい証拠だ。
街中にいる猫たちが、私の周りをうろつく不審者を教えてくれる。
変な動きを見せれば、集団で襲う……らしい。
逆に危険な目に遭いそうなので、心配だけど。どうやらそこら辺の匙加減はピナがしているのか、そういう事例はない。
「ルフィナ嬢に隠し事はできないようだな。実は今日の打ち合わせは、事前にルフィナ嬢のことを部下たちに認識させるのも、目的の一つだったんだ」
「あっ、そうですね。謂わば私も、皆さんと一緒に調査をする身。仲間……になるわけですから」
言い得て妙だが、少しだけ嬉しくなった。
猫たち以外の仲間……。それも人間の……。
「本来なら、きちんと席を設けて紹介するべきなのだろうが、それではルフィナ嬢が困ると思って、このような形にした。が、逆に不審がられてしまったようだな」
「いえいえ。そういう事情なら仕方がありませんわ。確かに、騎士の方々を目の前にしたら、今以上に緊張してしまいそうですから」
想像しただけで、身震いしそうだった。
代わりに猫たちがきちんと並んで、自己紹介をしてくれたら、と勝手に想像する。うん、これは可愛い。
「まぁ、理由はそれだけではないんだが……」
「何か言いまして?」
「いや、何でもない」
物思いに耽っていて、カーティス様の言葉を聞き逃してしまった。が、カーティス様は、手を振って苦笑いを見せただけ。
失礼を欠いたわけではないらしいが、少しだけ気になった。