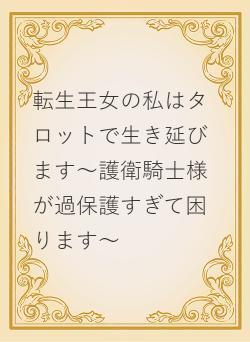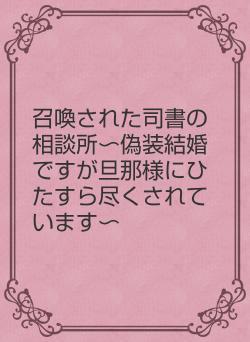今日の執務室は、やけに空気が重かった。
人工の光がそうさせているのか。もしくは私が勝手に、そう感じているだけなのか分からないが、これだけは言える。
目の前にいるお母様が、この重苦しい空気を作っているのだと。
眼鏡の奥で光る緑色の瞳が怖い……。
「報告が遅くなり、申し訳ありませんでした」
私は九十度に頭を下げた。
「モディカ公園での仕事は、今回が始めてだったか?」
「いいえ」
「ならば、やるべきことは分かっていたはずだ。それなのに、この体たらく、どうしてくれようか」
机を叩いてもいないのに、私の体がビクッと跳ねた。
「本来なら処罰を与えたいところだが、ピナがあの様子ではな。仕方があるまい。今回は不問としよう」
「それはお母様が我が家のルールを破ったからですか?」
不問ということは、クラリッサのように、私とピナの間に何かあったのか、調べたのだろう。
お母様憑きの猫、黒猫のシーラを使って。
考えてみると、帰宅してから呼び出されるまで、だいぶ時間が空いていた。私がいうのもなんだけど、クラリッサが来るよりも先に、呼び出されてもおかしくはなかったのだ。
少しだけ顔を上げると、お母様は図星なのか、バツが悪そうに咳払いをした。
それを合図に私は上半身を起こす。
「ピナがやって来たのよ。『ルフィナに怒られた~』ってね」
執務机の上に、黒猫が突然現れた。大きなぬいぐるみのようなピナとは違い、スラッとした置物のようなシーラ。
歩く姿すら、優雅である。
「騒ぎ立てるところはそっくりだな」
「そんなことは――……」
「あるだろう。ドタバタと廊下を走って」
否定するのは難しかった。ここへは走ってきたのだから。
念のため、執務室に着く前に息を整えたというのに、それもバレているとは……。
いや、帰宅直後のことを言っているのだろうか。走って自室に向かったから。
「以後、気をつけます」
「それで、依頼はどうした。断ったのか?」
「いえ、引き受けることにしました」
ほぉ、とお母様は机に肘をついた。
「あれだけ意気込んでおいてか」
「はい。内容が内容だけに、引き受けるのが得策だと思いまして」
「聞こうか」
「仮面舞踏会への潜入調査を依頼されました。ドリス王女殿下がシュッセル公子と共に、頻繁に行かれているそうです」
お母様は眉一つ動かさなかったが、『シュッセル』という言葉にシーラが尻尾を揺らした。
「シュッセル公子は確か、ドリス王女の婚約者候補だったか」
「はい。そのため、周りの者たちも口が出せないようで、ヴェルナー殿下のところにまで苦情が来ている、とのことです」
「なるほど。それでグルーバー侯爵が……。最近猫たちが、シュッセル公爵の派閥の家門に出入りしている理由も、これだったのか」
お茶会や舞踏会が開催された場所には、猫がやってくる。おこぼれを貰うために。
だからこれらは調べなくても、自然と入ってくる情報だった。
「お母様はシュッセル公爵様が裏で糸を引いていると?」
「まぁ、相手が王女なら、いくらでも考えられる。息子が婚約者候補なら尚更だろう」
「そうですわね。王女殿下の輿入れは勿論のこと。王家に取り入る算段もできます」
未だ婚約者のいないヴェルナー殿下に、息のかかった令嬢を送り込むことだって可能だ。
野心家ならば、他にもまだ企んでいてもおかしくはない。
「加えて王女は御し易い。ちょうどいい駒になる、と公爵が思っても不思議ではあるまい」
「つまり、ヴェルナー殿下の失脚を狙っていると?」
「否めんな。だからこそ、グルーバー侯爵を使って、我が家にコンタクトしてきたのではないのか?」
そう言われるとそんな気もするけど……。
「ならば、別に我が家でなくてもいいのでは?」
「引き受けたのはお前だろう。それに依頼は潜入調査であって、シュッセル公爵家を探るわけではない」
「あっ、そうでした。申し訳ありません」
先を読み過ぎて、肝心の依頼内容を見落とすところだった。
「その潜入調査だが、仮面舞踏会だったか」
「はい。ドレスなどの支度は問題ありません。そちらは用意していただいたので」
まだ中身は見ていないが、箱の大きさと数で、一式揃っているように思えた。そう、ドレスだけでなく髪飾りから靴までも……。
「お母様はご存知だったのですか? だから私に行けと仰ったんですよね」
「……普通なら二、三日で音を上げるというのに、一週間だからな。少しだけ探らせてもらった。すると、騎士団長には似つかわしくない、宝石店やらブディックの店員が出入りしているという。しかも、若者向けだ。何も知らなければ、グルーバー侯爵にもようやく春が来たのかと思うだろうさ」
「……何だか怖くなってきました」
「今更、何を言う」
だって、恐いじゃないですか! 知り合いでも何でもない女性のドレスや装飾品を、事前に買い揃えるなんて。不気味でないのなら、何と言うんですか!
「とりあえず、明日試着して詰めればいいだろう」
「そうですね。クラリッサも楽しみにしていたので」
「あとは……」
「仮面舞踏会について調べさせてもらえませんか? 噂だけで、実体を知らないんです」
予備知識もない状態で飛び込むほど、愚かではない。
「そうだな。悪い噂がどの程度なのかも知っておく必要があるだろう」
「はい。カーティス様の方は、あまり情報がないようでしたので」
「騎士団長はヴェルナー殿下の直属の部下だ。いくら王族でも、王女は管轄外。侍女の協力があるからといっても所詮、王女からの話のみだ」
そう限度がある。しかし、我が家は違う。
「裏にシュッセル公爵がいると分かれば話は早い。派閥の家門に出入りしている、もしくは飼われている猫たちに探りを入れてみよう。点と点を合わせれば、何か分かるかもしれん」
「ということは、お母様とクラリッサに協力を求めてもいいんですね」
「それで危険が少しでも減るのなら、構わんよ。私もそこまでは鬼ではないのだから」
すると、机の上にいたシーラがふわりと浮いた。
「けれどその前に、私のお願いを聞いてくれる? アレを解決してからにしてほしいのよ」
「皆まで言わなくとも分かるな」
「……はい」
事前にクラリッサに話をしたせいか、気持ちが落ち着いたのだろう。
ピナのことを思い出しても、もう腹は立たなかった。
人工の光がそうさせているのか。もしくは私が勝手に、そう感じているだけなのか分からないが、これだけは言える。
目の前にいるお母様が、この重苦しい空気を作っているのだと。
眼鏡の奥で光る緑色の瞳が怖い……。
「報告が遅くなり、申し訳ありませんでした」
私は九十度に頭を下げた。
「モディカ公園での仕事は、今回が始めてだったか?」
「いいえ」
「ならば、やるべきことは分かっていたはずだ。それなのに、この体たらく、どうしてくれようか」
机を叩いてもいないのに、私の体がビクッと跳ねた。
「本来なら処罰を与えたいところだが、ピナがあの様子ではな。仕方があるまい。今回は不問としよう」
「それはお母様が我が家のルールを破ったからですか?」
不問ということは、クラリッサのように、私とピナの間に何かあったのか、調べたのだろう。
お母様憑きの猫、黒猫のシーラを使って。
考えてみると、帰宅してから呼び出されるまで、だいぶ時間が空いていた。私がいうのもなんだけど、クラリッサが来るよりも先に、呼び出されてもおかしくはなかったのだ。
少しだけ顔を上げると、お母様は図星なのか、バツが悪そうに咳払いをした。
それを合図に私は上半身を起こす。
「ピナがやって来たのよ。『ルフィナに怒られた~』ってね」
執務机の上に、黒猫が突然現れた。大きなぬいぐるみのようなピナとは違い、スラッとした置物のようなシーラ。
歩く姿すら、優雅である。
「騒ぎ立てるところはそっくりだな」
「そんなことは――……」
「あるだろう。ドタバタと廊下を走って」
否定するのは難しかった。ここへは走ってきたのだから。
念のため、執務室に着く前に息を整えたというのに、それもバレているとは……。
いや、帰宅直後のことを言っているのだろうか。走って自室に向かったから。
「以後、気をつけます」
「それで、依頼はどうした。断ったのか?」
「いえ、引き受けることにしました」
ほぉ、とお母様は机に肘をついた。
「あれだけ意気込んでおいてか」
「はい。内容が内容だけに、引き受けるのが得策だと思いまして」
「聞こうか」
「仮面舞踏会への潜入調査を依頼されました。ドリス王女殿下がシュッセル公子と共に、頻繁に行かれているそうです」
お母様は眉一つ動かさなかったが、『シュッセル』という言葉にシーラが尻尾を揺らした。
「シュッセル公子は確か、ドリス王女の婚約者候補だったか」
「はい。そのため、周りの者たちも口が出せないようで、ヴェルナー殿下のところにまで苦情が来ている、とのことです」
「なるほど。それでグルーバー侯爵が……。最近猫たちが、シュッセル公爵の派閥の家門に出入りしている理由も、これだったのか」
お茶会や舞踏会が開催された場所には、猫がやってくる。おこぼれを貰うために。
だからこれらは調べなくても、自然と入ってくる情報だった。
「お母様はシュッセル公爵様が裏で糸を引いていると?」
「まぁ、相手が王女なら、いくらでも考えられる。息子が婚約者候補なら尚更だろう」
「そうですわね。王女殿下の輿入れは勿論のこと。王家に取り入る算段もできます」
未だ婚約者のいないヴェルナー殿下に、息のかかった令嬢を送り込むことだって可能だ。
野心家ならば、他にもまだ企んでいてもおかしくはない。
「加えて王女は御し易い。ちょうどいい駒になる、と公爵が思っても不思議ではあるまい」
「つまり、ヴェルナー殿下の失脚を狙っていると?」
「否めんな。だからこそ、グルーバー侯爵を使って、我が家にコンタクトしてきたのではないのか?」
そう言われるとそんな気もするけど……。
「ならば、別に我が家でなくてもいいのでは?」
「引き受けたのはお前だろう。それに依頼は潜入調査であって、シュッセル公爵家を探るわけではない」
「あっ、そうでした。申し訳ありません」
先を読み過ぎて、肝心の依頼内容を見落とすところだった。
「その潜入調査だが、仮面舞踏会だったか」
「はい。ドレスなどの支度は問題ありません。そちらは用意していただいたので」
まだ中身は見ていないが、箱の大きさと数で、一式揃っているように思えた。そう、ドレスだけでなく髪飾りから靴までも……。
「お母様はご存知だったのですか? だから私に行けと仰ったんですよね」
「……普通なら二、三日で音を上げるというのに、一週間だからな。少しだけ探らせてもらった。すると、騎士団長には似つかわしくない、宝石店やらブディックの店員が出入りしているという。しかも、若者向けだ。何も知らなければ、グルーバー侯爵にもようやく春が来たのかと思うだろうさ」
「……何だか怖くなってきました」
「今更、何を言う」
だって、恐いじゃないですか! 知り合いでも何でもない女性のドレスや装飾品を、事前に買い揃えるなんて。不気味でないのなら、何と言うんですか!
「とりあえず、明日試着して詰めればいいだろう」
「そうですね。クラリッサも楽しみにしていたので」
「あとは……」
「仮面舞踏会について調べさせてもらえませんか? 噂だけで、実体を知らないんです」
予備知識もない状態で飛び込むほど、愚かではない。
「そうだな。悪い噂がどの程度なのかも知っておく必要があるだろう」
「はい。カーティス様の方は、あまり情報がないようでしたので」
「騎士団長はヴェルナー殿下の直属の部下だ。いくら王族でも、王女は管轄外。侍女の協力があるからといっても所詮、王女からの話のみだ」
そう限度がある。しかし、我が家は違う。
「裏にシュッセル公爵がいると分かれば話は早い。派閥の家門に出入りしている、もしくは飼われている猫たちに探りを入れてみよう。点と点を合わせれば、何か分かるかもしれん」
「ということは、お母様とクラリッサに協力を求めてもいいんですね」
「それで危険が少しでも減るのなら、構わんよ。私もそこまでは鬼ではないのだから」
すると、机の上にいたシーラがふわりと浮いた。
「けれどその前に、私のお願いを聞いてくれる? アレを解決してからにしてほしいのよ」
「皆まで言わなくとも分かるな」
「……はい」
事前にクラリッサに話をしたせいか、気持ちが落ち着いたのだろう。
ピナのことを思い出しても、もう腹は立たなかった。