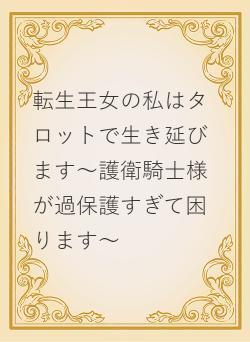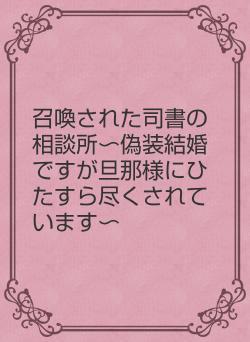そうして私は今、未だベッドの上にいた。
布団に包まり、音を遮断する。耳を塞いでみても、聞こえてくるピナの『声』
『ルフィナ~。どうしたんだよ~』
これは部屋の外からじゃない。直接、頭の中に話しかけてきているのだ。
『ねぇってば~。何でそんなに怒っているの~。入ってもいい~』
しばらくはピナの顔なんて見たくないほど、私は怒っているのに、その理由が分からないなんて。
さらに私の怒りに火をつけた。
手元にあった枕を、扉に向けて投げる。ボスンという鈍い音は、畏怖を与えるには程遠く、威嚇すらならない。
けれど理解してくれたようだった。『声』は止み、気配も遠退いていく。
目を瞑ると、後ろ髪を引かれるように、何度も振り返りながら離れていくピナの姿が見えた。
それほど深く繋がっている、私とピナ。
生まれた時から共にいる、家族以上の存在であり、楽しい時も辛い時も、共感してくれる。心を映す鏡のような存在でもあった。
今までの私は、代わりに喜怒哀楽を示してくれるピナを、心地よく感じていた。
しかし、今回のように私の感情を先走るのは許せない。勝手に“お相手”に選ぶことも!
ピナのことは好きだし、大事だけど、私たちは個々の存在だ。
別々の人格を有し、それぞれの世界を持った、独立した個体。
こんな風に干渉してほしくない。
けれど私の部屋には、未だピナの気配が薄っすらと満ちていた。マクギニス伯爵邸にいる限り、消えることのない気配。
そこに入り込んだザラっとした感触に、私は布団を捲った。
上半身を起こし、扉を見つめること数秒。待っていたとばかりに、扉がノックされた。
「お姉様。クラリッサです。開けてもよろしいですか?」
甘くて柔らかな声につられて、私は入室の許可を出した。
「まぁ、お姉様ったら。いくら自室でも、身だしなみは綺麗にしてください。お姉様は私の自慢なんですよ」
クラリッサは私の姿を見るなり、駆け足でベッドに近づいてきた。
揺れるオレンジ色の髪。華やな顔立ちを象徴するかのような緑色の瞳に見つめられると、堪らなかった。
まるで物語のヒロインのように可愛い、クラリッサ。
頭を撫でたくて手を伸ばすが、クラリッサの手が私の髪を掴む方が早かった。
おさげにしていた髪を解き、いつの間にか手にした櫛で、ゆっくりととかし始めたのだ。
「後ろを向いてもらえますか?」
暗にとかし辛いというクラリッサの言葉に、私は素直に従った。これではどちらが姉か分からない、と思うだろう。けれど私は、全く気にならなかった。
クラリッサが私を自慢というように、私もまたそんな妹が自慢だったからだ。余所へ出したくないほどに。
「本当に優しい子ね、クラリッサは。ピナに泣きつかれたのでしょう」
しかし、そんな姉と語らいに来たのではないことくらい、分からない私ではなかった。
「……はい。すみません。ルール違反だとは思ったんですが、私も気になったものですから」
「そうね。いくら家族でも、お互いトラブルに首を突っ込まない、というのが我が家のルールよ。特に憑いている猫との間で発生したトラブルなら、尚更。それを分かった上でなら、怒らないわ」
そう、マクギニス伯爵家には、他の家門にはない特殊なルールがある。
猫と人間の間で起こった出来事は、双方で解決するべし!
これは、他者が介入して、大きな騒動に発展させないための処置だった。
「良かった。私まで怒られたらどうしようと思っていたんです」
「まさかっ! 私がクラリッサを怒るなんてあり得ないわ!」
「でしたら、聞かせてくださいませ。一体、ピナは何をしたんですの?」
「それ……は……」
お願い。そんな目で見つめないで、と私はクラリッサから目を背けた。
しかし、クラリッサも手を緩めない。
「さっき馬車で送ってくださった方と関係があるんですか?」
「み、見ていたの?」
「いいえ。メイドたちが騒いでいるのを聞いたんです。ちょっと怖そうな殿方という話から、スラッとして格好いい、とも。お姉様、真相はどっちなんですか!」
良かった。ピナの頼みというより、メイドたちの話が気になったのね。さすが私の可愛いクラリッサだわ。
頭を撫でた途端、頬を膨らませたその顔も可愛い。
「お姉様!」
「ごめんなさい。あの方はカーティス・グルーバー侯爵様よ」
「えっ、もしかして、忠犬と言われている、近衛騎士団長様ですか!?」
クラリッサの驚く顔を見て、思わず昨日の自分を思い出した。
きっと、犬が我が家に来たという衝撃で、頭がいっぱいになっていることだろう。カーティス様を知った今の私と違って。
そんなところも可愛く思いながら、私はクラリッサに一連の出来事を話した。
布団に包まり、音を遮断する。耳を塞いでみても、聞こえてくるピナの『声』
『ルフィナ~。どうしたんだよ~』
これは部屋の外からじゃない。直接、頭の中に話しかけてきているのだ。
『ねぇってば~。何でそんなに怒っているの~。入ってもいい~』
しばらくはピナの顔なんて見たくないほど、私は怒っているのに、その理由が分からないなんて。
さらに私の怒りに火をつけた。
手元にあった枕を、扉に向けて投げる。ボスンという鈍い音は、畏怖を与えるには程遠く、威嚇すらならない。
けれど理解してくれたようだった。『声』は止み、気配も遠退いていく。
目を瞑ると、後ろ髪を引かれるように、何度も振り返りながら離れていくピナの姿が見えた。
それほど深く繋がっている、私とピナ。
生まれた時から共にいる、家族以上の存在であり、楽しい時も辛い時も、共感してくれる。心を映す鏡のような存在でもあった。
今までの私は、代わりに喜怒哀楽を示してくれるピナを、心地よく感じていた。
しかし、今回のように私の感情を先走るのは許せない。勝手に“お相手”に選ぶことも!
ピナのことは好きだし、大事だけど、私たちは個々の存在だ。
別々の人格を有し、それぞれの世界を持った、独立した個体。
こんな風に干渉してほしくない。
けれど私の部屋には、未だピナの気配が薄っすらと満ちていた。マクギニス伯爵邸にいる限り、消えることのない気配。
そこに入り込んだザラっとした感触に、私は布団を捲った。
上半身を起こし、扉を見つめること数秒。待っていたとばかりに、扉がノックされた。
「お姉様。クラリッサです。開けてもよろしいですか?」
甘くて柔らかな声につられて、私は入室の許可を出した。
「まぁ、お姉様ったら。いくら自室でも、身だしなみは綺麗にしてください。お姉様は私の自慢なんですよ」
クラリッサは私の姿を見るなり、駆け足でベッドに近づいてきた。
揺れるオレンジ色の髪。華やな顔立ちを象徴するかのような緑色の瞳に見つめられると、堪らなかった。
まるで物語のヒロインのように可愛い、クラリッサ。
頭を撫でたくて手を伸ばすが、クラリッサの手が私の髪を掴む方が早かった。
おさげにしていた髪を解き、いつの間にか手にした櫛で、ゆっくりととかし始めたのだ。
「後ろを向いてもらえますか?」
暗にとかし辛いというクラリッサの言葉に、私は素直に従った。これではどちらが姉か分からない、と思うだろう。けれど私は、全く気にならなかった。
クラリッサが私を自慢というように、私もまたそんな妹が自慢だったからだ。余所へ出したくないほどに。
「本当に優しい子ね、クラリッサは。ピナに泣きつかれたのでしょう」
しかし、そんな姉と語らいに来たのではないことくらい、分からない私ではなかった。
「……はい。すみません。ルール違反だとは思ったんですが、私も気になったものですから」
「そうね。いくら家族でも、お互いトラブルに首を突っ込まない、というのが我が家のルールよ。特に憑いている猫との間で発生したトラブルなら、尚更。それを分かった上でなら、怒らないわ」
そう、マクギニス伯爵家には、他の家門にはない特殊なルールがある。
猫と人間の間で起こった出来事は、双方で解決するべし!
これは、他者が介入して、大きな騒動に発展させないための処置だった。
「良かった。私まで怒られたらどうしようと思っていたんです」
「まさかっ! 私がクラリッサを怒るなんてあり得ないわ!」
「でしたら、聞かせてくださいませ。一体、ピナは何をしたんですの?」
「それ……は……」
お願い。そんな目で見つめないで、と私はクラリッサから目を背けた。
しかし、クラリッサも手を緩めない。
「さっき馬車で送ってくださった方と関係があるんですか?」
「み、見ていたの?」
「いいえ。メイドたちが騒いでいるのを聞いたんです。ちょっと怖そうな殿方という話から、スラッとして格好いい、とも。お姉様、真相はどっちなんですか!」
良かった。ピナの頼みというより、メイドたちの話が気になったのね。さすが私の可愛いクラリッサだわ。
頭を撫でた途端、頬を膨らませたその顔も可愛い。
「お姉様!」
「ごめんなさい。あの方はカーティス・グルーバー侯爵様よ」
「えっ、もしかして、忠犬と言われている、近衛騎士団長様ですか!?」
クラリッサの驚く顔を見て、思わず昨日の自分を思い出した。
きっと、犬が我が家に来たという衝撃で、頭がいっぱいになっていることだろう。カーティス様を知った今の私と違って。
そんなところも可愛く思いながら、私はクラリッサに一連の出来事を話した。