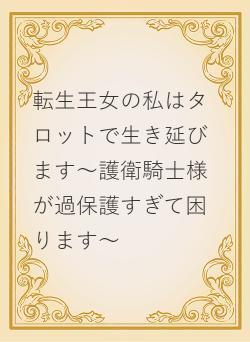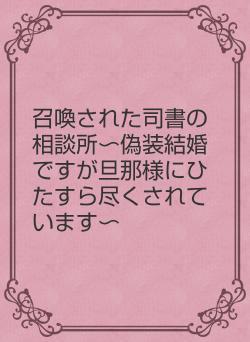「ピナなんか、大っ嫌い!」
カーティス様がお帰りになると、私はそのまま自室に直行して、ベッドにダイブした。
部屋の外からピナの声が聞こえてきたが、答えるつもりはない。布団を頭まで被って無視を決め込んだ。
だって、カーティス様の前に現れるんだもの。それだけだって許し難いのに、あんなことまで言うなんて!
本当にもう知らない! ピナなんて!
***
遡ること数分前。
突然現れたピナに、カーティス様は驚いていた。
無理もない。私たちマクギニス伯爵家の女は、自分たちに憑いている猫を、他の者に見せるようなことはしないからだ。
嫌がられたり、差別の材料にされたりと、苦い経験の末に身につけた行為だった。
人は自分と違う者を排除したがる。生まれや生き方、性格など十人十色だというのに、なぜか同じじゃないと納得しない。理解しない生き物だ。
排除して排除して、自分たちの王国を作り上げる。
そうやって、私は普通の令嬢たちと距離を取っていた。カーティス様もきっとそう。他の令嬢たちと同じ反応をするに違いない。
恐る恐る、顔を上げた。けれど、直視まではできなかった。
「えっと、君はもしかして……ルフィナ嬢の」
「そ~。ピナだよ~」
私は卒倒しかけた。カーティス様の反応ではなく、ピナに対して。
な、な、何で自己紹介しているのよー!
「さっきも言ったけど、あの子は連絡係~。話しかければ、僕を通してルフィナに繋がるよ~」
カーティス様の前で、ふよふよと浮きながら、尚も話しかけるピナ。
「何か合図のようなものはあるのだろうか」
ぬいぐるみのような大きな猫。それも半透明な浮遊体を見て、物怖じしないカーティス様。
「ないよ~。必要なら作る~?」
「いや、問題ない」
そんな二人のやり取りを見て、私は急に恥ずかしくなった。
カーティス様を、『猫憑き』という言葉だけで判断してきた者たちと、同列に扱ってしまったことに。
いや、そうじゃない。思い込みでそうだ、と決めつけた私自身に。
モディカ公園で出会ってから、カーティス様は偏見を持つような方ではない、と知ったばかりなのに。もう忘れてしまったなんて。
失礼にも程があるわ。
「それとは別に、一つ聞いてもいいだろうか」
「ん~。いいよ~。何~?」
そんな私の思いとは裏腹に、二人の会話は続いていた。
「俺には君が見えているんだが、そういう体質なのか、というのは考え辛くてな。だから君が見えるようにしてくれているのだろうか」
カーティス様の言葉にドキッとした。
そうだ。普段のピナは他の人には見えないはず。つまり……。
「正解~。でも、依頼人になったからじゃないよ~」
マズい……。
「ん? どういうことだ?」
「それはね~、認めたからだよ~」
「認めた……。つまり、もう猫たちに避けられない、ということか?」
そう言うことではないのです。けれど、そのまま誤解していてください。なんだか、ピナも誤解しているみたいなので……。
という私の想いは、ピナに届かなかったらしい。いや、無視された、と言った方が正しいのかもしれない。
「避けないよ~。そんなことをする奴がいたら、僕がお仕置きするからね~」
「いや、そこまでする必要はない。好き嫌いは自由にしていいのではないか?」
「ダ~メ~! 僕が認めたルフィナの相手なんだから~」
「相手? どういう、意味だ?」
良かった。ピナが言葉足らずで。
「エ、エスコートの相手です! 仮面舞踏会の。ピナは私を通して事情を知っているんです。だから、その相手」
「違うよ~」
「違わない!」
否定するピナに手を伸ばす。が、向こうも私の意図に気づいて、上へ逃げていく。
こんな時、精神が繋がっているのは不便だと実感する。それも一方的だから質が悪い。
私の想いや考えを汲み取っている、とピナは思っているようだが、都合の良いように解釈している場合もある。
今回がまさにそれだ。
普段、異性に心を開かない私が、珍しく褒めたものだから、勝手に“お相手”認定をしてしまったのだ。
それをカーティス様に知られるわけにはいかない。知られたら最後、恥ずかしくてお会いすることは、もうできないと思うから。
けれど、ピナは止まらなかった。私から逃げるように、カーティス様の背後に回ったのだ。
「ルフィナを裏切ったら許さない、という意味だよ~」
「ピナ!」
「なるほど。それなら大丈夫だ。俺はルフィナ嬢を裏切らない。誓ってもいい」
「っ!」
さすが忠犬……じゃなかった。ピナの言葉に、とんでもない返答をしないでください!
さらに誤解しちゃうじゃないですか!
もう知らない!
居た堪れなくなった私は、別れの挨拶をすることなく、逃げるように邸宅へと駆けて行った。
それほど余裕がなかったのだ。何もかもが。
カーティス様がお帰りになると、私はそのまま自室に直行して、ベッドにダイブした。
部屋の外からピナの声が聞こえてきたが、答えるつもりはない。布団を頭まで被って無視を決め込んだ。
だって、カーティス様の前に現れるんだもの。それだけだって許し難いのに、あんなことまで言うなんて!
本当にもう知らない! ピナなんて!
***
遡ること数分前。
突然現れたピナに、カーティス様は驚いていた。
無理もない。私たちマクギニス伯爵家の女は、自分たちに憑いている猫を、他の者に見せるようなことはしないからだ。
嫌がられたり、差別の材料にされたりと、苦い経験の末に身につけた行為だった。
人は自分と違う者を排除したがる。生まれや生き方、性格など十人十色だというのに、なぜか同じじゃないと納得しない。理解しない生き物だ。
排除して排除して、自分たちの王国を作り上げる。
そうやって、私は普通の令嬢たちと距離を取っていた。カーティス様もきっとそう。他の令嬢たちと同じ反応をするに違いない。
恐る恐る、顔を上げた。けれど、直視まではできなかった。
「えっと、君はもしかして……ルフィナ嬢の」
「そ~。ピナだよ~」
私は卒倒しかけた。カーティス様の反応ではなく、ピナに対して。
な、な、何で自己紹介しているのよー!
「さっきも言ったけど、あの子は連絡係~。話しかければ、僕を通してルフィナに繋がるよ~」
カーティス様の前で、ふよふよと浮きながら、尚も話しかけるピナ。
「何か合図のようなものはあるのだろうか」
ぬいぐるみのような大きな猫。それも半透明な浮遊体を見て、物怖じしないカーティス様。
「ないよ~。必要なら作る~?」
「いや、問題ない」
そんな二人のやり取りを見て、私は急に恥ずかしくなった。
カーティス様を、『猫憑き』という言葉だけで判断してきた者たちと、同列に扱ってしまったことに。
いや、そうじゃない。思い込みでそうだ、と決めつけた私自身に。
モディカ公園で出会ってから、カーティス様は偏見を持つような方ではない、と知ったばかりなのに。もう忘れてしまったなんて。
失礼にも程があるわ。
「それとは別に、一つ聞いてもいいだろうか」
「ん~。いいよ~。何~?」
そんな私の思いとは裏腹に、二人の会話は続いていた。
「俺には君が見えているんだが、そういう体質なのか、というのは考え辛くてな。だから君が見えるようにしてくれているのだろうか」
カーティス様の言葉にドキッとした。
そうだ。普段のピナは他の人には見えないはず。つまり……。
「正解~。でも、依頼人になったからじゃないよ~」
マズい……。
「ん? どういうことだ?」
「それはね~、認めたからだよ~」
「認めた……。つまり、もう猫たちに避けられない、ということか?」
そう言うことではないのです。けれど、そのまま誤解していてください。なんだか、ピナも誤解しているみたいなので……。
という私の想いは、ピナに届かなかったらしい。いや、無視された、と言った方が正しいのかもしれない。
「避けないよ~。そんなことをする奴がいたら、僕がお仕置きするからね~」
「いや、そこまでする必要はない。好き嫌いは自由にしていいのではないか?」
「ダ~メ~! 僕が認めたルフィナの相手なんだから~」
「相手? どういう、意味だ?」
良かった。ピナが言葉足らずで。
「エ、エスコートの相手です! 仮面舞踏会の。ピナは私を通して事情を知っているんです。だから、その相手」
「違うよ~」
「違わない!」
否定するピナに手を伸ばす。が、向こうも私の意図に気づいて、上へ逃げていく。
こんな時、精神が繋がっているのは不便だと実感する。それも一方的だから質が悪い。
私の想いや考えを汲み取っている、とピナは思っているようだが、都合の良いように解釈している場合もある。
今回がまさにそれだ。
普段、異性に心を開かない私が、珍しく褒めたものだから、勝手に“お相手”認定をしてしまったのだ。
それをカーティス様に知られるわけにはいかない。知られたら最後、恥ずかしくてお会いすることは、もうできないと思うから。
けれど、ピナは止まらなかった。私から逃げるように、カーティス様の背後に回ったのだ。
「ルフィナを裏切ったら許さない、という意味だよ~」
「ピナ!」
「なるほど。それなら大丈夫だ。俺はルフィナ嬢を裏切らない。誓ってもいい」
「っ!」
さすが忠犬……じゃなかった。ピナの言葉に、とんでもない返答をしないでください!
さらに誤解しちゃうじゃないですか!
もう知らない!
居た堪れなくなった私は、別れの挨拶をすることなく、逃げるように邸宅へと駆けて行った。
それほど余裕がなかったのだ。何もかもが。