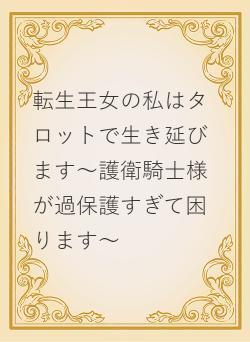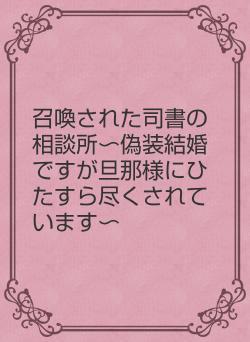「というわけなんだ」
我がグルーバー侯爵家の応接室で、普段は招かないような客人を前に、俺はドリス王女殿下のことを掻い摘んで説明した。
シュッセル公子に誘われて仮面舞踏会に行っていること。彼がドリス王女殿下の婚約者候補であること。
さらに、父親であるシュッセル公爵が、意図的にヴェルナーを忙しくさせて妨害している疑惑についても。
主に昨日、ヴェルナーと話したことを伝えた。さすがに目の前にいる女性、白猫を抱くマクギニス嬢に、すべてを打ち明けるわけにはいかない。
あくまでも、依頼に関することのみだ。
去年のことなど、ここで話せるわけがない。もっと、親しくなってから……いやいや、それでも話せない内容だ。
そもそも、親しくなれるのだろうか。依頼とはいえ、仮面舞踏会へ行くのを再三、断られているというのに。
なんとなくモディカ公園で見かけた猫たちの行動が、そのままマクギニス嬢の気持ちを表しているかのように思えた。
「そうだったんですか。てっきり、ドリス王女殿下の火遊びか、ヴェルナー殿下の過保護かと思ったんですが、事はそれだけではない、ということなんですね」
白猫を抱いたまま思案するマクギニス嬢の声に、俺は我に返った。
「……どうだろうな。ヴェルナー殿下もそれだけで済むのなら、大事にしたくないと仰っていた。騎士団も、シュッセル公子との逢瀬だけなら、出動させたくもない」
それが本当だった場合、笑い者になってしまうからだ。俺だけじゃなく、近衛騎士団全体が。
「それにシュッセル公爵も、ドリス王女殿下を迎え入れたいがため、過度に応援をしている可能性も否定できないんだ」
「息子想いじゃなくても、王女殿下の輿入れ先というのは魅力的ですものね」
それ故に、ドリス王女殿下の婚約者候補は多かった。
性格に難があるわけでもなく、可愛らしい姫だからだ。一つ欠点があるとするならば、幼い。この一言に尽きる。
年齢はすでに成人しているため、間違った言い方かもしれないが、ドリス王女殿下の醸し出す雰囲気、容姿、喋り方。良い意味で可愛らしく、悪い意味で幼稚だった。
「加えて扱い易い人物だ。ドリス王女殿下は」
「噂は予々聞いています。王女であるため構わないのでしょうが、政治に全く興味がない方だとか。お選びになるドレスも年齢に合わない……可愛らしいものを選ぶそうですね。あと、勉強したくないがために、お忍びで市街地に行かれるとも聞きました」
さ、さすがはマクギニス嬢。外部に伏せている情報まで知っているとは。
これは俺だから言うのだろうか。それとも無自覚で? それならば危険な行為だ。
「些細な我儘も、ドリス王女殿下の魅力の一つですが、過保護にお育てになった結果だと思います」
「反動だと言いたいのか」
「一生、籠の中で過ごすことは無理だと言いたいだけですわ。我がメゼモリックの王女は一人。他国へ嫁ぐか降嫁するか、二つに一つなのですから」
籠の中……。猫たちの目を通して、世の中を見ているからこその表現か。それとも、自由に歩き回る猫としての気持ちか。
「過保護な扱いを受けて良いことなど、何一つありませんわ。王女という身分であれば尚更です」
「だが、護衛を常につけている以上、行動は制限せざるを得ない」
貴族の令嬢でさえも侍女を伴うのだ。王女ともなれば……。
「私が過保護だと言ったのは、そういう意味ではありません。何が良くて何が悪いか、良い人か悪い人か。それを養う機会を潰してしまっているのが、良くないと言っているんです」
確かに、王城にはさまざまな人間が出入りする。中には、野心を持って近づいて来る者もいるだろう。
だからだろうか。ヴェルナーも時々、俺に聞いてくる。新たに大臣に就任した者の人相や印象を。それが自分と一致しているかどうかを確認しているように見えた。
まさか、ドリス王女殿下は人を見る目を養っておられないというのか。
「だから、良い社会勉強なのだから口を出すな、というのがマクギニス嬢の考えか」
「ヴェルナー殿下に申し上げるのなら、です。一介の伯爵令嬢たる私が、口を出していいことではないと思いますので」
「いや、俺から進言しておこう。恐らく、本人も気づいていない可能性もあるからな。俺は一人っ子だからか、ヴェルナー殿下の可愛がりようは、よく分からないんだ」
「まぁ、そうでしたか。妹は可愛いものですよ。私にもいますので」
その妹を思い浮かべたのか、マクギニス嬢は目を細めた。白猫もそれに合わせた仕草をする。
まるで自分がその眼差しを受けたような錯覚を抱き、返答に困ってしまった。
「ヴェルナー殿下のお気持ち、同じ妹を持つ者としてとても理解できます。今回の件、そういった事情があるのでしたら、引き受けさせていただきます」
一瞬、言葉を疑った。それは白猫も同じだったのか、マクギニス嬢の顔を見ていた。
「……こちらとしては有難いが、なぜだ。あれほど断っていたというのに」
ヴェルナーに同調したからといっても、そんな簡単に切り替えられるのか?
「そ、そうですね。驚かれるのも無理はありません。実はカーティス様の話を聞いて、思い出したんです。王城にいる猫たちのことを」
「猫?」
思わずマクギニス嬢が抱いている白猫に視線を向けた。白猫は「何の用だ」とでもいうように、俺を睨む。
ほんの少し、傷ついた顔に気づいたのか、マクギニス嬢は白猫の頭に手を乗せて、優しく宥めた。
「はい。ドリス王女殿下は猫たちに対して、良くしてくださいましたし、何より王城が混乱すると、猫たちも困ってしまいます。私としては、それが一番嫌なのですわ。あと、恩が返せないことも」
実にマクギニス嬢らしい返答に、顔をほころばせた。が、違う解釈をしたのか、さきほどの白猫のように、ムッとした表情をされてしまった。
「わ、笑わないで下さい。そもそも、先にこの話をしてくだされば、断るようなことはしなかったんですよ」
「すまない。ようやく接触ができたのと、時間がないのとで焦ってしまったのだ」
「っ! それについては、大変申し訳ありませんでした。猫たちの分も、お詫びいたします」
「いや、結果的に依頼を引き受けてくれたんだ。それで構わない」
引き受けてもらわなければ、マクギニス嬢との接点も、これで終わってしまう。
『別に、ドリスをネタに、マクギニス嬢とお近づきになりたい、なんて魂胆には気づいていないから、安心していいよ』
唐突に、ヴェルナーの言葉が脳裏に浮かんだ。
あの時は返答できなかったが、今だったら肯定の言葉を返していただろう。
俺は立ち上がって、マクギニス嬢に手を差し伸べる。
「逆にお礼として、伯爵邸まで馬車で送らせてもらえないだろうか」
「えっ! 大丈夫です。一人で帰れますわ」
「だが来週、迎えに行くのが最初では、周りが怪しいと思うのではないか。なら今日、送るくらいはさせてもらわないと」
「……そうですね。分かりました。お願いします」
苦渋の決断とばかりの返事をされ、落ち込みそうになった。
たった送るといった行為だけで、この押し問答。果たして、マクギニス嬢との距離を縮めることができるのだろうか。自信がないな。
我がグルーバー侯爵家の応接室で、普段は招かないような客人を前に、俺はドリス王女殿下のことを掻い摘んで説明した。
シュッセル公子に誘われて仮面舞踏会に行っていること。彼がドリス王女殿下の婚約者候補であること。
さらに、父親であるシュッセル公爵が、意図的にヴェルナーを忙しくさせて妨害している疑惑についても。
主に昨日、ヴェルナーと話したことを伝えた。さすがに目の前にいる女性、白猫を抱くマクギニス嬢に、すべてを打ち明けるわけにはいかない。
あくまでも、依頼に関することのみだ。
去年のことなど、ここで話せるわけがない。もっと、親しくなってから……いやいや、それでも話せない内容だ。
そもそも、親しくなれるのだろうか。依頼とはいえ、仮面舞踏会へ行くのを再三、断られているというのに。
なんとなくモディカ公園で見かけた猫たちの行動が、そのままマクギニス嬢の気持ちを表しているかのように思えた。
「そうだったんですか。てっきり、ドリス王女殿下の火遊びか、ヴェルナー殿下の過保護かと思ったんですが、事はそれだけではない、ということなんですね」
白猫を抱いたまま思案するマクギニス嬢の声に、俺は我に返った。
「……どうだろうな。ヴェルナー殿下もそれだけで済むのなら、大事にしたくないと仰っていた。騎士団も、シュッセル公子との逢瀬だけなら、出動させたくもない」
それが本当だった場合、笑い者になってしまうからだ。俺だけじゃなく、近衛騎士団全体が。
「それにシュッセル公爵も、ドリス王女殿下を迎え入れたいがため、過度に応援をしている可能性も否定できないんだ」
「息子想いじゃなくても、王女殿下の輿入れ先というのは魅力的ですものね」
それ故に、ドリス王女殿下の婚約者候補は多かった。
性格に難があるわけでもなく、可愛らしい姫だからだ。一つ欠点があるとするならば、幼い。この一言に尽きる。
年齢はすでに成人しているため、間違った言い方かもしれないが、ドリス王女殿下の醸し出す雰囲気、容姿、喋り方。良い意味で可愛らしく、悪い意味で幼稚だった。
「加えて扱い易い人物だ。ドリス王女殿下は」
「噂は予々聞いています。王女であるため構わないのでしょうが、政治に全く興味がない方だとか。お選びになるドレスも年齢に合わない……可愛らしいものを選ぶそうですね。あと、勉強したくないがために、お忍びで市街地に行かれるとも聞きました」
さ、さすがはマクギニス嬢。外部に伏せている情報まで知っているとは。
これは俺だから言うのだろうか。それとも無自覚で? それならば危険な行為だ。
「些細な我儘も、ドリス王女殿下の魅力の一つですが、過保護にお育てになった結果だと思います」
「反動だと言いたいのか」
「一生、籠の中で過ごすことは無理だと言いたいだけですわ。我がメゼモリックの王女は一人。他国へ嫁ぐか降嫁するか、二つに一つなのですから」
籠の中……。猫たちの目を通して、世の中を見ているからこその表現か。それとも、自由に歩き回る猫としての気持ちか。
「過保護な扱いを受けて良いことなど、何一つありませんわ。王女という身分であれば尚更です」
「だが、護衛を常につけている以上、行動は制限せざるを得ない」
貴族の令嬢でさえも侍女を伴うのだ。王女ともなれば……。
「私が過保護だと言ったのは、そういう意味ではありません。何が良くて何が悪いか、良い人か悪い人か。それを養う機会を潰してしまっているのが、良くないと言っているんです」
確かに、王城にはさまざまな人間が出入りする。中には、野心を持って近づいて来る者もいるだろう。
だからだろうか。ヴェルナーも時々、俺に聞いてくる。新たに大臣に就任した者の人相や印象を。それが自分と一致しているかどうかを確認しているように見えた。
まさか、ドリス王女殿下は人を見る目を養っておられないというのか。
「だから、良い社会勉強なのだから口を出すな、というのがマクギニス嬢の考えか」
「ヴェルナー殿下に申し上げるのなら、です。一介の伯爵令嬢たる私が、口を出していいことではないと思いますので」
「いや、俺から進言しておこう。恐らく、本人も気づいていない可能性もあるからな。俺は一人っ子だからか、ヴェルナー殿下の可愛がりようは、よく分からないんだ」
「まぁ、そうでしたか。妹は可愛いものですよ。私にもいますので」
その妹を思い浮かべたのか、マクギニス嬢は目を細めた。白猫もそれに合わせた仕草をする。
まるで自分がその眼差しを受けたような錯覚を抱き、返答に困ってしまった。
「ヴェルナー殿下のお気持ち、同じ妹を持つ者としてとても理解できます。今回の件、そういった事情があるのでしたら、引き受けさせていただきます」
一瞬、言葉を疑った。それは白猫も同じだったのか、マクギニス嬢の顔を見ていた。
「……こちらとしては有難いが、なぜだ。あれほど断っていたというのに」
ヴェルナーに同調したからといっても、そんな簡単に切り替えられるのか?
「そ、そうですね。驚かれるのも無理はありません。実はカーティス様の話を聞いて、思い出したんです。王城にいる猫たちのことを」
「猫?」
思わずマクギニス嬢が抱いている白猫に視線を向けた。白猫は「何の用だ」とでもいうように、俺を睨む。
ほんの少し、傷ついた顔に気づいたのか、マクギニス嬢は白猫の頭に手を乗せて、優しく宥めた。
「はい。ドリス王女殿下は猫たちに対して、良くしてくださいましたし、何より王城が混乱すると、猫たちも困ってしまいます。私としては、それが一番嫌なのですわ。あと、恩が返せないことも」
実にマクギニス嬢らしい返答に、顔をほころばせた。が、違う解釈をしたのか、さきほどの白猫のように、ムッとした表情をされてしまった。
「わ、笑わないで下さい。そもそも、先にこの話をしてくだされば、断るようなことはしなかったんですよ」
「すまない。ようやく接触ができたのと、時間がないのとで焦ってしまったのだ」
「っ! それについては、大変申し訳ありませんでした。猫たちの分も、お詫びいたします」
「いや、結果的に依頼を引き受けてくれたんだ。それで構わない」
引き受けてもらわなければ、マクギニス嬢との接点も、これで終わってしまう。
『別に、ドリスをネタに、マクギニス嬢とお近づきになりたい、なんて魂胆には気づいていないから、安心していいよ』
唐突に、ヴェルナーの言葉が脳裏に浮かんだ。
あの時は返答できなかったが、今だったら肯定の言葉を返していただろう。
俺は立ち上がって、マクギニス嬢に手を差し伸べる。
「逆にお礼として、伯爵邸まで馬車で送らせてもらえないだろうか」
「えっ! 大丈夫です。一人で帰れますわ」
「だが来週、迎えに行くのが最初では、周りが怪しいと思うのではないか。なら今日、送るくらいはさせてもらわないと」
「……そうですね。分かりました。お願いします」
苦渋の決断とばかりの返事をされ、落ち込みそうになった。
たった送るといった行為だけで、この押し問答。果たして、マクギニス嬢との距離を縮めることができるのだろうか。自信がないな。