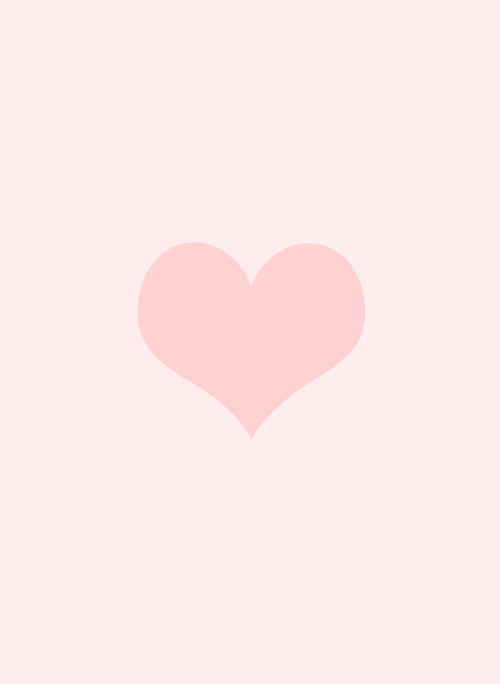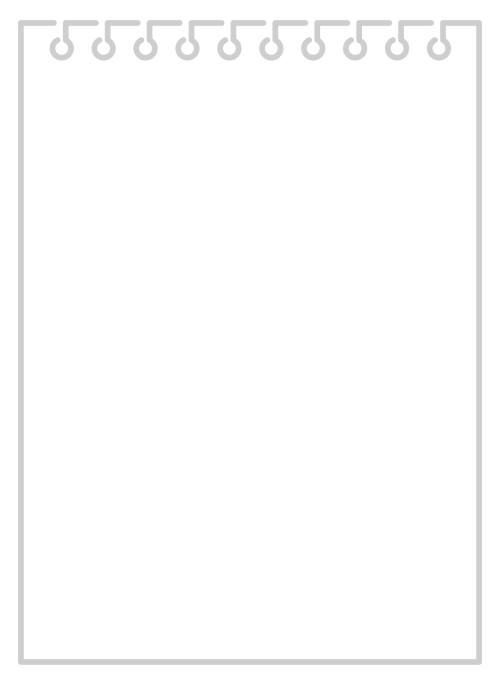* * *
年末に差し掛かろうとする12月。実家からいつ帰ってくるのかと連絡が来て、そういえば帰省の時期だったことを思い出す。そんなことを思いつつ、カウンターでポトフを咀嚼していた。今日は珍しく健人はいなかった。
「スケジュール帳とにらめっこなんて、珍しいですね。」
「行儀悪くてすみません!」
「ああ、いえいえ。年末ですしね、お忙しいのにお越しいただいてありがたい限りですよ。」
「ちょっと、実家に帰る時期を検討しなきゃいけなくて…。」
「そうですね、確かにそんな時期です。」
そういえばお店は年内のいつが最終営業日で、年明けはいつから再開だろうか。それは確認しておかなくては思い、綾乃は口を開いた。
「お店の年末年始はどのような感じですか?」
「そうですね…。僕もあの子も実家はないに等しいので、帰省というものはしないのですが。」
「…あの。」
「何でしょう?」
「…オーナーさんは、健人くんのお父様じゃないんですよね。」
「はい。…健人は湯本さんに、家族の話をしていませんか?」
「…私が、えっと…うーん…何て言ったらいいのかわからないので、今から話すことが支離滅裂だったら本当に申し訳ないんですけど…。」
「大丈夫ですよ、それで、何か気にかかることでもありますか?」
時折話すバイトの大学生とただの社会人という間柄で、首を突っ込んでいいのかわからなくて聞いてこなかったことがあった。
「…あの、健人くんは時々、なんというか…寂しそうに見えるときがあって。」
「はい。」
「誕生日、なんですけど。」
「はい。」
「…誕生日を、あまり祝ってもらったことがないのかなって。でも、だとしたら、というか、誕生日を祝ってもらえないような家庭環境にあって、あんなに穏やかに優しく育つものなのかな…とか、あの、ちょっと大学では少しだけ心理とか教育をかじっていたもので…余計な詮索だなとは思うんですけど。」
綾乃がそこまで言うと、オーナーはいつもよりも目を細めて微笑んだ。
「祝ってもらっていましたよ、ずっと。優しい両親に育てられましたから。ただ、高校1年生までですが。」
重たい話なのに、柔らかい表情を浮かべるオーナーに、思わず表情を歪めてしまったのは綾乃のほうだった。
年末に差し掛かろうとする12月。実家からいつ帰ってくるのかと連絡が来て、そういえば帰省の時期だったことを思い出す。そんなことを思いつつ、カウンターでポトフを咀嚼していた。今日は珍しく健人はいなかった。
「スケジュール帳とにらめっこなんて、珍しいですね。」
「行儀悪くてすみません!」
「ああ、いえいえ。年末ですしね、お忙しいのにお越しいただいてありがたい限りですよ。」
「ちょっと、実家に帰る時期を検討しなきゃいけなくて…。」
「そうですね、確かにそんな時期です。」
そういえばお店は年内のいつが最終営業日で、年明けはいつから再開だろうか。それは確認しておかなくては思い、綾乃は口を開いた。
「お店の年末年始はどのような感じですか?」
「そうですね…。僕もあの子も実家はないに等しいので、帰省というものはしないのですが。」
「…あの。」
「何でしょう?」
「…オーナーさんは、健人くんのお父様じゃないんですよね。」
「はい。…健人は湯本さんに、家族の話をしていませんか?」
「…私が、えっと…うーん…何て言ったらいいのかわからないので、今から話すことが支離滅裂だったら本当に申し訳ないんですけど…。」
「大丈夫ですよ、それで、何か気にかかることでもありますか?」
時折話すバイトの大学生とただの社会人という間柄で、首を突っ込んでいいのかわからなくて聞いてこなかったことがあった。
「…あの、健人くんは時々、なんというか…寂しそうに見えるときがあって。」
「はい。」
「誕生日、なんですけど。」
「はい。」
「…誕生日を、あまり祝ってもらったことがないのかなって。でも、だとしたら、というか、誕生日を祝ってもらえないような家庭環境にあって、あんなに穏やかに優しく育つものなのかな…とか、あの、ちょっと大学では少しだけ心理とか教育をかじっていたもので…余計な詮索だなとは思うんですけど。」
綾乃がそこまで言うと、オーナーはいつもよりも目を細めて微笑んだ。
「祝ってもらっていましたよ、ずっと。優しい両親に育てられましたから。ただ、高校1年生までですが。」
重たい話なのに、柔らかい表情を浮かべるオーナーに、思わず表情を歪めてしまったのは綾乃のほうだった。