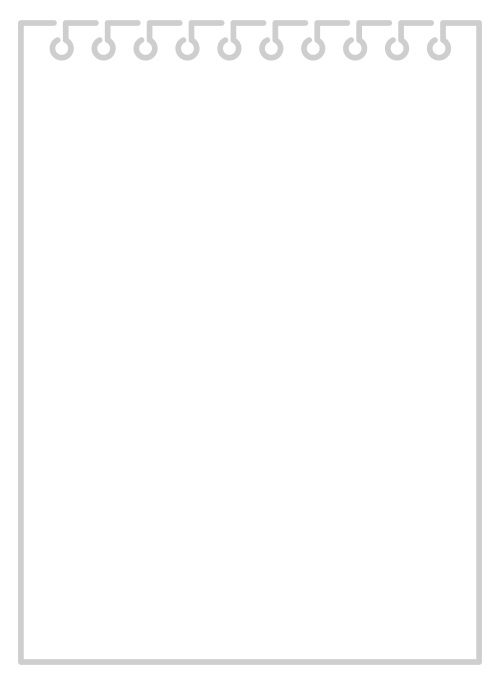多分、すごく頑張って言ってくれているのだろう。危ないと心配してくれているのも本心だろうし、店員と客という関係で送るなんて言われて困らせないかとか、そういうことも考えているのだろうなということは想像に難くない。だからこそ、その気持ちを無下にしたくはなかった。
「…じゃあ、お言葉に甘えちゃっていいですか?」
「え?い、いいんですか?」
「でも、お皿洗いは手伝いますから。ここから入って大丈夫ですか?触っちゃいけないものありますか?」
「触っちゃいけないもの、水回りにはないですけど!僕もやります!」
大した量の食器ではなかったためあっという間に終わり、店を後にする。
「綾乃さんのお家はここから近いんですか?」
「はい。歩いて15分くらいなので、休みの日に引きこもりがちな私には丁度良い運動です。」
綾乃がそう答えると、健人は少しだけ目を丸くした。意外なことを言ってしまっただろうか。
「何か変なこと言いましたか、私?」
「あ、いえ。綾乃さん、オーナーと話しているとき、明るくて元気なのでアウトドア派なのかと勝手に思っていました。」
「キャンプとかやるほどアウトドアではないですが、出かけるときは出かけますよ。歩くのとか、体を動かすことが嫌いというわけではないので。」
「そうなんですね。」
「健人くんはアウトドア派?」
少しだけ見上げた健人の頭の後ろには、星が輝いていた。それが突然綾乃の目に入ってきて、『そうですね…』なんて考えこんでしまった健人の口が再び開くのよりも先に、綾乃が言葉を発してしまう。
「今日は星が綺麗です。アウトドアとはあんまり関係ないかもしれませんが、星を見るのは好きなんですよね、私。」
「…空、見上げるのは僕も好きです。晴れの日もいいけど、夜は夜で。」
「夜は夜の良さがありますよね。何となく、わかるかも。」
ぬくい風が二人の間を吹き抜けていく。手が触れるわけでも、腕を組むわけでもない絶妙な距離感。それが今は、心地よかった。
「…じゃあ、お言葉に甘えちゃっていいですか?」
「え?い、いいんですか?」
「でも、お皿洗いは手伝いますから。ここから入って大丈夫ですか?触っちゃいけないものありますか?」
「触っちゃいけないもの、水回りにはないですけど!僕もやります!」
大した量の食器ではなかったためあっという間に終わり、店を後にする。
「綾乃さんのお家はここから近いんですか?」
「はい。歩いて15分くらいなので、休みの日に引きこもりがちな私には丁度良い運動です。」
綾乃がそう答えると、健人は少しだけ目を丸くした。意外なことを言ってしまっただろうか。
「何か変なこと言いましたか、私?」
「あ、いえ。綾乃さん、オーナーと話しているとき、明るくて元気なのでアウトドア派なのかと勝手に思っていました。」
「キャンプとかやるほどアウトドアではないですが、出かけるときは出かけますよ。歩くのとか、体を動かすことが嫌いというわけではないので。」
「そうなんですね。」
「健人くんはアウトドア派?」
少しだけ見上げた健人の頭の後ろには、星が輝いていた。それが突然綾乃の目に入ってきて、『そうですね…』なんて考えこんでしまった健人の口が再び開くのよりも先に、綾乃が言葉を発してしまう。
「今日は星が綺麗です。アウトドアとはあんまり関係ないかもしれませんが、星を見るのは好きなんですよね、私。」
「…空、見上げるのは僕も好きです。晴れの日もいいけど、夜は夜で。」
「夜は夜の良さがありますよね。何となく、わかるかも。」
ぬくい風が二人の間を吹き抜けていく。手が触れるわけでも、腕を組むわけでもない絶妙な距離感。それが今は、心地よかった。