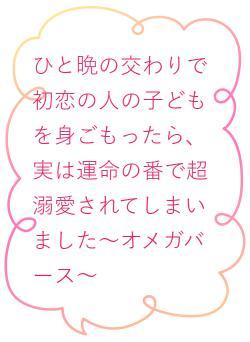両親と私は困惑したように、顔を見合わせる。
父が小さなため息をついた。そうして紅月家の代表として躊躇いながら口を開く。
「……お言葉ですが、それでは神永様にとって得するものが、なにもないと思うのですが」
「そんなことはございませんっ!」
バッと効果音がしそうなほどの勢いで、神永さんが顔を上げ、父を振り仰いだ。
その顔が必死さを帯びている。
けれどそうまでして自分と紅月家へ必死になられる理由の分からない私は、神永さんから寄せられる無償のような好意に、なにか裏があるのではないかと構えてしまう。
もちろんこの場にいた紅月家の面々も間違いなくそう思っていたのだろう。
「ですが正直なところ、我が不肖の娘は神永様に釣り合うほど、見た目も中身も器量良しとはとうてい思えないのですが……」
父の言葉に思わず私も目を瞬かせた。
残念ながら、佇まいからして生まれながらに華やかで品のいい神永さんとは違い、下町生まれの素朴な雰囲気を持つ容貌の私とでは、まず見た目からして釣り合っていないのは、誰からみても明白なのだから。
「問題ありません。僕はそのままのきらりさんが大好きなので、器量がなんだとか気になりません。むしろ、きらりさんとの結婚を認めていただけることが、僕の得になります」
私のことをいつの間にか何度も名前呼びをしていたけれど、神永さんは実直な瞳で父を見据えていた。
「きらりさんを愛しているんです。どうか、この結婚を認めてください。お願いします」
もう一度神永さんは自身の意志をはっきりと父へ告げると、正座姿勢のまま最敬礼の角度で静かにお辞儀する。
その姿は誰が見ても嘘偽りのない、心からのもののように映った。
だからこそ、不覚にも神永さんの姿勢に私の胸はどきっと揺れる。
強引すぎる婚約を締結させるための納得できる理由が、なにひとつないというのに。
父が小さなため息をついた。そうして紅月家の代表として躊躇いながら口を開く。
「……お言葉ですが、それでは神永様にとって得するものが、なにもないと思うのですが」
「そんなことはございませんっ!」
バッと効果音がしそうなほどの勢いで、神永さんが顔を上げ、父を振り仰いだ。
その顔が必死さを帯びている。
けれどそうまでして自分と紅月家へ必死になられる理由の分からない私は、神永さんから寄せられる無償のような好意に、なにか裏があるのではないかと構えてしまう。
もちろんこの場にいた紅月家の面々も間違いなくそう思っていたのだろう。
「ですが正直なところ、我が不肖の娘は神永様に釣り合うほど、見た目も中身も器量良しとはとうてい思えないのですが……」
父の言葉に思わず私も目を瞬かせた。
残念ながら、佇まいからして生まれながらに華やかで品のいい神永さんとは違い、下町生まれの素朴な雰囲気を持つ容貌の私とでは、まず見た目からして釣り合っていないのは、誰からみても明白なのだから。
「問題ありません。僕はそのままのきらりさんが大好きなので、器量がなんだとか気になりません。むしろ、きらりさんとの結婚を認めていただけることが、僕の得になります」
私のことをいつの間にか何度も名前呼びをしていたけれど、神永さんは実直な瞳で父を見据えていた。
「きらりさんを愛しているんです。どうか、この結婚を認めてください。お願いします」
もう一度神永さんは自身の意志をはっきりと父へ告げると、正座姿勢のまま最敬礼の角度で静かにお辞儀する。
その姿は誰が見ても嘘偽りのない、心からのもののように映った。
だからこそ、不覚にも神永さんの姿勢に私の胸はどきっと揺れる。
強引すぎる婚約を締結させるための納得できる理由が、なにひとつないというのに。