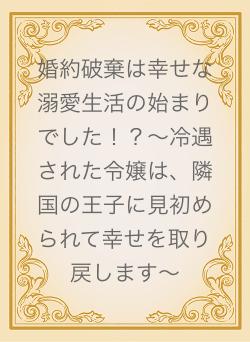『その言葉が本音か嘘かが分かるのは、言い放った本人だけ。結局、どんな声を持っていたって、他人の心なんて分からないのよ』
グラアナの言葉は、私の心にぐさりと刺さった。
そうかもしれない。
だけど……だけど。
「うっ……うわぁぁあん!!」
堪えきれず大きな声を出すと、グラアナがぎょっとした顔で私を見た。
「……ちょっ、いきなりなによ! あなたもしかして泣いてるの?」
「泣いてるよ! 泣くよ! こんな話聞かされたら誰だって!」
泣きながら叫ぶ。
海の中では、私の涙は真珠にはならないから、泣いても目には見えない。
それでも、グラアナは気付いてくれた。私の涙に……。
「……バカな子ね。あなたにはこれっぽっちも関係ないことでしょ」
「そんなことないっ」
私はごしごしと涙を拭いて、
「そんなことないよ!!」
「きゃっ……!? ちょっと、なにするのよ!」
むぎゅっとグラアナに抱き着いた。驚いたグラアナは私を引き剥がそうとするけれど、私はぎゅうっと強く抱き着いたまま言った。
「やだ! こうしたいの!」
「……まったく……子供なんだから」
グラアナは私を引き剥がすのを諦めて、手から力を抜いた。私は抱きついたまま、グラアナを見上げた。
「……ごめんなさい。私、ずっとグラアナのこと誤解してた。グラアナがシュナの声を奪ったんだって、疑ってなかった。グラアナ本人から聞いたわけでもないのに……確かめもしないで勝手に決めつけて、最低だよね。本当にごめんなさい」
ふぅ、とグラアナが息を吐く。
「……あなたは友達を信じた、ただそれだけ。それは悪いことじゃないわ」
「ねぇ、グラアナ。我慢はたしかに立派だし、すごいことだと思うよ。だけど、自分の悲しみを誤魔化すのはよくないよ。それじゃ自分が救われない。嘘で守られても、国王様もシュナもきっと悲しくなるだけで嬉しくなんて思わないよ。本当のことを話に行こう?」
グラアナはふいっと目を逸らした。
「……行かない」
「どうして!?」
「話しても、だれも幸せにならないからよ」
「そんなことないよ。少なくとも、グラアナが救われるよ」
「……私は、救われようなんて思わないわ」
「どうして?」
「……あなたに私の気持ちなんて分からないわ。なに不自由なく魔法養成学校に通ってるような、いいとこ生まれのお嬢様にはね」
ぐっと奥歯を噛む。
「……たしかに分からないよ。でも、分からないから、話し合って分かり合うんじゃないの?」
すると、グラアナは鼻で笑った。
「そんな簡単じゃないのよ、大人はね」
「…………」
どうしたら、グラアナを助けられる? シュナを助けられるんだろう……。
考えても、やっぱり答えはひとつしか見つからない。
「……私、これからアトランティカに行ってくる」
「は……?」
「グラアナが行かないなら、私が代わりにシュナやみんなと直接話してくるよ」
「なに勝手なこと言ってるの!? ダメよ、そんなの。そんなことしたって意味ないわ!」
「話せばきっと分かるのに、なにもしないなんて絶対おかしい! 行く!」
「本当にもういいのよ。無理なのよ。今さらなにを言ったところで、私の言うことなんて誰も信じない」
諦めたようなグラアナの声に、拳に力が籠る。
「……私なんてって、一番いやな言葉だよ。……ねぇ、グラアナはなんでそんなに自分を否定するの? やってないなら、やってないって言おうよ! 私じゃないって!」
グラアナはまたもふっと投げやりに笑った。まるで、自分自身を嘲笑うみたい。
「……ごめんなさいね。あいにくだけど私、自分で自分を守りたいと思うほど、自分のことを好きじゃないのよ」
「……どうして?」
「……私は、家族にも、愛するひとにも捨てられるようなつまらない人間だからよ。誰も私を知らないこの世界に来ても疎まれてる。……そんな人間を、どうして好きになれるの」
きゅっと喉が絞られるように苦しくなった。
きっと、グラアナには口でなにを言ってもダメだ。こうなったら、やってみせるしかない。
「……分かったよ。それなら私が証明してみせる」
「証明って、なにを?」
グラアナは不思議そうに私を見上げた。私はにっと歯を見せて笑う。
「まぁ見ててよ。じゃ、ちょっとアトランティカ行ってくる!」
私は元気よくグラアナの家を飛び出した。
「えっ!? ちょっと……!!」
私がグラアナに教えてあげるんだ。
血が繋がってなくたって、家族になれる。心を繋げられるってことを……。
私と同じように、親に見捨てられた思いをしたグラアナに。
絶対、なんとしてでも。