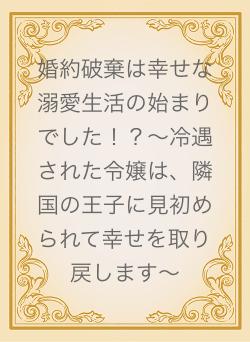「マーメイドプリンスって、なに?」
「お姫様のことをマーメイドプリンセスっていうでしょ? 海の王子様のことは、マーメイドプリンスっていうのよ」
「じゃあ、それってつまり、グラアナが恋した男の子はアトランティカの王子様だったってこと?」
「そういうこと」
王子様かぁ。
……ん? ちょっと待てよ。グラアナが子供の頃にアトランティカの王子様だったってことは……。
「ねぇ、それってもしかして……シュナの」
「そう。私が恋をしたのは、あなたの大切なお友達であるシュナのお父さんよ。今は王子から国王になって、正真正銘アトランティカの国王様ね」
「じゃあ、シュナはグラアナの娘なの?」
「違うわ。だって私たちは、結局すぐ離れ離れになってしまったから」
「え? でも、好き同士だったんでしょ?」
「……何度目かのデートのあと、言われたの。婚約者がいるって」
「え……」
「その婚約者というのが、今の王妃よ」
当時、彼には婚約者がいた。但し婚約者とは言っても名ばかりで、会ったこともなかったらしい。
それでも、彼は婚約者と結婚する道を選んだ。すべては王国のために。
「そして、彼は最後に愛してると告げて、私の前から姿を消した」
「そんな……」
「私は大人しく身を引いた。彼を本当に愛していたからよ」
彼への想いは消えるどころか、日に日に増していったわ。彼になにか会ったとき守ってあげられるようにと強く思うようになったの。
それから私は、必死に魔法を勉強した。魔法が使えれば、彼になにかあったとき助けてあげられるかもしれないから。
「そして、正式に魔女の称号を得た日、私は海で生きることを決めたの」
もちろんそれは、彼の幸せを壊すためじゃなく、ただ彼の幸せを守るためだった。
未練がましいと言われても、彼が別のひとと結婚していても、どうしてもそばにいたかった。
彼が幸せであることが分かれば、それだけでよかったの。
「彼は婚約者と結婚して、すぐに子をもうけた。その子がシュナよ」
「そうだったんだ……」
姫が生まれて、彼も王妃様もとても幸せそうだった。その笑顔を見て、私も幸せになったわ。
「でもね、姫には生まれながらに欠陥があったの」
「欠陥……?」
生まれてきた姫は、産声を上げているはずなのに、声を発していなかった。
泣いている。でも、声は聴こえない。
まるで、この世界から音が消えてしまったと錯覚するようだった。
彼も王妃様も心配してすぐに医者にみせたわ。でも、姫の体に異常はなし。
結局王宮には、姫の声を聴ける者がだれひとりとしていなかったの。
そのとき、私は魔女の勉強をしていたときに見た一冊の本の内容を思い出したの。
「本?」
「……生まれつき、そういう個体がいるとなにかの本で見たのよ」
マーメイドの中には、ごくまれにみんなと違う声を出す個体がいる、と。
「私たちの耳で聴き取れる音域には限度がある。極端に高過ぎる声や低過ぎる声っていうのは、私たちの耳に届いていても認識ができてなかったりするのよ」
つまり、私たちに聴き取れる音域から大きく外れた域の声で、シュナは普段話をしている。
「でも、私には聴こえるよ?」
「あなたもシュナと同じ、特殊体質なんじゃない? それか単にバカのなせる技なのかもね」
「なぬ。バカ……はやだけど、そのおかげでシュナの声が聴こえるなら、悪くもない……のか? うーん」
「あなた、音の高さとかよく分からなそうだものね」
「失礼な! たしかに楽譜は読めないけど、音の高さくらい分かるよ!」
「あらそうなの? ま、どうでもいいけど」
「よくないやい!」
「まぁ、その話は置いておいて。シュナの声について心当たりがあった私は、一度陸に戻ってもう一度その本を探したの。そして、彼女の声をみんなに届ける方法を、見つけた」
「えっ! 見つけたの!?」
「人間になれば、彼女は普通の声を手に入れることができる」
「人間に……」
但し、人間になってしまったら、海では生きられない。人間になるということは、海の中で早く泳げたひれも失うことになるし、海の仲間たちとも会えなくなる。
そしてなにより、家族と離ればなれになる。
「……難しい選択だね。それで……グラアナはどうしたの?」
「悩んだけれど、見過ごすことはできなかった」
私は、彼や彼の家族を助けるためにアトランティカに行ったわ。
そこで、久しぶりに彼と再会した。
驚く彼に、私は言ったわ。
私なら、この子を助けられるかもしれない。
人間になれば、彼女は声を手に入れることができると。
すると彼は言った。
自分たちは陸では生きられない。
人間になったら、この子を守ることができない。
それなら、私がシュナを育てるわ。誰より愛するひとの子ですもの。
私は、彼と王妃様にそう言った。
「それで?」
彼は少し考えさせてくれと言った。考えがまとまったら、使いを出すからと。
私は了承して、アトランティカを出た。
「そしてその七日後、使いは来たわ」
使いは、マーメイドの大軍だった。
「えっ!? どういうこと!?」
「王妃様は私を信用できなかったのよ。それどころか、国王をたぶらかし、姫の声を奪った悪い魔女として私を討伐しようとした」
そして私は、深海に追いやられた。今は暗い海の底で、息を潜めるようにして生きている。
少しでも明るいほうへ行くと、魔女が船を沈めただとか、マーメイドの声を奪いにやってきただとか言われるから……。
「そんなのって酷すぎるよ! グラアナはシュナのためにやったのに」
「仕方ないわ。私だって、彼女の立場なら疑ってしまうかもしれないもの」
「でも!」
「その言葉が本音か嘘かが分かるのは、言い放った本人だけ。結局、どんな声を持っていたって、他人の心なんて分からないのよ」
私はただ、彼を守りたくて、彼の子を守りたかっただけ。でも、いくら訴えても王妃様は信じてくれなかった。
たとえ届けられる声があっても、私の言葉はだれにも伝わらなかった。
「そう思ったら、なんだかもうバカらしくなってきちゃってね。いっそ海の生き物たちが噂するとおりの魔女を演じてやっていたってわけよ」
私は前に落ちた紫色の髪を、さらりと後ろへ流して立ち上がる。
「さて、お望み通り話はしたわ。そろそろ帰ってくれる?」
私は動こうとしない小さな魔女の腕をそっと掴んだ。