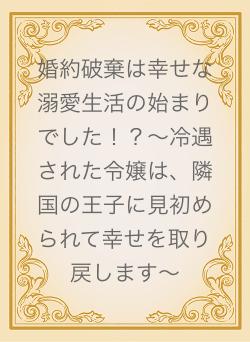「あたっ!」
ドサッと地面に落とされ、思わず声を上げる。
ひどい! こんなの、荷物を降ろすときの降ろし方だよ! 私、荷物じゃないのに!
「っていうか、ここどこ?」
いつの間にか、知らない場所にいる。
岩と岩の間に空いた空間のような場所。
辺りは真っ暗で、少し寒い。
たぶんここ、海の中でもかなり深い場所っぽい。
さっとステッキを振って灯りを灯すと、目の前には、立派な鉄の扉。よく見ると、私は小さな家の前にいるらしかった。
もしかしてここ、グラアナのお家かな?
「もしも~し! だれかいますか~」
しーん。
無視かい! 絶対聞こえてるでしょ!
「グラアナ~。そこにいるのはわかってるんだよ~!! ここ開けてくださいよ~」
「取り立て屋か! うるさいわよ! さっさと帰れ!」
返事が返ってきた。ということは、ここはやっぱりグラアナのお家。
締め出しを食らったみたいだ。
「ここ開けてよ~! 中に入れてよ~! グラアナってば~」
とんとんと扉を叩きながら、中にいるはずのグラアナに泣きつく。
「むぅ……」
どうしたら中に入れるだろう。ぐるぐる周囲を回ってみる。
いくつか窓があるし、割って入る?
若しくは魔法で……。
ぎゅるるるるっ!
「――う?」
なに、今の音。私のお腹辺りから聞こえたような……。
……あ、そういえばお腹が減ったかも……って、お腹?
そっか、この手があった!
「こんこん。グラアナさん。今気付いたんだけど私、お腹が減ったんだよね。だからさ、もしよかったらグラアナの手料理をごちそ……」
ガン、と扉が蹴られる音がした。
「うわっ!」
なにごと!?
「いい加減にして! なんでそれで中に入れると思ったのよ!? あなた、バカにもほどがあるでしょう!!」
「――バカ?」
バカだって? 追い出したひとには言われたくないよっ!
「それはこっちのセリフだよっ! グラアナこそ、なんでそんな意固地になってんのっ!? バッカじゃないっ!?」
「なってない! そもそもなんで私があなたのような落ちこぼれ魔女に自分の事情を教えなくちゃならないのよ!」
それはたしかに……いや、それより。
「バカの次は落ちこぼれって言った!?」
ひどいっ!
「私はバカでもないし落ちこぼれでもなーいっ!」
「ふん。落ちこぼれよ! 自分の身すら守れないんだから」
ぐぬぬぬっ……!!
「言ったなぁ!!」
もう怒っちゃったもんね!
私は扉にステッキを向けた。
「ロジカル・マジカル! 泥棒になれっ!!」
ぽんっ!
緑色の地味な風呂敷を頭に被って、手には細長い金属。
「泥棒は鍵を開けるプロだからね!」
マーメイド姿で泥棒の格好ってちょっとシュールだけど、ま、いっか。
「いざ!」
さっそく鍵穴に金属を差し込み、ガチャガチャといじってみる。
がっちゃん。
「よし!」
扉の鍵を壊し開けること成功!
さすが私!
「なっ……」
グラアナにまた鍵をかけられる前に、すすっと身をひるがえして中に入る。
「へっへーん! 私の勝ち~!」
「あなたね……!! 強引にもほどがあるでしょう!! というかなによ、その格好!!」
「泥棒です」
「いい加減にしなさいよ……この落ちこぼれ魔女……!!」
グラアナがメラメラし始めた。
わお。髪の毛が逆立ってる。
「お、落ち着いてグラアナ」
強引なことをしてるっていうのは、分かってる。でも、このままなんて絶対ダメ!
「こ、怖くないよ!」
私はグラアナの正面に立って、強い眼差しで見据えた。
「だって……だってさ! グラアナだって、自分のこと泣かせてるよ! 全然自分のこと守れてないよ!」
「あーもううるさいうるさい! 私はべつになにも抱えてない! くだらないお節介はやめてよ!」
「くだらなくなんてないよ! 苦しいなら叫ばなきゃダメだよ! 叫ばなきゃ、だれにも気付いてもらえないんだよっ!」
半ば叫ぶように訴える。
「バカなこと言わないでよ」
すっと波が引くように穏やかな声で、グラアナが言う。
「え……」
グラアナは自嘲気味に笑って、投げやりに言った。
「……叫んだって、だれも私の声なんか聴いてくれないわ」
「そんなことっ」
ない、と否定しようとしたけれど、グラアナは私が口を開く前に、首を横に振る。
「私は悪い魔女なのよ。海の生き物みんなに嫌われてる。恐れられてる。私は、優しくて可愛らしいマーメイドプリンセスとは違うの」
キュッと、心臓が素手で鷲掴みにされるような声だった。
きっとこれまで、グラアナは声をあげられずに泣いていたんだ。ここで、シュナと同じようにたったひとりで……。
そっとグラアナのそばに行って、その手を握る。グラアナは驚いた顔をして、私を見た。
「……私が聴くよ」
「…………」
「だからさ、グラアナ。私にわけを話してよ」
グラアナは一度寂しげに目を伏せた。
「私は……」
口を開いては、ぐっとなにかを詰まらせたように黙り込む。
「ゆっくりでいいよ。だから、私に本当のグラアナを教えて」
すると、グラアナは遠慮がちに話し出した。
***
私が生まれ育ったのは、スコーティアランドという海辺の街。
私はその街で一番有名な魔女家系の貴族の家に生まれたわ。でも私は、生まれつきほとんど魔力のない子供だった。だから両親は、私の魔力が弱いことを知るとすぐに施設に私を捨てたわ。
「なにそれ! ひどい!!」
思わずグラアナの話を遮って怒ってみせると、グラアナはふっと笑った。
「そんなもんよ、貴族なんて。魔女は魔力が命。魔力のない魔女に価値なんてないのだから」
「グラアナ……」
寂しげな笑みに、心臓がずきんとした。
「それから、施設の暮らしが始まったのだけど」
グラアナは再び話し出した。
施設に入ってからは、私は魔女になることを早々に諦めて、施設で幼い子たちの世話をしながら普通の学校に通っていた。
学校では、いじめられたわ。
みなしごだとか無能魔女だとか、毎日のようにからかわれた。
けれど、それは施設で育つみんなが経験していること。自分だけじゃない。
そう思って、毎日自分の悲しみを誤魔化して生きていた。
「そんなときに、私は彼に出会ったの」
「彼?」
学校帰り、砂浜を散歩しながら帰ることを日課にしていた私は、そこで不思議な姿の少年と出会ったの。
そのひとは、上半身が人間の体をしていて、下半身は魚のひれを持った男のひとだったわ。
「それってもしかして、マーメイド?」
「そう。マーメイド。そのとき彼、尾ひれを怪我していてね。私は彼を助けて、そして恋に落ちたの」
優しくて、明るいひとだった。陸の話をするととても喜んで、そして私に海の世界の話をたくさんしてくれた。
「当時、生きる希望なんて欠片もなかった私に、彼は生きる力をくれたのよ」
「まさに運命の出会いだね!」
「学校が終わったあと、海岸でこっそりふたりきりでお話をしたり、浅瀬で水遊びをして遊んだり。とっても楽しかった」
「青春だぁ」
会えば会うほど、私は彼をどんどん好きになっていった。
ある日、私はとうとう勇気を出して彼に告白をしたわ。
「そうしたら彼も私に同じ言葉を返してくれたの」
「きゃ~! それってもしかしなくても両想いってことだよね!?」
「そうね」
「きゃあ~!!」
でも、初恋は実らないのよ。いつの世も。
「……グラアナ? どうしたの?」
「彼は、私とは住む世界が違うひとだった」
「住む世界?」
「彼はマーメイドプリンスだったのよ。海の王国の」
「え……?」
ドサッと地面に落とされ、思わず声を上げる。
ひどい! こんなの、荷物を降ろすときの降ろし方だよ! 私、荷物じゃないのに!
「っていうか、ここどこ?」
いつの間にか、知らない場所にいる。
岩と岩の間に空いた空間のような場所。
辺りは真っ暗で、少し寒い。
たぶんここ、海の中でもかなり深い場所っぽい。
さっとステッキを振って灯りを灯すと、目の前には、立派な鉄の扉。よく見ると、私は小さな家の前にいるらしかった。
もしかしてここ、グラアナのお家かな?
「もしも~し! だれかいますか~」
しーん。
無視かい! 絶対聞こえてるでしょ!
「グラアナ~。そこにいるのはわかってるんだよ~!! ここ開けてくださいよ~」
「取り立て屋か! うるさいわよ! さっさと帰れ!」
返事が返ってきた。ということは、ここはやっぱりグラアナのお家。
締め出しを食らったみたいだ。
「ここ開けてよ~! 中に入れてよ~! グラアナってば~」
とんとんと扉を叩きながら、中にいるはずのグラアナに泣きつく。
「むぅ……」
どうしたら中に入れるだろう。ぐるぐる周囲を回ってみる。
いくつか窓があるし、割って入る?
若しくは魔法で……。
ぎゅるるるるっ!
「――う?」
なに、今の音。私のお腹辺りから聞こえたような……。
……あ、そういえばお腹が減ったかも……って、お腹?
そっか、この手があった!
「こんこん。グラアナさん。今気付いたんだけど私、お腹が減ったんだよね。だからさ、もしよかったらグラアナの手料理をごちそ……」
ガン、と扉が蹴られる音がした。
「うわっ!」
なにごと!?
「いい加減にして! なんでそれで中に入れると思ったのよ!? あなた、バカにもほどがあるでしょう!!」
「――バカ?」
バカだって? 追い出したひとには言われたくないよっ!
「それはこっちのセリフだよっ! グラアナこそ、なんでそんな意固地になってんのっ!? バッカじゃないっ!?」
「なってない! そもそもなんで私があなたのような落ちこぼれ魔女に自分の事情を教えなくちゃならないのよ!」
それはたしかに……いや、それより。
「バカの次は落ちこぼれって言った!?」
ひどいっ!
「私はバカでもないし落ちこぼれでもなーいっ!」
「ふん。落ちこぼれよ! 自分の身すら守れないんだから」
ぐぬぬぬっ……!!
「言ったなぁ!!」
もう怒っちゃったもんね!
私は扉にステッキを向けた。
「ロジカル・マジカル! 泥棒になれっ!!」
ぽんっ!
緑色の地味な風呂敷を頭に被って、手には細長い金属。
「泥棒は鍵を開けるプロだからね!」
マーメイド姿で泥棒の格好ってちょっとシュールだけど、ま、いっか。
「いざ!」
さっそく鍵穴に金属を差し込み、ガチャガチャといじってみる。
がっちゃん。
「よし!」
扉の鍵を壊し開けること成功!
さすが私!
「なっ……」
グラアナにまた鍵をかけられる前に、すすっと身をひるがえして中に入る。
「へっへーん! 私の勝ち~!」
「あなたね……!! 強引にもほどがあるでしょう!! というかなによ、その格好!!」
「泥棒です」
「いい加減にしなさいよ……この落ちこぼれ魔女……!!」
グラアナがメラメラし始めた。
わお。髪の毛が逆立ってる。
「お、落ち着いてグラアナ」
強引なことをしてるっていうのは、分かってる。でも、このままなんて絶対ダメ!
「こ、怖くないよ!」
私はグラアナの正面に立って、強い眼差しで見据えた。
「だって……だってさ! グラアナだって、自分のこと泣かせてるよ! 全然自分のこと守れてないよ!」
「あーもううるさいうるさい! 私はべつになにも抱えてない! くだらないお節介はやめてよ!」
「くだらなくなんてないよ! 苦しいなら叫ばなきゃダメだよ! 叫ばなきゃ、だれにも気付いてもらえないんだよっ!」
半ば叫ぶように訴える。
「バカなこと言わないでよ」
すっと波が引くように穏やかな声で、グラアナが言う。
「え……」
グラアナは自嘲気味に笑って、投げやりに言った。
「……叫んだって、だれも私の声なんか聴いてくれないわ」
「そんなことっ」
ない、と否定しようとしたけれど、グラアナは私が口を開く前に、首を横に振る。
「私は悪い魔女なのよ。海の生き物みんなに嫌われてる。恐れられてる。私は、優しくて可愛らしいマーメイドプリンセスとは違うの」
キュッと、心臓が素手で鷲掴みにされるような声だった。
きっとこれまで、グラアナは声をあげられずに泣いていたんだ。ここで、シュナと同じようにたったひとりで……。
そっとグラアナのそばに行って、その手を握る。グラアナは驚いた顔をして、私を見た。
「……私が聴くよ」
「…………」
「だからさ、グラアナ。私にわけを話してよ」
グラアナは一度寂しげに目を伏せた。
「私は……」
口を開いては、ぐっとなにかを詰まらせたように黙り込む。
「ゆっくりでいいよ。だから、私に本当のグラアナを教えて」
すると、グラアナは遠慮がちに話し出した。
***
私が生まれ育ったのは、スコーティアランドという海辺の街。
私はその街で一番有名な魔女家系の貴族の家に生まれたわ。でも私は、生まれつきほとんど魔力のない子供だった。だから両親は、私の魔力が弱いことを知るとすぐに施設に私を捨てたわ。
「なにそれ! ひどい!!」
思わずグラアナの話を遮って怒ってみせると、グラアナはふっと笑った。
「そんなもんよ、貴族なんて。魔女は魔力が命。魔力のない魔女に価値なんてないのだから」
「グラアナ……」
寂しげな笑みに、心臓がずきんとした。
「それから、施設の暮らしが始まったのだけど」
グラアナは再び話し出した。
施設に入ってからは、私は魔女になることを早々に諦めて、施設で幼い子たちの世話をしながら普通の学校に通っていた。
学校では、いじめられたわ。
みなしごだとか無能魔女だとか、毎日のようにからかわれた。
けれど、それは施設で育つみんなが経験していること。自分だけじゃない。
そう思って、毎日自分の悲しみを誤魔化して生きていた。
「そんなときに、私は彼に出会ったの」
「彼?」
学校帰り、砂浜を散歩しながら帰ることを日課にしていた私は、そこで不思議な姿の少年と出会ったの。
そのひとは、上半身が人間の体をしていて、下半身は魚のひれを持った男のひとだったわ。
「それってもしかして、マーメイド?」
「そう。マーメイド。そのとき彼、尾ひれを怪我していてね。私は彼を助けて、そして恋に落ちたの」
優しくて、明るいひとだった。陸の話をするととても喜んで、そして私に海の世界の話をたくさんしてくれた。
「当時、生きる希望なんて欠片もなかった私に、彼は生きる力をくれたのよ」
「まさに運命の出会いだね!」
「学校が終わったあと、海岸でこっそりふたりきりでお話をしたり、浅瀬で水遊びをして遊んだり。とっても楽しかった」
「青春だぁ」
会えば会うほど、私は彼をどんどん好きになっていった。
ある日、私はとうとう勇気を出して彼に告白をしたわ。
「そうしたら彼も私に同じ言葉を返してくれたの」
「きゃ~! それってもしかしなくても両想いってことだよね!?」
「そうね」
「きゃあ~!!」
でも、初恋は実らないのよ。いつの世も。
「……グラアナ? どうしたの?」
「彼は、私とは住む世界が違うひとだった」
「住む世界?」
「彼はマーメイドプリンスだったのよ。海の王国の」
「え……?」