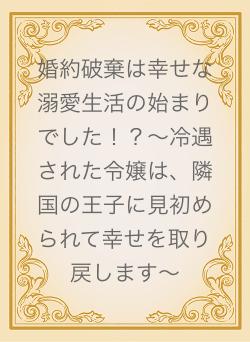――昔から、俺はひとりが好きだった。
理由は簡単。俺がおぼっちゃまだったから。家柄や容姿に惹かれた奴らがよく群がってきて、ウザかった。
俺の容姿だけを見て寄ってくる奴、官僚マークベル一家という家柄を見て食いついてくる奴、いろいろいた。
親の手前邪険にするわけにもいかなかったので、幼稚園に通い出す頃には、完璧な愛想笑いを習得していた。
毎日、ただただ面倒くさかった。
だから基本、俺は幼稚園でも誰とも仲良くなろうとしなかった。
そんなときだ。火花と出会ったのは。
火花は、五歳のときに知り合った。遠くから引っ越してきたらしい火花は、幼稚園に通うこと自体初めてだったらしい。
いつも教室の隅っこで本を読む、大人しい子だった。その姿は、少しだけほかのやつらと違って大人びて見えた。
当時俺は、火花のことがあまり好きじゃなかった。
両親に極端に甘やかされていたことを知っていたから。
あるとき、俺は火花が男の子にいじめられているところを目撃した。
当時の俺は、いじめられる火花を庇うこともせず、黙って見ていた。
だって、火花には絶対的な味方がいる。
家に帰ったら、どうせすぐに甘やかしてくれる親に泣きついていじめも解決するんだろうと思っていたから。
でも、火花はなぜだかいじめられていることを親に言わなかった。
誰にも助けを求めず、たったひとりで耐えていた。
『なぁ知ってる? あいつ、孤児なんだって!』
火花が、孤児?
『施設から今の親に引き取られてこっちに来たんだってさ。うちのママが言ってた!』
なるほど、言われてすぐ納得する。
火花の両親は、火花とは髪色からして全然違ったから。
それに、あんなに甘々な両親に対して、火花はどこか距離を置くような、怯えるような態度をとっていた。
そうか。
『孤児』
その言葉ひとつで、これまで分からなかった火花のすべての行動を理解した。
『やい、ニセモノ娘!』
『みなしご~!』
ある日、火花が孤児だということを知ったクラスメイトが、いつものように火花をからかった。
『孤児』
そう吐き捨てられた瞬間、火花の顔は凍りついた。
いつもなにを言われても軽く言い返すだけで受け流していた火花が、さすがにそのときだけは動揺し、逃げ出した。
先生たちは大慌てだった。
いじめられた火花の家はクラリネット家といって、とても有名な政治家の家だったし、いじめたほうの親も貴族の爵位を持っていたから。
先生たちは子供たちを頭ごなしに怒ることもできず、おろおろするばかりだった。
仕方なく、俺が魔法で居場所を見つけ出して迎えに行った。
『火花』
火花は雑木林の切り株に座って、ひくひく泣いていた。
『……どうしてきたの?』
迎えに行くと、火花は開口一番、涙声でそう言った。俺は火花の隣に座って、訊ねた。
『……いじめられていること、なんで親に言わないんだよ。お前溺愛されてるんだから、言えばすぐ解決しただろ』
『……だって、面倒だから』
『は?』
面倒? 親にいじめられていると告白するのが?
理解しかねていると、
『ママにもパパにも、面倒かけたら捨てられちゃうから』と、火花は小さな声で付け足した。
ハッとした。
面倒というのは、自分ではなく相手が、ということだったのだ。
それはつまり……。
『それは、お前が孤児……だからか?』
思い切って訊ねると、火花はこっくりと頷いた。
『そう。私、出来損ないのいらない子だから。捨てられた子どもだから』
それは、初めて火花が漏らした本音だった。