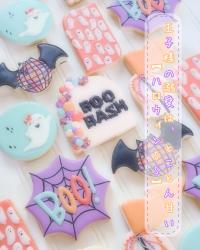「…もっと自覚してよ。凛子先輩は自分のことわかってなさすぎ」
何が気に食わないのか、口を尖らす東都はそう言ってから私を引き寄せた。
引き寄せられるがままに腕の中へとすっぽりはまってしまうけど、それより気になるのは今言われたことのほう。
「っな、何言ってるの。自分のことは自分が1番わかってるに決まってるでしょ」
頭を精一杯に上へと向けて睨みつける。
だって、言い返してやりたくなったから。
私の何を知ってるんだ、って。
年下のくせに、いつも私を手のひらの上で転がして遊ぶのも大概にしろ。
そんな思いを込めた視線を向けていれば、東都は呆れたように。
「…馬鹿じゃねぇの」
呟いてから、チュッと触れる程度のキスを落とした。
「っ!?な、なにして…っ」
「わかってないから言ってんじゃん。俺がどんだけ我慢してるか、教えてあげよーか」
腰に絡みついた長い腕がするりと背中に回って、シャツの中へと侵入してくる。
触れられたところが途端に熱を持ち、そこから全身を駆け巡るように沸騰して。
「〜〜っいい加減にしなさい!!」
熱さと恥ずかしさでたまらなくなった私は、本日2度目の怒号を放った。