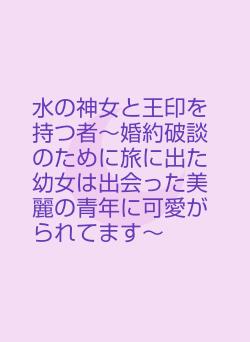立ち塞がった二人は、眉を吊り上げて淑女とは言い難い形相でエスティラを睨んでいた。
「どこに行くつもりだ⁉」
そしてエスティラ達を追いかけてきたロマーニオによって囲まれてしまう。
どうしよう……あの離れから出れたのは良いけど……。
脱出に必死で脱出した後のことは全く考えていなかった。
このままだとまたあの離れに閉じ込められてしまい、今までよりももっと酷い扱いを受けるかもしれない。
そんなの嫌っ……!
エスティラは無意識にミシェルの服をぎゅっと掴んで不安からくる震えを誤魔化す。
「彼女は僕の元で働いてもらう。今後、彼女と接触したいなら公爵家を通してもらおう」
毅然と言い放つミシェルにエスティラは目を見開く。
ミシェルはロマーニオやリーナの言葉ではなく、エスティラを信じてくれたのだ。
信じてくれたんだ……あの人達の嘘じゃなくて、私のことを。
それがエスティラにはとても嬉しく、胸の中が温かくなる。
仕事が何であれ、私は全力でこの人に応えよう。
エスティラは心の中で決心した。
「あんた! どういうつもりよ⁉」
今にも掴みかからんとばかりにリーナはがなり立てる。
「汚い手を使ってミシェル様に近づいたんでしょ⁉ 毒だってそんなもの最初からなかったんでしょ⁉ 自作自演の猿芝居でミシェル様の気を引いていやらしいったらないわ! この男好きが!」
エスティラを大声で罵ったリーナはミシェルに縋るように近づく。
「ミシェル様、どうか騙されないで下さい! 魔女の思惑に乗ってはなりません!」
そう言って可憐な乙女が神へ祈るように胸の前で手を組む。
「リーナの言葉を信じて下さい。ミシェル様が心配なのです」
「そうです、心優しいこの子は公爵様にその娘が害になることを心配しているのです」
潤んだ瞳でミシェルを見つめるリーナは傍から見ればとても愛らしく、その可憐な容姿の虜になる男も多い。
しかし内面を知っているエスティラにとってはただの『裏表が激しい女』にしか映らない。
今しがた、エスティラのことを目を吊り上げて罵倒したばかりだということを忘れているのだろうか。
流石に絆されたりしないわよね?
リーナに騙されるような人じゃないと思うものの、何せ、男という生き物はああいう女に弱い。
少しだけ不安になりながらミシェルを見上げる。
そしてミシェルの顔を見た瞬間、エスティラはゾッとした。
誰にでも愛想の良い笑顔を振りまく、魅惑の貴公子。
しかしそこには甘い笑顔も微笑みもなく、冷たい表情でリーナを見つめるミシェルの姿があった。
「僕が君を信じられる要素がどこにある?」
表情も冷たいが声はもっと冷たかった。
「…………え?」
ミシェルの言葉にリーナは間の抜けた声を出す。
一体、何を言われているのか分からない、という表情だ。
目を潤ませて上目遣いで見つめ、甘い声を出して縋るようにミシェルの身を案じれば自分に有利な状況になると思っていたらしい。
予想外な言葉が返ってきてリーナは戸惑っているようだ。
「公爵である僕に対しての虚偽の発言を繰り返し、僕がエスティラ・ルーチェを直接訊ねてきたにもかかわらず、会わせまいとこんな離れに手足を縛り、口を塞いで拘束する……軽蔑しか覚えない。僕の信用を損なう真似を平気でしておいて、信じろだなんて厚かましいと思わないのかな?」
ミシェルはそう言ってリーナとセザンヌ、ロマーニオを順にねめつける。
「彼女は連れて行く」
そう言って三人に背を向け、エスティラの肩を抱いて門の側に停めてあった馬車の方に歩き出す。
「公爵様であってもこれは人攫いですぞ!」
背中にぶつけられた声はロマーニオのものだ。
「その娘を連れて行くなら私の許可が必要です!」
ニヤリと後ろで笑みを浮かべているのが見なくても分かった。
「何故、貴様に許可を得る必要が?」
ミシェルはゆっくりと後ろを振り返り、地を這うような低い声で言った。
「そ……それは、私がこの家の―――」
「当主は貴様ではないだろう?」
ロマーニオの言葉がミシェルによって遮られる。
「貴様はウォレスト・ルーチェが成人するまでの当主代理に過ぎない。代理風情が家門の当主を名乗るなどおこがましい。養い親としてきちんとした生活を送らせているならまだしも、彼女がこの邸でどのような扱いを受けていたか僕が知らないとでも思ってるのか?」
その様子に気圧された三人は声が出ない。
「新聞の一面を飾りたくなければ大人しくしているんだ。聖女になるどころか嫁ぎ先にも影響が出るだろう」
ミシェルの言葉にリーナは意気消沈する。
崩れるように膝を着き、セザンヌが寄り添って身体を支えている。
「行くよ」
そう言ってミシェルはエスティラの背中を押す。
ちらりと邸の方を盗み見ればリーナとセザンヌが激しい憎悪の視線をエスティラに向けている。
全部自分達が蒔いた種でしょ。
エスティラは前を向き、馬車に乗り込む。
それ以降は邸も叔父夫婦もリーナのことも振り向かなかった。