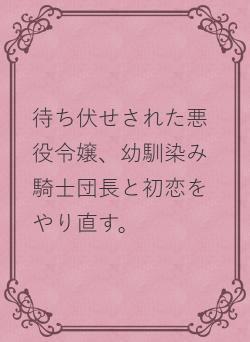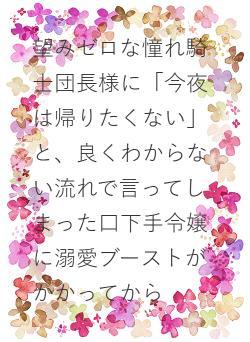何故かというと、自分の好きな人の服を洗って乾かして、整えることまで出来るからだ。ちなみにこのことは、ガイは知らない。彼が何も知らずに着ている軍服は、私が毎日せっせと汚れを落としている特別仕様なのだ。
私は手に持っていたガイの軍服を、じっと見つめる。そして、出来心でそれを身に纏った。
「おっき……当たり前か。ガイは背が高くて……身体が大きいものね」
私の太もも半ばになるほどの丈に、袖は長過ぎて手は出てない。
これは彼がいつも着ている服だというだけなのに、ただそれだけで服までも愛しく思えてしまった。
同じ職場の男性となんて、付き合うべきではなかった。
私は失恋した男性と同じ職場に留まれるほど、心は強くあれない。彼と別れればこの城での好待遇を捨てて、逃げるように転職をしようと心に決めていた。
今は遠くを歩いている姿も、たまに見ることが出来る。付き合っていた時は、それが喜びだったけど……別れてしまえば、きっと見るたびに、針を刺されるような痛みが胸を襲うはずだ。
「あら。パトリシア。こんなところに居たの?」
私は手に持っていたガイの軍服を、じっと見つめる。そして、出来心でそれを身に纏った。
「おっき……当たり前か。ガイは背が高くて……身体が大きいものね」
私の太もも半ばになるほどの丈に、袖は長過ぎて手は出てない。
これは彼がいつも着ている服だというだけなのに、ただそれだけで服までも愛しく思えてしまった。
同じ職場の男性となんて、付き合うべきではなかった。
私は失恋した男性と同じ職場に留まれるほど、心は強くあれない。彼と別れればこの城での好待遇を捨てて、逃げるように転職をしようと心に決めていた。
今は遠くを歩いている姿も、たまに見ることが出来る。付き合っていた時は、それが喜びだったけど……別れてしまえば、きっと見るたびに、針を刺されるような痛みが胸を襲うはずだ。
「あら。パトリシア。こんなところに居たの?」